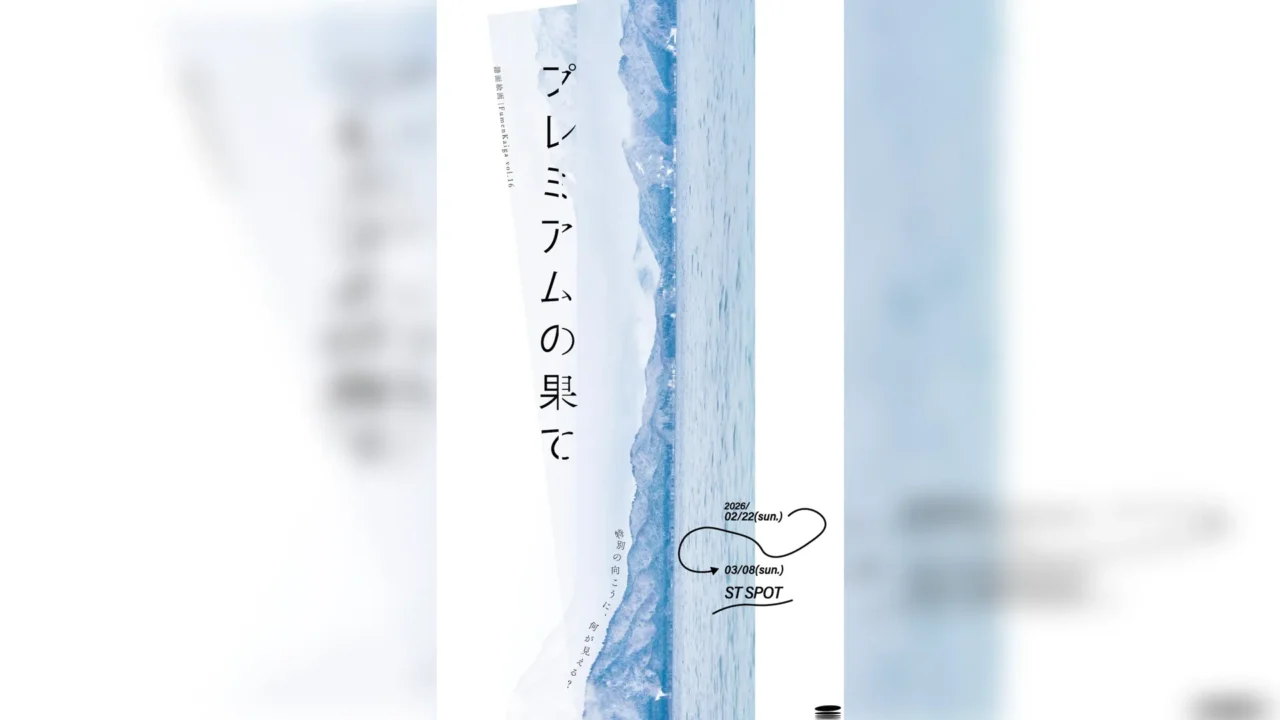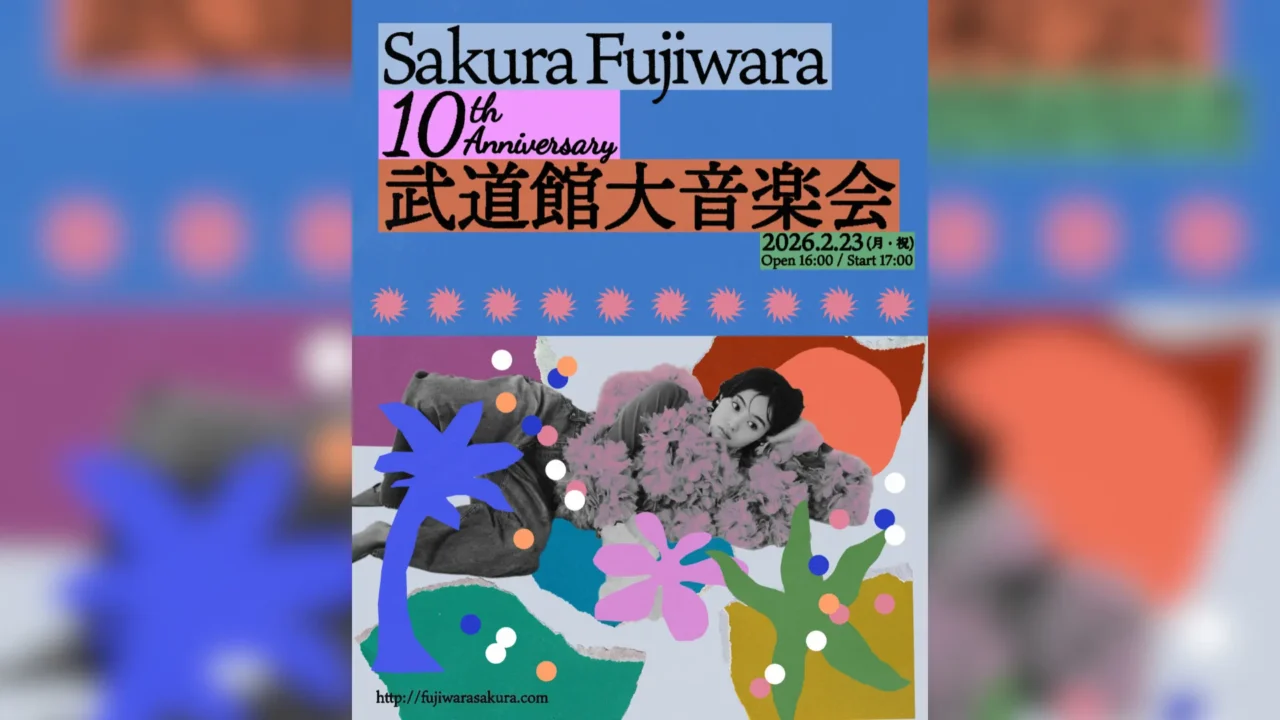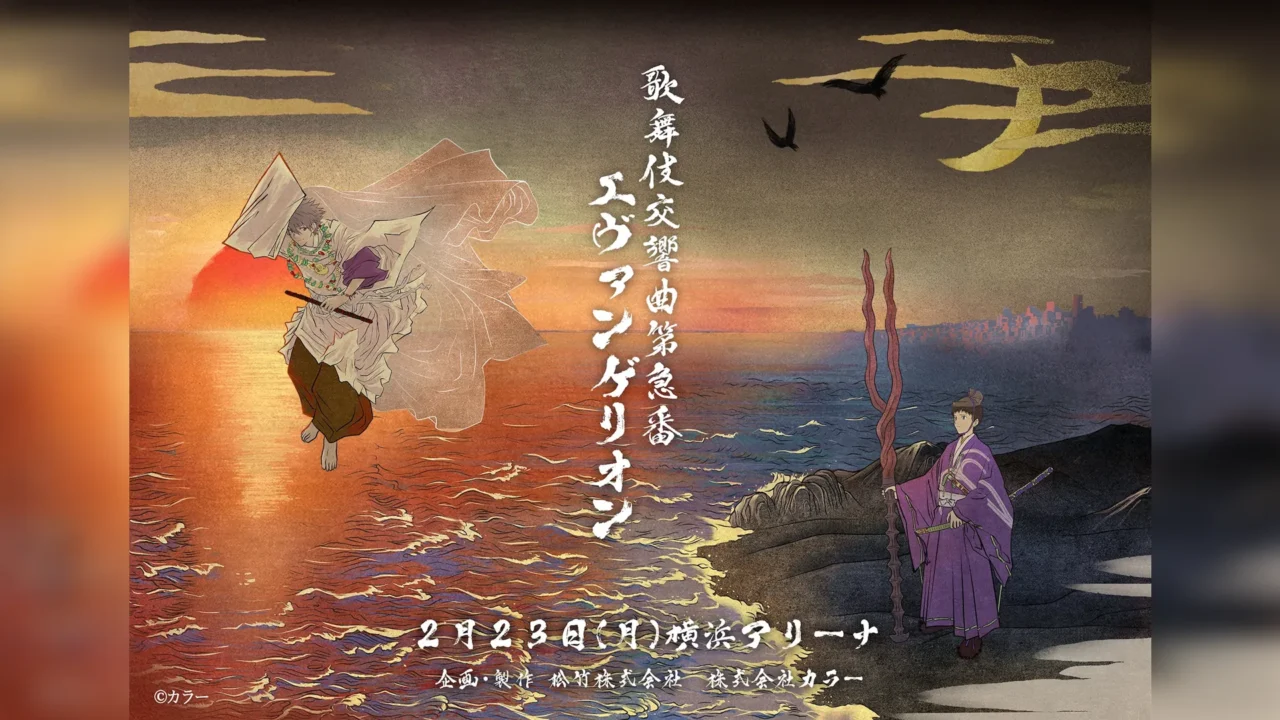INDEX
1990年代にアメリカで新興したデジタル設計と生成AI時代の共通項
平野:最初に平野スタジオ全体の感想からお聞きしたいと思います。このスタジオをやっていて思い出したのが、隈さんがニューヨークのコロンビア大学にいた1990年代頃にバーナード・チュミが始めたペーパーレススタジオ(*)です。当時出始めた、ハリウッドの特撮技術などのデジタルテクノロジーを応用して「新しい建築」の実践を試みた、教育現場における実験的なスタジオでした。それと似たようなことが今回のスタジオでも起こっていて、新しいものが芽生えそうな予感がします。
*バーナード・チュミ(Bernard Tschumi):スイス生まれの建築家・理論家。建築と哲学、文学、映画理論を融合させた革新的な設計思想が特徴で、建築を静的な空間ではなく、動的な「出来事の場」として捉え、脱構築主義(Deconstructivism)を代表する建築家の一人として知られる。
ペーパーレススタジオ:1990年代にコロンビア大学建築学部(GSAPP)で導入されたコンセプト。コンピュータを活用し、手作業のドラフティングを排除することで、新しいデザインの可能性を追求したもの。一部では手描きスケッチの重要性を軽視するものだと批判されたが、デジタル設計が主流となった現在では、建築教育の革新的な取り組みとして評価されている。
隈:バーナード・チュミがペーパーレススタジオを始めたときは、「とんでもなく変なことを始めたやつがいる」というのが周囲のリアクションだったわけです。建築の世界は、実在の建造物、つまり「リアリティ」にこそ価値があるという考えがまだ根強かった。リアリティが全くない画面の中の世界に突き進んでいこうとするチュミは、世間から冷たい目で見られていたような気もするんだけど、今の世の中はむしろ逆なのかもしれない。AI無しではもう世の中が進まない雰囲気があって、そういった危機感がAIを作っているようなところがある。1990年代と30年後の2020年代を比較して、似ているところと対照的なところがあるような気がしますね。つまり、これまでの建築の現場では全てをそぎ落とさないと合格点を取れないところがあった。だから、平野さんが表現する「過剰」な日常と建築スタジオの現場は相容れなかった。
しかし、今回のスタジオはむしろ、その「過剰」に適応する能力を学生に求めている。学生たちの取り組みを通して、現代の建築学生がAIに全く抵抗なく順応している印象を受け、頼もしく思いました。彼らの日常は既にそういうイメージやテクノロジーが溢れる過剰性の中にある。その過剰性の波を「どう波乗りするか」が彼らの日常であって、それの延長線上に今回のようなプロジェクトがあるように感じました。通常の建築のスタジオの「全てを削り取る」方向性と逆の態度を学生に求めているので、学生たちはすごくハッピーに見えましたね。

1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。50を超える国々でプロジェクトが進行中。自然と技術と人間の新しい関係を切り開く建築を提案。主な著書に『隈研吾 オノマトペ 建築 接地性』(エクスナレッジ)、『日本の建築』(岩波新書)、『全仕事』(大和書房)、『点・線・面』(岩波書店)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数。
平野利樹(ひらの としき)/ 写真右
1985年生。2009年、京都大学建築学科卒業。2012年、プリンストン大学建築学部修士課程修了後、Reiser + Umemoto勤務。2016年、東京大学建築学専攻博士課程修了。東京大学建築学専攻助教を経て、現職。建築意匠・建築設計を専門に、建築における新しい美学とは何かを、デジタルテクノロジーの活用や、美術・哲学など他領域との議論を通して探究。2020年から東京大学総括プロジェクト機構 国際建築教育拠点総括寄付講座 SEKISUI HOUSE – KUMA LAB特任講師を務める。作品として 《Reinventing Texture》《Ontology of Holes》など。著書として『a+u 2017年5月号 米国の若手建築家』(ゲスト編集)など。