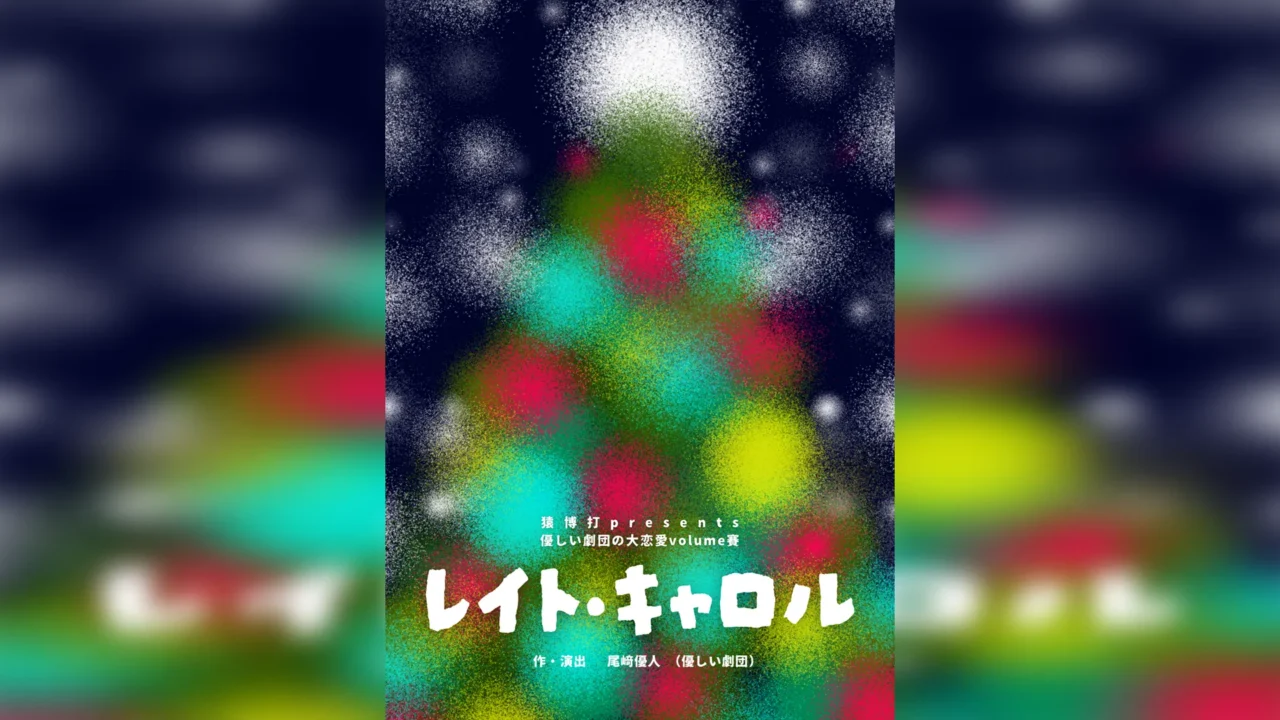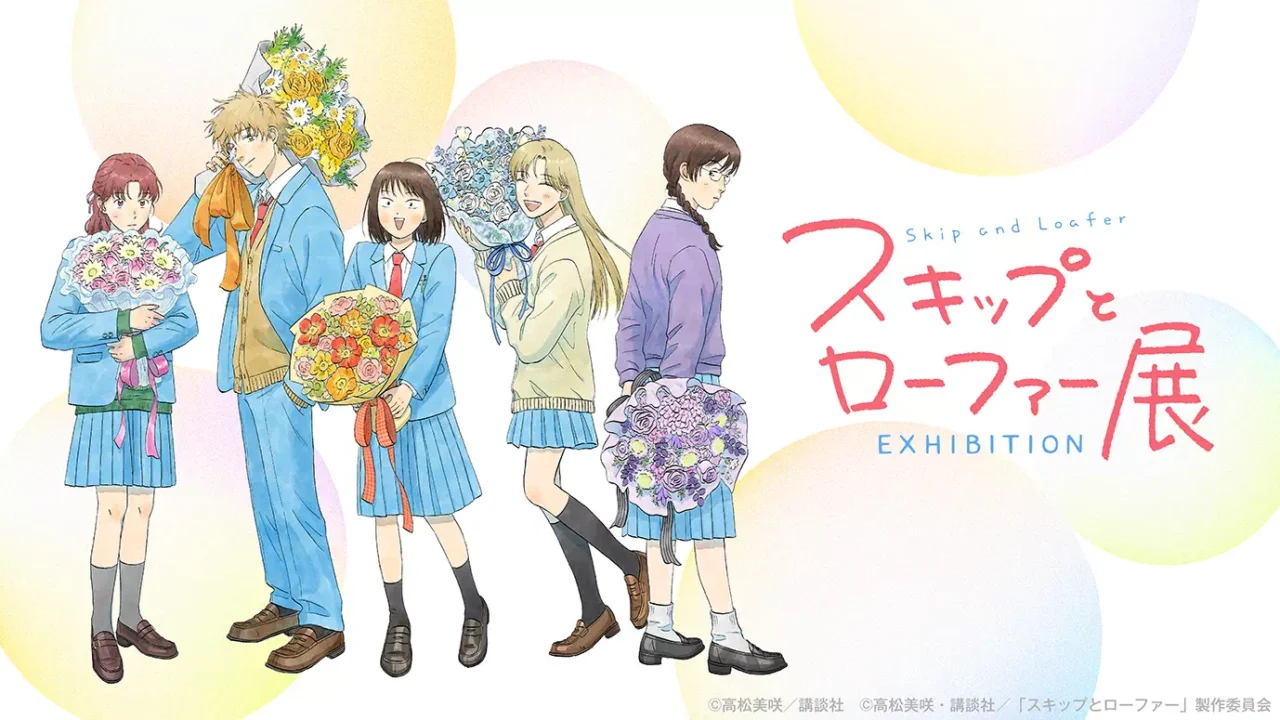2024年7月、東京・多摩ニュータウンの一角に、NiEWが運営する子どもと地域のためのカルチャースペース「tomoto(トモト)」がオープンした。
近隣の子どもや、子育て中の家族をはじめとした人たちが、気軽に立ち寄れる地域の居場所として、無料の子ども食堂や、アーティストによるワークショップなども開催。文化や芸術を通じて、さまざまな状況にある人たちにとっての、拠り所となることを目指している。
そんなtomotoを訪れたのは、シンガーソングライター、エッセイストの寺尾紗穂。個人や家庭が抱える暮らしの負担や、孤独の問題が、コロナ禍以降とくに顕在化してきたなかで、困りごとを抱える人が孤立せず、伸びやかに子どもが育っていくために、どのようなことが社会に求められるのだろうか。
ホームレス状態にある人が生計を立て直すための雑誌『ビッグイシュー』を応援する音楽イベント『りんりんふぇす』を主催し、『子どもたちに寄り添う現場で』と題したWeb連載では子ども食堂への取材を行うなど、福祉や人をつなぐ場づくりに関心を寄せてきた寺尾に、自身の経験や活動を通して感じることを聞いた。
INDEX
公園や児童館、子どもたちの遊び場の減少
─寺尾さんは、多摩ニュータウンのこの辺りにゆかりはありますか?
寺尾:昔、母の友達が住んでいて、小さい頃に一度訪ねたことがありました。なんだかすごいところだなと思った記憶があります。大学も近くでした。

1981年東京生まれ。2007年ピアノ弾き語りアルバム『御身』でデビュー。大林宣彦監督の『転校生 さよならあなた』、安藤桃子監督の『0.5ミリ』など主題歌の提供や、CM楽曲制作(KDDI、キューピー、JA共済ほか)、音楽に限らず新聞(日経、北海道)やウェブでの連載も多数。オリジナルの発表と並行して、ライフワークとして土地に埋もれた古謡の発掘およびリアレンジしての発信を行う。『ミュージック・マガジン』誌では「戦前音楽探訪」の連載を6年間担当した。また、全国各地のアートプロジェクト、東東京エリアの『隅田川怒涛』(2021)、高知・須崎の『現代地方譚』(2022)、横須賀の『SENSE ISLAND/LAND』(2024)などに招聘され、リサーチを経ての表現活動も増えている。2009年よりビッグイシュー・サポートライブ『りんりんふぇす』を自ら主催。2024年に11回目を迎え、山谷・玉姫公園にて開催した。また、女工たちを描いた『女の子たち 紡ぐと織る』、兵器製造に動員された女学生を描く『女の子たち 風船爆弾をつくる』など、作家小林エリカとタッグを組み、歴史に埋もれた女性たちの声を、当時の音楽と共に甦らせる音楽朗読劇を制作している。あだち麗三郎、伊賀航と共に3ピースバンド「冬にわかれて」でも活動を続ける。音楽アルバム近作は「しゅー・しゃいん」。前作「余白のメロディ」(2022)に続いて『ミュージック・マガジン』の年間ベスト(ロック部門)10枚に選出された。2025年6月、アルバム「わたしの好きな労働歌」をリリース予定。
─団地が多く、大学も多いので子どもたちから学生、家族連れ、地域のお年寄りまで、さまざまな人が暮らしている街とのことです。寺尾さんは東京ご出身で、いまも東京に暮らしながら子育てをされているんですよね。
寺尾:何度か引っ越していて、最初は世田谷で、離婚したあと上の子が中学にあがるくらいまでは杉並の実家の近くにいました。ちょうど残っていたような農地が売られて杉並にどんどんマンションが建っていた時期でした。子どもが増えているのに、経費削減のためか杉並全体で児童館が統廃合されていたこともあって、私が子どもの頃に放課後行っていた児童館も、学童の子たちだけでいっぱいで、他の子どもが入りきれなくなっていたのはかわいそうだなと思っていました。公園は確かにあるけど、一輪車に乗れたり、カードゲームをするうちに他校の子と自然と仲良くなれたり、ちょっと年上のお兄さんのような児童館スタッフに出会える場所がなくなるのは結構深刻じゃないかなって。
─いまは公園もルールが厳しいですよね。
寺尾:ボール遊びができなかったり、「この木には登らないでください」って立て札があったりね。前にそれを破って木登りをしている子がいて、「おお、登ってるな」と見ていたら、怒られると思ったのか降りちゃって。私も子どもたちが小さな頃は一緒に木登りをすることがあったんですけど、それを「危険だから」と止めるお母さんもいたし。公園側が禁止してしまうのは、都会の子どもにとって数少ない自然と直に触れ合う貴重な機会を奪っていると思うんですけどね。

─寺尾さんの子ども時代についてもお聞きしたいです。学校はお好きでしたか?
寺尾:多分、いい先生に恵まれたからなんですけど、そのせいか学校は嫌いじゃなくて。私は学ぶことが結構好きだったんです。集団はあんまり好きじゃなかったけど、すごく嫌というほどではありませんでした。「みんなでドッジボールしよう」ってなっても、自分がしたくないときは、教室に残ってずっと金魚を見ていたりしましたね。
─自分のペースで過ごせていたんですね。
寺尾:ただ、自分の娘たちも含め、いまの子たちを見ていると、傷つけたくないし、傷つきたくなくて、気を遣って生きている感じがすごくします。親がこんなルーズな感じでも、子どもは学校という社会の中で、主な枠がつくられてしまうんだなと。
─どんなときにそれを感じるんですか?
寺尾:担任の先生のやり方が、ちょっとどうなんだろうと感じたときに、連絡帳に書いて伝えてみようかなと言ったら、「やめて」と。「目立ちたくないし、言わなくていい」と言うんですよね。でも、そういう事なかれ主義的な感覚だけになってしまうのは怖いと思っていて。「優しさが正義」というのは間違いではないけれど、そこに偏りすぎると、疑問を持っても、なにかを正したり、直していくことができなくなってしまうんじゃないかと思います。
INDEX
子どもの声が聞こえるのは、平和な証拠
─tomotoは、カルチャーが一つの軸になっている場所ですが、寺尾さんが子どもの頃、文化的なものに触れた経験として、印象に残っているものはありますか?
寺尾:母が劇団の女優をやっていたこともあって、7歳くらいの頃に、演劇集団「円」の公演に連れて行ってもらったことがありました。たしか、別役実さんが戯曲を書いた『卵の中の白雪姫』だったかな。それが印象に残っていたからか、中学にあがってから、3つ上の先輩たちがオリジナルミュージカルをやっていたのに感動して、見よう見まねで、ミュージカルサークルをつくって活動したりしていました。自分の子どもたちにもああいうものを観てほしいなと思って、同じく別役実さん作の『不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会』を観に行きましたね。
─子どもの頃、文化や芸術に触れることの意義って、どのようなところにあると思いますか?
寺尾:「よくわからないけれどすごく印象に残っている」ということが大事なんじゃないかな。どう大事なのかはわからないけど、特別な体験をしたという記憶が、おそらくいろいろな形で可能性を広げていくんだと思います。お金のない家庭は、なかなかそういうものに触れさせられなかったりしますよね。学校で劇団を呼んだりするところもあると思うんですけど、文化の格差も是正されてほしいです。

─寺尾さんのライブにも、お子さんはいらっしゃいますか?
寺尾:うん、結構います。ライブ中に子どもが思いがけず声を発したとき、たまに、振り返ったり気にする感じの人もいます。でもたまたま子どもの声がなんとなく歌詞とリンクして、思いがけない感動が生まれたりすることもあって。「そういう奇跡みたいな瞬間を楽しみにしてくださいね」とMCで呼びかけたりすることで、感性をそこに合わせてもらえたらと思っています。気にしだすととことん気になってしまう。逆にそうかもな、と思えれば人の感じ方って大分変わると思うんです。子どもの声が響いていることや、音楽が鳴っていることって、平和じゃなければあり得ないので、そういうことも含めて感じてもらえたら嬉しいです。
─ちょうど昨日(※取材は1月下旬)、昨年度の小中高生の自死者が過去最多だったというニュースを見て。
寺尾:ああ、見ました。
─そういう状況があるなかで、子どもが育まれる場所として、社会にどんなことが必要なんだろうと考えていました。
寺尾:一つは、学校がもっと緩まないといけないのかなと感じます。先生たちが規律みたいなものを頑なに守ろうとすると、生徒たちもその雰囲気の中で育つんですよね。そうすると、規律を乱す子どもを毎回注意したり、まわりの子どもたちもそれを見て責めたりするわけじゃないですか。子どものうちに自己肯定感を育むために、小さな成功体験を積み重ねていかなきゃいけないのに、ずっと怒られているようなことは、おかしいです。発達に問題を抱えた子に、どういう風に声かけすればいいのか、逆にどんなことを言ってはいけないのかを指導要領などのガイドラインなどで共有していれば、傷つく子どもが減ると思います。これだけそういう子たちが増えてきているのに、文科省がはっきりした指針を出さないために、まだ足並みが揃っていないですよね。
大阪府の大空小学校という公立の学校を撮った、『みんなの学校』というドキュメンタリー映画があるんです。その学校は、当時の校長先生が一大改革をして、「あの子が行くならほかの学校にしましょう」と言われるような子たちを積極的に受け入れて、不思議なことに、結果的に学力もすごく上がった。規律を守らせれば、勉強に集中できるという考え方とは、まったく違う新しい常識をつくっているんです。象徴的な場面は、さっきのライブでの子どもの声の話と似ています。授業中に声を発してしまう子がいる教室の中で、先生は「彼は今こういう状態だけど、あなたたちは自分のやることあるんだよ。集中できるよね」といった声かけをしていたんです。気になると言えば気になる、でもそう言われたとき、切り替えられる力が人にはあるんだな、と感じました。公立の先生の考え方が変わっていかないと、苦しい子どもが増えるばかりなんじゃないかなと感じます。
INDEX
子どもの居場所づくりが、民間の善意任せになっている現状
─寺尾さんはご自身の連載(せかいしそう「子どもたちに寄り添う現場で」)のなかで、子ども食堂など、既存の学校教育以外の子どもを育む場にフォーカスして訪ねられていますね。取材を重ねられてきたなかで、どのようなことを感じていますか?
寺尾:子どもの貧困や格差が、より広がっていると感じています。子ども食堂が増えていることも、美談にされやすいけれど、そもそも国の取り組みが遅いんです。もちろん、そうした場所があることのプラスの面もいっぱいあると思うけれど、そこで踏ん張っている人たちが、息切れしているところもあるんだろうなという印象を持っています。

─連載の中でも、ボランティアや寄付など、意思ある個人の力に支えられている部分が大きいことに触れられていました。
寺尾:社会学者の芝田英昭先生が本に書かれていたのですが、厚生労働省がまとめている『厚生白書』を年代ごとに読み込んでいくと、この20年くらいで、「公助」という言葉が少なくなってきた代わりに、「共助」という表現の記載が増えてきたらしいです。でも、そうじゃないだろう、と思います。
夏休みに子ども食堂で1日1食しか食べられない子がいるような状況のなかで、国はなかなか給食費を全額出さないし、本当に未来のことを考えているのかなと感じます。助成金なども、ボランティアでぎりぎりで動いている団体は、申請したうえに、使ったお金の報告までしている余裕がなかなかないところも多いのではないでしょうか。そうした煩雑な報告が必要なため、大変だけれど一切助成金はとっていないという団体さんもいますね。民間の善意任せになっている場所が多いけれど、本来は自治体や民間任せではなく国としてもっと取り組むべきことだと思うんです。
※tomotoは一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)による助成金を取得している。