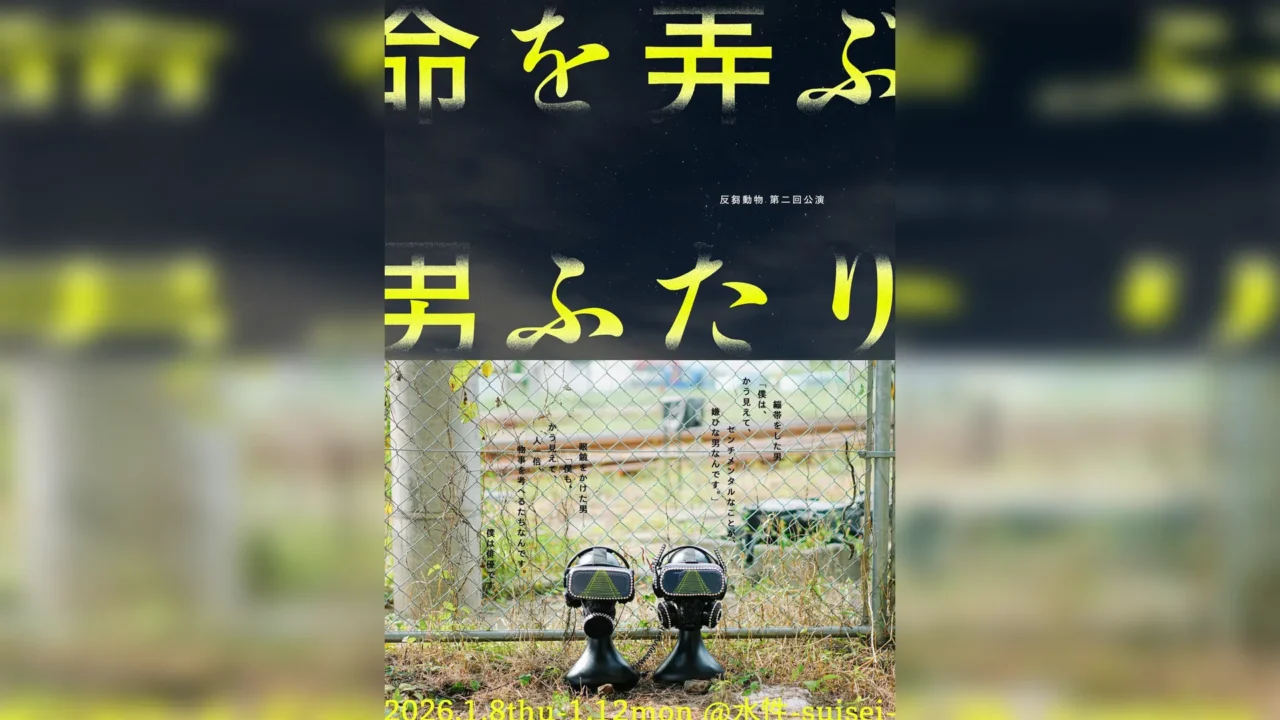シンガーソングライターのむらかみなぎさが、安部勇磨(never young beach)プロデュースのシングル“理由はない”と“裏庭”を2ヶ月連続で配信リリースした。保育士として働く傍ら、都内の喫茶店やライブハウスでギター弾き語りでの活動を開始したむらかみは、フォークをルーツとした音楽性や伸びやかな歌声が話題を呼び、これまでにTHEラブ人間やkiss the gamblerらとも楽曲を制作。2024年には安部が『HOSONO HOUSE COVERS』に提供した“冬越え”や、ソロアルバム『Hotel New Yuma』にコーラスとして参加し、それをきっかけに今度はむらかみの楽曲を安部がプロデュースすることとなった。
2人の共通点は音楽性のみならず、自身の創作に対する譲らなさ、頑固さだと言えそうだ。どちらも普段の物腰は柔らかいし、楽曲からは温かみや楽しさもにじみ出ているのだが、その芯にはつくり手としての信念が色濃く刻まれている。何事にもわかりやすい意味や理由を求められがちな時代に対してノーを突きつける“理由はない”にしろ、セルフケアの重要性を説く“裏庭”にしろ、まずはむらかみが自分自身と向き合い、そこに安部が新たな可能性を注入して出来上がった楽曲たち。出会いから楽曲制作の裏側、共有する感覚について、語り合ってもらった。
INDEX
はじまりは安部勇磨からのDM
―お2人はどうやって知り合ったのでしょうか?
安部:僕から声をかけました。去年個人の活動で録音をしていたときに、女性の声が欲しかったんですよね。そうしたら、SNSでたまたまなぎささんが歌ってる動画が出てきて、この人の声すごくいいなと思って。で、他の動画とかも見てみたら、共通の知り合いも多かったので、InstagramのDMで連絡をして、まずご飯を食べに行って。
―なぎささんの声のどんな部分に惹かれたのでしょうか?
安部:そのまんまな感じというか、作為がないというか、この人の歌が入るだけで、景色がガラッと変わる、そんな印象がありました。あとなぎささんの曲を聴いたら、「こういう曲でこういうコード進行に対してこういう歌詞を歌うんだ」みたいな、言葉の選び方も他にあんまりいないなと思って、どんなことを考えてるのか知りたくて、それで連絡をしたのもありました。

1990年東京生まれ。never young beachのとして2014年に活動を開始。細野晴臣や俳優・渥美清主演の映画『男はつらいよ』シリーズなど、「東京」の文化からの影響を強く受ける。2021年に自身のレーベル「Thaian Records”」を設立、6月に自身初のソロアルバム作品『Fantasia』を発表。2023年5月にはThaian Records / Temporal Drift (U.S)よりEP『Surprisingly Alright』をリリース。2024年2月には11都市12公演に及ぶ自身初の北米ツアーを行った。
ーどの曲が印象に残りましたか?
安部:まず最初に“育て!”がすごくキャッチーでいいなと思ったし、金延幸子さんとかを聴いてるときみたいな気持ちになったんですよね。そういう雰囲気をいま持ってる人はなかなかいない気がしたので、すごく重要だなと思って、最初は“冬越え”という細野(晴臣)さんの曲を一緒にレコーディングしました。
―なぎささんはネバヤンであり安部さんの音楽にはどの程度触れていましたか?
むらかみ:高校生ぐらいのときからnever young beachを聴いてて、安部さんのことはずっと知っていました。SNSもフォローしてたので、急に連絡が来て、最初は「これ本当?」と思いました。でもさっき安部さんもおっしゃったように、共通の知り合いが結構いて、それで知ってくださったのかなと思って。音楽も人柄も好きなので、ご一緒できてすごく嬉しかったです。
―実際に喋ってみて、お互いどんな印象でしたか?
安部:いい意味で変わってるというか、嫌なことは嫌だと言える人なんだなと思って、それだけで僕は信用できると思いました。
むらかみ:安部さんの音楽や話す言葉から、自分と同じく頑固な部分が感じられました。実際制作の現場に入ると、安部さんが自分自身と向き合っている姿を何度もみて。苦しいと思っていることを隠さない安部さんの姿を見て、「音楽って楽しいだけじゃないよな」と改めて感じて、すごくいい経験になりました。

東京を中心に活動するシンガーソングライター。フォークをルーツとしたメロディーに、しなやかなノリとうねりのある声が随一の魅力で、独自のパワーが宿っている。2022年にはTHEラブ人間の楽曲“晴子と龍平”にゲストボーカル、2024年には安部勇麿(never young beach)やグソクムズの作品でもコーラスとして参加するなど、活躍の機会も徐々に増えつつある。
INDEX
安部勇磨のソロ作『Hotel New Yuma』でのコーラスワーク
―“冬越え”のコーラスにはなぎささん以外にも藤原さくらさんと優河さんも参加されていましたね。
安部:いろんな人と一緒に曲をつくってみたいなと思って、僕の中で「声がいい人」というとその3人だったので、あれはすごく贅沢だったなと思います。なぎささんにはその延長で、自分のアルバムにも参加してほしいなと思って声をかけました。
むらかみ:“冬越え”のレコーディングはコーラスが3人いたので、ある程度歌い方が決まっている状態で録音に入りました。今回の安部さんのアルバムでは、レコーディングをしながら、都度指示をいただいて、普段では出さないような声も使いました。「私ってこういう声も出せるんだ」って気がつく瞬間が結構あって。きれいに出すというよりも、音としての面白さを重視しているように感じました。合いの手のようなコーラスをやってみたり。やったことがないコーラスに挑戦できて、すごく楽しかったです。

―“惚けるな”はまさにそういう感じだし、『Hotel New Yuma』には耳に残る音やコーラスがたくさん入ってますよね。
安部:今回のアルバムは今までで一番頑張ってつくったと思っていて、その中になぎささんの声はどうしても必要で。なぎささんの声はブラジルの音楽を聴いてる気持ちになるんですよ。ブラジルの音楽には男性と女性が混合で歌ってるものも多いんですけど、スウィートな感じというか、だけど野暮ったさもちゃんとあって、へにょっとしてるというか、ニュアンスなんですけど(笑)。今回もしなぎささんに歌ってもらってなかったら、聴いたときにこのホテルがどこにあるかの印象も変わってくるかなと思うので、本当によかったなと思ってます。
INDEX
むらかみなぎさの歌遍歴は小学生から
―なぎささんはもともとどういうきっかけで歌を歌うようになったのでしょうか?
むらかみ:小学校のときから自分で適当に曲をつくって歌ってたんです。頭で思いついた言葉をそのまま歌に乗せて、放課後の家に帰る途中とかに歌ってて。家に帰ったら忘れちゃうんですけど、既存の曲を歌うんじゃなくて、なぜかそのときからつくってて……当時は「つくってる」とも思ってなかったんですけど。
―ギターを手にするよりも前に、もう頭の中でつくっていたと。
むらかみ:そうなんです。歩きながら歌うのが楽しいとか、お風呂だと声が響いて楽しいとか、小学2年生ぐらいからずっとそういう感じ。家族もみんな歌が好きで、みんなよく歌ってたんですけど、全員がそれぞれ違う歌を歌ってました(笑)。

ーご家族も音楽好きだったんですね。
むらかみ:みんな自分の好きな歌を勝手に歌ってただけなんですけどね(笑)。おじいちゃんの家に行くとずっとフォークやクラシックが流れてたので、弾き語りのスタイルになったときにつくった曲は、意識せずともフォークっぽくはなりました。
―金延幸子さんとかも自然と聴いていたのかもしれない。
むらかみ:そうですね。かぐや姫、加川良、あとはドノヴァンとかも流れてて、そういう人の曲は今聴いても聴き馴染みがいいなと思いますね。
―そういう名前は安部くんとも通じるところがあるかもしれないですね。
安部:そうですね。親戚みたいな感じがします(笑)。

―なぎささんはもともと保育士として働きながら弾き語りでの活動を始めて、2023年に休職をして、現在はベビーシッターをされているそうですが、自分が音楽をやっていることとお仕事にはどんな関連があると思いますか?
むらかみ:さっき安部さんが「作為がない」とおっしゃっていましたが、私は歌をつくるときにそれを一番意識していて。子どもと話すときも、やっぱり子どもは作為を感じとるから、自分の考えを押し付けてないか、すごく意識して接するようにしています。
それに子どもは音が鳴ると自然に体を揺らしたり、歌とは思わずとも何かを口ずさむから、音を感じる力は私たちにもともと備わってるものなんだろうなって思うんですよね。私は音楽が、音楽として独立しているんじゃなく、生活に根付いているような音楽を聴きたいと思っていて、自分の作る歌もそうでありたいと思っています。自然に音を感じて、楽しんでいる子どもの姿をみると、すごく親和性があると感じます。
INDEX
一緒にレコーディングした“理由はない”“裏庭”のこと
―安部さんの曲のレコーディングに参加した経験を踏まえて、なぎささんは自分の曲を安部さんにプロデュースして欲しいと思ったのでしょうか。
むらかみ:そうですね。安部さんとは制作中に、音楽と全然関係ないこともたくさん話しました。その積み重ねで信頼できる人だなと思って。私のつくった音楽を安部さんがプロデュースしたらどういうものができるのかなと思って、勇気を出してお願いしました。

―どんな話をしたことが印象に残っていますか?
むらかみ:私の持ってる歌の個性について話をしてくださって、自分では気づいていない部分もたくさんありました。今回は安部さんのプロデュースで引き出してもらえた気がします。音楽のジャンルを広げてくれたのもそうなんですけど、それよりも私の人間的な要素を引き出してくれて。頑固さとか曲がらなさみたいな部分も、音で表現できるんじゃないかとか、そういう話もよくしたんですよね。
―実際安部さんはプロデュースするにあたってどんな部分を意識しましたか?
安部:なぎささんのこれまでの曲を全部聴いて、インディっぽくなくていいんじゃないかと思いました。声がすごくいいから、シンプルにいい楽器やいいプレイヤーと一緒にやったらそれだけで十分いいんじゃないかなって。

安部:ただ最初にデモが送られてきたときは、全然変えちゃおうかなとも思ったんですよね。当時ファンクやソウルをよく聴いてて、いま吉田美奈子さんみたいなことをやってる人って他にいないけど、なぎささんはボーカル的に多分できるし、それをいまの人たちといまの録音環境でやったらいいんじゃないかと思って。それで実際ちょっとつくったんです。でも細野さんが「人の作品で自分の方向に持っていきすぎるのは僕はあんまりやらないな」と言ってたのを思い出して。それで最初はなるべくいまのなぎささんのスタイルに沿うような形でやろうと思って、今回はこういう形になりました。
―安部さんとレコーディングをするにあたって、なぜ“理由はない”と“裏庭”の2曲を選んだのでしょうか?
むらかみ:“理由はない”は歌詞からつくったんです。歩きながらボイスメモに言葉を残して、書きたいことがきちんと書けた感覚がありました。綴った言葉をみながら、どういうコードがいいか、どういうバッキングがいいかなって、家でいろいろやってみて、すごく好きな曲ができました。安部さんがプロデュースしたらこの曲がどう変わるのか、すごく興味があったので、”理由はない”を選びました。2曲プロデュースしていただくことが決まっていて、いろんな側面を見せたかったので、違う雰囲気の曲がいいなと思って、“裏庭”を選びました。
―歌詞から曲をつくることが多いんですか?
むらかみ:普段はそういう曲のつくり方をすることはあんまりなくて、歌詞とメロディーとコードを同時につくっています。でもこの曲は、アーティスト写真の撮影があって公園に行ったときに、ちょっと早くついたので散歩をしてたら急に思いついたんです。とりあえず、思いついた言葉をばーっとボイスメモに録ったから、いつもよりも歌詞が詰まってるんですよ。空白がほとんどなくずっと言葉がいて、リズムがあって、コードはあまり変わらない。
―安部さんはデモをもらって、どう解釈しましたか?
安部:本人にも言ったんですけど、「これ押し曲なの?」って言いました(笑)。
むらかみ:あははははは。

安部:「ずっとワンコードじゃん。なんでこれを押そうとしてるの?」みたいな、それも込みでやっぱり面白い人だなと思いました。だから“理由はない”は未だに「難しい曲だったな」という印象で、録音に参加してくれたメンバーとも「これでいいと思う?」みたいな話を結構しましたね。こうやって人の曲をアレンジするのは初めてだったので、感じたことのない責任感があって、自分の曲だったらふざけても自分で後始末ができるんですけど、なぎささんの曲だからあんまりふざけてもダメだしなとか悩みながら、最終的に「これかな」っていう。ギターの歪みをちょっとサイケな感じにしたり、ただのメジャーコードの明るい曲にはしたくなくて、はっぴいえんどの“夏なんです”みたいな、ああいう宙ぶらりんな感じ、着地しない感じが出せたらいいなと思いました。
―「着地しない感じ」というのは“理由はない”というタイトルにも通じますよね。
むらかみ:理由をわかりやすく説明することがいいとされがちだけど、私はそこに回収されないものがすごくたくさんあると思っていて。簡単でわかりやすいものじゃない方が好きだし、別に理由をわかってなくても、それをやりたいとか、その気持ちだけでいいと思うんです。なので、歌詞はなるべく枠にはめないで書きたいと思うし、自分も何にも当てはめずに生活できたらと思うので、それで“理由はない”にしました。
―セルフライナーノーツによると歌詞は、公園を歩きながら小学校の頃を思い出して、それをそのまま書いてるわけですよね。
むらかみ:そうですね。何かを伝えるために書いたというよりは、子どもの頃の景色をそのまま歌にしたっていう感じ。でもつくった後に聴いてみると、今思っていることがきちんと書けていた。特に理由がなく思いつきで書いた言葉でも、理由が後からついてきたり、またその理由も変わっていくと思うし、そういう流動性のあるものがいいなといつも思っています。

INDEX
“裏庭”で歌われているセルフケア
―“裏庭”はなぎささんの自主企画(※)のタイトルにもなっていて、セルフライナーノーツでは「誰にも侵害されない安全な場所を想像しながら書きました」とのことでしたが、いつできた曲でしょうか。
※自主企画『裏庭』は2023年12月に三輪二郎を招いて初開催。その後はぎがもえか、宗藤竜太、浮、石指拓朗、牧野容也、工藤祐次郎が登場。
むらかみ:この曲は企画を始める前くらいにつくった曲です。ずっと自分の企画が、セルフケアできる場所になったらいいなと考えていて。ライブハウスは初めて来る人にはハードルが高い場所だなとずっと思っていて。だから演者とお客さんという枠を超えて、ただそこにいられる、それぞれ好きに音楽を聴いたり聴かなかったりできるような場所がつくりたかったんです。それを考えたときに連想したのが「裏庭」でした。私の想像する裏庭は自分だけが知っている場所の象徴で、セルフケアできる場所。自分の歌う場所がそういう空間になったらいいなと思っています。
ここは裏庭 誰ものぞかない
話す言葉は 誰にも届けない
ここは裏庭 誰ものぞかない
胸の中には 大きな穴があるむらかみなぎさ“裏庭”
―セルフケアやセーフスペースの重要性は、現代人にとって大きなテーマになっているようにも思います。なぎささんにとってのセルフケアは、どういうことでしょうか?
むらかみ:まずは自分のことをちゃんと考えてみる、そこに集中するのが私のセルフケアです。自分の傷をちゃんと見ることで他者の傷も見えるんだろうなってすごく思うから、自分のことを考えることは自分のためだけじゃないなと思いました。内省して作品をつくっても、それが結局他者に繋がっていくのをずっと感じていて。やっぱり自分と他者は切り離せないから、繋がろうと思ってなくても結局繋がっていくし、閉じてるようだけど、開かれていく感覚がずっとあるんです。

―安部さんは音楽をつくることにセルフケアの側面があると思いますか?
安部:あると思います。もちろんこれでご飯を食べてるのもあるし、つくらないとイライラしちゃうんですよ。自分の理想があって、全然できてないんですけど、曲をつくってるうちに救われたりするので、やっぱり自分のためですね。でもそうやって自分のために曲をつくったら、意図しないような人たちが集まってくれたりして、やっぱりこれが僕らなりの友達を増やせるやり方なのかなと思うんですよ。僕は打ち上げにも行かないし、居酒屋にも行かないけど、音楽だったらみんなと遊べる。だからすごく助かるというか、音楽がなかったら結構困ってるなと最近よく思います。