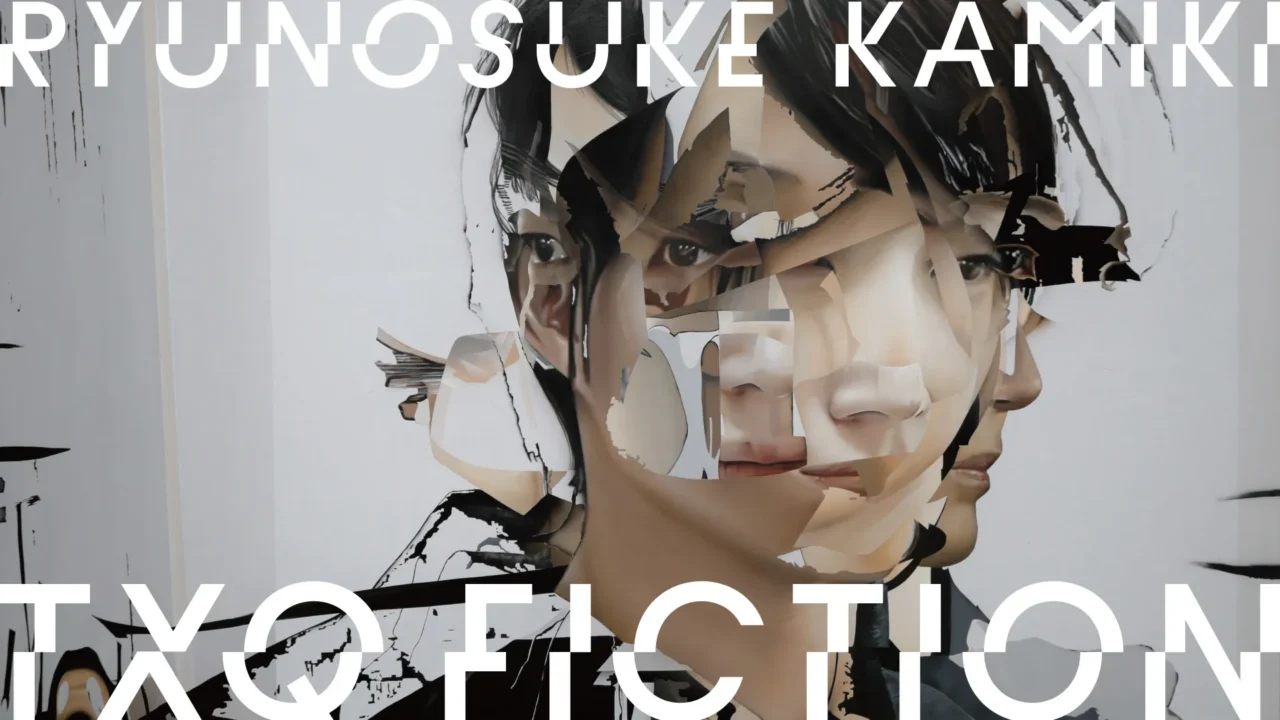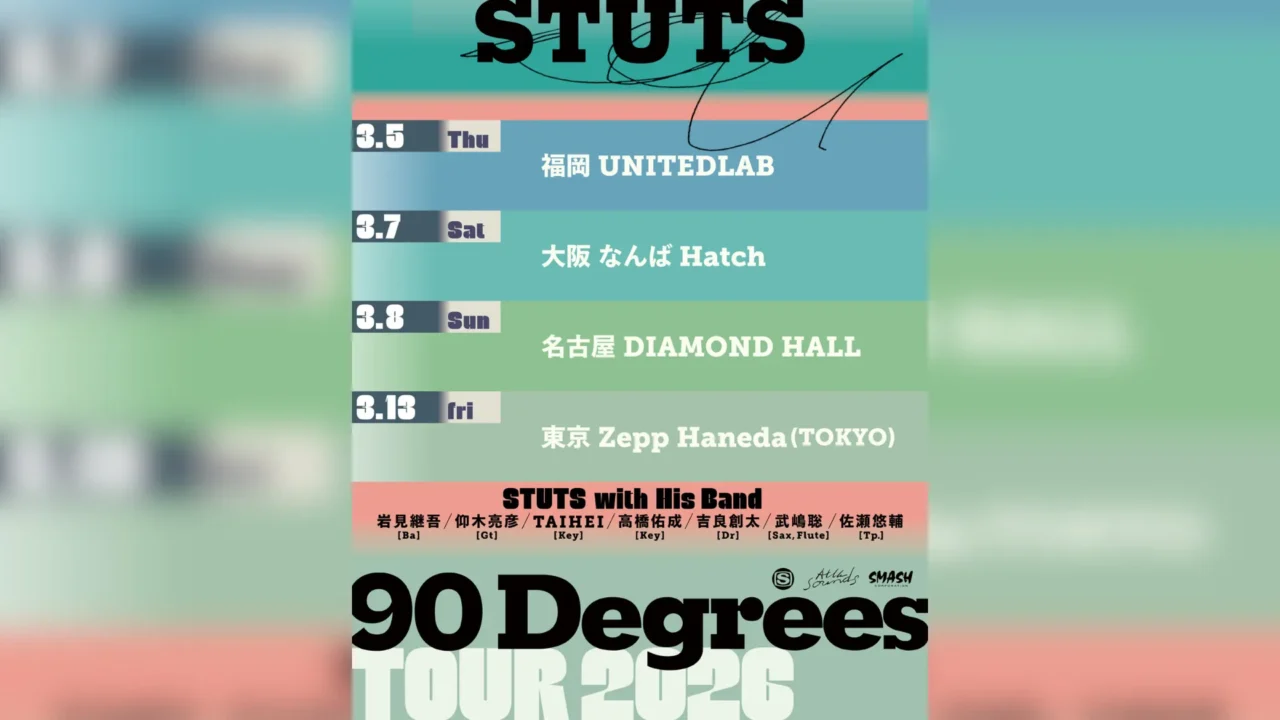INDEX
現代性を踏まえつつ、箏の新しい一面に挑戦した最新作
ー『GRID//OFF』に収録されている坂本さんのカバー“Andata”で編曲とシンセを担当した網守将平さんは、『microcosm』にも参加されています。
LEO:『GRID//OFF』でご一緒した際に、網守さんの音楽性や人間性に惹かれて、今回のアルバムも一番最初の段階でご相談をしました。最初にLAUSBUBとのコラボが決まっていたんですけど、テクノと箏は掛け合わせたことがないし、参考にするような音源も世の中に存在していない。しかも彼女たちは楽譜で音楽を見ている人たちじゃないので共通言語も少ないから、橋渡しをしてくれる人がプロデューサーとしていてくれた方がいいと思ったんです。あと、ドラムと箏という編成もすごくやりたかったので、ドラマーの大井一彌さんを紹介していただいて、2曲目の“Vanishing Metro”を作っていただきました。

ー“Vanishing Metro”は大井さんとの演奏をメインにしたミュージックビデオも公開されていますが、どのように作った曲なのでしょうか?
LEO:ドイツ人のピアニストであるカイ・シューマッハーがドラムとピアノでミニマルミュージックをやっている曲があって、それがすごくかっこいいなと思って、網守さんにまずそれを共有しました。あとちょっとプログレっぽい要素を入れたり、ティグランの影響でメトリックモジュレーション(※)を取り入れたりしました。そういういろんなリクエストを網守さんが全部消化してくださった感じでしたね。
※元の楽曲のテンポを変えることなく、別のテンポへ切り替わったように聴かせる手法
ーエフェクターを使っているのも印象的です。
LEO:エフェクターは「箏から箏じゃない音が鳴ってたら面白いな」という気持ちで使い始めました。でもこのアルバムでは、そのアンサンブルに欲しい音色の質感を出すためにちょっとだけ加えてあげる、みたいな感覚で使っていることが多いですね。
ー弾いているのは一般的な13絃の箏ではなく、25絃なんですよね。
LEO:13絃だと5つの音で構成されるペンタトニックにチューニングすることが多くて、音域がすごく狭いのでできることが限られちゃって。僕の所属している流派はわりと25絃否定派なので、弾いてる人は少ないですけど、気づいたらほとんどの曲で25絃を使ってました。でも、師匠である沢井一恵先生も同じように、箏をドラムスティックで叩いたり、コップで弦を引っかいたりして、今まで誰もやったことない表現に挑戦してきた方なんですよ。すごい批判の的だったはずだけど、それでも一恵先生のやりたい音楽性はしっかりあったんだと思います。僕も一恵先生のことをリスペクトした上で、自分のやりたい拡張の方法を見つけてきた。師匠の背中を追っていたのかもしれません。

ードラムスティックではないものの、LEOさんも箏をパーカッション的に叩いたりしていますよね。
LEO:そんなに強く叩いてないので、あれぐらいだったら許されると思います(笑)。現代音楽の分野で、和楽器はもう50〜60年ぐらい使われているんですけど、いろんな特殊奏法自体は試されているわりに、目新しさを感じることが少なくなってきているので、「本当の現代性」みたいなのも結構テーマにはしていて。例えばTikTokで、箏の音がポーンって鳴ったあとに余韻をちゃんと聴かせて、5秒後に次の音が鳴るっていう動画を投稿したら、次の音を聴く前にすぐにスワイプされちゃうじゃないですか。そういう今の時代の特徴を加味したら、エレクトロニクスを用いた編成にたどり着くのも自然なことだし、それが現代性なのかなって。ポップスの文脈に乗ってはいますけど、芸術的な考え方を残したいエゴもあって、その中で表現した現代性が今回のアルバムなのかなという意識はありますね。