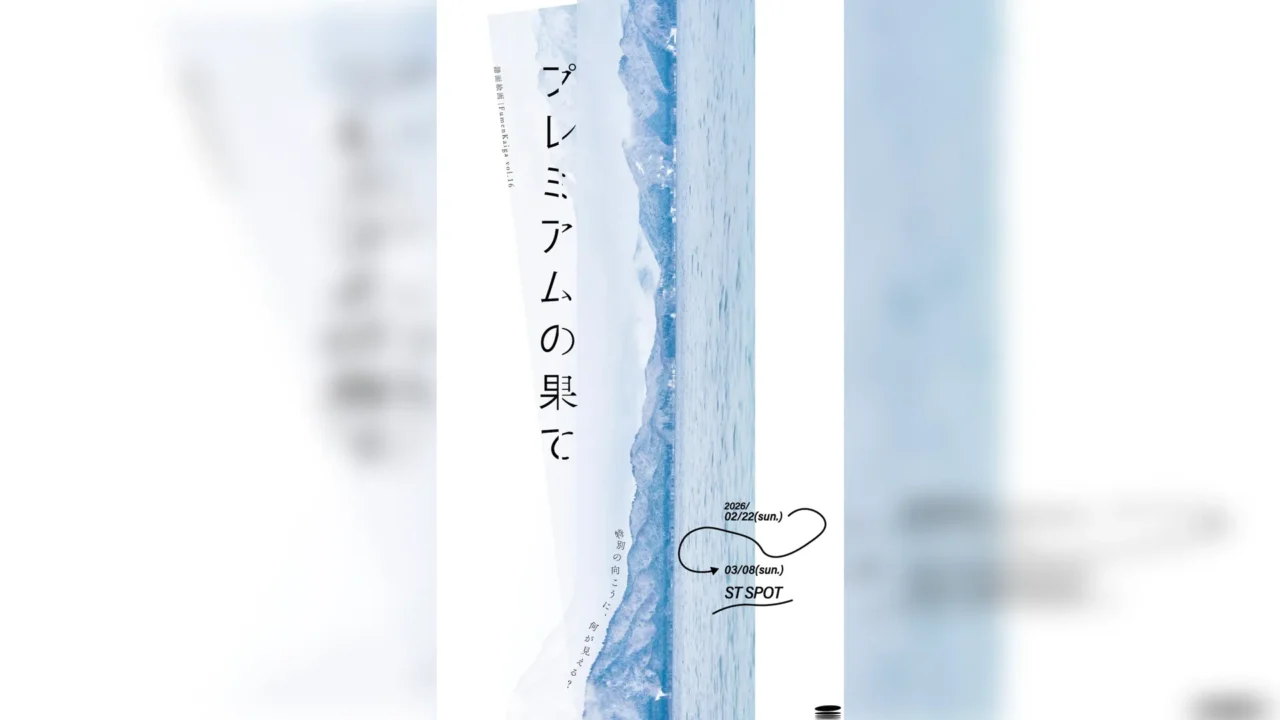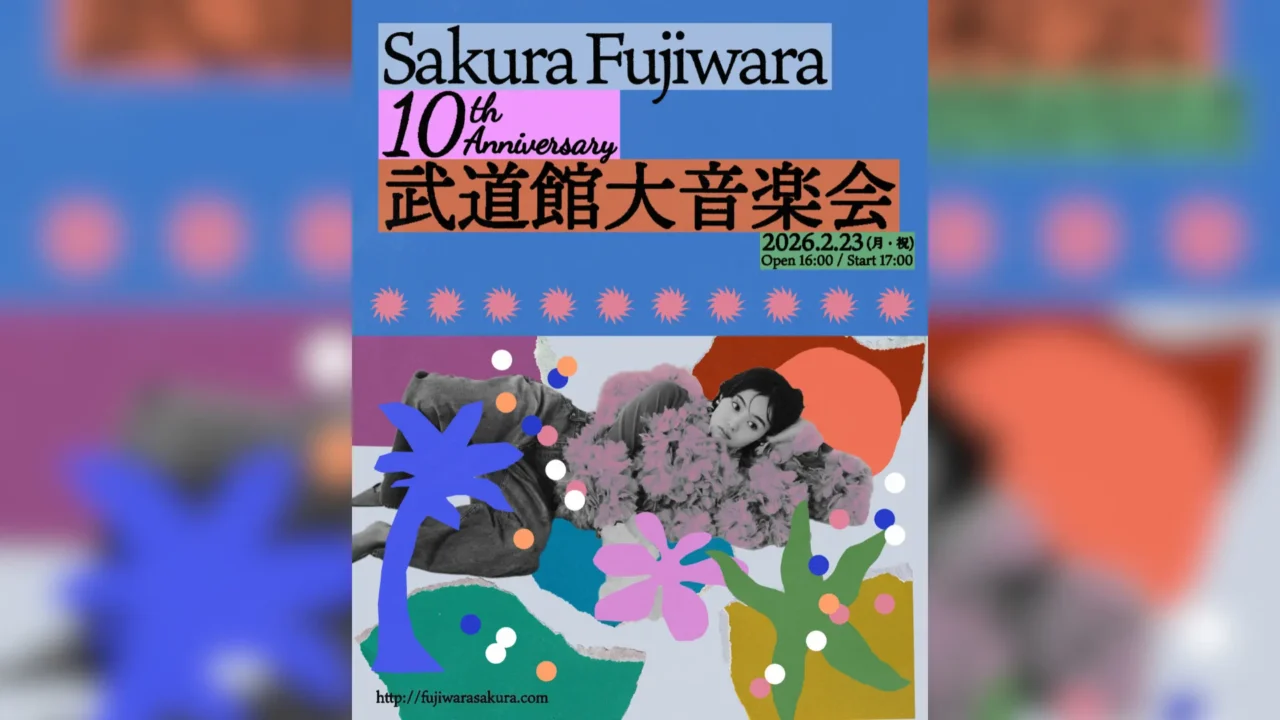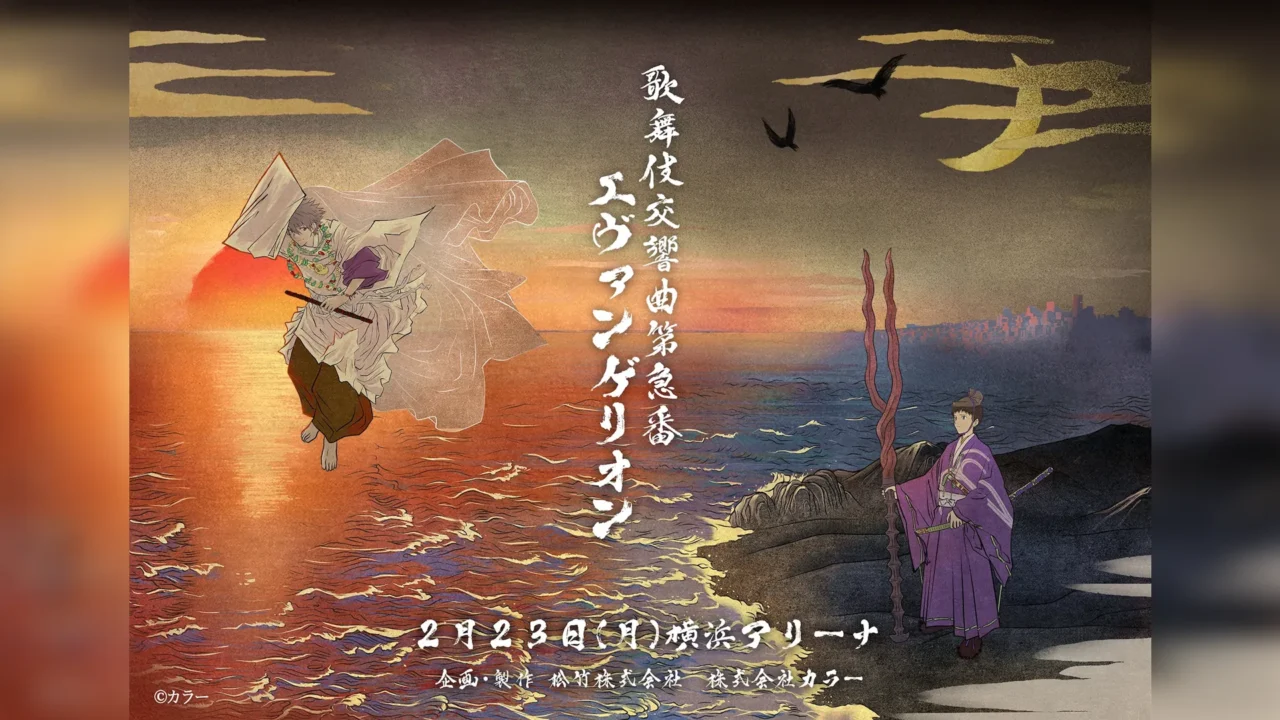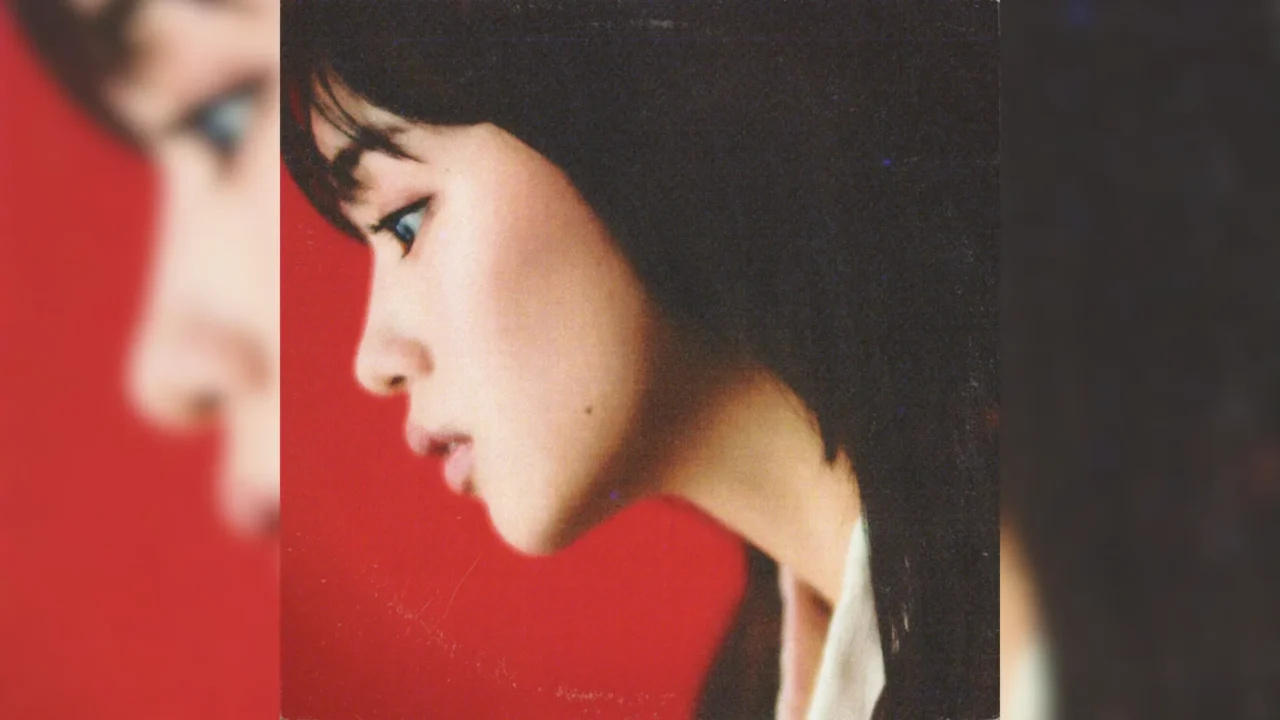8月8日(金)より『ジュラシック・ワールド/復活の大地』が公開中だ。
シリーズの第1作は、マイケル・クライトンの同名小説を原作とし、スティーヴン・スピルバーグが監督した1993年の『ジュラシック・パーク』。エンターテインメントとしての完成度もさることながら、「恐竜が本当にいる」とさえ思える革新的なCG表現は、映画史の大きな転換点となった。
第7作目となる今回の印象は、これまでのシリーズの「いいとこどり」、特に第1作の魅力をストレートに打ち出した「原点回帰」的な作品だ。同時に、いい意味で「無邪気」という印象も強い。何しろ、もはや「陸・海・空を制覇する恐竜すごろく」的な楽しさでいっぱいだったからだ。その理由を説明しよう。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
ギャレス監督の恐竜愛、スピルバーグ愛がたっぷり
今回の最大のトピックは、やはりギャレス・エドワーズ監督作品ということ。ギャレス監督は日本の怪獣映画『ゴジラ』シリーズの大ファンで、出世作となった2010年の『モンスターズ/地球外生命体』からして怪獣映画である。そして2014年にはハリウッド版『GODZILLAゴジラ』も手がけた、いわば「怪獣オタク」だ。フィクションの怪獣を愛する作家が、今度は実際に存在していた恐竜を題材に「巨大な生物への畏怖」を描くという時点で、この企画との相性は抜群だとわかる。
さらに重要なのは、ギャレス監督が初代『ジュラシック・パーク』とスピルバーグ監督そのもののファンであるということ。実は、ギャレス監督は2023年のSF映画『ザ・クリエイター/創造者』を完成させて心身ともに燃え尽きていたため、本作のオファーを受けた際も「まだ見ぬ脚本が断る言い訳になれば」と願っていたそうだ。しかし、脚本を読むと「スピルバーグ映画の数々に対する郷愁の念が、慎ましいラヴレターのようにそこにあった」「好きになりたくなかったのに」「まったくもう」「どうせやりたくなると自分でわかっていましたよ」と思ったのだという。
ギャレス監督の愛情は、もはや「オタクの早口」だ。プレス資料から丸ごと引用しよう。
特殊任務もの、転じてサバイバルものでしょ。その過程でどんどん変化球が投げられる。探求と冒険の旅路が、家族にまつわる感動の物語と絶妙なバランスで交錯して、陸・海・空それぞれを舞台に明確に異なる章で成り立っている。その一つ一つがハラハラドキドキするアトラクションのような短編物語で、それらがやがてジェットコースター並みに壮大な一つのストーリーに流れ着く。『ジョーズ』みたいかと思いきや『インディ・ジョーンズ』的。はたまたその中間も。それでいて、まるでデヴィッド・アッテンボローの映画のように、自然の雄大さを享受する。白状すると、脚本を読みながら、『ジュラシック・パーク』でTレックスが襲ってくるシーンに匹敵するほどスクリーン映えして緊迫感もあるシーンを撮れるチャンスが一つでもあるのなら、引き受けてもいいと、なんとなく思っていました。ところが、デヴィッド(・コープ)の脚本にはそういうチャンスがいくつもあったので、それを片っ端から描きたくてたまらなくなったわけです
プレス資料より引用
また、ギャレス監督は「僕の映画はほとんど、自分なりの『ジュラシック・パーク』を作ろうという密かな試み。それがあからさまな作品もなかにはありますしね」とも語っている。確かに『モンスターズ/地球外生命体』の狭い空間での攻防や、『ザ・クリエイター/創造者』での子どもと大人の危険な旅路など、振り返ってみればギャレス監督作には『ジュラシック・パーク』を彷彿とさせるポイントがいくつもある。今回はもともと用意された脚本のおかげもあって、「遠慮なく『ジュラシック・パーク』を全部やる」内容になった作品だと言える。
2014年の『GODZILLAゴジラ』は賛否が大きく分かれた作品だったが、「ゴジラが現れる場面」の演出は高く評価されている。今回も、恐竜が登場するその演出に、身震いするほどの恐怖と感動があるので、ギャレス監督のファンは楽しみにしてほしい。