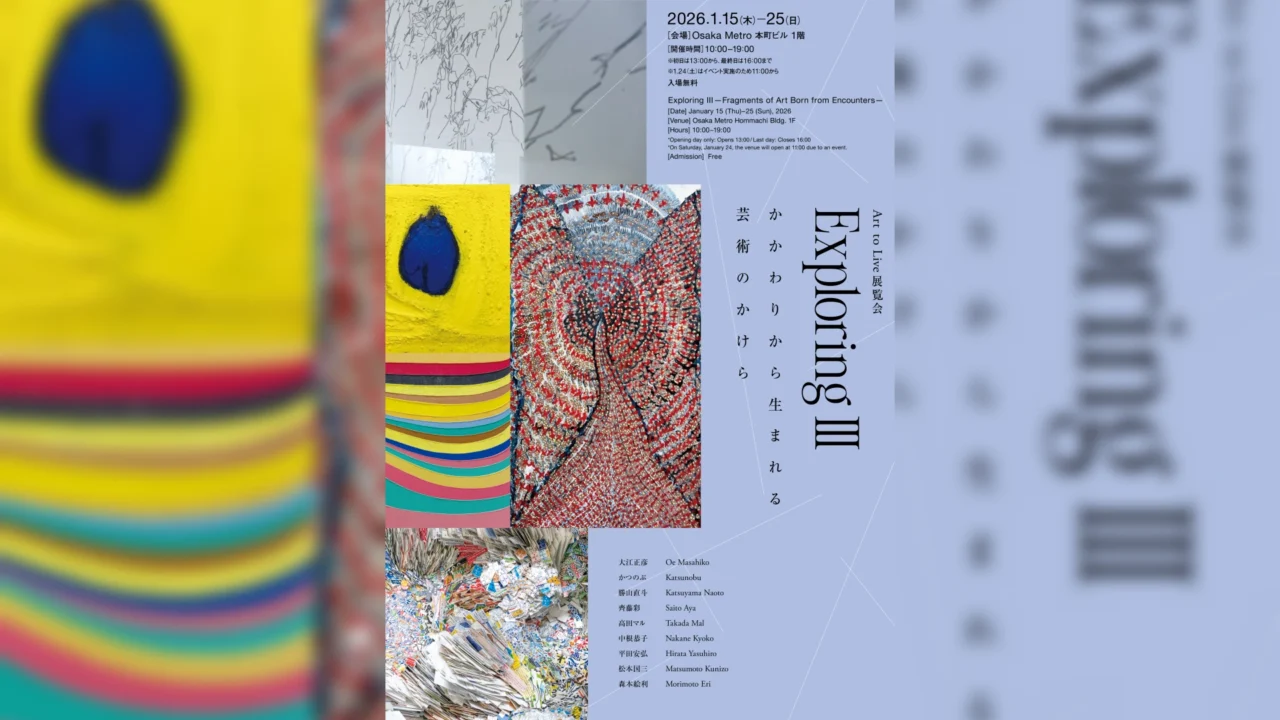ある日、いつものようにInstagramのショート動画を徘徊していると、ひとつの動画が目に入った。4人のミュージシャンが古民家で車座になって演奏をしていて、ドラムンベースのトラックの上で坊主頭のボーカリストが柔らかい歌声を聴かせている。その歌声は懐かしさと同時に、他にはない新鮮さも感じさせる。それがHUGENの“MAYA”という曲との出会いだった。
HUGENはかつてプロデューサーとしてオルタナティブR&B的なアーバンポップを作っていたTPが中心となり、2024年に結成された。2025年5月にリリースされた初EP『祭』で奏でられているのは、日本の土着的感覚もナチュラルに表現された現代のフォークロアポップだ。TPのインタビューを交えながら、来たるべき「東京の音」について考えてみたい。
INDEX
HUGENは「2020年代の東京の音」を奏でるグループ
現代は国境を超えてあらゆる人とモノが行き交うグローバリゼーションの時代である。無数の情報が飛び交うなかで文化やライフスタイルの均質化が進み、ポップミュージックのあり方も大きく変容してきた。国を超えたコラボレーションが推し進められることでグローバルなポップミュージックが(ビジネス的にも音楽文化的にも)大きく発展する一方で、地域ごとの個性が薄れ、地域アイデンティティーが見えにくくなりつつあるとも言える。
音楽社会史の研究者である東谷護は「21世紀になると、ポピュラー音楽文化を検討する際にインターネット等の音楽配信を無視することは出来なくなった。インターネットの技術は、場所(place)に縛られていた多種多様な音楽を空間(space)に瞬時に解放できるようになった」(『学術の動向 23巻』所収、「ポピュラー音楽とグローバル化」)としている。かつては場所(place)に縛られていた多種多様な音楽が空間(space)に解放される現代、「東京の音」とはどのような形をしているのだろうか。
グローバリゼーション時代のポップミュージックのあり方から強い影響を受けつつ、東京という場所(place)の音楽を掴み取ろうとしているHUGENはまさに「2020年代の東京の音」を奏でるグループである。彼らの音楽は時に民謡や祭りのリズムにアプローチし、「都市の民族音楽」という形を取ることもあれば、都市生活者としての実感や生活感覚が色濃く反映されることもある。グローバルなポップミュージックや現行エレクトロニックミュージックを下敷きにしつつも、個人的な感覚や思考までもが均質化されることを拒むその音には、現代の東京の「リアル」があるとも言えるだろう。

2024年始動。VoのTPを中心に構成された音楽プロジェクト。エレクトロミュージックを基軸に、民族音楽や民謡などを掛け合わせたオルタナティブな楽曲を展開する。結成1年目にして、りんご音楽祭、TAMARIBA FESTIVAL、TAMATAMA FESTIVAL等、様々な音楽フェスに出演。また、NHK Eテレドラマ「聞けなかった あのこと」にて寺尾紗穂と共作で主題歌を担当。精力的に活動を展開している。
INDEX
匿名でポップスをやっていたCity Your City時代
TPの出身地は敦賀湾に面した福井県南西部の敦賀市。
TP:歩いて2、3分で海に行けるような場所で、家の中でもいつも潮の匂いがするようなところで育ちました。友達から歌がうまいって言われていたし、音楽をやろうと思って高校卒業後に上京しました。RADWIMPSが好きで、当時は野田洋次郎になりたかったんですよ(笑)。

やがてビートミュージックやアンダーグラウンドなエレクトロニックミュージックに傾倒。2015年にはボーカルのK-OverとCity Your Cityというユニットを結成し、オルタナティブR&Bの雰囲気もあるポップなビートミュージックを作るようになる。
TP:大宮のヒソミネっていうライブハウスの店長をやってて、そこでひとりでライブをやり出すんです。当時はTPSOUNDという名義で、HUGENの原型みたいなことをやっていました。そんなころ、術ノ穴のレーベルオーナーであるKussyさんに声をかけてもらい、ボーカルのK-OverとCity Your Cityを始めるんですよ。術ノ穴はもともと埼玉拠点のアンダーグラウンドヒップホップレーベルという感じだったけど、泉まくらさんとかDOTAMAさんが出てきて、少しサブカル寄りになってたんですよね。なので、City Your Cityではあえてポップスをやろうと。
City Your Cityが奏でていたのは、ビートミュージックとポップスが交差する2010年代の東京のアンダーグラウンドシーンならではの音でもあった。当時のTPはアーティスト写真でも自身の顔を出すことなく、インタビューでも自身のルーツをまったく語っていない。いわばDaft Punk的な匿名的ユニットであった。City Your Cityは2017年にファーストアルバム『N/S』をリリース。にわかに注目を集めるものの、やがて活動を休止する。
INDEX
「アーティストと呼ばれたい」という承認要求が原動力
City Your Cityの活動休止以降、TPはいくつかのプロジェクトにプロデューサーとして関わる一方、CM音楽の仕事に携わるように。そうしたプロジェクトもコロナ禍で一区切りつき、沸き起こってきたのが「自分の表現を認めてほしいという承認要求みたいな感覚」だったという。
TP:当時周りの人たちからはプロデューサーやCM音楽の人と思われていたけれど、東京に出てきた当時の「アーティストと呼ばれたい」という思いが蘇ってきちゃって。自分は片親だったんで、子供のころから親に認められない寂しさがあったんです。だから承認要求がちょっと高めなのかも。

2022年12月には本名である北野哲平名義で“パン”を配信リリース。当初はTPひとりで地道なライブ活動を行なっていたが、やがてHamachi(パーカッション)、久津間俊平(ベース)、谷崎健太(サックス)が加わり現在の編成に。TPがサンプラーでビートを出し、Hamachiが打楽器類とサンプリングパッドを叩くという現在のライブのスタイルに行き着く。その経緯をTPはこう話す。
TP:最初はジェイムス・ブレイクのイメージがあったから、サンプリングパッドだけ叩いてもらおうと思っていたんですよ。でも、やっていくうちにやっぱり生楽器を叩いてもらったほうがおもしろいような気がしてきて。今は生楽器のグルーヴを中心にしつつ、両方やってもらっています。ビートがあまり前に出ると他の楽器に対して支配的になっちゃうので、ハマちゃん(Hamachi)やベースの久津間(俊平)くんにはできるだけ自由にやってもらっていますね。サックスの谷崎(健太)くんも基本的に即興ですし。
INDEX
幼少期の想い出や歌い方、HUGENとして出したいのは「そのまま」
HUGENというユニットは、自分がどこからやってきたのか表現したい。「ルーツ」に対するそんな思いは、あくまでも匿名的なユニットであったCity Your City時代にはないものだった。

HUGENとして最初に作られた楽曲が、疾走感あふれるドラムンベースのトラックの上にTPの歌がふわりと乗った“MAYA”だ。この曲は生まれたばかりのTPの子供をテーマにしており、グループのスタートと新しい生命の誕生が同じタイミングであることに必然を感じさせる。ポジティブなエネルギーに満ち溢れた“MAYA”は、いわば命を賛美する歌でもあるのだろう。
TP:娘が生まれた日はまだコロナ禍だったので、出産の日は僕ひとりで家に帰らなきゃいけなかったんですよ。何か無性に曲を作りたくなって、その日中に歌詞を書いてインスタに動画をアップしました。子供が生まれるというのは自分にとってすごくメモリアルなことで、何か残さなきゃと思ったんでしょうね。この曲も大それたメッセージがあるわけではなくて、娘のことは好きだし、会いたいし、それをそのまま歌おうと。

その後リリースされた初EP『祭』は、祭り囃子を思わせるビートが敷かれた“桜源郷”で幕を開ける。City Your Cityでは匿名性の高いポップミュージックをやっていたTPが、HUGENで土着的なエッセンスに向き合うのはなぜなのだろうか。
TP:もともと祭りっぽいビートが好きで、いつかやりたいと思ってたんですよ。でも、エレクトロニックミュージックで「和」を取り入れたものって日本的すぎるものが多いイメージがあって。海外から見た和のイメージが過剰に意識されているものというか、企画ものっぽい感じというか。それはそれで好きなんですけど、自分がやるならばそういうものじゃないほうがいいと思っていて。そんなときに“桜源郷”のトラックができたんです。
TP:“桜源郷”は曲調も夢の国っぽい感じだし、『千と千尋の神隠し』みたいな世界観にしようと思って、ああいう歌詞になりました。実家の近くに海津大崎(滋賀県高島市)という場所があるんですけど、そこは桜の名所なんですね。父ちゃんと一緒に車で行ったことがあったので、そこをイメージして『桃』ではなく『桜』にしました。
“桜源郷”の朗々としたTPの歌唱にはどこか民謡的な香りも漂うが、その理由はこんなところにもあるようだ。
TP:僕のことを育ててくれたじいちゃんが詩吟をやってたんですよ。家ではテレビのチャンネル権がじいちゃんにあって、3時間の演歌番組を見せられていました(笑)。その影響なのか、昔から僕が歌うとコブシがよく回るところが演歌みたいだと言われていましたね。自分ではジェイムス・ブレイクみたいなことをやりたいのに(笑)。でも、今となってはそれもありだなと思えるようになりました。