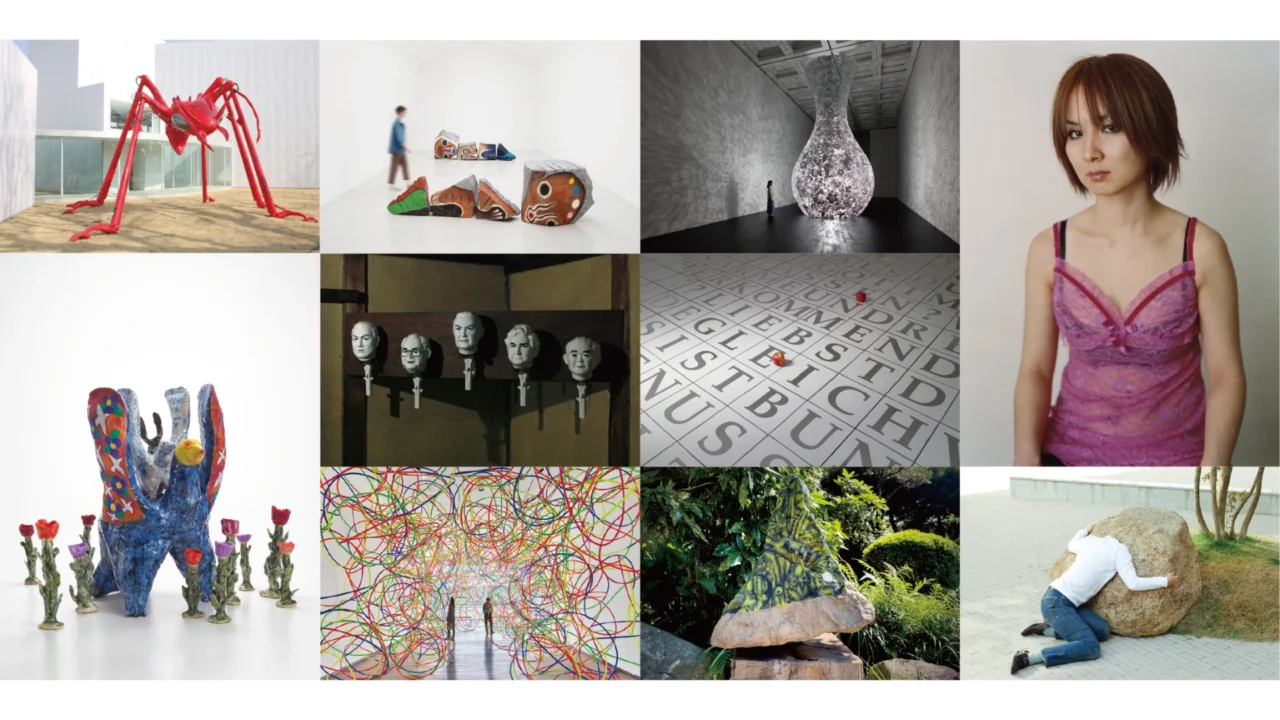『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『フォレスト・ガンプ/一期一会』から、『マリアンヌ』『マーウェン』まで、数々の優れた作品を残す名匠ロバート・ゼメキス。その最新作がリチャード・マグワイアのグラフィック・ノベルを映画化した『HERE 時を越えて』だ。
今回、長くゼメキス作品を鑑賞し続けてきた映画研究者・評論家の南波克行に本作の魅力を綴ってもらった。それは本作だけでなく、過去に南波がゼメキス作品に触れてきた記憶の数々の堆積にもなっていくだろう。
※本記事には映画の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
壮大な時空の堆積が形作る、ちっぽけな私
ロバート・ゼメキス監督が描く、時間軸のスケールはケタ外れだ。何しろ『HERE 時を越えて』は、最初から最後まで同じ場所にカメラを置いたまま、地球の起源から現代までを見せるのだ。一方、語られる物語はとても小さくて、ある家族の物語。それも大家族の一代サーガといった壮大なドラマではなく、結婚や出産、記念日のお祝いや、子どもの成長、両親との死別など、誰にでも訪れる生活の一断面ばかりだ。

『コンタクト』(1997)の冒頭でも、実に宇宙の果てまでの壮大な時空間が、一気にワンショットで示され、それがすべてヒロインの瞳の中へと収斂する。この驚くべき導入が伝えるのは、天文学的な時空の中ではちっぽけな「私」であっても、数十億年、数億光年もの時空の堆積が、「私」を形作っているということだ。だからこそその作品は時空を越えて、運命を切り拓く。
ゼメキス最大の人気作、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)では、未来の自分が過去を救い、救った過去が現在の自分を救う。そして救った過去と現在の先には、真っ白の未来が待っている。『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』(1990)の最後に、ドク(クリストファー・ロイド)がマーティ(マイケル・J・フォックス)に贈る、「未来はまだ白紙だ」という言葉がすべてを表している。そして「それは自分で作るのだ」と。
INDEX
ゼメキス作品が表す、過去から現在までの「一本道」
その最初の一歩を踏み出す瞬間、ゼメキスの映画はいちばん高揚する。冒険の列車に乗るのをためらう『ポーラー・エクスプレス』(2004)の主人公が、勇気をもって乗車すると、少年は車掌(トム・ハンクス)から「Learn(学び)」と書かれた切符を受け取る。未来を切り開く学びの旅だ。
今はなきニューヨークのツインタワーにロープを張り、決死の綱渡りを試みる『ザ・ウォーク』(2015)の主人公(ジョセフ・ゴードン=レヴィット)が、綱渡りをマスターするため、最初の一歩を踏み出す感動は格別だ。
歩きやすいよう、最初は4本のロープを横に束ねて足元を支えていたところ、上達するにつれ1本ずつ消えていき、やがて1本のロープの上を歩けるようになる。白紙の未来を書きこむことは、同時に現在を過去へと送り出すことでもあり、それを消えていくロープで表現していた。そして、彼が歩くまっすぐ伸びた1本のロープは、今後の人生の道を示すかのようでもあった。
『マリアンヌ』(2016)が描いた運命のカップル(ブラッド・ピットとマリオン・コティヤール)も未来を開くため、戦時はスパイだった互いの過去を消し去る必要があった。一方、そうした過去がすべて嘘の上に成り立っているとしたら? 『ホワット・ライズ・ビニース』(2000)の、外見上は理想的な夫婦(ハリソン・フォードとミシェル・ファイファー)は、その疑惑で未来に暗雲がたちこめる。
このときゼメキス作品には、「嘘はつき通せば真実になるのか」というテーマが持ち上がる。飛行士である『フライト』(2012)の主人公(デンゼル・ワシントン)は、飛行中に大事故に見舞われるが、天才的な操縦技術で被害を最小限におさえ、一躍ヒーローになる。しかしアルコールと薬物依存の疑惑が持ち上がる。英雄か犯罪者か。嘘と真実の狭間で、彼は何を選択するのか。
どの作品でもゼメキスは、その人物がどんな過去を経て、現在に至ったかの因果をしっかり描く。その因果とは誰の人生にも何度か訪れる選択の瞬間、運命の分かれ道だ。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』では、やがてドクは殺されることを、あらかじめ教えるか否かをマーティは悩む。ディケンズの古典をCGアニメ化した『Disney’s クリスマス・キャロル』(2009)は、主人公の選択が周りにどんな影響を与えたかを、再現する物語だった。右に行くか左に行くか、両方は選べないから人の道は一本なのであり、ゼメキス作品に頻出する、画面の向こうへとまっすぐ伸びた一本道はその象徴だ。
『ロジャー・ラビット』(1988)のラストでは、キャラ全員が手に手を取って、多幸感たっぷりに一本道を歩いていく。『キャスト・アウェイ』(2000)でも、無人島で失った過去を再び生き直せと言わんばかりに、失った時間に匹敵するほど長い道が伸びていた。
INDEX
ゼメキス作品の特筆が集約された最新作『HERE 時を越えて』
『HERE 時を越えて』はそんなゼメキスの特質が、集約されている。原作はリチャード・マグワイアのグラフィック・ノベル『HERE』(リチャード・マグワイア著, 大久保譲訳 / 2016 / 国書刊行会)。この本にゼメキスが関心を寄せたことは、彼の持ち味としていかにもだが、本人は製作の動機を「数百年前に建てられた家に泊まった時、石の壁を見ながら、いったい何人が私の座っているこの場所を通り過ぎていったのだろうと考えた」と述べている。家屋を石で造る文化のない日本人には、築100年を超す住まいはイメージしにくいが、永い時間への感性はむしろなじむのではないか。

中心はリチャード(トム・ハンクス)とマーガレット(ロビン・ライト)の夫婦の物語。HERE(ここ)に置かれたカメラは、地球創生から生命の誕生、巨大生物の滅亡を経て、人類が生まれて家が建ち、その持ち主の代替わりも見つめている。その移り変わりは、スクリーンの中にもうひとつのスクリーンが開き、次々と窓を開くように描かれる。
そこに描かれる風景は、なんとも知れず胸を打つ。それはそこに描かれる風景が、誰もが身につまされるものだからか。各エピソードを支える過去の堆積。その重さがこの映画を深く切なく、しかも温かいものにしている。

決定的なシーンがある。マーガレット50歳の誕生パーティ。大勢の友人を集め、リチャードが準備したケーキを前に、最初ははしゃいでいた彼女だったが、いつしか泣き崩れてしまう。「私は何も成し遂げていない。こんな人生はもういやなの」と。
願いをこめて吹き消すケーキのロウソクも、何本か残ってしまう。白紙だったはずの未来も、どんどん過去として塗りつぶされていく。それも自分が望まなかった形で。

リチャードの口癖は「光陰矢の如し」。時の速さに、ポジティブな気持ちも少しずつ色あせる。それが老いというもので、過ぎゆく毎日をそのまま受け入れることが、彼の時間との向き合い方だ。彼の選択は、幸福のための諦念なのだ。そしてそれは彼の父から受け継ぐ考え方でもあった。
あらすじ:太古の時代から現代まで時間が経過する中、ある空間が映され続ける。やがて一件の家が建ち、様々な人々が入れ替わり、暮らす。そして1945年、アルとローズ夫妻が購入し、息子リチャードが誕生。絵が得意なリチャード(トム・ハンクス)は、激動の時代にアーティストを夢見るようになる。高校生で出会った弁護士志望のマーガレット(ロビン・ライト)と恋に落ち、2人の人生が始まる。