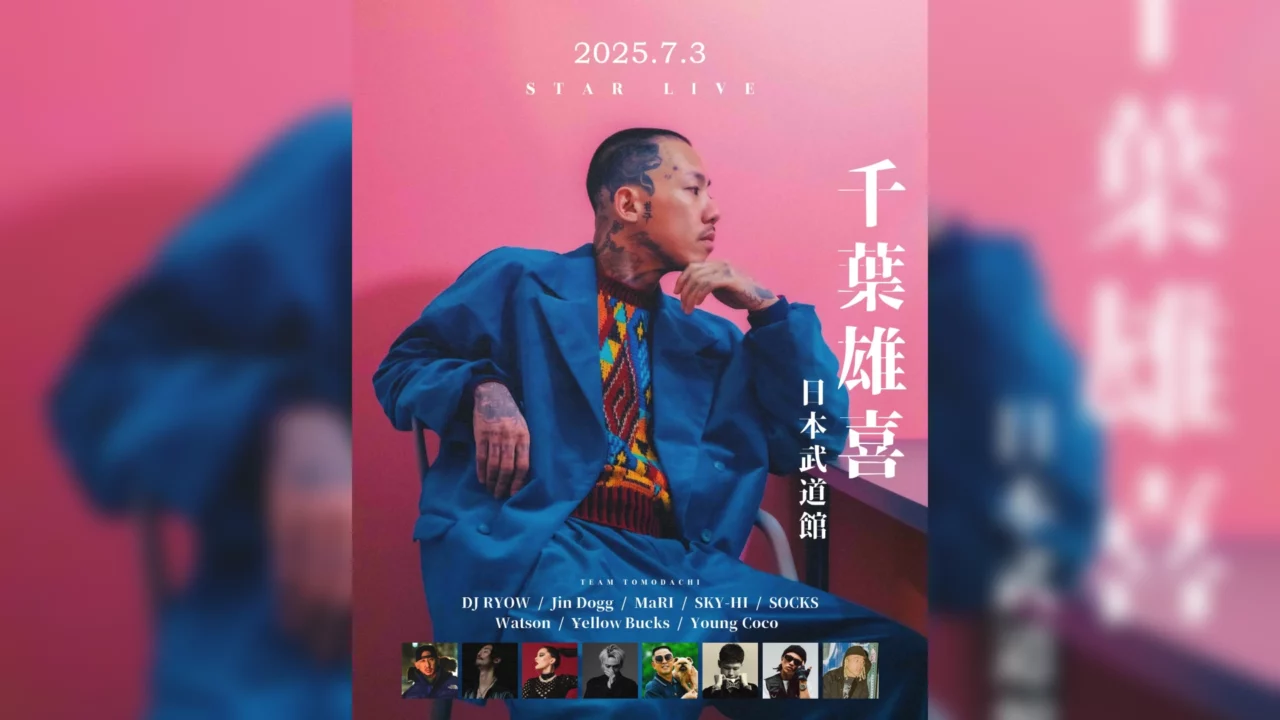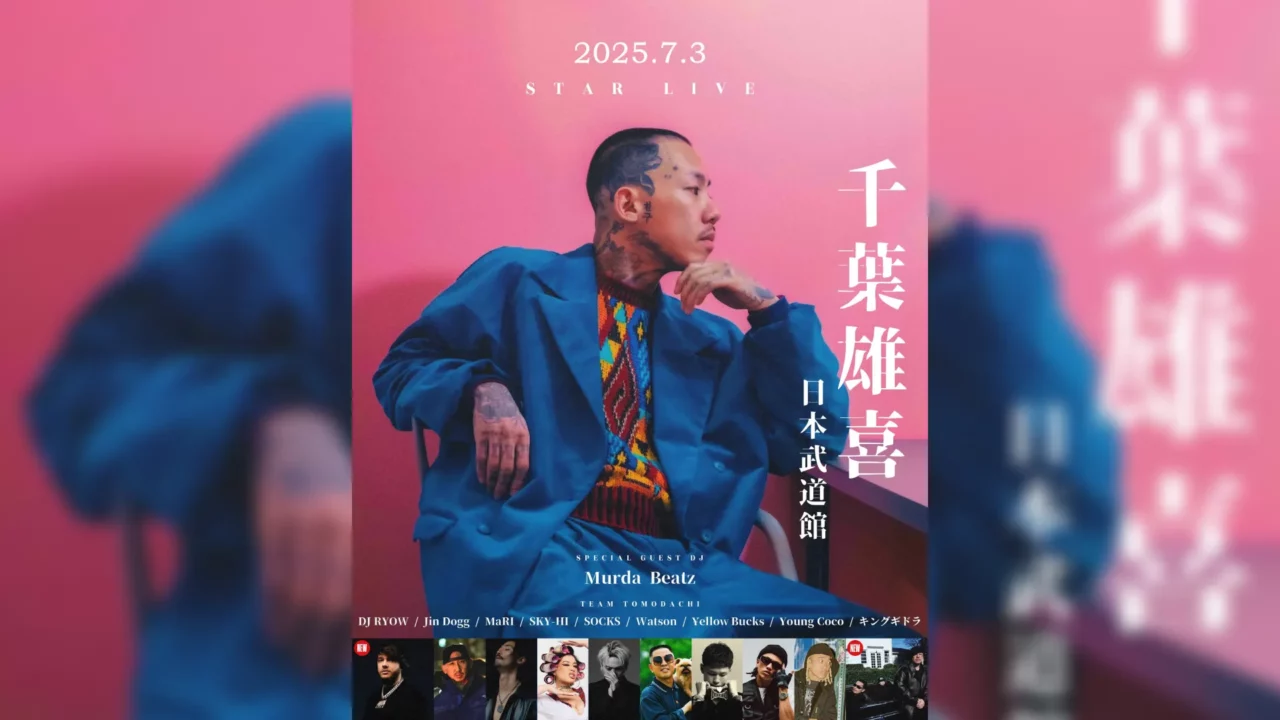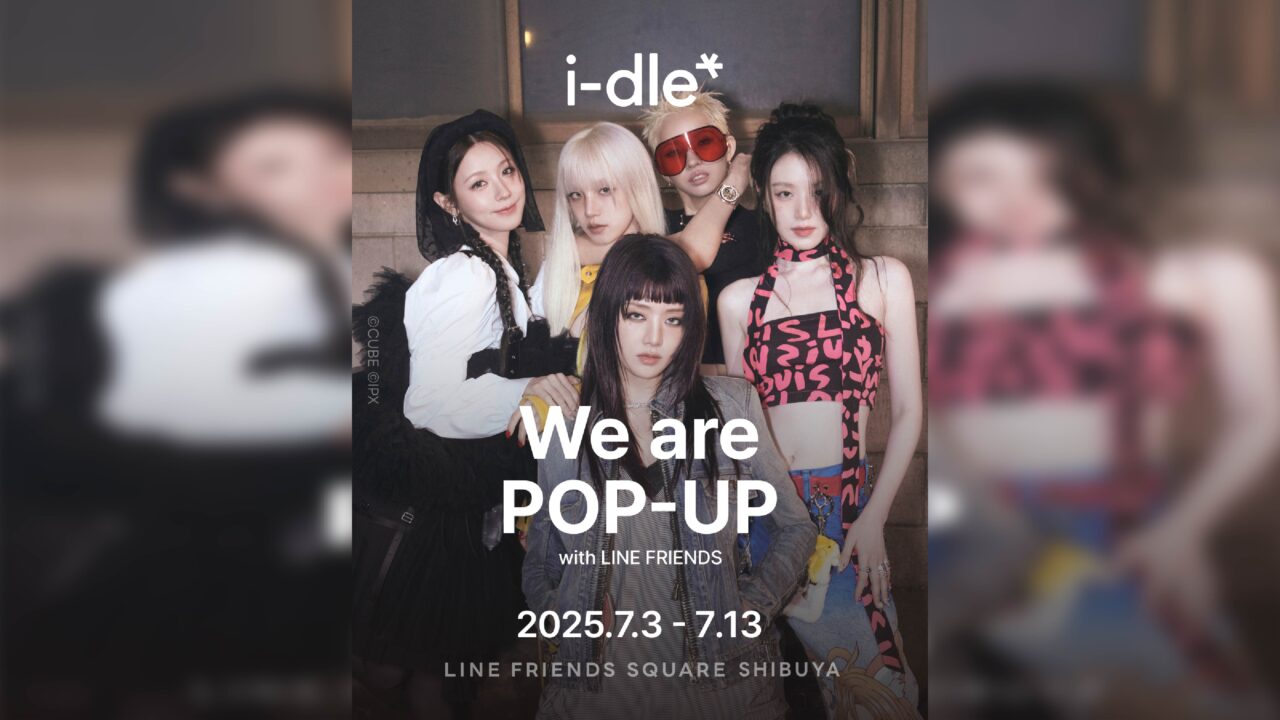グータッチでつなぐ友達の輪! ラジオ番組『GRAND MARQUEE』のコーナー「FIST BUMP」は、東京で生きる、東京を楽しむ人たちがリレー形式で登場します。
12月17日は、お粥研究家の鈴木かゆさんからの紹介で、「東京ディープチャイナ研究会」代表の中村正人さんが登場。21世紀の現代中華料理「ガチ中華」の魅力や、情報発信やイベントをするようになったきっかけ、料理だけではない中国カルチャーについて伺いました。
INDEX
21世紀の現代中華料理「ガチ中華」を研究
タカノ(MC):「東京ディープチャイナ研究会」では、町中華ならぬガチ中華を研究されていると伺ったのですが、ガチ中華とは一体何なんでしょうか?
中村:研究というほど大層なことではないんですが、ガチ中華って一言で言うと、21世紀の現代中華料理なんです。中国の経済が発展したことによって、上海とか北京といった都会だけではなくて、雲南省とか湖南省とか、そういう地方の料理もどんどん豊かになって、新しい料理が生まれてきたんです。そういった料理を中国に行かずに、東京で食べられる時代が7、8年前から始まっているんです。
長井(MC):とても気になります。
中村:なぜ東京で食べられるようになったかというと、中国に限らず台湾とか東南アジアとか、いわゆる中国語圏の若者が留学だったり働くために、東京を中心にやってきたからです。彼らが顧客になったから、彼らが満足する料理を出す店がどっと増えました。今は首都圏でおそらく1000軒ぐらいあります。
タカノ:そんなにあるんですか! ということは、日本人向けではないってことなんですね。
中村:そうです。もともと日本人向けの中華って日本人の口に合わせてローカライズされているんですが、ガチ中華は、海外から来た人たちの口に合わせているので、僕らが知らない未知な料理がすごく沢山あるんです。
長井:だからガチ中華なんですね。
中村:そうですね。
長井:この「東京ディープチャイナ研究会」は、具体的にどんな活動をされているんですか?
中村:基本的にはガチ中華の店が増えてきたので、それを実際にみんなで食べたり、情報交換したりしています。SNSでゆるく繋がったコミュニティで、みんなが「今日こんなものを食べたよ」というのを投稿したり、「ここのお店いいから食事会やろう」と提案したり、100人ぐらい集めてイベントをしたり、ガチ中華まち歩きツアーをやったり、色んなことをやっています。
タカノ:なるほど。ガチ中華ってどこから始まったんですか?
中村:東京の中でお店が一番多いと言われているのは池袋とか上野とか、あと高田馬場ですね。池袋は2000年前後ぐらいからガチ中華のお店が始まっているので、最初にガチ中華ができ始めた場所なんです。
長井:なぜ池袋がガチ中華の聖地になったのでしょうか?
中村:1980年代の後半ぐらいから、日本に中国系の人たちが来始めているんですけど、そこからの歴史があるんです。詳細は「Forbes JAPAN」というサイトで記事を書いているので、そこを読んでいただければと思います。
タカノ:高田馬場とかは、言われてみれば留学生が多いですね。
中村:そうなんです。日本語学校があるので中国の留学生が多くて、今の中国の方たちは経済力もあるし、新しいお店ができるんですよね。