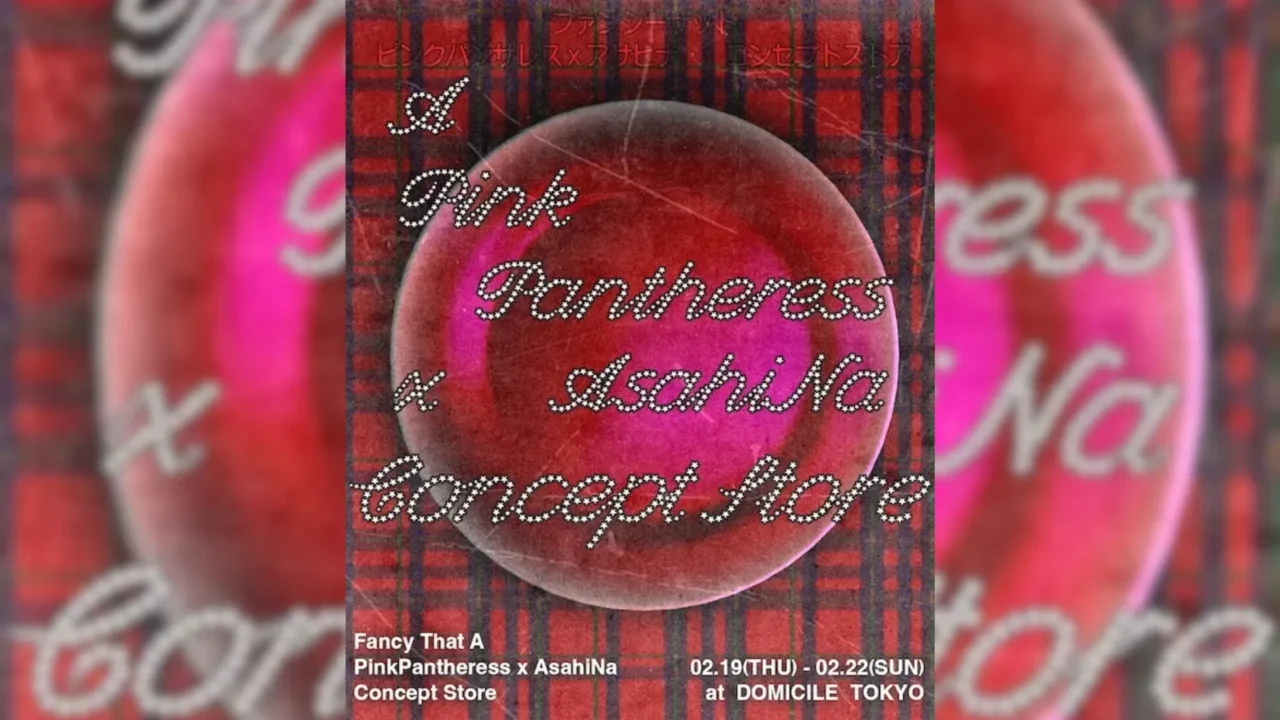グータッチでつなぐ友達の輪! ラジオ番組『GRAND MARQUEE』のコーナー「FIST BUMP」は、東京で生きる、東京を楽しむ人たちがリレー形式で登場します。
9月5日は、建築家の菅原大輔さんが出演。今回は、建築だけでなく街作りにも取り組む菅原さんに、街作りのプロジェクトの内容やその魅力、ご自身のもの作りの原点などについて伺いました。
INDEX
自分の寿命よりも長いものをデザインしているというのが仕事の醍醐味
Celeina(MC):昨日のレンガ職人の高山登志彦さんからのご紹介で、建築家の菅原大輔さんです。よろしくお願いします。
菅原:菅原です、よろしくお願いします。
Celeina:まずプロフィールをご紹介させていただきます。菅原大輔さんは、1977年東京都生まれです。日本やフランスの建築事務所で、10カ国22都市のプロジェクトを担当し、2007年に菅原大輔建築事務所を設立。ルイ・ヴィトンから地域活性まで多岐にわたり活動されています。
タカノ(MC):世界で活躍されて、お忙しい中だと思うんですけれども。
菅原:これだけ聞くとそんな感じですけど、普通のお兄さんです。
Celeina:いやいや。
タカノ:でもすごく親近感のある感じで、お話ししやすい空気を感じております。そんな菅原さんなんですけれども、昨日の高山さんから「接着剤のような役割を果たす人」という、すごく良いワードをいただきまして。これは人を繋ぎ合わせるプロジェクトというイメージなんですかね。
菅原:そうですね、何かすごいお題をいただいたので、どうやって話そうかなと思ったんですけど、多分言ってくださっているのは、僕の街作りのことかなと。僕は建築家ではあるんですけど、街作りの仕事を結構沢山やっていて、島根県とか山梨県の山中湖村、秋田県五城目町の3つぐらい、特に大きなものをやってるんですけど。
建物って使い方や使われる機能というのは大体決まっていたりするんですけど、街ってなると、そこに暮らしている皆さんの気持ちをくみ取ったりしないといけないんです。あとは、そこにある風景とか気候風土も違って特徴的だし、祭りを含めた歴史とか文化というものを繋ぎ合わせて、今後100年、200年、数千年の骨格を作っていくというのが街作りなので、その辺の繋ぐということを言ってくださったんじゃないかと自分なりには解釈してるんです。
タカノ:確かに街って、イコールと言っていいほど人と言いますか、そこに住む人たちのことを考えて、ということですもんね。
菅原:それこそね、街の中でも、そこに住まわれている皆さんは色んな考え方をお持ちだったり、色んな年代があるので、1個のことを決めていくことって結構難しいんです。それでも、街作りって道とか建物とかを最終的に1つに決めないといけないので、学術的な調査も当然並行してするんですけど、気持ちを色々話したり、一緒に飲んだり、祭りに参加したりしながら、どうやったら皆さんが繋がる一言のキーワードとか、街の形が見えるかな、というのをやっているかなと思っています。
タカノ:今されている3つのプロジェクトは、難しいかもしれないですけども、それぞれ簡単に言うと、どういったプロジェクトになるんですかね。
菅原:どれもめちゃくちゃ面白くて、喋り始めたら数時間喋っちゃうんですけど、簡単に言うとですね、島根県の隠岐の島町というのは、当然島なんで港があるんですけど、その港を中心に3万平米のエリアを10年間かけて、少しずつ対話を重ねながら街の方と作っていく。新しい交通ハブというか、商業とか交通の中心を作っていこうというプロジェクトです。
実は山中湖村のお祭りに昨日参加して、今日は車で帰ってきたところなんですけど、そこは逆に山の中なので、基本的にバス交通がその街の主要な交通なんです。そこでバス停とコミュニティセンターを合わせて開発しながら、その街をどうやって活性化させていくか、新しい回遊性を作っていくかみたいなことをやってます。
秋田の五城目町は、この間ちょっと雨の災害でも大変だった街なんですけど、333年も続く酒蔵がありまして、そこの蔵元の渡邉康衛さんがすごく志の強い方なんです。今、蔵の生産ラインを僕らが設計でお手伝いしてるんですが、その蔵の生産ラインを変えたときに余る蔵の敷地を開いて、街の活性の祭りの場とかイベントの場にしよう、というのも今やっています。3つとも共通するのは、何を作るかがまだ決まっていなくて、何を作るかから一緒に話しながら今作ってるっていうところです。そこはちょっと普通のプロジェクトとは違うかなと思いますね。
Celeina:なるほど。
タカノ:でも島根県の隠岐の島町とか10年っていう単位が出ましたけど、規模もそうですけど、時間的なスケール感もすごい。
菅原:そうなんですよ。それが建築とか街作りですごく面白いところで、僕らが死んでも100年200年その骨格は残っていくんですよね。自分の寿命よりも長いものをデザインしてるというのが、僕らの仕事の醍醐味なんですが、あいつは駄目だったなって何百年言われ続けないようにしないと、といつも不安に思うところもあります。
タカノ:菅原さんならではのプレッシャーというのもあるってことですよね。
菅原:そうですね。
タカノ:でもちょっと質問いいですか。例えば10年後とか20年後、更には100年後とかっていうことを想像しながら色々、言葉だったりとかを考えていくわけじゃないですか。どうやって、ヒントを得ていくんですか?
菅原:それもいつも悩むんですけど、1つは、街の方とめちゃくちゃ飲んだり出かけたり祭りに参加して、その地域の人になりきるというのは大事ですね。
タカノ:溶け込んで。
菅原:溶け込んでいくというのは大事なのと、あともう1個。100年、1000年の未来をどうやって見るかというと、実は逆に100年前1000年前のこの街では、どうやって人々が生活してきたのか、どういう動物が暮らしていたのか、どういう気候でどういう植物が育ってきたのかを知ると、昔から今までの変化が、実はこれからの未来の変化を予測することに繋がったりするんですよ。
タカノ:面白い。過去を知れば未来が。
菅原:ことわざみたいですけど、結構それは本質を突いてるなって最近仕事していてよく思いますね。
タカノ:でも場所もバラバラじゃないですか。移動がすごく大変そうだなと思うんですけど。
菅原:そうですね、それが大変なんですけど、僕は生まれが東京の浅草なんですけど、逆に都会の中で生まれてしまったから、いわゆる「郷土を感じるふるさと」というのがないんです。なので、色んな街で街作りしながら、自分にとって子どもみたいな感じというか、どんどん第2の故郷が増えていくようなことが楽しくて、旅は長距離大変ですけど、それなりに楽しくやっています。
Celeina:いいですね。
タカノ:素敵なお話。ちょっとまだまだお話を聞いていきたいんですけれども、ここで1曲挟みましょうかね。菅原さんにこの時間にラジオでみんなで聴きたい曲を選んでもらいました。どんな曲でしょうか。
菅原:まず昼間に皆さんに元気になってほしいなという思いと、ちょっと仕事に繋げて曲を選んでみました。
タカノ:では紹介お願いします。
菅原:Pharrell Williamsの”Happy”お願いします。
INDEX
様々なスケールを横断した活動がもの作りの原点
Celeina:菅原さんの選曲でPharrell Williamsの”Happy”をお送りしました。リスナーのみんなに元気になってもらいたいというお言葉もいただきましたが、お仕事ともかけてって先ほど仰ってましたけれども、これはどういった意味合いがあったんですか?
菅原:冒頭では街作りの話をしましたが、建築家としての仕事でルイ・ヴィトンさんのお仕事として、2回ほど東京のポップアップショップをやらせていただいたんです。Pharrell Williamsさんは歌手なのに、ルイ・ヴィトンのメンズのクリエイティブディレクターに就任したというのが、結構衝撃的だったんです。そういう意味も絡めながら、みんなにハッピーになってほしいなということで、今日はこの選曲をしました。
Celeina:いいですね。そしてルイ・ヴィトンのお仕事もされているということですけど、他にどういったお仕事をされてたりするんですか?
菅原:そうですね、本当に街スケールから小さいスケールまで色々やっているんですけど、本当に簡単に概要でいくと、最近は働き方がコロナ禍によって変わったので、「ワーキングヴィラ」というタイトルで、村のような高層のオフィスビルを作ろうというプロジェクトがあるんです。それで今、千駄ヶ谷の新宿御苑のすぐ近くにビルを2本設計していたり、逆に思いっきり小さいのでいくと、オフィス家具の設計をしています。
タカノ:本当に様々ですね。
菅原:いわゆる都市の大きい景観から、人の居心地自体をデザインするみたいに、スケールを横断した活動をしています。
タカノ:でもその視点だったり視座が切り替わったりしていくわけじゃないですか。混乱とかもありそうですけど、繋がってそうな気もしますよね。
菅原:街作りはキロメートル、家具作りはミリメートルのデザインになってくるんですけど、片方じゃなくて両方、さっきの接着剤じゃないですけど、全然違うものを繋げたときの方が、クリエイティブが発揮されるなと僕は思っていて。例えば小さいことを考えていた経験が街のキロメートルのことに生かされることもあるし、逆にキロメートルの大きい大枠の考えが、実はミリメートルの方向性を決めていくというのが結構あって、両方やっていることが、多分僕のもの作りの原点に繋がっているんじゃないかなというのは、最近なんとなく思っています。
INDEX
サーフィンでリフレッシュし、現代アートに刺激を受ける
Celeina:なるほど。でも本当にお忙しく、動き回られてるということですけど、時間の使い方とか、ご自身なりのリフレッシュ方法とか何かあったりするんですか?
菅原:そうですね、基本的にはいい仲間に支えられてるのは大前提なんですが、建物ってわりかし都心だったり集落の中にあるんですけど、趣味がサーフィンなので、切り替える時は自然の中に大没入して、全部忘れて、デジタルもデトックスするみたいな感じです。そういう時間は結構重要に考えていて、できるだけそういう機会を作るようにしますね。
Celeina:サーフィンいいですね。
菅原:はい。リフレッシュになりますね。
Celeina:ほかにも、アート鑑賞もご趣味だということで。最近ご覧になられた作品とかありますか?
菅原:僕、先ほど言ったように、違うものを繋げるということが好きで、そういう意味では現代アートがすごく好きなんです。現代アートは、特に新しい視点を見つけ出すみたいなところに共感していて、自然の偶然と人間が作った規則性が合わさっているというか、人間がちょっと介在しながら自然と一緒に作っていくみたいなアートを見に行くことが多いんです。最近は、東京都現代美術館で個展もされていた、ユージーン・スタジオというアーティストスタジオをされている寒川裕人さんの埼玉の方のアトリエに、友人の縁で10人ぐらいの仲間で伺わせてもらったんですけど、そこですごく刺激を受けたんです。例えば、一色に塗った紙があるんですけど、ちょっと置き方を変えて、太陽の光で退色させるスピードを変えることで、色にまだら差をつけて、それを絵画にしようみたいな。人間の作ったものと自然現象の偶然性とか劣化していくみたいなものをポジティブに捉えて、自然だけでも人間だけでもできない、2つ一緒にいないとできないみたいなことに大感動して帰ってきましたね。
Celeina:その考え方がちょっと建築にも繋がってるような感じもしますけれど。
菅原:そうですね。僕、錆びているような自宅に住んでるんですけど、実は鉄粉を混ぜた左官材で自宅をくるんであって、そこに流れる空気とか、風、雨の降り方、太陽のあり方で錆び方をまだらにさせているんです。ルールは僕が決めたんですけど、最終的には自然とか生活の汚れとかがついて、それ自体が外観を作っていくというのを自宅で実験的にやってみたりしています。
タカノ:いいですね。経年変化も楽しめるという。
Celeina:盛り沢山なお話ありがとうございます。「FIST BUMP」なんですけれど、グータッチで繋ぐ友達の輪ということでお友達をご紹介してもらってるんですが、菅原さんがご紹介してくださるのはどんな方ですか?
菅原:すごく面白い友人が沢山いるんでどなたにしようかなと思ったんですけど、その中で上條・福島都市設計事務所の上條さんと福島さんというお2人を今回ご紹介できればなと思っています。
Celeina:一言で表すなら。
菅原:一言で表すなら、「大地をデザインする若手のホープ」という感じですね。
タカノ:良いコピーですね。ありがとうございます。明日は上條・福島都市設計事務所の上條さんと福島さんに繋ぎます。
Celeina:FIST BUMP、今日は建築家の菅原大輔さんをお迎えしました。ありがとうございました。

GRAND MARQUEE

J-WAVE (81.3FM) Mon-Thu 16:00 – 18:50
ナビゲーター:タカノシンヤ、Celeina Ann