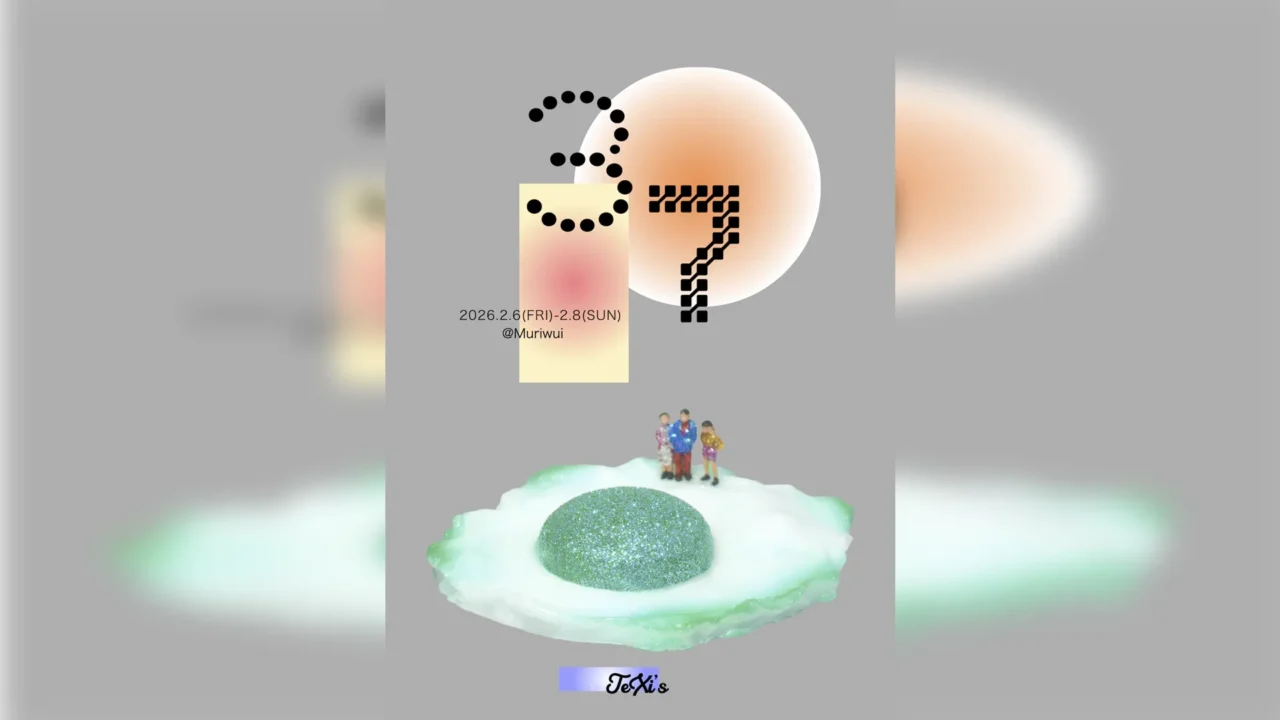コロナ禍の日本の小学校に1年間密着取材をした山崎エマ監督のドキュメンタリー映画『Instruments of a Beating Heart 心はずむ 楽器たち』が、米国アカデミー賞・短編ドキュメンタリー賞にノミネートされ、世界の注目を集めたことは記憶に新しい。馴染み深い小学校の風景は、ドキュメンタリーとなったことで世界への訴求力を発揮し、日本への理解を深めるきっかけになった。同じ取材を元にした山崎監督の長編ドキュメンタリー映画『小学校〜それは小さな社会〜』は全国にて大ヒット上映中で、さまざまなスタンスの人がいる教育というテーマでありながら、立場の違いを超えて人々の心を揺さぶり、結びつけている。
日本に眠っている、そんなドキュメンタリーの力を育もうと、この春、原宿を拠点に小さなフィルムスクールが立ち上がった。山崎監督も講師として参加するDDDD Film School。代表を務めるのは、LINEヤフーで映像ドキュメンタリーのプラットフォームを立ち上げ、日本最大級のショートドキュメンタリー配信の場に育て上げたプロデューサーの金川雄策だ。
アメリカでドキュメンタリー映画を学び、日本でも様々なドキュメンタリーの制作に携わってきた二人が仲間たちとともに、なぜ今ドキュメンタリー教育を始めるのか、目指す未来はどこなのか。その背景を紐解きながら、日本のドキュメンタリー映画の現在地を探ってみた。
INDEX
アカデミー賞ノミネートは、ドキュメンタリーやテーマに関心を持ってもらうきっかけ
─まずは、先日アメリカ、ロサンゼルスで開かれました「第97回アカデミー賞 授賞式」にご出席されたということで、ノミネートおめでとうございました。現地に行かれた率直なご感想をお聞かせください。
山崎:一緒にドキュメンタリー映画を作ってきた仲間や、今回映画に出演してくれたあやめちゃんや、協力してくださった皆さんとそこに行けたことが良かったなと思います。頑張ってきたことへのご褒美の1つというか。

日本人の心と外国人の視点を活かすドキュメンタリー監督。代表作は高校野球を社会の縮図として捉えた『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』。公立小学校を1年見つめた最新作『小学校~それは小さな社会~』が2023年東京国際映画祭上映され、現在各国で上映中。第97回米国アカデミー賞において、同映画から生まれた短編の『Instruments of a Beating Heart』が短編ドキュメンタリー賞にノミネートされる。ニューヨーク大学映画制作学部卒。
山崎:ただ同時に、私は14歳から映画監督を目指してきたのに、自分がアカデミー賞に行くという想像を1度もしたことがなく、夢にも思っていなかったことに気がつきました。その点を逆に反省したということが大きいですね。

山崎:それぐらい、まだ米国アカデミー賞を日本の女性が、ドキュメンタリーで目指すということが当たり前ではなかった。だから、自分たちがそういう場所に行けたことで、日本にいる皆さんにも「世界は行きたければ行ける」と思う人が増えればいいのかなという感じです。現地で業界の内側を学べたこともよい社会見学になったと思います。優秀な作品がないから日本がノミネートされないわけではなく、そこには選挙にも似た大きなシステムがあるということも今回垣間見ることができました。
金川:色々な点がビジネス化されていて、こうやって仕組み化しないとダメなんだなっていうのはすごく思いました。ある部分は見習わないといけないんだろうなと。

山崎:もちろん学びはとてもありましたが、じゃあ戦略としてそこを最終目標に置いて今後制作をするかというと、全くそうは思わないですね。ドキュメンタリー映画自体があまり知られていない中で、アカデミー賞ノミネートがどういう意味を持つのかというと、10年かけて取り組んできた日本の小学校教育というテーマに、関心を持ってもらう機会だととらえています。ノミネートをきっかけに、長編版映画の『小学校〜それは小さな社会〜』を知って、初めて映画館にドキュメンタリーを見に行ったという方々が多分何万人もいて、そういうきっかけになったことが嬉しい。
山崎:それに、映画を見た観客の方から「ドキュメンタリーなのに笑いました」とか「ドキュメンタリーなのに泣きました」っていう感想をいただいたんですけど、なんというか、ドキュメンタリー映画が泣いたり笑ったりするものだと思われていないわけですよ。もっと硬くて遠くにあって、肩の力を入れないと見に行けないもの……という印象だったというのが悲しいですが現状です。今回のフィルムスクールでやりたいこととも重なりますが、ドキュメンタリーのとらえ方はまだまだ進化できるし、可能性がいっぱいある。
私は、相手の気持ちが理解できないためにお互いが敵になっていくような分断社会を少しでも変えたいと思って、ドキュメンタリーを作っています。今学校は「敵」とか、ブラックな職場だといわれることも多く、教員を目指す人が減っていますよね。この映画では、先生たちが生きがいも感じながら、正解のないものを探して生徒たちに向き合う、というところを映し出したことで、世の中の空気を少しばかり変えた気がするんです。もっと気軽に自分が経験したことのない世界を体感してみるとか、普段会うことがない人たちの気持ちがわかるとか、そんなふうに社会の身近にドキュメンタリーがあればなと思ってきたので、今回の作品は大きなことが1つ達成できたかなとは思います。

INDEX
「ドキュメンタリーを学んでも、発表する場所がなかった」(金川)
─ドキュメンタリー映画はまだまだ日本では浸透していないというお話でしたが、お二人はなぜそこを目指したのですか?
金川:元々は新聞社で報道カメラマンをやっていたのですが、インターネットでの発信が増えるに伴い、動画撮影を任されることも増えていきました。社内で映像報道部門が立ち上がったりする中で、情報をより早く、わかりやすく伝えることに重点が置かれるニュースの限界を感じ、きちんとドキュメンタリーについて学びたいと思ってニューヨークフィルムアカデミーに留学し、一からドキュメンタリーを学びました。

全国紙の報道カメラマンとして活躍の後、2004年より映像報道記者として、東日本大震災、熊本地震、パリ同時多発テロ事件、ブラジル・リオパラリンピックなど国内外の現場で取材。NY でドキュメンタリーフィルムメイキングを学ぶ。17年にヤフー(現・LINEヤフー)へ入社し、「Yahoo! JAPANクリエイターズプログラム」(現「Yahoo!ニュース エキスパート」)や映像ドキュメンタリーのプラットフォーム、中高生向けのドキュメンタリー教材「探究ステップゼロ」等の立ち上げを主導。22年、ドキュメンタリーの教科書を作りたいと『ドキュメンタリー・マスタークラス』を玄光社から出版。特定非営利活動法人Tokyo Docs 理事・一般社団法人 デジタルジャーナリスト育成機構 理事。現在は、「Yahoo!ニュース ドキュメンタリー」 チーフ・プロデューサーとして従事。
金川:ところが、いざ帰国してみるとドキュメンタリーを学んでも発表する場所がなかったんですよ。日本のドキュメンタリー制作者の多くは制作会社に所属していて、普段はスタジオ番組などを作っているけれども、本当はドキュメンタリーをやりたいというような方がいっぱいいらっしゃる。一方でフリーのドキュメンタリー監督として頑張ってきた方もいて、色んな背景を持つその人たちのためにまずは発信できる場を作ろうと、LINEヤフーでドキュメンタリーのプラットフォームを作りました。

金川:みんなの表現の場所を作るというのが一番の原動力だったので、色々な人たちの希望を聞き取ったりしているうちに、自分の立場に近いのは何か、と当てはめてプロデューサーという肩書きになりました。
INDEX
「後進の育成は、一流になればなるほどやる」(山崎)
山崎:私の場合、切っても切れない「イチローとの出会い」というのがあって、小学校の時、課題図書になっていたプロ野球選手のイチローの本を読み、何か好きなことを見つけて努力を重ね、夢を大きく持って一流になる、という生き方に憧れました。それ以来、イチローにとっての野球は、自分にとってはなんだろうというのを探している中で、中学2年の時に授業で映像制作に出会って、これを私にとっての野球にすると誓ったわけです。
でも、大学に行くまで映画に色々な種類があることも知らなかったくらいで、ドキュメンタリー映画を志したのはニューヨーク大学映画制作学部の2年の時です。ドキュメンタリーの基本を学ぶ授業で、アメリカを代表するドキュメンタリー編集者であり、キャリアの後半は映画監督でもあったサム・ポラードという巨匠と運命的に出会いました。

山崎:ストーリーテリングを上手く運べばこんなに伝わるんだとか、ドキュメンタリーにおいて編集ほど大事なものはないんだというような考えを彼から学びました。卒業後は助手になり、生きていくために編集スキルをどう上げてお金を稼ぐかなど全部を教えてもらって独り立ちしていったんですけれど、自分の作品をいつか撮れたらいいなという人生のキャリアモデルみたいなものも学んだ気がします。

山崎:あと、サムさんは第一線で活躍しながら、何十年も先生として、私に限らず後進を育成していたんです。若い人を雇って自分の助手にして、教えながら一緒に制作していくというような、そういうことはやっぱり一流になればなるほどやっていくんだという姿勢も学びましたね。
─そこから後進の教育につながっていくんですね。
金川:僕は前からずっと学校をやりたいというのは言っていました。ドキュメンタリーをどうにかしなければいけないという危機意識があり、そのためには教育が必要でそれをやらない限り変わらないねと、山崎さんも含めたドキュメンタリーの仲間内で集まるたびに話していました。

金川:今回スクールの拠点として、今日の取材場所でもある東急プラザ原宿「ハラカド」内のクリエイティブラウンジ「BABY THE COFFEE BREW CLUB」を使わせていただくのですが、1年ほど前にここがオープンする時に声をかけていただいて、山崎さんから「あそこで温めていたスクールをやったほうがいいよ!」って言われて。場所も見つけたし、これはやらざるを得ないなと本格的に準備を始めました。

INDEX
日本で生まれたドキュメンタリーがより、世界に届きやすくなるように
─先ほど危機意識とおっしゃいましたが、ドキュメンタリーの教育をやらなければいけないと考えた、その背景にはどんなことがあったんでしょうか。
山崎:この10〜15年、特に私がニューヨークに留学に行った頃から、アメリカを中心にドキュメンタリーが急速に進化して、広く一般的に視聴されるようになったんです。それまでは記録映画といわれたりするような割と狭い概念だったのが、一気に監督の作品性が注目されるようになりました。マイケル・ムーア監督のように自分で映画の中で喋ったり、フィクションに勝る感情移入の体験があったり、エンターテイメント性があるような、色々な分野の作品が出てきて、その手法や技術も研究され進化してきたその中心にちょうど私はいたんです。

山崎:だからアメリカでドキュメンタリーを作っていると言うと、「クールだね!」っていう反応なんですけど、日本に戻ってきたら、ドキュメンタリーというとNHKが作るナレーションのある情報ドキュメンタリーのイメージが強いのか、「公共サービスを作っているんですね!」と言われることも。そこにすごくギャップがありました。

山崎:一方で、私が日本に帰ってきた大きな理由の一つに、海外の人が日本で撮ったドキュメンタリーばかりが世界に送り出されてしまうということがありました。「寿司」とか、「セックスしない日本人」とか、そういう特異な題材のものばかり取り上げられて、その良さもあるかもしれないけれど悔しかった。ただ、日本から世界に作品を出していくことを考えると、やっぱり撮影手法が世界的な時代の潮流に追いついていない。もちろん制作会社や放送局で働く方たちは、その中で研鑽をつんでいらっしゃいますが、そのことが逆にガラパゴス化を招いてしまうということは、中にいる方達からも聞きます。
金川:日本と海外のドキュメンタリーの違いは色々あると思うんですが、ぱっと見てわかるのはルックの違い。構図だとか、画そのものに対するこだわりの部分があるのかなと思っています。ですから、DDDD Film Schoolのカリキュラムを作る時に、最初に取り組むこととして、音と写真だけでストーリーテリングをするという課題を設定したんですよ。映像って、写真が24枚繋がったものなんですよね。ドキュメンタリー写真家の林典子さんに講師を務めてもらうのですが、カメラマンを目指している人だけではなく、ディレクターも含めて、画(写真)の何が良いのか、美しいのかという基準を持つようになってもらいたいなと考えています。

山崎:確かにニューヨーク大学映画制作学部の最初の1年間は、写真と音だけで作品を作ります。ただ、別にニューヨークでやっているスタイルをそのまま日本でやることに価値があると思っているわけではないんですよ。フィクションとノンフィクションが混ざりすぎはじめている欧米と比べ、日本のドキュメンタリー制作は純粋で、粘り強さとか取材相手に対するリスペクトとか、文化的にドキュメンタリーに向いている気質があると思うんです。そこに、世界で今どんなふうにドキュメンタリーが撮られているのかということを伝え、プラスしていくことで、日本で生まれたドキュメンタリーが、コアなファン以外の人たちや、世界により届きやすくなるのではないかっていう思いです。

金川:あとは円安の問題もあって、今海外に留学しようと思うと、僕が留学したニューヨークフィルムアカデミーでも当時に比べ学費が倍になっているんです。今1年留学しようとすると生活費も込みで1,000万円は超えてしまう。正直ハードルが高いですよね。それもあって、日本にいても世界的な流れをキャッチアップすることができる場所を作りたかった。