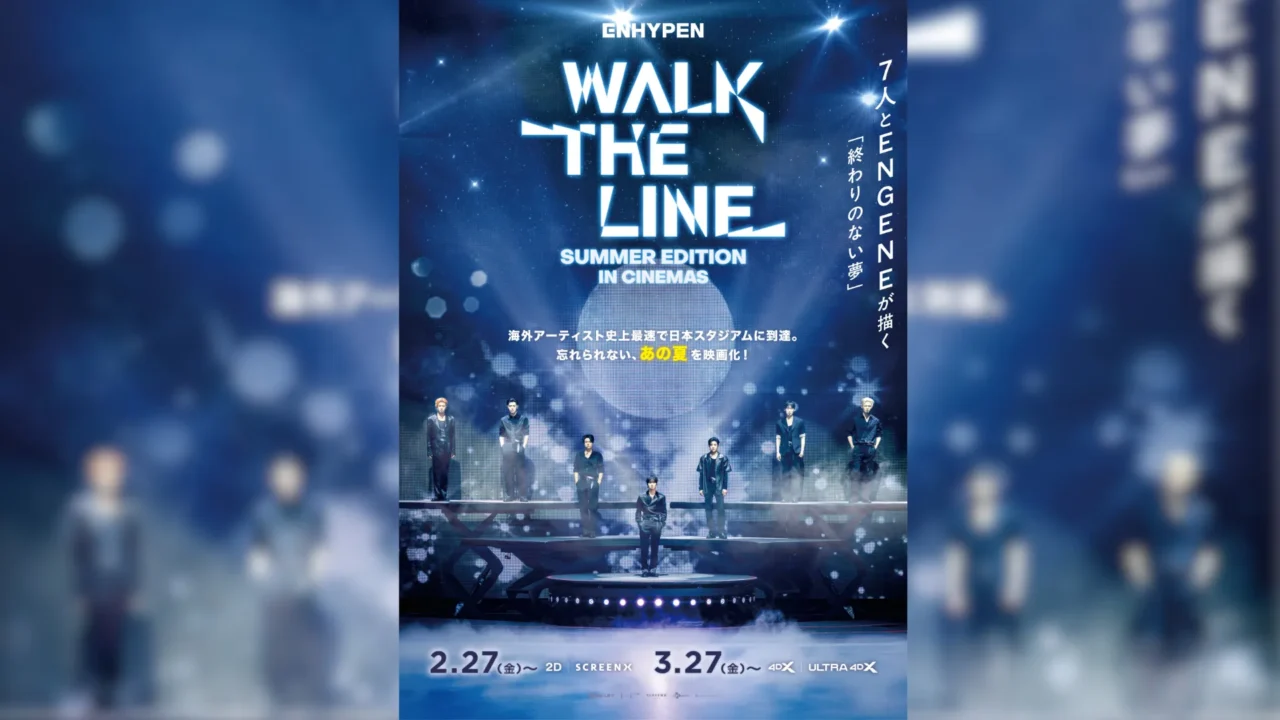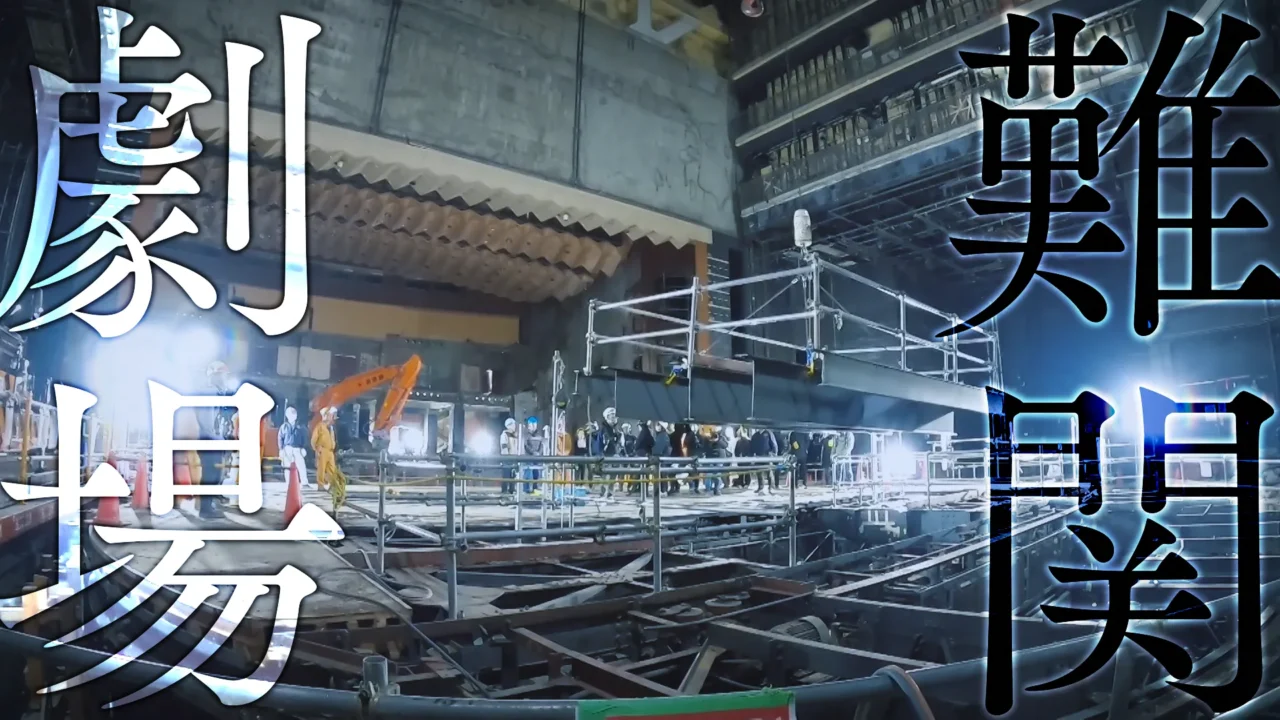INDEX
日本で生まれたドキュメンタリーがより、世界に届きやすくなるように
─先ほど危機意識とおっしゃいましたが、ドキュメンタリーの教育をやらなければいけないと考えた、その背景にはどんなことがあったんでしょうか。
山崎:この10〜15年、特に私がニューヨークに留学に行った頃から、アメリカを中心にドキュメンタリーが急速に進化して、広く一般的に視聴されるようになったんです。それまでは記録映画といわれたりするような割と狭い概念だったのが、一気に監督の作品性が注目されるようになりました。マイケル・ムーア監督のように自分で映画の中で喋ったり、フィクションに勝る感情移入の体験があったり、エンターテイメント性があるような、色々な分野の作品が出てきて、その手法や技術も研究され進化してきたその中心にちょうど私はいたんです。

山崎:だからアメリカでドキュメンタリーを作っていると言うと、「クールだね!」っていう反応なんですけど、日本に戻ってきたら、ドキュメンタリーというとNHKが作るナレーションのある情報ドキュメンタリーのイメージが強いのか、「公共サービスを作っているんですね!」と言われることも。そこにすごくギャップがありました。

山崎:一方で、私が日本に帰ってきた大きな理由の一つに、海外の人が日本で撮ったドキュメンタリーばかりが世界に送り出されてしまうということがありました。「寿司」とか、「セックスしない日本人」とか、そういう特異な題材のものばかり取り上げられて、その良さもあるかもしれないけれど悔しかった。ただ、日本から世界に作品を出していくことを考えると、やっぱり撮影手法が世界的な時代の潮流に追いついていない。もちろん制作会社や放送局で働く方たちは、その中で研鑽をつんでいらっしゃいますが、そのことが逆にガラパゴス化を招いてしまうということは、中にいる方達からも聞きます。
金川:日本と海外のドキュメンタリーの違いは色々あると思うんですが、ぱっと見てわかるのはルックの違い。構図だとか、画そのものに対するこだわりの部分があるのかなと思っています。ですから、DDDD Film Schoolのカリキュラムを作る時に、最初に取り組むこととして、音と写真だけでストーリーテリングをするという課題を設定したんですよ。映像って、写真が24枚繋がったものなんですよね。ドキュメンタリー写真家の林典子さんに講師を務めてもらうのですが、カメラマンを目指している人だけではなく、ディレクターも含めて、画(写真)の何が良いのか、美しいのかという基準を持つようになってもらいたいなと考えています。

山崎:確かにニューヨーク大学映画制作学部の最初の1年間は、写真と音だけで作品を作ります。ただ、別にニューヨークでやっているスタイルをそのまま日本でやることに価値があると思っているわけではないんですよ。フィクションとノンフィクションが混ざりすぎはじめている欧米と比べ、日本のドキュメンタリー制作は純粋で、粘り強さとか取材相手に対するリスペクトとか、文化的にドキュメンタリーに向いている気質があると思うんです。そこに、世界で今どんなふうにドキュメンタリーが撮られているのかということを伝え、プラスしていくことで、日本で生まれたドキュメンタリーが、コアなファン以外の人たちや、世界により届きやすくなるのではないかっていう思いです。

金川:あとは円安の問題もあって、今海外に留学しようと思うと、僕が留学したニューヨークフィルムアカデミーでも当時に比べ学費が倍になっているんです。今1年留学しようとすると生活費も込みで1,000万円は超えてしまう。正直ハードルが高いですよね。それもあって、日本にいても世界的な流れをキャッチアップすることができる場所を作りたかった。