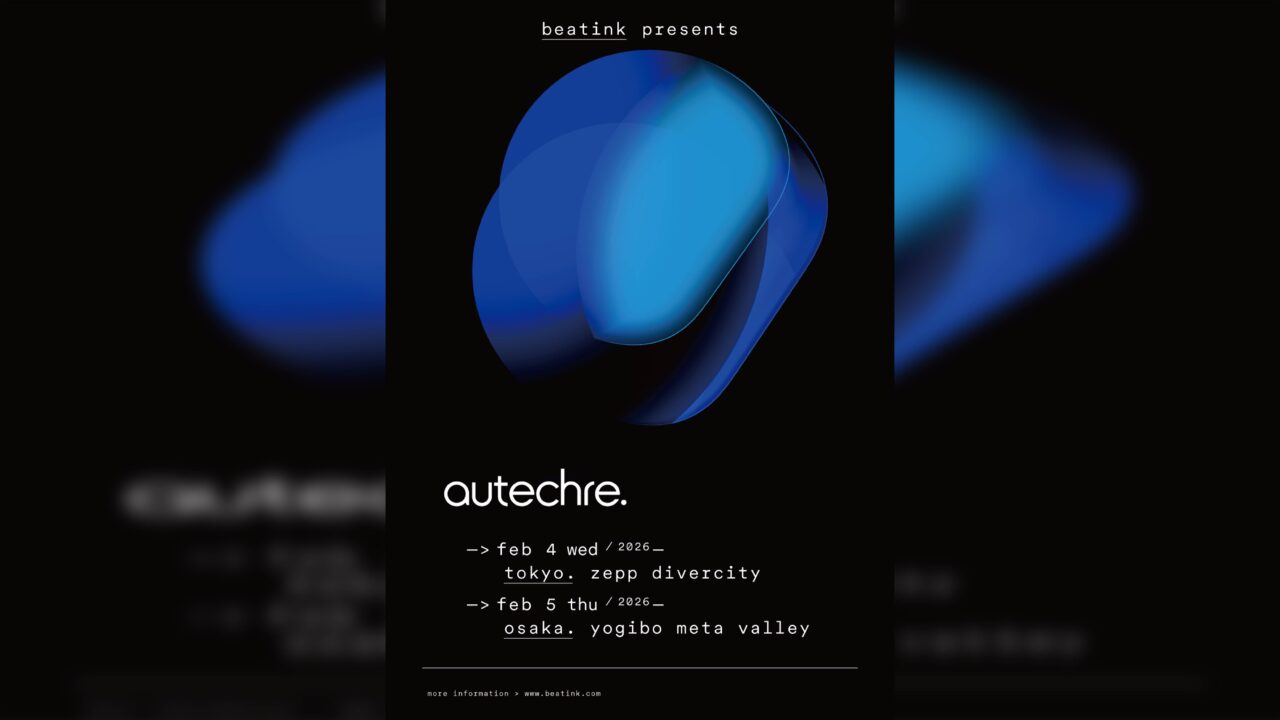世の中には、普段の会話からSNS上まで、誰かの思惑で誰かを操作しようとする言葉に溢れている。それらを拒絶して、引いた目でやわらかく抵抗するのが、福岡在住のシンガーソングライター、山本大斗の音楽だ。
2023年1月に発表した“船出に祈り”から本格的に音楽活動を開始し、作詞 / 作曲 / 編曲からミックスまでを自ら行う。パーソナルに迫った繊細な弾き語りから壮大なサウンドスケープのポップソングまで、その表現方法は様々だ。水のように形を固定せず、その時々で形を変えながら、考えていることを音楽にする山本の音楽は、内に潜る中で外部と繋がる。孤独を抱えている人にとっての居場所は、ここかもしれない。キャリア初となるロングインタビューを敢行した。
INDEX
バンドArt titleから、ソロアーティスト「山本大斗」の活動へ
―まず、ご自身にとって「楽曲を作る」ということはどんな行為なのか、というところから伺えますか。
山本:自分の中にある解釈できないような感情や環境をそのまま記録するためのものですね。
ーつまり、普段生きている中で、あるいはこの世界を見ている中で、「これは何なんだろう?」と思うような事象だったり、そこで生まれてくる感情だったりを自分なりに理解するためのツールというか。
山本:そうですね。
ー曲作りが自分にとってそういうものであることを自覚されたのは、いつ頃だったんですか。
山本:最初に曲を作り始めた時はおそらくそういう自覚はなかったと思うんですけど、ソロをやり始めてから曲を作る時の意識が変わったというか……何か出てくるまで待って自然に出すというよりは、ちゃんと何か形にするんだという意志を持って曲を作るようになりました。

歌声、詞世界、メロディーセンス。そのどれもが、自由でありオルタナティブ。豊かな情景を生み続ける、福岡在住のシンガーソングライター。
ー山本さんはソロを始める前からArt titleというバンドで活動されていて、そこではVo / Gtとソングライティングを手掛けていますけど、バンドを始めた時はどういう感覚だったんですか?
山本:バンド自体は誘われてやり始めたので、あまり責任というか、そういうのがなくて(笑)。
ー要するに作家としての意識や責任感というよりも、音を奏でるということの楽しさや面白さが強かった?
山本:そうですね。ただ、誘われる前から自分で曲を作っていたので、ちょうどいいからっていう感じで始めたところもあって。とはいえ、当時はさっき言ったような、あくまでも出てくるものを自然な形で曲にしていたという感覚でした。そこからソロで何かを表現するっていうふうになった時に、必然的に作家としての意識が生まれたんだと思います。
ー“船出に祈り”という楽曲ができた時に「これはバンドではできないな」と思い、ソロでやろうと思い立ったと伺いました。バンドを始めた当時は「表現として自分が作品を生み出す」ということに関してそこまで自覚的ではなかったところから、Art titleをやっていく中でどんなことを感じたからこそ、そこに踏み出していったんだと思います?
山本:バンドでEPを2枚出したんですけど、当時はスタジオで1日2日で録って、そこからミックスはお任せで……みたいなやり方をしていたから、あまり自分で作品を作っているという感覚がなかったんですよ。で、家で自分でやってみようと思ったタイミングで作ったのが“船出に祈り”という曲で。そうやって家で録音して、自分でミックスもやって楽曲を仕上げた時に、作品を作っているという実感が凄くあったんですよね。
ー宅録で制作することの利点のひとつとして、時間をかけてとことん自分と向き合うことができる――自分の中にある言語化できない感覚や景色みたいなものを追求して、精緻にスケッチするように曲全体を構築していけるという点があると思うんです。それゆえに必然的にその人の感情や、もしかしたら自分でも気づいていなかった深層心理にあるものをも音に表していける。これがバンドでスタジオで制作したり、ミックスを他の人に委ねるという形だと、どうしても他者の解釈が入ってきてしまうところがあって。もちろんそれが人と一緒に音楽をやる面白さでもあるけど、同時に自分自身の中にあるものを形にするという意味だと難しいところでもある。今の話を聞いていると、おそらく山本さんは“船出に祈り”を作った時に、初めて自分の心がひとつ形になったという実感を持ったということなのかなと推測したんですが。
山本:まさにそういう感覚でしたね。言語化できない無意識の部分に向き合えた実感もあって。それは僕にとって他にはない時間というか、初めてのことだったんです。それによって、自分にとって音楽を作るということは、自分が自覚していない部分と出会う作業なんだなと気づいたところがありましたね。

ー2023年1月に“船出に祈り”を発表した後、2024年8月の“バベル”まで、コンスタントに8曲をリリースしていきましたよね。どれも軸にあるのは弾き語りなんだろうなと感じつつも、音楽的に様々なバラエティを誇っていて。そうなったのは、自分が表現できる音楽性や、そこに映し出せる感性みたいなものを、1曲1曲実験しながら作っていったからなんじゃないかと思うんです。で、その一連の制作を経た上で、2024年11月にドロップした『私の背景』というEPで、ソロアーティストとしての自分のアイデンティティ、あるいは自分が音楽を作る源にあるものは何なんだろう? というところに向かい合ったのかなと。実際、そのあたりはどんな流れだったのか教えてください。
山本:本当に今おっしゃっていただいた通りなんですけど(笑)。とにかく最初の頃はいろいろ試したくて、いろんなタイプの曲を作り続けていったんですね。で、その作業にちょっと疲れたというか(笑)。
ーはい(笑)。
山本:中には「自分じゃないことをしてる」みたいに感じる瞬間もあって。もちろんそれはそれで楽しいんですけど、『私の背景』を作った時は、自分のために作ろうっていう意識がありました。そういう意味では、あのEPは自分のアイデンティティを改めて記録した作品だと思います。
INDEX
パーソナルなものを表現できるのが、アコースティックなサウンドだった
ーそもそも山本さんって、音楽的なルーツはどんなところにあるんですか。Art titleの作品を聴いてると1990年代のUKロックからの影響を強く感じるところがあるんですけど。
山本:UKロックはおそらく人生で一番聴いていた音楽なので、意識せずとも素で出てきてしまう要素なんだと思います。で、ソロに関してはまずは弾き語り主軸で曲を作っていくんですけど、なるべくアコギを入れるように意識してますね。バンドはエレキギターが3人いるんですけど(笑)。
ー今の時代、トリプルギターってなかなか珍しい。
山本:そうなんです。Radioheadになりたくてそうやってたんですけど、実際やってくと、単純にエレキギターが多いなっていう。
ー(笑)。
山本:ただ自分の場合はどうしても、自然にやるとギターが鳴ってるサウンドになるんですよね。だったらアコギも弾きたいし、単純にアコギに置き換えたほうが音的にもスッキリするな、みたいなところもあって。
ーよりパーソナルなもの、距離感が近いものを求めた結果、アコギに行き着いた部分もあったりするんですか。
山本:確かにそれはあるかもしれないです。生々しいというか、マイクに乗る空気感はアコースティックなもののほうが録れるし。手元の衣擦れの音とかも入っちゃうような、そういうのが音として好きなんですよ。
ーそういうものがしっくりくる。
山本:そうですね。

ーその上で、“船出に祈り”から“バベル”までの楽曲群は、フォークやカントリー的なアプローチからEDM、オルタナティブR&B、モータウンやヒップホップなど、様々なアプローチがなされていました。これは自分に最適なアプローチを探っていった結果なのか、それよりも純粋な好奇心が強かったのか、どんな感じだったんですか。
山本:好奇心が強いかもしれないですね。それこそ根本にある自分が曲を作る意味合いみたいなものとはまた別軸で、音楽でいろいろ実験したいみたいな気持ちもあって。なので、割と直近で聴いている音楽にかなり影響を受ける節はあります。制作スタイル的にもタイムリーな状態で出すことが多いので、その時期に聴いたことが、素直に出ているのかなと。「こういうの、面白そうだな」と思ったことをフレキシブルに反映させているかもしれない。
INDEX
“バベル”とEP『私の背景』収録の“夜明迄”のこと
ーそうやっていろんなことを試していった中で、“バベル”は非常に大きなサウンドスケープを描く壮大なポップソングとして仕上がっていて、その上で『私の背景』へと向かいましたよね。“船出に祈り”からリリース順に聴いていくと、“バベル”でひとつ、弾き語りで作った楽曲を自分なりにポップソングとして最大化するということを果たせたからこそ、『私の背景』という、今一度、ご自身の一番深いところを見つめ直して、それを形にするところに向かったのかなと感じたんですけど。
山本:確かに“バベル”に関しては、自分自身とのギャップがない状態でよりポップにするというか、おっしゃったように最大化することが1回完全にできた感覚がありましたね。だからこそ、その反動じゃないですけど、もう少し内省的な、音楽的にももっとテンポが遅くてメロウな感じをやりたいなっていうふうに思って『私の背景』に向かった感じだったと思います。
あのEPは4曲目の“夜明迄”という曲が先にできたんですけど、それまで作った中でも一番好きな曲ができたんですよね。だから“夜明迄”のための作品というか、あの曲の前後に物語をつけたいなっていうのがあって。それで作り始めました。
ー“夜明迄”はウォームなアコースティックギターとクワイア的に重ねられた声の響きを主体として構成されている楽曲ですが、これができた時に一番好きだなと思ったポイントはどんなところにあったんですか。
山本:まず音楽的なところでいうと、ビートがない曲――フランク・オーシャンの“Self Control”が大好きなんですけど、ああいう曲ができたらいいなっていうのがずっとテーマとしてあって。リズムがなくて、コーラスとかリバーブとかの鳴りで埋まってるような感じのサウンドデザインですね。それができたのと、あとは歌詞も気に入っていて。他の方の曲や小説や詩にしても、堅い文章よりも口語っぽかったり、ちょっと可愛さがある言葉が好きで。で、“夜明迄”の詞は柔らかい感じがあって、だけど強さもあって、というところが気に入ってますね。
ーそういうものが好きなのはどうしてなんでしょう?
山本:確かにどうしてなんでしょうね? (長い沈黙)僕は言葉というものには、その言葉の持ってる匂いみたいなものがあると思っていて。同じことを言うにしても、硬い表現よりも口語的な表現だったり、柔軟なもののほうが伝わりやすい気がするからかもしれないです。

INDEX
「水のような音楽を作りたい」と思う理由
ー『私の背景』というEPの中で、自分は1曲目の“漣”と最後の“粼”という2曲が非常に好きなんです。どちらも賛美歌のように聴こえるところがあるし、特に“粼”は、山本さんが音楽を作る一番ベースにある感覚が歌詞にされているようにも感じます。まず、“漣”が生まれた時のことを教えてください。
山本:EP全体を通してなんですけど、水のイメージがあって。で、“漣”に関しては川ではなく、水たまりや湖みたいな、停滞している水のイメージで作りました。水滴がパッと落ちて、ちょっと水面が動く、そうやって誰かや何かによって起こされたちょっとしたアクションが、自分を動かしていくきっかけになるのかもしれない、みたいなイメージです。
ー自分が編集長をしている『MUSICA』という音楽雑誌でメールインタビューをさせてもらった時に、「山本大斗として表現したい音楽とはどんなものなのか、教えてください」という問いに対して、「先進性と普遍性が同居した、水のような音楽を作りたいというイメージが常にあります」という回答をいただいて。その「水のような音楽を作りたい」という言葉が非常に興味深いなと思ったんですが、どうしてそう思ったんですか。
山本:水っていうのは強さもあるし、けど柔らかい部分もあるし、包容力もあるじゃないですか。形を留めずにずっと流れ続けていくものであることも含めて、自分がどういう音楽を作りたいか考えた時に一番マッチするイメージなんですよね。形を固定せず、その時々で自分が思ってることとか作りたいものを形にしたい、流れを止めずに形を変えながらやり続けていきたいっていうのがあって。水のような音楽を作りたいというのは、そういうことだと思います。

ーおっしゃる通り、水は常に形を変えていきますけど、一方で、なくてはならないもので。すべての生命は水がなければ生きられない、つまりは生にとって不可欠かつ非常に本質的なものでもある。ご自分にとって音楽もそういうものだという感覚があるんですか。
山本:作る立場においても聴く立場においても、その感覚はありますね。音楽とか音というもの自体、意識して求めているものというよりも、自然に、当然そこにあるものとして捉えているというか。まさに不可欠な存在。そういう意味でも、水にかなり似てると思います。
ー“粼”はどんなふうに生まれたんですか。
山本:曲自体は以前からあったんですけど、アレンジは“夜明迄”を作った後に始めたんですよ。というのも、EPをどういうものにするかイメージが固まるまでは手をつけなくて。で、“夜明迄”ができたことである程度それが見えたので、そこから取り掛かった感じでしたね。4曲目の“夜明迄”から5曲目の“粼”へと進んでいく中でひとつカタルシスを作りたいなと思って、さっき言った停滞のような、溜まっているものが動き始めるイメージで作った曲です。
ー“粼”には<どうやっても取り戻せない一瞬の春の光と / 行き場のない怒りも固く閉ざされた日々も / 洗いざらい流す雨が降る>というラインがあります。こういう詞が生まれてきたのは何故なのか、教えてください。
山本:このEPに主人公がいるとしたら、その人は孤立した場所に家があって、そこにひとりで住んでいるような孤独感を抱えていて。そういうのが<閉ざされた日々>に表れてると思うんですけど、<雨>に関しては、恵みの雨みたいなイメージで綴ってますね。雨が降ることによって溜まっていたものが流れていく、新たな場所へと動き出していくような、そんなイメージで書きました。

ー曲を書く時は、自分はそれこそ誰もいない孤立した場所に存在しているという感覚が凄く強いんですか。
山本:作ってる時は強いですね。
ーそういう孤独感は普段、生きている中でも感じているもの?
山本:理解されない悲しさに近い孤独感は、常にある気がします。たとえば音楽を作るにしても、ある程度の軌道に乗って、ギターを弾きながらメロディを作り始めて歌詞も書いてっていう作業の段階に入ったら、傍から見ても「ああ、この人は音楽を作ってるんだな」ということになると思うんですけど、その前の段階って、動きとしては何もしていない状態じゃないですか。そういう、自分の頭の中にはあるんだけど外からは見えないがゆえに理解されない孤独感みたいなものは、普段生きてる上でも、他者とどれだけ話しても理解されない悲しさと似てるかもしれないです。
ーその悲しみは、昔からある感覚なんですか。
山本:そうですね、割とあったと思います。僕は自分の気持ちをそんなに話さないというか……それも「話したいけど、話せない」というよりは、話す必要がないと思ってしまっている節があって。それは幼少期からずっとあったと思います。そんなにしゃべる子供じゃなかったんで。
ー他者に話す必要がないと自己完結するのは、諦めみたいなものが背景にあるんですか? それとも、それとは別の何か?
山本:諦め、ですね。
ー幼くしてそれを諦めたのは、どうしてなんでしょう?
山本:なんででしょうね? 当然しっかり話を聞いてくれる人もいたとは思うんですけど………ただ、特に幼少期は、「子供が言ってることとして」しか話を聞かない大人もけっこういるじゃないですか。
ーわかります。
山本:そういう状況って、当時の自分にはどうすることもできない。で、そういう時に僕の場合は、自分の気持ちをなんとか言葉にして伝えるよりも別の方法を試すというか、回避しがちというか。だから諦めてるんだと思いますね。

ー「子供が言ってることとしてしか聞かない」というのは、大人が子供に対して無意識に取ってしまう態度でもあると思うんですが、ただ今の世界を見渡してみると、それは大人と子供の間に限らず、人と人との間に横行している態度だなとも思うんですよ。特にSNSを見ていると、相手が言わんとしていることやその奥にあるものを理解しようとするよりも、自分の先入観や自分の正義に基づいて相手の話を勝手に決めつけ、一方的に断罪するようなことが凄く多い。で、それはSNSに限ったことではなく、今起きている侵攻や争いも、紐解いていけば近い構造があると思うんです。そういう人間の性(サガ)だったり世界の構造みたいなものを幼少期から肌で感じていて、そこに対する諦観があった、みたいなところもあるんですかね?
山本:そうですね。今も確かにそういうのは感じますね。その人が言ってる意味まで考えない、さらにはそれを一方の都合でキャンセルするというのが凄く加速している印象があって。それは危険だなと思います。少なくとも自分の気持ちとしては、もう少しお互い歩み寄りたい。そういう歌詞を書くことも多いなって、今思いました。