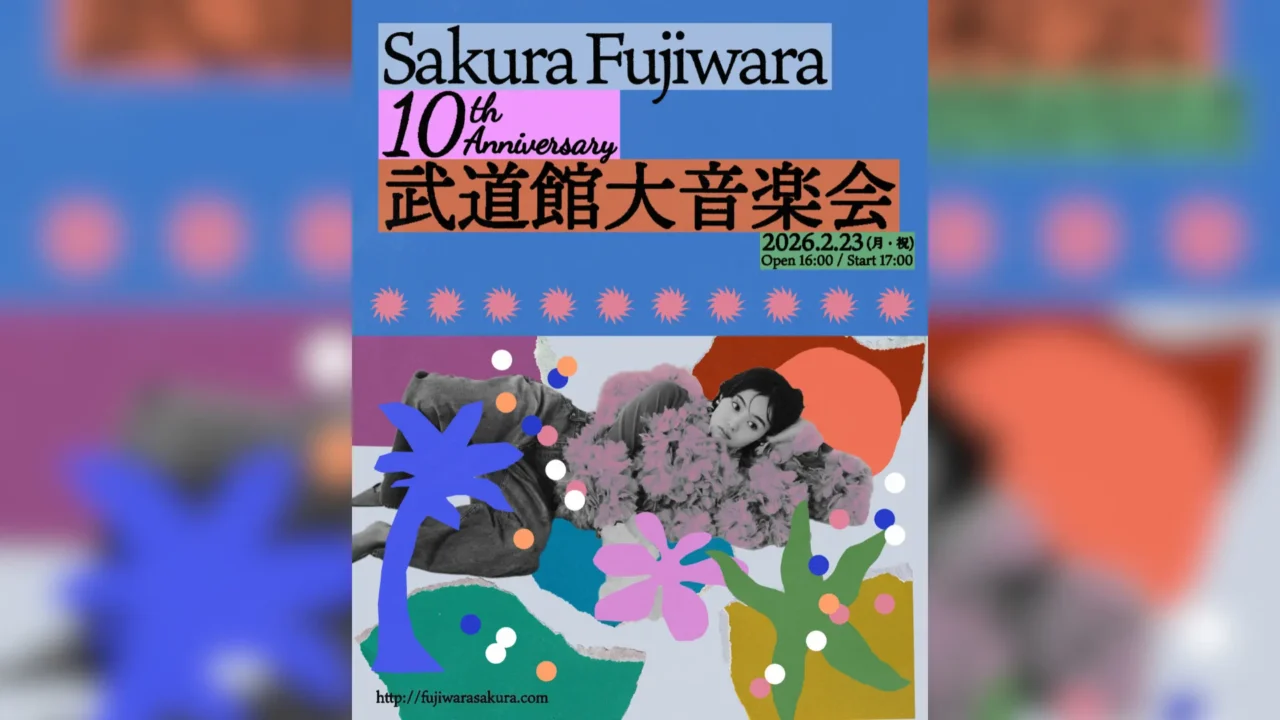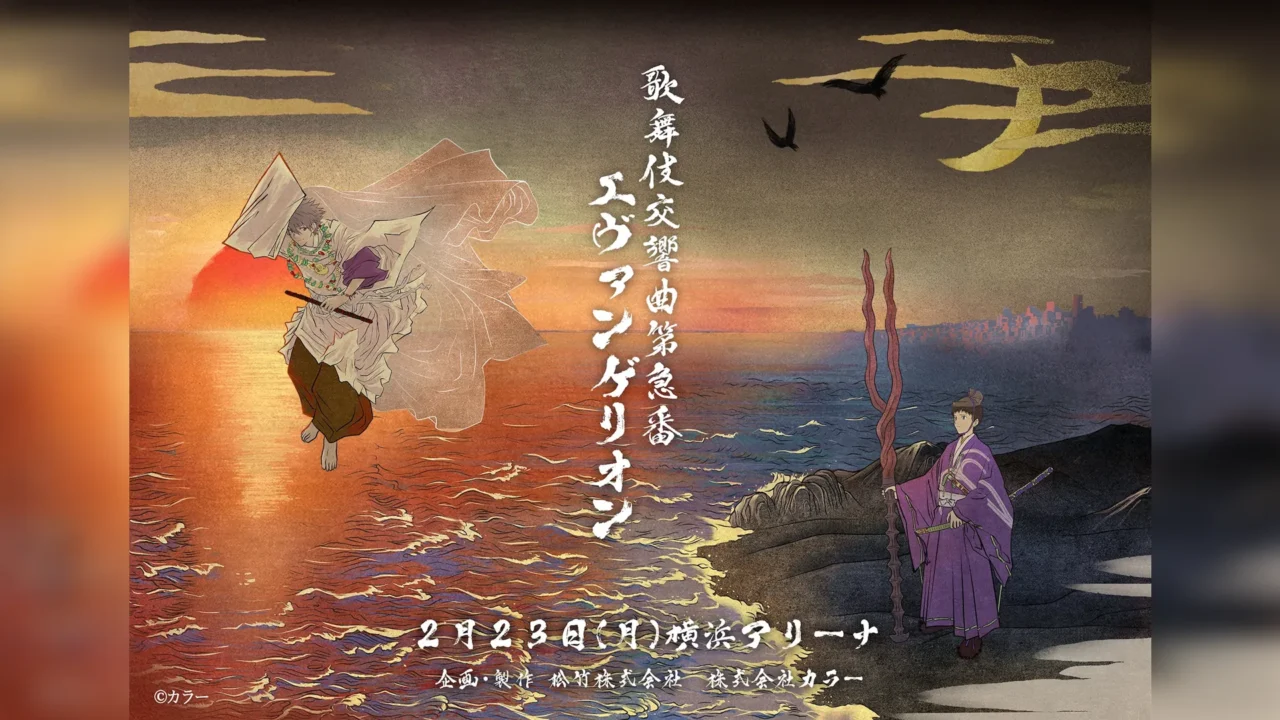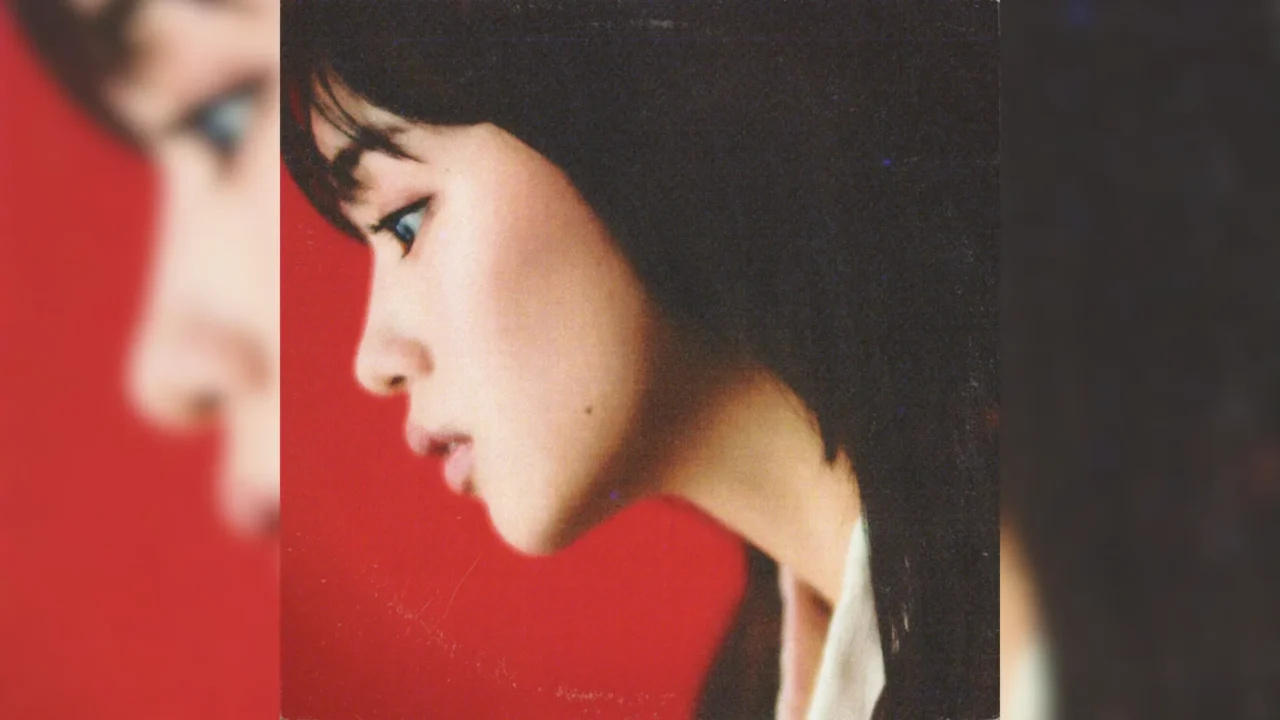INDEX
ライブを通じて音楽を深化させてきたcero。ステージ上では何が起こっているのか
─ceroほど楽曲のアレンジがライブで変わってきたバンドはないと思うんですよ。
高城:「僕ら三人が飽きっぽいから、次々にアレンジを変えちゃうんですよね」ってインタビューでもよく言うんだけど、最近、サポートの人たちも結構飽きっぽいんじゃないかって思ってるところもあって(笑)。一緒になってアイデアを考えてくれるし、ライブは誰が中心に考えているのか、作っているのか、さらによくわからないことになってます。だからこそ、この状態をひとつの作品にしておかないと、って思いました。
荒内:今の編成になったのが2016年の後半だから、成熟期なのかな。2020年くらいから、「結構仕上がってんな」と手応えを感じています。コロナ禍でライブの本数が減って、1本1本のライブが特別になってきたというのもあるし、サポートメンバーも新鮮に取り組んでくれている感覚がまた出てきて。だから成熟してるし、フレッシュだし、すごくいい状態なんですよね。

─ceroのライブがどういうコミュニケーションのもと成り立っているのか、不思議に思ってる人も多いと思う。
高城:サポートメンバーとライブ中にアイコンタクトをとろうとしても、全然目が合わないってことがよくあって(笑)。みんな踊ってたり、くるくる回ってたりするから(笑)。
荒内:みっちゃんもめちゃ演奏に入り込んで、こっちを見ないこともあるし(笑)。
高城:「あーーーーー!」って叫びながら叩いてたりするからね(笑)。
荒内:まあ、リハで何回も試すからそれでも成立するんだけど。
高城:ceroみたいなタイプの音楽だったら、マニピュレーター入れたり、イヤモニつけてドンカマ(クリック)を聞いて、みたいな方法は普通になされるべきなんだけど、なぜか二の足を踏む傾向がある(笑)。特に信念があってやらなかったわけじゃないんだけど、結局ここに至るまで人力でやっていて、気がついたら特殊な存在になっていた。
─クリックを聞いて合わせたり、トラックを同期したライブを否定するわけじゃないけど、ceroがそうせずにライブを続けてきたことで保たれた詩情みたいなものはありますよね。
高城:それはある。スネア一発の音にしても毎回違うわけだし、ステージ上の隣近所でそういう違いが群発して、それが何か大きな流れになっていくことがceroのライブにはあると思う。そこはわりと重要なところかな。