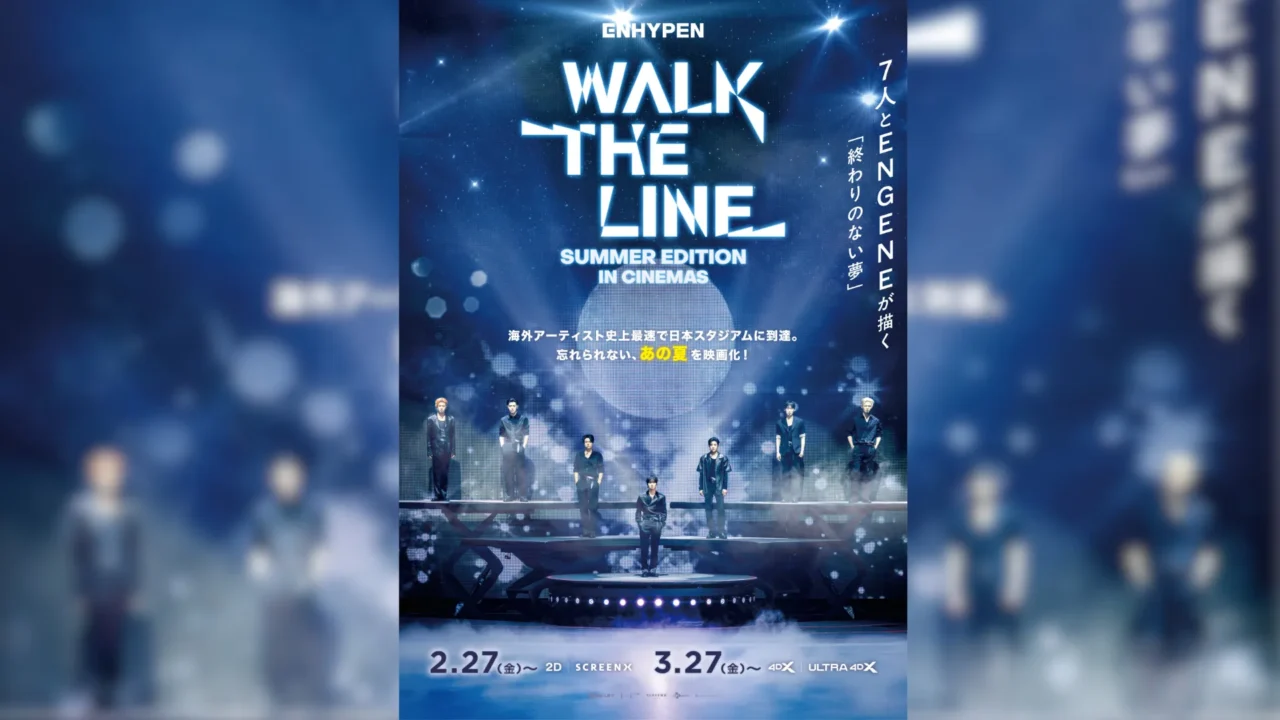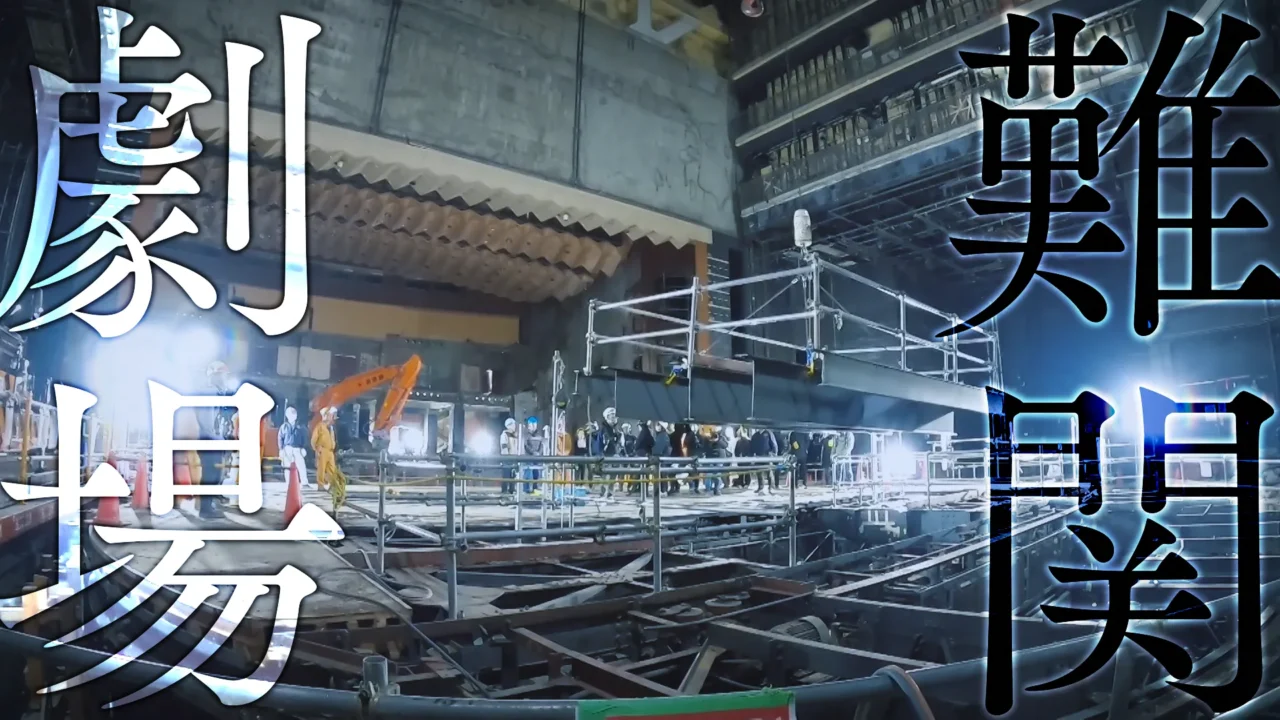INDEX
豪華プレイヤーやアレンジャーが共鳴
―6月にリリースした“cosmos”の歌詞はPORINさんによるものですが、これも精神年齢が上がったからこそ書ける内容だなと思いました。10代のラブソングではなく、大人の恋愛や別れ……もっと言ってしまえば、夫婦の結婚や離婚などまでを想起させるもので。
PORIN:デモ聴いたときから好きすぎて。歌詞がつく前から映像がイメージできたんですよね。
atagi:それだったら、もしよかったら歌詞で参加してもらえないかなって相談して。
PORIN:ちょうどその頃に知人の話を聞いて自分の中で心が動いたことがあって、そこから広げていきました。今やれるラブソングを最大限表現したという感じですね。ちょっと悲しすぎるけど、こうやっていっぱい傷ついてきた人もいらっしゃるだろうから、そういう人に響くといいなと思います。

―これは林あぐりさん(Ba)、GOTOさん(Dr / 礼賛、DALLJUB STEP CLUB)、宮川純さん(Key / LAGHEADS)という豪華プレイヤーたちと、一発録りで仕上げたそうですね。
PORIN:そうです、ツアーメンバーで録りました。去年のライブハウスツアーがめちゃくちゃよくて、「やっぱりバンドサウンドっていいなあ」という感情になったので、それを音として一生残しておきたいな、この曲なら合いそうだなという想いからお願いしました。それぞれがいっぱいアイデアを出してくださって、みんなで作り上げたサウンドになっていますね。
atagi:1発目に録ったのがむっちゃよくて、「念のためもう1回録ろう」ってやったけど、やっぱり1発目のほうがよくて。「理由はわからないけど、なぜか1発目がいい」みたいなことはよく聞く話だと思うんですけど。大袈裟に言えば「バンドマジック」だと思うんですけど、それをちゃんと録れたのがよかったなって思いました。アレンジ自体はそんなに凝ったことをやってないんだけど、それでもずっしりと重く残る説得力があるのは、やっぱりプレイヤーの妙だなって感じがします。
―そして7月発表の“Run and Run”は、テーマ性でいうと、2022年に出した“On Your Mark”に近いものがあるけど、あれはNHKのパラスポーツアニメ「アルペンスキー編」に書き下ろしたもので。さっき「自分たちから滲み出てくるものを形にした曲が多い」と話してくれましたけど、これはまさに、今の自分たちを歌った曲という印象を受けました。
atagi:そうですね、自分に向けて鞭打つ曲みたいな感じもありましたね。その頃は切羽詰まっていたりもして、「走れ!」って自分でケツを叩くみたいな(笑)。その思いっきりのよさが出た曲という感じもします。がむしゃらさみたいなものを意外と忘れちゃいけないなって感じもしますし、いくら10周年で落ち着いてきた部分があるとはいえ「必死ですよ」みたいなスタンスは大事だなって思います。
―<選ばれた場所で咲く建気な花にはなれないや>とか、ミュージシャンという立場に限らずどんな仕事をしていても、大人になってからもこういったスタンスを忘れないでいるのは大事だなと私も思います。
atagi:僕、好きな言葉があって。「終わりのないトラックレース」という。どういう人も、生きている中で、終わりが見えないことのしんどさを考えるじゃないですか。「いつまでこの会社で働くのかな」とか。社会的な活動する人みんなが、心のどこかで覚えている不安ってあると思うんですよ。「それでも走るんだよ」みたいなことを曲にしましたね。
―そこから最後の<笑顔で満ち足りた世界に 今決別の合図を>には、どういう思いを込めたと言えますか。
atagi:人生において判断を迫られるときって、都度あるじゃないですか。大きな判断でも小さな判断でも、その判断がよかったねって言えるのは、その後の自分の行動でしか示せないと思っていて。すべての判断がよかったと思えるように走ろう、という曲ですよね。
PORIN:この曲は、今回リリースしている中で一番新鮮に感じました。初めて聴いたとき、ACCとしては新しいけど、ちょっと平成初期の懐かしさを感じて。私の青春のJ-POP、楽しい時代のJ-POPという感じがしたんですよ。
atagi:それ言うけど、俺は全然わからない(笑)。どこがなんだろう?
―ビートのアプローチとか、m-floのトラックと接続するところはあるかもしれないですね。
atagi:ああ、なるほど! 最初に作っていたものは、いい意味でも悪い意味でも、ACCっぽい曲になっちゃうなと思って。どの楽曲もそうなんですけど、どこかで1個は外したいんですよね。色々試した結果、この曲ではリズムパターンをこういうアプローチにしてみました。PORINと言っていることとは違うんですけど、たとえばGorillaz、Black Eyed Peasとかが台頭してきた1990年代後半から2000年代の洋楽のイメージがあったかもしれないです。ジャンルが細分化し始めた頃、新しい解釈がそれぞれのジャンルに入り込んでごちゃ混ぜな感じになっている雰囲気みたいなものが、頭の片隅にありました。
―そして8月にリリースした“スロウ・サマー”には、『東京パラリンピック2020 開会式』や『大阪・関西万博開会式』などの音楽監督を務め、Omoinotake“幾億光年”やTOMOOさんの楽曲などを手掛ける小西遼さんがサウンドプロデュース&アレンジャーとして入っています。これは、どういうことを求めて小西さんにお願いしたんですか?
atagi:ここ近年、デジデジしたもの(デジタルっぽいもの)よりも、有機的な豊かさとか生っぽさが似合うなという所感があって。この曲も生っぽいよさを感じられる曲にしたいなと思って、小西さんにお願いしました。実際に一緒にやらせていただいて、表現としてデジタルっぽいものをちゃんと嫌味なく使えるし、生っぽいものも古臭いものとしてではなくモダンなものとして再解釈できるバランス感覚とアンテナを持っている人だという感じがしましたね。この曲は、何者になれなくても、こんな夜があってもいいじゃんって言ってあげられるようなものができたらなと思って作りました。若い頃の「何者かになりたくて、だけど頑張り方わからなくて」みたいな不安が爆発するのは、大体夏なんですよね。
モリシー:これはみんなと飲んでいた若い頃を思い出す音というか。それこそアレンジしてくれたこにたん(小西)とは、だいぶ前にうちの近所で飲んだことが何回かあって、その頃のことを思い出しました。