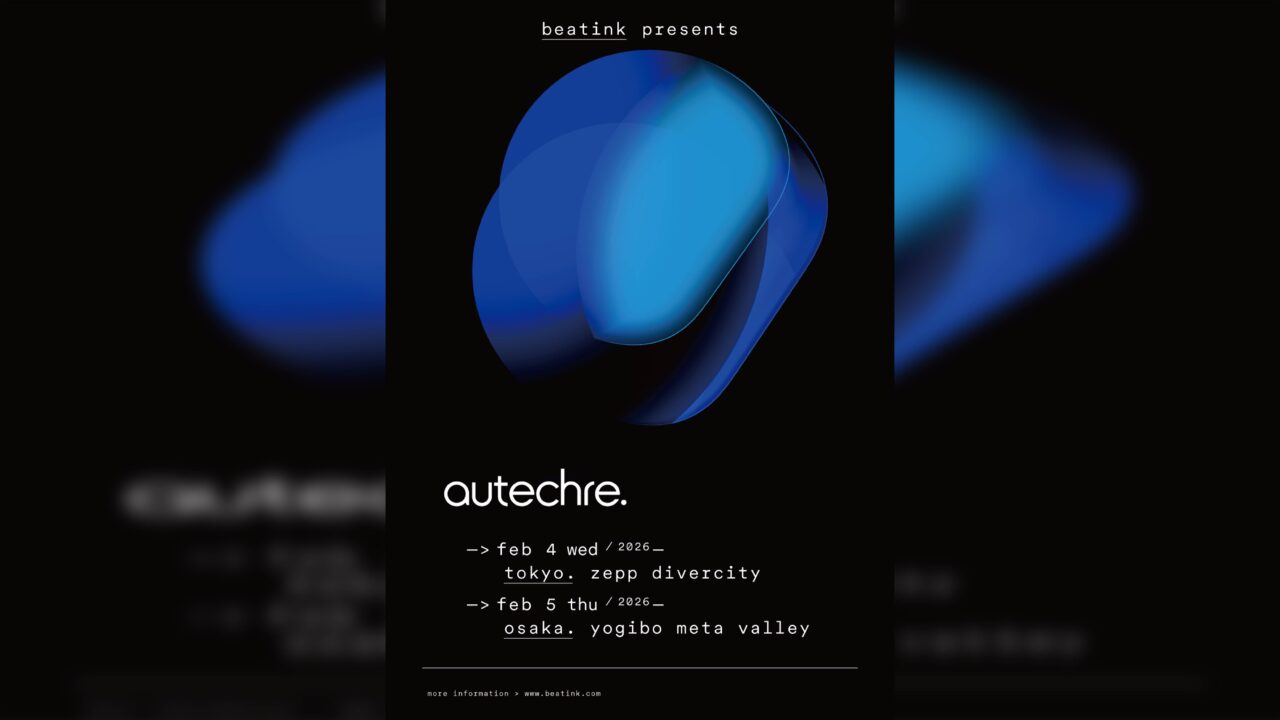写真家・奥山由之の初監督映画『アット・ザ・ベンチ』が、11月15日(金)から劇場公開中だ。
もともとVimeoで無料公開されていた第1編「残り物たち」、2024年4月に公開された第2編「まわらない」に3編を追加した計5編で構成されるオムニバス形式の同作。奥山監督が普段から目にしていた東京・二子玉川の川沿いにある古ぼけたベンチを記録したいと思ったところから映画の制作がスタートしたという。
ゆったりした時間、オムニバス構成、ワンシチュエーション、精緻なショット……同作にはジム・ジャームッシュ監督やヴィム・ヴェンダース監督との共通点を見出すことができる。また、豪華俳優たちのそれぞれの演技に比重を置いている点、自分以外の脚本家に頼っている点など、映画監督としての経験不足を補う選択をしているところがクレバーだといえよう。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
奥山由之の個人的体験から生まれた『アット・ザ・ベンチ』
川沿いにポツンと佇む、一つのベンチ。写真家として、そしてCM、ミュージックビデオなどの映像作家としても知られている奥山由之は、いつも散歩するコースで目にしていた風景のなかに、車道からも水辺からも離れていて、ほとんど使用されていない、このベンチがあることが気になったのだという。
数年後、そんなベンチのある風景だけを舞台にして、仲間たちと自主映画を撮り始めたというのが、オムニバス映画『アット・ザ・ベンチ』の成り立ちであるらしい。何気ない風景に惹かれ、それを切り取り収めようとする発想は、まさに「写真家」の情動なのだろう。そして、そのようなプライベートなところからインスピレーションを得て、劇場公開される映画作品へと結実させるというケースは、非常に少ないといえよう。
本作『アット・ザ・ベンチ』は、5つの会話劇といえるエピソードからなる。第1編と第5編は脚本を生方美久が担当し、広瀬すず、仲野太賀が、幼馴染の役柄で登場する。観客は、この2人のやりとりを楽しみながら、会話の内容を頭の中で繋げていくことで、それぞれの状況や微妙な関係性を読み取っていくことになる。
INDEX
ジム・ジャームッシュ、ヴィム・ヴェンダースとの共通点
ベンチや、その周辺の風景、俳優たちしか画面に収めることができないという制約と、基本的に現実の時間と映画内の時間感覚が同じだという条件が共通している本作の趣向は、観客にむしろ豊かな印象を与えるかもしれない。それは展覧会で展示されるビデオインスタレーションのようでもあり、コントや小劇場の演劇のようでもある。
その雰囲気に、アメリカで長年インディペンデント映画を取り続けてきた巨匠ジム・ジャームッシュの『パターソン』(2016年)や、同じくドイツの巨匠監督ヴィム・ヴェンダース監督が日本で撮った『PERFECT DAYS』(2023年)をなんとなく想起させられるというのは、作中でベンチが印象的なものとして使われていることだけではないだろう。
この2人の巨匠監督に共通しているのは、ショットの精緻さであり、アートフィルム特有のゆったりした時間感覚、そして、日本を代表する映画監督、小津安二郎への深いリスペクトがあるということだ。小津監督はカメラスタッフや美術スタッフの役割を奪ってしまうほど、数センチ、数ミリ単位で小道具の位置や、全体の画角にこだわり抜き、目の覚めるような洗練されたショットを生み出すことで知られている。そして、それが独特の「間」による時間感覚とともに並べられていくのである。
2人の人物と風景、そして互いが話し合う時間……。街が開発されることで変化していくように、人生においてもまた、新しい人との出会いや会話の機会がある。ありふれたものだとその時に思っていたとしても、後になって考えると、それがかけがえのないものになり得ることを、われわれは経験で知っている。だからこそ、その一見、平凡に見える特別な時間を切り取ろうとする映画監督に、一種の「願い」のような熱量が生まれるのではないか。そしてそれこそが、小津映画や、ヴェンダース、ジャームッシュ作品に荘厳ともいえる静謐さを与えていると思えるのである。
奥山由之監督が初めての劇場公開作である『アット・ザ・ベンチ』において、3人の巨匠監督と同等の力で、それが表現できているとまで主張するつもりはない。しかし本作の第5編において、広瀬すずの顔を逆光で後ろから捉える、写真家ならではといえる被写体への強いこだわりを感じるところや、監督自身が「これ以上に純粋な創作は、生涯の中で何度と出来ることか分かりません」と語っているように、多くの劇映画とは異なるアプローチによって撮られた本作が、ある種の「特権性」を持ったものになっているのは事実だ。
ベンチのある風景を映画として記録する……このような個人的な感情が優先される映画づくりが可能となる機会というのは、そうそうあるものではない。だが、そういったプリミティブな原動力を肯定することで、本作はジャームッシュ監督やヴェンダース監督に繋がるものを得ているように感じられる。それは、映画監督としての一つの理想的な映画とのかかわり方なのかもしれない。