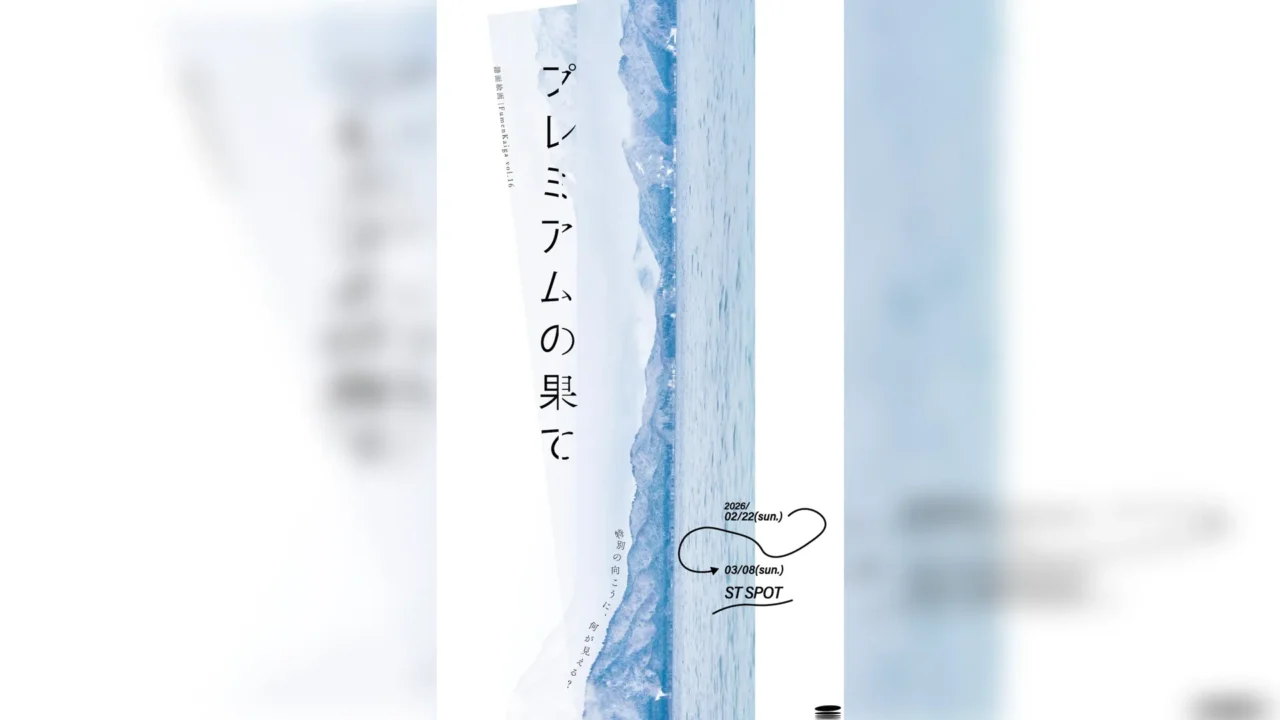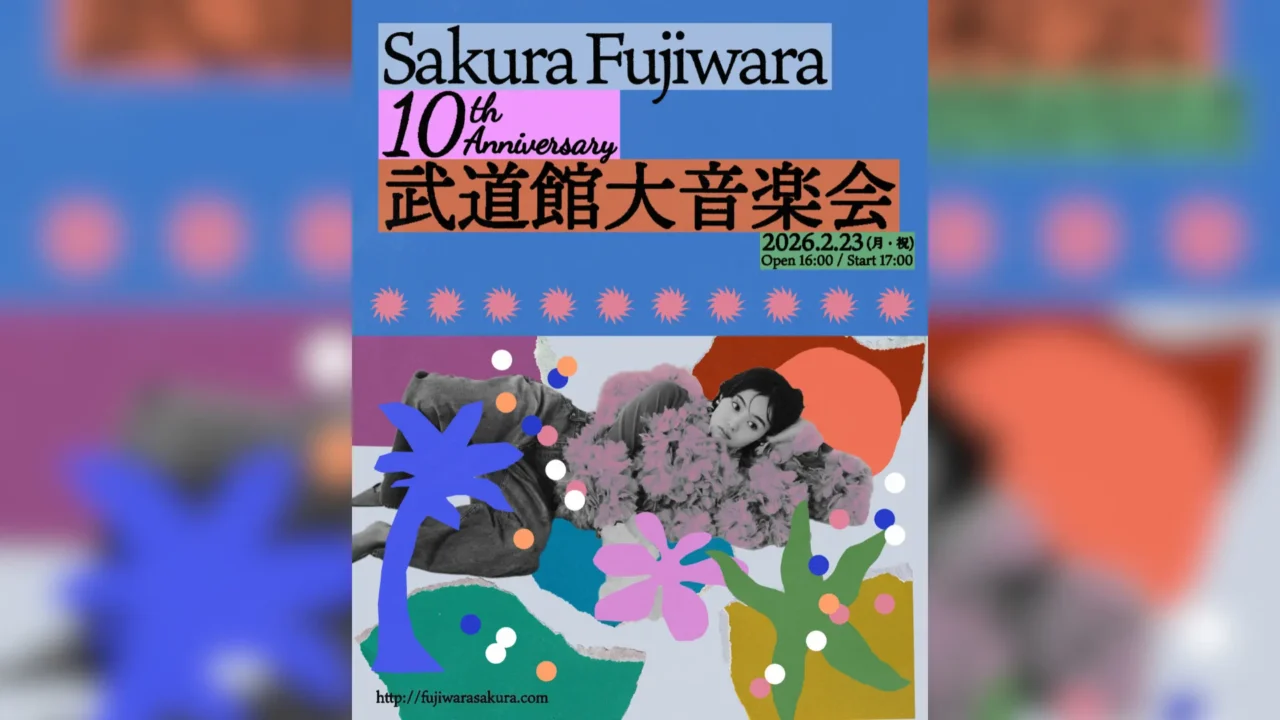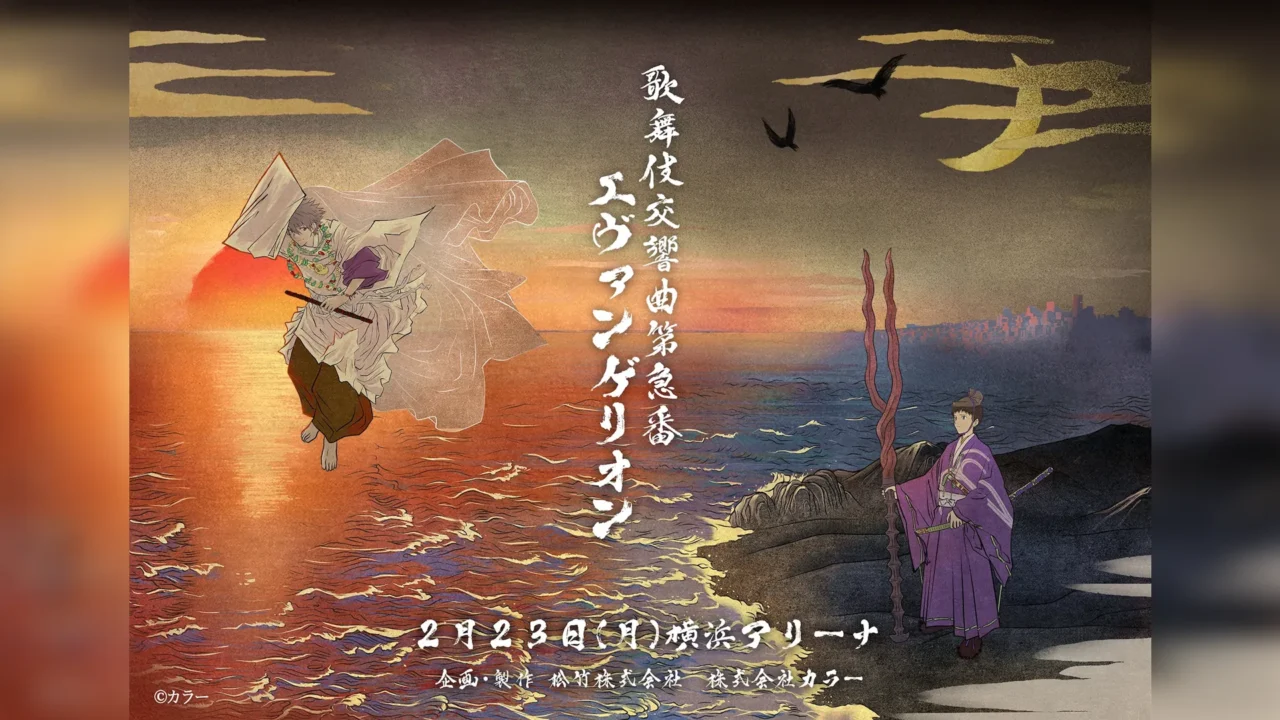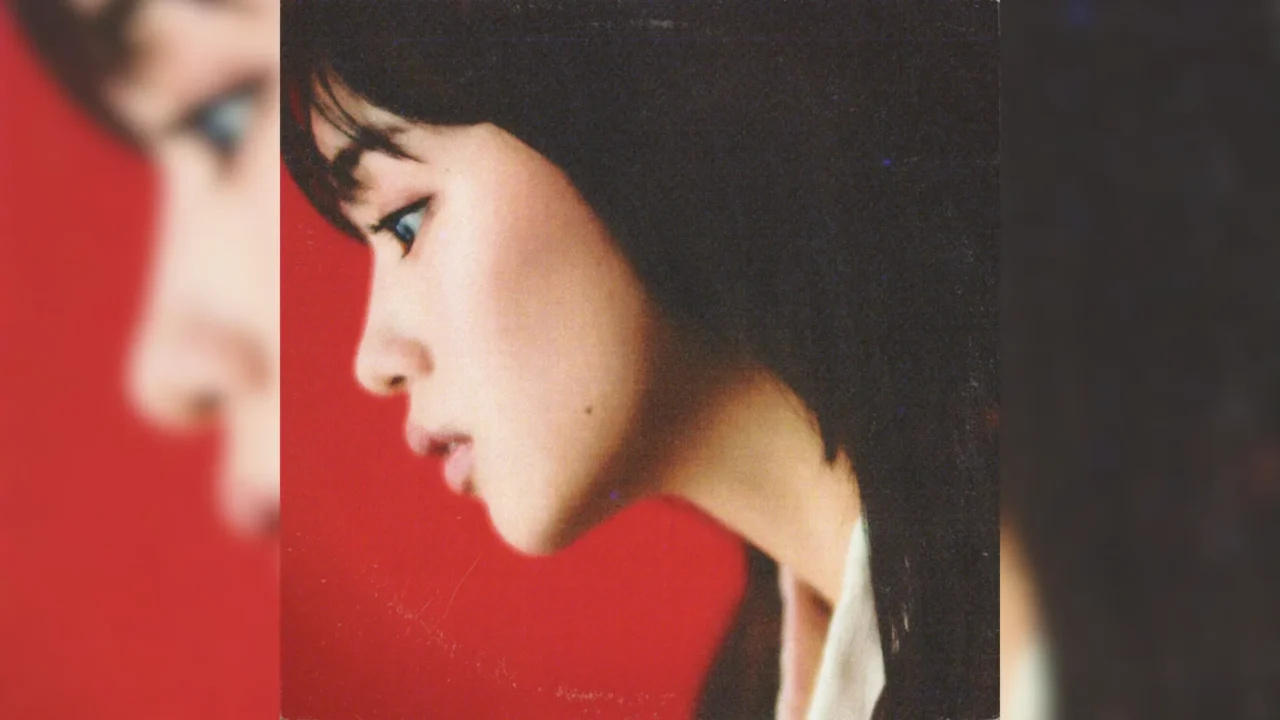INDEX
それまでは自分が冒険の主体だったけど、子供が生まれて変わっていった。
―制作スタイルの変化は楽曲自体にも表れていて、生演奏のバンドサウンドの割合が減り、ポストプロダクション含めて曲ごとにかなりつくりこまれた印象を受けます。
高城:そうだと思います。レコーディングでやることがグッと減って、その代わりポスプロ的なことがすごく増えました。アレンジもポスプロも一緒で、とにかくどんどんいじっていく。手を動かすのは圧倒的に荒内くんが多かったわけですが……(笑)。それってファーストアルバムのつくり方にすごく似てるんですよね。当時もただひたすら集まって、一年くらいかけてグダグダずっとつくってたので、すごくデジャブ感があって、「40歳近くなって、またこれやってる」みたいな(笑)。
―どこか一周したような感じもあると。
高城:やっぱりみんなソロ作品を出したのが大きかったんじゃないかと思います。住み分けというか、2つのアウトプットができたことで、「じゃあ、ceroではなにをやるべきか」っていうことに対して、もうちょっと純粋になっていくというかね。

―“Nemesis”も特に青写真はイメージせず、3人で自由につくっていったわけですか?
高城:そうですね。思いつくままに声を入れてたらクワイア的になっていったり、「ベースもそんなにいらないよね」って感じで、ホントに必要なところだけに入れたりとか。他の楽曲に関しても同様なので、「誰がつくった」っていう感じがないし、未だに自分たちがつくった感覚もなくて。特に“Nemesis”はそうですね。
歌詞に関しては、何曲かつくっていくと、言葉のあいだにリンクが生まれていくので、あたかもなんらかのプランに沿って進んだように最終的には見えると思うんですけど、一曲一曲はホントに断絶したプロジェクトというか、その都度ゼロからのスタートで。“Nemesis”を「#1」にして、それから「#2、#3」って、タイトルのない曲がひたすら量産されていく感じ。最後の最後まで青写真っぽいものはなかったです。

―楽曲のタイプはバラバラですけど、作品全体としてはこれまで以上にSF感が前に出ているように感じました。これまでもceroの作品にはSF的な要素があって、現実と非現実の中間や揺らぎを描いていたと思うんですけど、“Nemesis”は『STAR TREK』シリーズのタイトルで、昨年行われたツアータイトルも『TREK』だったし、『e o』というタイトルも「『キャプテンEO』?」と思ったり。これはコロナ禍以降、現実がまさにSFのような世界になったこととも関連しているように思ったのですが、いかがでしょうか?
高城:SF的と言われればまぁそうなのかもしれないですね。ただceroのアルバムにはこれまでずっと歌詞のなかに「冒険する主体」がいたと思うんですね。それが都市を散歩するくらいの規模感のものから、『My Lost City』みたいにもっと大きな舞台に飛び出して行ったり、『Obscure Ride』みたいに裏世界に行っちゃうような感じがあったり。でもそれが『POLY LIFE MULTI SOUL』から少し変わってきていて。その前に子供が生まれて、すっかり子育てのターンに入ったので、それまでは自分が冒険の主体だったけど、それがやんわり下に譲られていったというか、『POLY LIFE MULTI SOUL』は来るべきものがやってくるのを待つ主体に変わっていったと思うんですよね。
今回そういう青写真を描いたわけではないですけど、“Nemesis”も送る側の視点だと思う。なので、SFというには本人の動きがあまりないというか、なにかを切り開いて進んでいくような、線的な時間軸、リニアな世界観はどんどんなくなっていってる。そんな経過がここ最近のceroにはあるなって、個人的には分析していて。

―なるほど。
高城:そうなると、言葉の形式としてはだんだんリリカルになっていく。前はもっと叙事的だったけど、いまはもっと叙情的というか。だから、たしかにSFっぽいモチーフは使われてるんだけど、それは方便でしかないというか、もっとメタフォリカルなものかなって、できあがったものを聴いて思ったりしました。