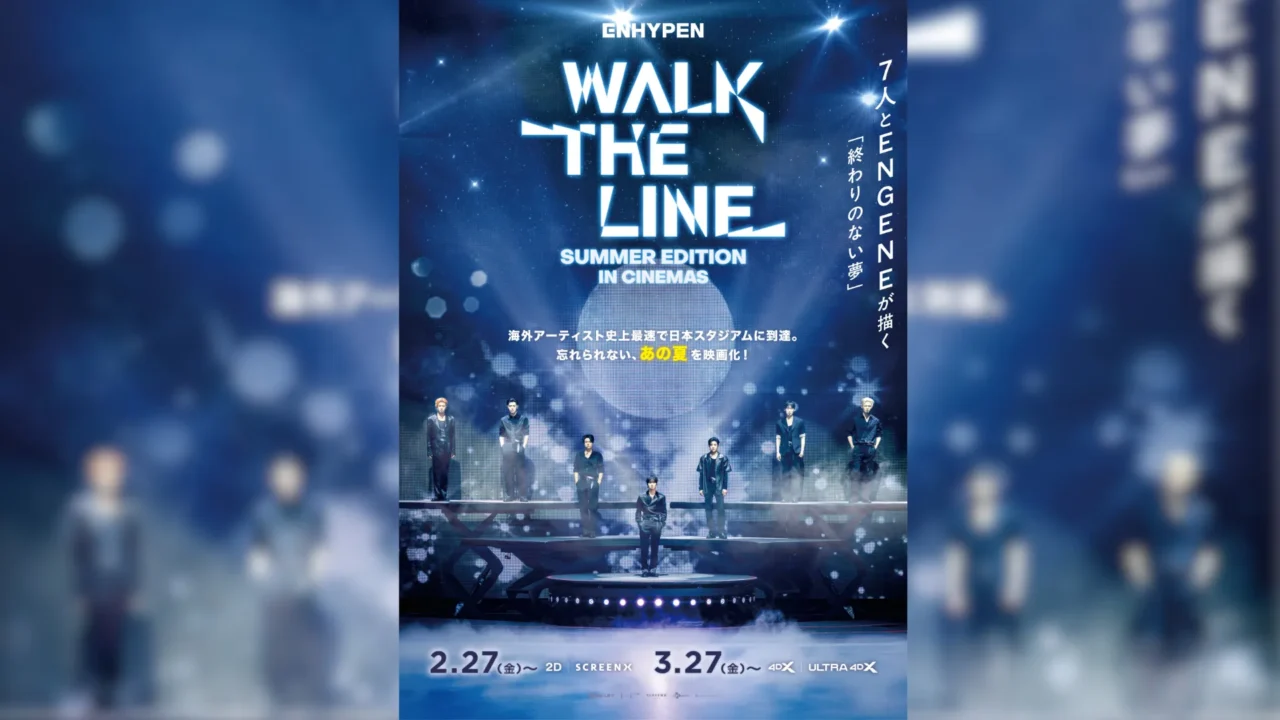近年、映画『オッペンハイマー』以上に賛否両論の度を越して醜聞と賛辞が噴出した作品はなかっただろう。
本作はクリストファー・ノーラン監督に、自身初『アカデミー賞』作品賞受賞の栄誉をもたらした。しかし一方で、現代の価値観に則って言い逃れし難い批判も存在しているのもまた事実だ。その一部はここでも紹介しているが、本作は政治的には必ずしも正しい作品ではないかもしれない。しかしその先で、映画監督としてクリストファー・ノーランが世界に対して描き出そうとしたものがたしかにあった。それは一体何だったのだろうか。ライター/マンガ研究家の小田切博が論じる。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
INDEX
『オッペンハイマー』の日本公開までに「作品の外側」で噴出した醜聞と賛辞
2023年度の『アカデミー賞』で作品賞、監督賞など7部門を受賞したクリストファー・ノーラン監督の最新作『オッペンハイマー』。助演男優賞を受賞したロバート・ダウニー・Jr.の授賞式での振舞が人種差別的であるとネット上で話題になるなど(註1)、3月29日にようやく日本でも公開されたこの作品は、アメリカでもあらためて注目を集めている。
2023年7月の全米公開時には、同時期に公開された『バービー』と本作のキャラクターを組み合わせたファンアートがSNSを中心に拡散(※)、「原爆被害を茶化している」と炎上したことも記憶に新しい(註2)が、結果的に同作はゴシップ的なエピソードに事欠かない作品になってしまった。
※編注:映画『バービー』を配給するワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、「#Barbenheimer」は「公式なものではありません」とし、一部のファンアートに本国のオフィシャルアカウントがリアクションしたことに対して「アメリカ本社の公式アカウントの配慮に欠けた反応は、極めて遺憾なものと考えており、この事態を重く受け止め、アメリカ本社に然るべき対応を求めています」とコメントを発表している(Xを開く)

特に日本では、「広島、長崎に投下された原子力爆弾の開発者であるロバート・オッペンハイマーの伝記」というセンシティブな題材のためか、炎上時にも公開は予定されておらず、アメリカでの配給元であるユニバーサル・ピクチャーズ、日本での同社作品の主要な公開窓口である東宝東和は、ともに本作の劇場公開に積極的に動かなかったことが報じられている(註3)。その後12月になってから独立系配給会社ビターズ・エンドが本作を日本公開することをアナウンスし(註4)、2024年3月の公開がようやく実現した経緯がある。
コミックスヒーロー、バットマンを主人公とした『ダークナイト』3部作など、日本でも高い人気、知名度を誇るノーラン監督の、世界的にヒットした新作が観られないことは、結果としてそれ自体がネットニュース的な関心を呼んだ。この「幻の作品」はここ半年強のあいだ、だからこそ繰り返し日本語でも語られ続けてきた。
INDEX
米国での賛辞の裏で指摘されていた「画面から消された人たち」
「作品が劇場で観られないかもしれない」という特殊な状況は、必然的にそのヒットや映画としての価値の主張、賞賛の声を強調することにもなっている。
『アカデミー賞』の受賞結果を見てもわかるように、評価が高いのはたしかだが、じつは本作にはアメリカでもほぼ全否定に近い反応もある——それは、日系に限らないアジア系アメリカ人による作中の人種的な偏りに対する拒否反応だ。
たとえばサンフランシスコの日系人記者オリビア・クルス・マエダは「『オッペンハイマー』が消したのは誰か」(注5)と題する記事において、実際に原爆被害を受けた日本人はもちろん、研究所の置かれたロスアラモスから強制退去させられ、核実験後に放射能汚染された土地に帰還せざるを得なかったネイティブアメリカン、1946年から1958年のあいだにアメリカによる核実験の舞台となったマーシャル諸島の住民など、核開発によって実際に被害を受けた人々の存在がほとんど顧みられていないことを指摘し、ハリウッド映画の白人中心主義を痛烈に批判している。
また、ウェブメディア「Business Insider」のライター、ハン・ユンジによれば、現実の「マンハッタン計画」の現場には女性研究者、アジア系、アフリカ系の研究者が参加していたにも関わらずこの映画の画面からはその存在自体が消されているという(註6、7)。

こうしたアメリカでの反応を読むまで私自身考えてもみなかったことだったが、「Black Lives Matter」や「アジアンヘイト」といった人種問題の深刻化を経たアメリカ合衆国という多民族社会において、クリストファー・ノーランというイギリス人監督がこの映画の画面に描き出してしまっている無自覚なエスノセントリズム(※)は、じつは「広島、長崎の具体的な被害描写がないこと」以上に深刻な問題であるように思える。
※編注:「自文化中心主義」とも訳され、自分が属する集団の文化や価値観を基準として、ほかの文化の優劣やよし悪しを判断する見方のこと
INDEX
『オッペンハイマー』に反戦、反核の意図はあったのか?
先にも触れたが、日本でもアメリカでも本作に対するもっとも頻繁になされている批判は、劇中に原爆投下後の広島と長崎の惨状についての具体的な描写が一切ないことに対するものだ(註8)。
ノーラン自身はこうした批判に対して「彼は、当時の世界の人々と同じく、広島と長崎への爆撃をラジオで知ったのです」と答え(註9)、この描写の欠落が、「主人公であるオッペンハイマーの視点から語られる物語」(※)であることを重視したためだという主旨の説明をしている。
このような発言も踏まえ、日本国内で本作公開を求め、作品を賞賛する目的で書かれたテキストにおいてはしばしば、「実際に映画を観ればこの映画が持つ反戦、反核の意図はあきらかだ」という主旨のメッセージが語られてきた(註10)。
※編注:脚本におけるオッペンハイマーに関する箇所は一人称で書かれていた。その異例な手法の意図について、監督は「脚本を読む人は、我々観客がオッペンハイマーと同じ視点を共有していることが分かる。我々はオッペンハイマーの肩越しにものを見、彼の頭の中にいて、どこに行くにも彼と一緒なんだ」と説明している(映画『オッペンハイマー』プロダクションノーツより)
私自身は、実際に作品を鑑賞し、この映画に関する国内外のレビューや評論をある程度読んだうえで、こうした見方に対して一定の違和感を持つ。
この映画では、ノーラン監督らしく、時系列の異なる2つのシークエンスを交互に見せることで「原爆の父」オッペンハイマーの人生が語られていくのだが、じつはその双方の描写を合わせたうえで劇中ではほとんど無視されている期間が存在している。
このことは本作が原作としてクレジットされている評伝『オッペンハイマー』(註11)の記述と映画の描写を照らし合わせてみれば明確にわかることだが、1945年のハリー・トルーマン大統領との印象深い対話後、映画後半のクライマックスとなる1954年の公職追放に至る1953年末の告発と査問会までの9年ほどの出来事が、映画のなかでは部分的にしか描かれていないのだ。
そして、この「原作」の記述に従うなら、実在するオッペンハイマーという人物が核兵器の拡散や核戦争の抑止といった「反戦」「反核」的な意味を持つ活動にもっとも精力的だったのは、まさにこの9年間なのである。