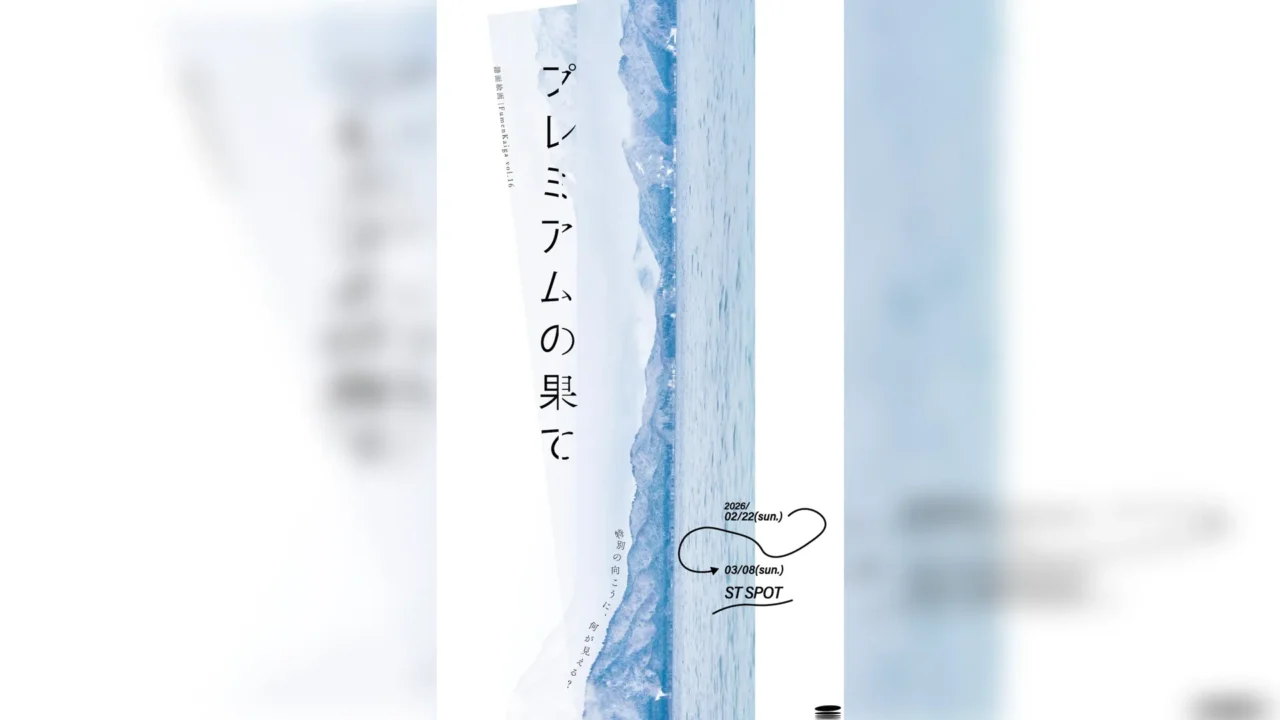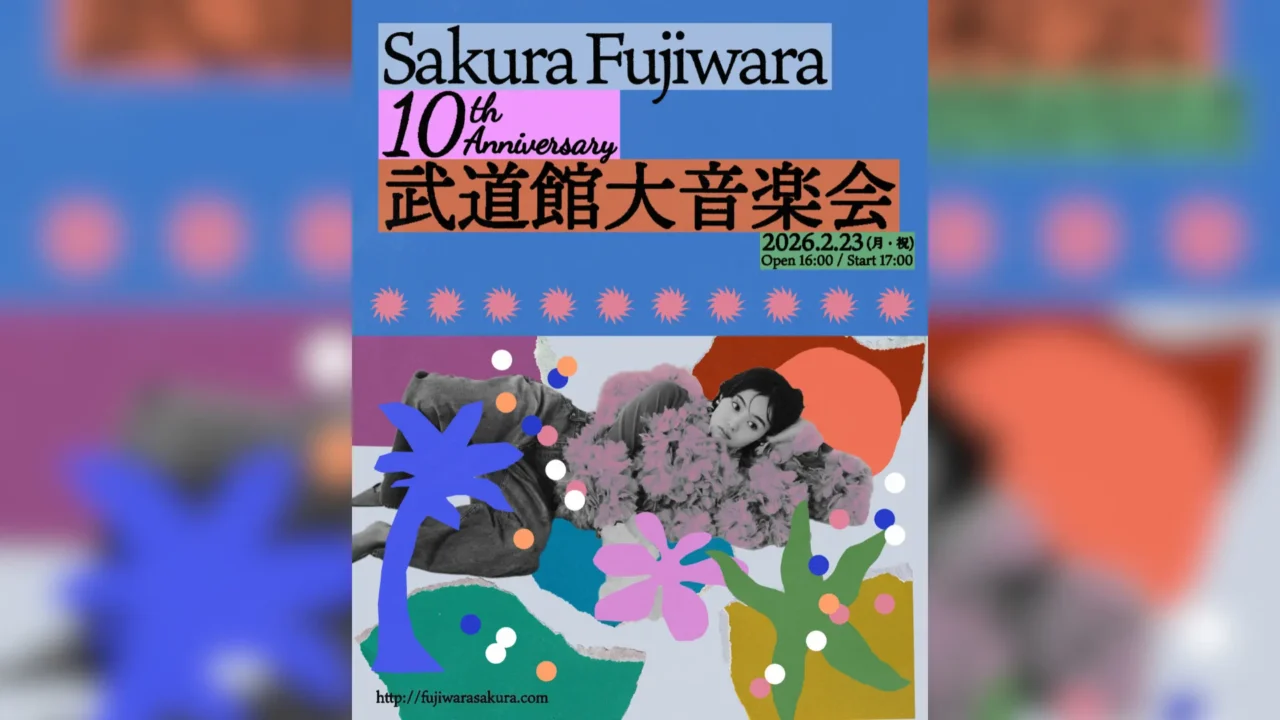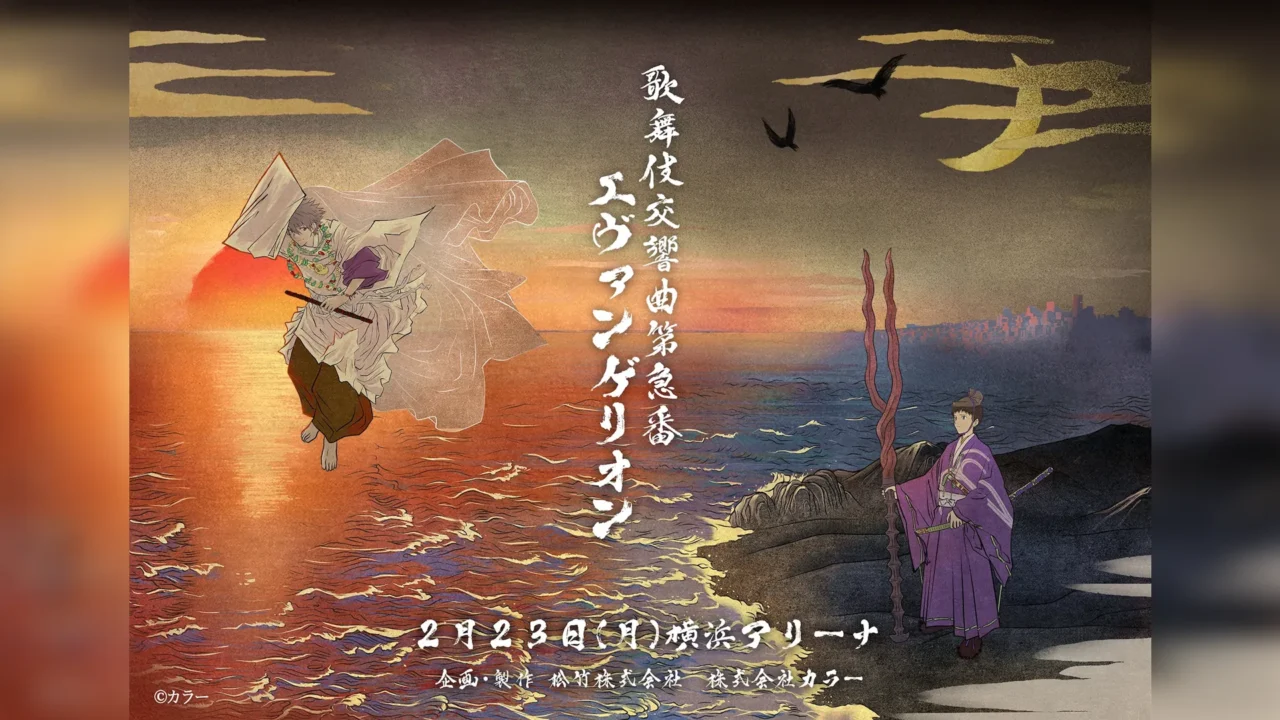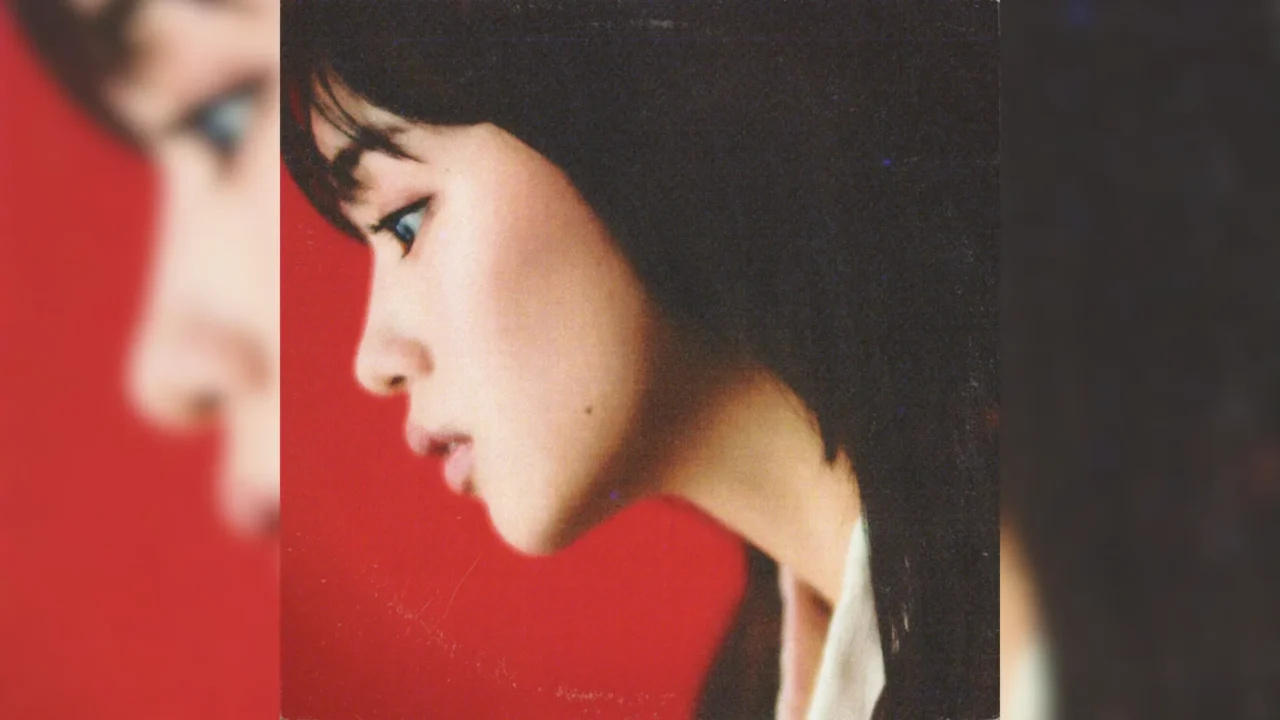INDEX
歌詞とはちがい、手がかりが少なく難しい「言葉を書く」作業
─『文學界』での川野芽生さんとの対談でも、歌詞と違って「文章では最終的には意味を言葉で書き切るんだっていう気持ちが大事だなといつも感じる」という話をされていましたね。
柴田:歌詞や短歌や小説は、伝わり切らなくても良いところが残ると思うんですけど、エッセイってそこが曖昧だなと思っていて。すごく芸術的に書く人もいれば、「天声人語」みたいなエッセイもありますし。表に出すものである以上、どうしてもつくりものとしてのフィクション性はあると思うんですけど、歌詞とはまったく違う書き方をしないと面白くならないという印象があって。
歌詞の場合は、音とか演奏する人とか、いろいろな要素と合わせて伝えることができるんですけど、文字って抽象的で、それだけで何かを表していくことってかなり難しくて。土台がないところに家を建てられないというか、きちんと構造を持たないと伝わっていかないということはすごく感じていました。
─その助けになったのがプレーンな文体だったという感覚ですか?
柴田:たとえば林檎だって、文字だけで書き表そうとすると結構大変です。林檎なら大体想像がつくかもしれないけど、ちょっと不思議なこととか、現実から離れたこと、心の中で思っていることって、人にはあんまり共感できなかったりしますよね。
それを表すためには構造をしっかりさせないといけなくて、文章のつなぎ目を正しく使っている感じがする文章は伝わりやすいなと思います。誰も見たことがないものを書くことこそが面白いような気がするから、言葉を書いている人たちは孤独な作業をしているんだなと感じました。

─文章の場合、メロディーはないかもしれないけれど、リズムやグルーヴのようなものはあると思うのですが、そこについてはどんな意識を持って書いていましたか?
柴田:普段から詩を書いて、メロディーに当てるうえでもリズムは重要視しているので、癖になっているところがあって。読んでいて気持ちいいなとか、スピード感が出るなとか、逆に落ちるなとか、そういうことは意識していましたね。音楽よりも文章の方が、より自由にリズムを組み立てられるのは面白いなと思いました。
─文章の方が自由だと感じたんですね。
柴田:ただ、無限大の自由を前にして、逆に何もできないときってあるじゃないですか。制約がほぼないので「広大だな、この地平は」と感じていました。音楽の場合、詩を書いたり、曲をつくったり、アレンジをつくったり、ミックスしたりする全部の過程が、私はずっとつながっているんです。でも文章の場合は、手がかりが文字しかなくて。長い文章を書く人はどうやって把握しているのかすごく不思議でした。
─タイトルに「ダイアリー」とあるように、日記形式だったことは、一つの制約ではありましたね。
柴田:初代の編集さんに、どう書き始めていいかわからないという話をしたときに「何月某日」という入り方にしてみてはどうですかという提案をもらって。確かに縛りが一つあることは大事だなと思いました。