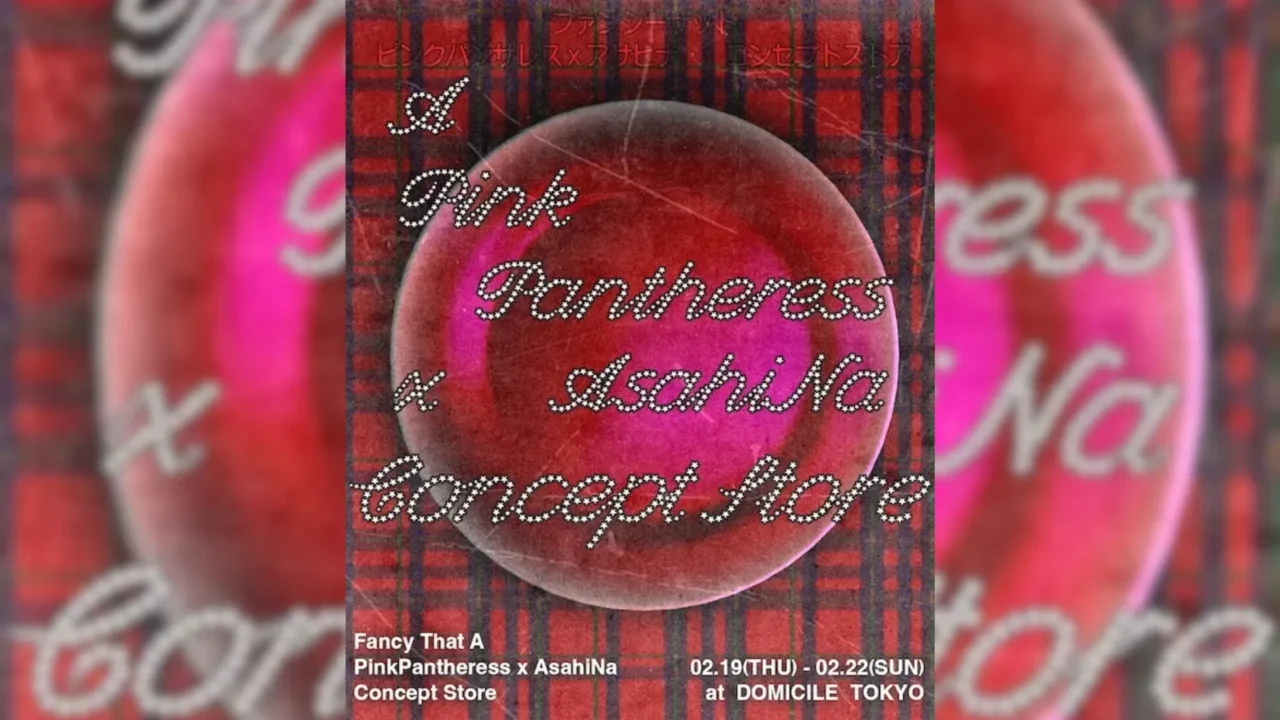INDEX
新しいことができるなら「とにかくまずは試してみたい」
─ここまで、音楽を軸にお話を伺ってきましたが、音楽以外の趣味はあったのですか?
江﨑:ありました。僕、ずっとロボットエンジニアになりたかったんですよ。小学校高学年の頃は、プログラミングをやったり、福岡市立少年科学文化会館のクラブ活動「発明クラブ」に入会していたり(笑)。サッカーロボットを組み立て、それをプログラミングしてロボット同士でサッカーをさせる「ロボカップジュニア」にも参加していました。
─へえ!
江﨑:小学校の卒業文集には、「工学部を出て30歳になるときには、二重跳びができる自律型の二足歩行ロボットを作る」という具体的な目標を掲げていて、ちょうど今30歳なんですけど、ボストン・ダイナミクスのロボットが宙返りができるようになっているから、目標設定の仕方は結構いい線いっていたんだなと(笑)。

─あははは。じゃあ、その頃はミュージシャンになろうとは……。
江﨑:全く思っていなかったです。高校二年生の途中までは、工学部に行くことしか考えてなかったですね。そうやって小さい頃から理系的なことをやっていたからこそ、音楽は自分のエモーショナルな部分を出すフォーマットというふうに捉えているかもしれないです。
─たしかに江﨑さん、音楽活動の中で、新しいテクノロジーに対して敏感ですよね。WONKでの『EYES』スペシャル3DCGライブや、『artless』のDolby Atmosミックスも、江﨑さんのアイデアから実現したことですか?
江﨑:3DCGライブに関しては、ベースの井上幹がゲーム会社で働いているという兼ね合いもあったんですが、Dolby Atmosは僕がメンバーに強くアピールして実現したことでした。今も、音楽よりテック関係のニュースを見る時間の方が多いので、新しいことができるなら「とにかくまずは試してみたい」という気持ちがすごくあるんです。
「ポストAI時代」の到来で揺らぐアイデンティティ
─それでは今、江﨑さんがもっとも興味があるのはどんなことですか?
江﨑:「これから僕たちは、一体どうやって生きていったらいいのだろう?」ということですね。今って産業革命前夜みたいな空気じゃないですか。地球上の様々なことが不安定だし、これまで当たり前に繰り返されてきたことが成立しなくなる瞬間が見え隠れしていて、遅かれ早かれものすごいパラダイムシフトが起きそうだなと思うんです。それに対してみんなはどう対峙するのだろう? というのが、今もっとも興味のあることですね。
例えば職能一つとってみても、僕は「音楽を作る人」という自覚があり、それを好きでやっている自覚もある。変な話、誰かに求められなくてもこれからも音楽を作っていくだろうし、自分が手を動かしていることに意味を感じているんですけど、みんながみんなそういう生き方をしているわけじゃないから、今後いろいろなものが自動化される時代が到来したときに、人はどう生きていくのかなと。

─何か人から求められることに「応える」という形で仕事をしてきた人が、求められなくなったときにどう生きていくのか、ということですね。
江﨑:そうですね。もし機械が圧倒的にクオリティの高いものを短時間で出してくるようになったとき、人は何に生きがいを見出すのか。音楽も、機械が人間のクオリティを超える時が来るかもしれない。でも、僕は誰にも求められていないのに手を動かし音楽を作っていることそのものに意味を見出しているから、そこは関係ないし「僕がやっていることに意味がある」と割り切れる。でも、そう思えない方もいらっしゃるだろうし、そうも言っていられない領域も絶対にあるわけだから。
そうやって社会が大きく転換していく時って、みんな拠り所を求めると思うんですよね。アイデンティティがかなり揺らぐわけですから。そうなったときに、日本に住む我々は何に立ち返るのだろう? と。例えば明治維新は、日本にとって紛れもない大転換期だったわけですが、その時には『武士道』(新渡戸稲造)という本が出たり、茶の湯が見直されたりしたわけじゃないですか。谷崎潤一郎の『陰影礼賛』もそう。
「今の世の中になる前、本来はこうだったよ?」「こういうことが、脈々と受け継がれているよね?」みたいなことが、こういう揺らぎの時代に整理される。であれば、今この瞬間どこかで誰かがそういう整理をしてくれているのではないか、だとしたらそれはどんなものなのかがすごく気になっています。
─それこそ江﨑さんの今回のソロ作『はじまりの夜』のコンセプトにも通じるところがありますよね。
江﨑:今回のソロアルバムの背景には2つのテーマがあります。まずは自分自身のこと。20代は、自分のルーツにないものを音楽家としてたくさん演奏してきたことで、「自分ってなんだろう?」というのが少し揺らいでいたんです。それから、今お話しした「ポストAI時代」のこと。それはおそらく、明治維新期の「揺らぎ」に何かしら似たところがあるのかなと思っていて。そんなタイミングで『陰影礼賛』という本に出会ったとき、「もともとこういう感性があったはずだ」みたいなことを、自分の作品の中で自分に対して言いたいという気持ちが芽生えたんです。自分自身の原点に立ち返るということ、そして、大きな空間で皆で聴くのではなく、あくまで一人で聴くことを前提とした音楽であること。この2つをアルバムのテーマに設定しました。
インタビュー後編はこちらから。
初のソロアルバム『はじまりの夜』について詳しく伺います。