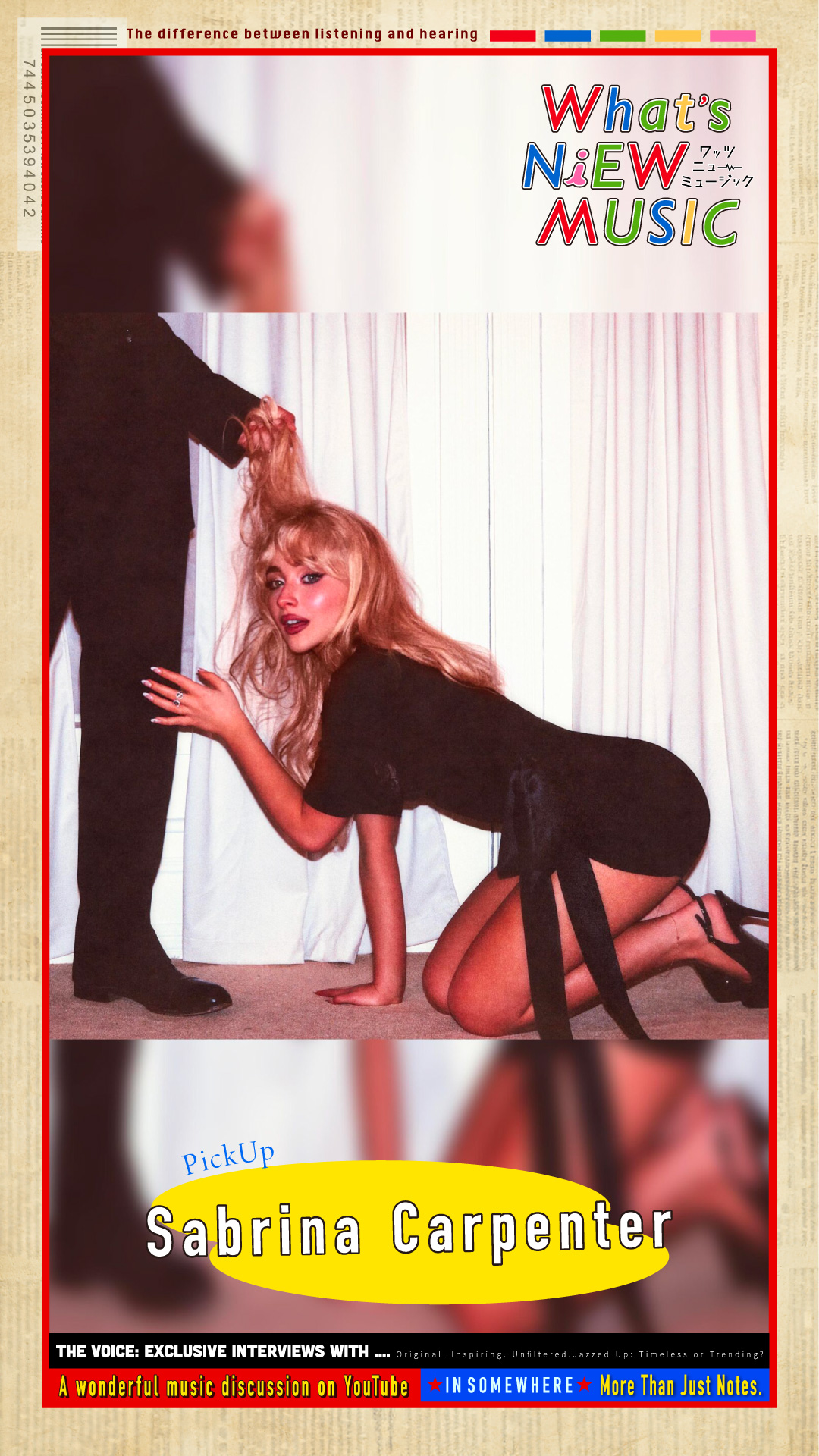INDEX
ハイパーポップは実存と結びついている
つやちゃん:自分は国内のハイパーポップと言われているアーティストの取材をけっこうやっているんですけど、みなさん口を揃えて「次のJ-POPにしたい」というのは言っていて、実際そのコミュニティ周辺ではSATOHなどメジャー契約を結ぶアーティストもちらほら出てきています。ハイパーポップのテクスチャを導入したJ-POPも、今年になって増えていて。でも、アーティストと話していて思うのは、メジャーに行ってやりたいことと違う音楽をやることへの恐怖感だったり、それがタブー視されているような感覚が強いんですよね。時間をかけてゆっくりと自分の追求する音楽をやっていきたいというのはすごく感じます。先日インタビューしたkillwizもそういったことを言っていましたね。
伏見:すごく面白いですね。ハイパーポップって刹那的な感じがするし、ネットカルチャー自体、出ては消えるものっていう感覚がふつうだったと思うので、ハイパーポップと呼ばれるジャンルが「時間をかけて成熟させる」みたいな方向にいっているとしたら、それはすごく面白いと思いました。
つやちゃん:もともとジャンルの起源的に、読めない記号を曲名に使うとか、検索回避みたいな性質があったりするじゃないですか。ハイパーポップという名称をあえて使わず、ハイパーミュージックやオルタナティブヒップホップみたいに表現してコミュニケーションするとか、ハイパーポップっていう文化をどう守っていこうか、みんなで考えている感じはしますね。
伏見:ハイパーポップはvaporwaveと違って、「ネットのおもちゃ」感も実はしないというか、ネットにあるものが実存的に結びついてる人達がやっている音楽ですよね。実存がかかっているからシャバいものにはできない、というのがあるんじゃないかと思います。
つやちゃん:はい、はい。
清家:シャバい売れ方をしないというのは、ファンのことも考えているのかなと思います。ハイパーポップ的なパーティーに来てる人って、それがコミュニティライフラインの人もいると思うので、そういう人を置き去りにして、タイアップとかをガンガンやって音楽性を変えて売れると、やっぱちょっと、というのはありますよね。
つやちゃん:自分もハイパーなイベントにけっこう行く方で、自分自身もすごくそこに救われたっていう気がしています。この4、5年、あのカルチャーがなかったら、こういう仕事はしてなかったかもしれない。ふつうにクラブ行きます、ライブ見に行きますとは全く違う、「あそこが居場所である」っていう感覚があって、だからみんなであそこを守っていこうというのはあると思います。