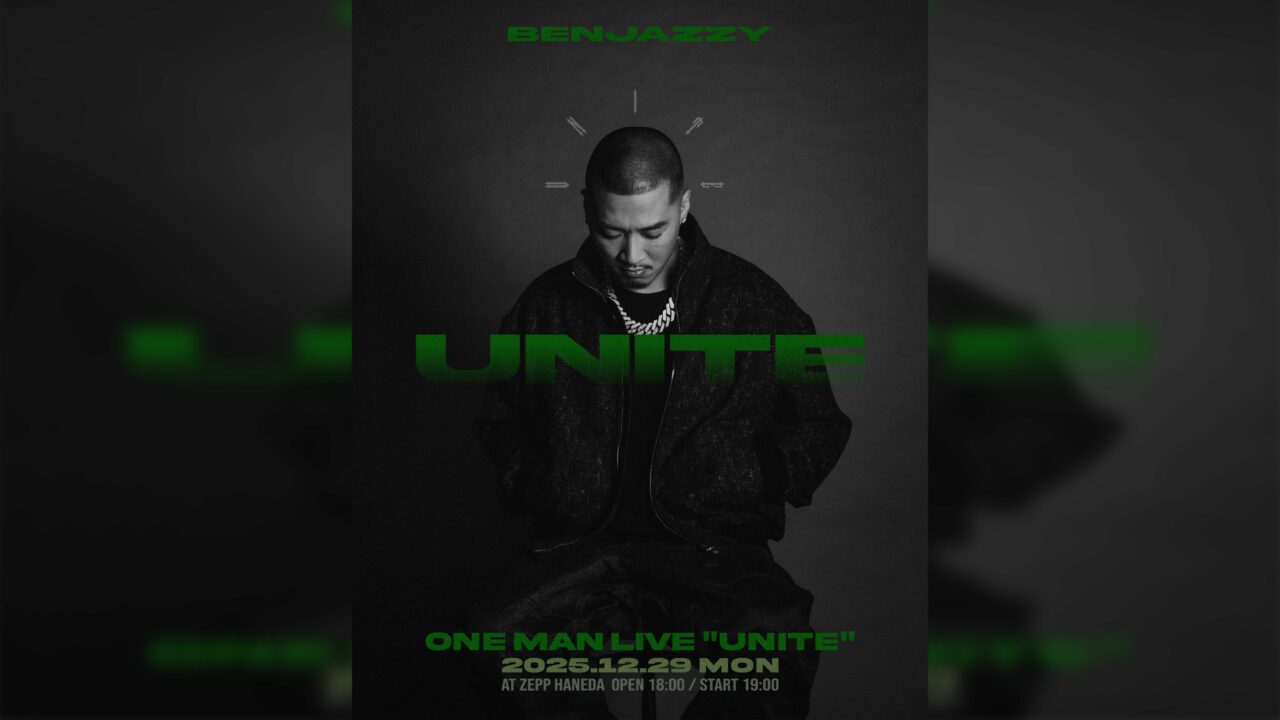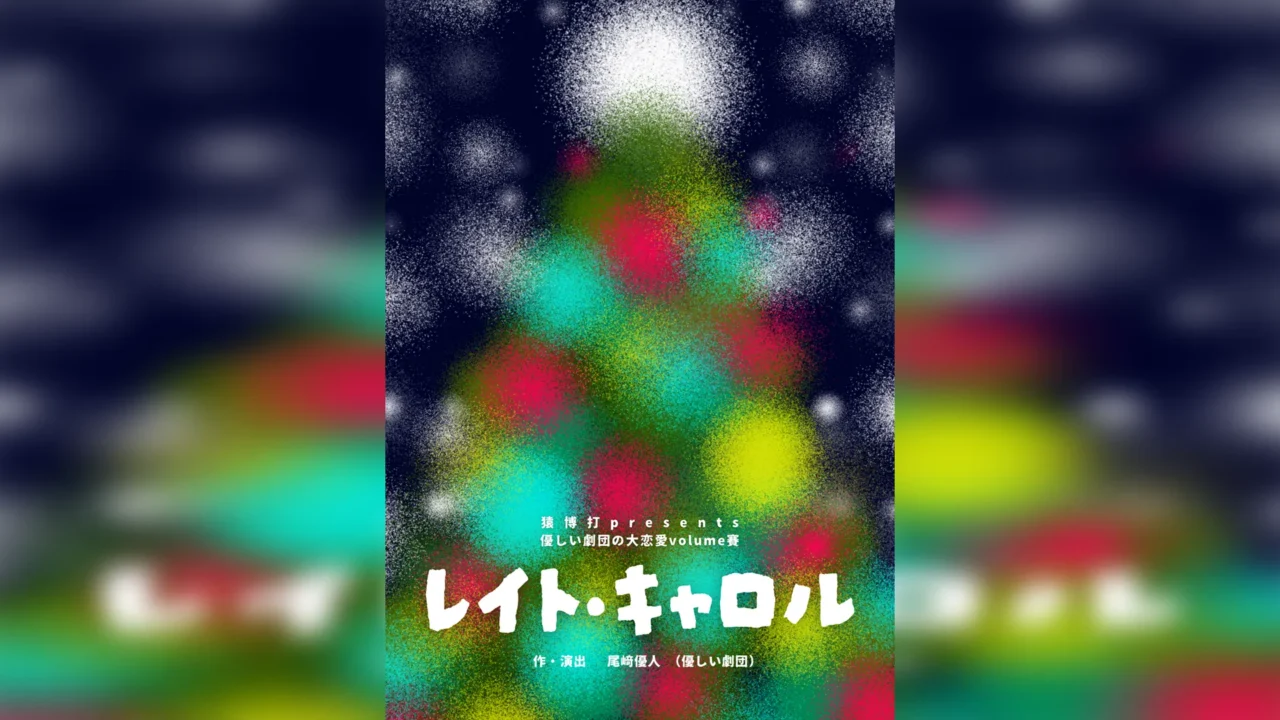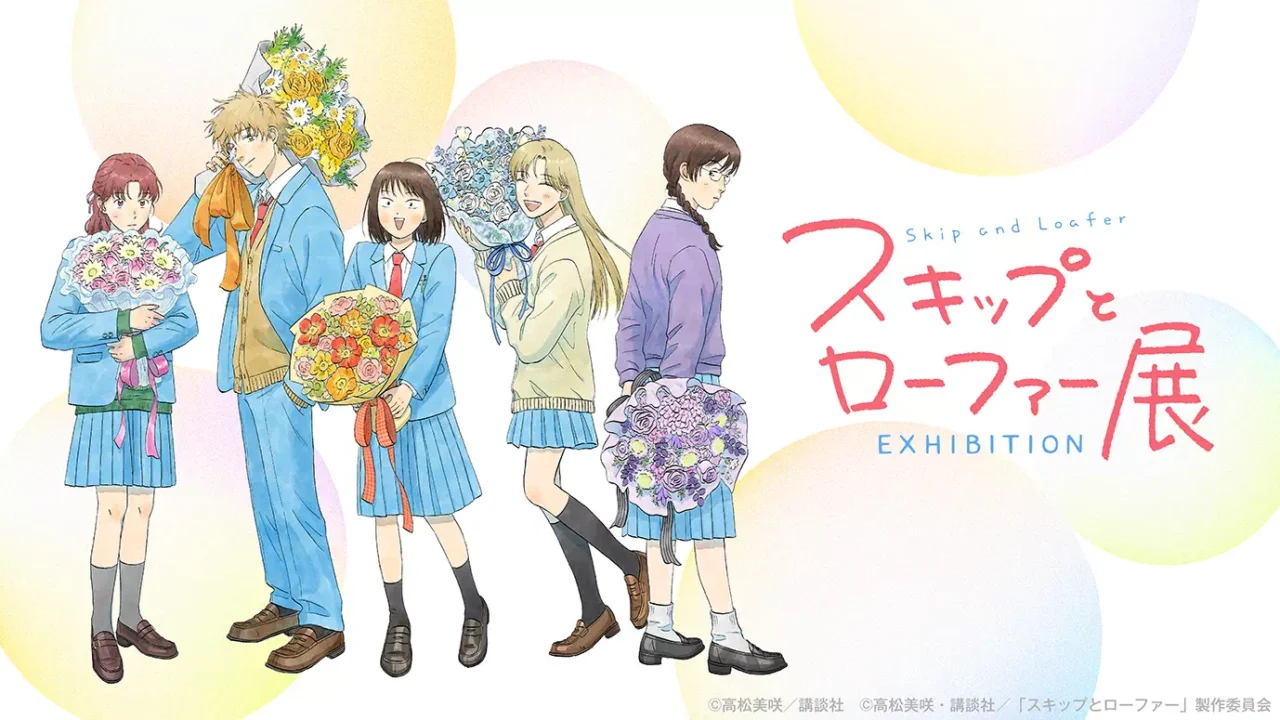現代社会に生きる女性を取り巻く問題を、フェミニズムの見地から捉え直す漫画『わたしたちは無痛恋愛がしたい 〜鍵垢女子と星屑男子とフェミおじさん〜』(以下『無痛恋愛』)を連載中の瀧波ユカリさん。
さまざまな事情を抱えながら人生を突き進む登場人物たちに、ハラハラしたり腹を立てたり涙したり、社会的なテーマを真正面から扱いながらも(扱っているからこそ)とにかくめっぽう面白い。
『無痛恋愛』の単行本を購入した読者から送られた相談に瀧波さんが答える「人生悲喜交々、とにかく瀧波ユカリに相談だ」という企画も、漫画のスピンオフの範疇を超えて一級品の人生相談だ。
寄せられた悩みに対して、瀧波さんはかなり具体的な解決法を提示する。この連載で今まで話を聞いてきたお2人よりも、一歩二歩踏み込んだスタンスに思える。しかし、押し付けがましくなることはなく、その線引きは非常に鮮やか。相談内容からブレることなく、瀧波さんが言いたいことをしっかり添えて、的確に打ち返している。
瀧波さん、自分のメッセージを躊躇せず、しかも相手にとっても有益な方法で伝えるのって、ものすごく難しくありませんか?
INDEX
人生相談のコツは掴みました
ー『無痛恋愛』の読者に向けて人生相談をやったきっかけはなんだったんですか?
瀧波:担当編集さんが販促の一環として提案してくれたんです。あまり聞いたことがない企画だし、やってみましょうかと。めちゃくちゃ相談が来たらどうしようかと思ってたんですが、この企画で答えられそうなものはそんなには来ませんでしたね。
相談と言いつつ私への質問やメッセージだったりもしますし、文章量がものすごく多いものは掲載するときに削らなくちゃいけないので、そうすると真意が伝わらないこともあるから選べなかったり。こういった人生相談に送られるお悩みは、寄せられた時点である程度ふるいにかけられる運命にあるんですよね。

漫画家。札幌市に生まれ、釧路市で育つ。日本大学芸術学部を卒業後、2004年に24歳のフリーター女子の日常を描いた4コマ漫画『臨死!!江古田ちゃん』でデビュー。現在、『わたしたちは無痛恋愛がしたい』を連載中。そのほか、「ポリタスTV」にて、「瀧波ユカリの なんでもカタリタスTV」にも出演中。
ー内容以前に採用されうる形式が決まっていると。
瀧波:その上で、あまりにも特殊だと読む人も共感しづらいので、なるべく普遍的で答えやすいものを選んでいくしかなくて。そうすると3、4つに絞られるんです。
ーどの相談に対しても、堂々たる答えっぷりですよね。
瀧波:『ESSE』で人生相談の連載(『瀧波ユカリのごきげんで行こう!』)をしていたときは、初めてだったので難しいなと思ってました。今は、こう言っちゃうと人生相談に対する夢がなくなると思いますが、コツがつかめました(笑)。
ーまさにそのコツをお聞きしたいです。
瀧波:まず絶対に必要なのは「相談者の立場に立って考える」ことですよね。でも、相談者はたいてい大変な状況にいるので、それだけだと解決策は出てこないんです。
なので、まず「大変だね」ということを言葉にしてあげるのが大事だと思っていて。相談内容に共感した上で問題を削ぎ落としていく。なんて言うんだろう、レントゲンを撮るような感じ。
ー診察にも似ていますね。
瀧波:生身の患者と接して、「それはお辛いですね」と話した後にレントゲンを撮って、「ここにちょっと影が出てます」と悪い部分を見つけるのがコツだと思うんです。その影が全身に散らばりすぎていると解決は不可能もしれないけど、人生相談に送ってくる人はまだ取り返しがつく状態だと思うんですよ。でも混乱していて、具体的に何かするには至らないような状況。
このまま医学になぞらえると、「この部位に影がある」ということがわかれば対処療法はだいたい確立されているじゃないですか。自分の中に人生相談的な対処療法があれば、すぐに答えられるんです。それをどうやって見つけるかは、自分の今までの生き方によると思いますね。

ー自分が経験したことがないことはお勧めできないというか。
瀧波:でも、雑誌やラジオで人生相談に答えている人は私も含めフリーランスが多いですけど、みんな会社での悩みに答えてますよね。勤めたこともないのに(笑)。だから、同じ経験をしていなくてもいいんだけど、極力近い経験を持っていて、それをすでに俯瞰できていることが大事なのかなと思うんです。
「いつも落ち込んでしまいます」というお悩みが来たとして、自分が落ち込んだときの解決法を俯瞰できているなら「こうすれば大丈夫かも」と答えられるし、どうにもならなかった経験を俯瞰できていれば「どうにもなりませんよ」を答えられる。答える人もどっぷり落ち込んで悩んでいる最中だったら、うまく答えられないですよね。自分がその悩みにどんな結末を迎えたとしても、俯瞰していれば答えられるんじゃないのかなと。小説家とかエッセイストとか、ものを書いている人には俯瞰癖があると思うんですよ。
ー世界のことを自分のフィルターを通して文章として再構成しているわけなので、俯瞰そのものの作業です。
瀧波:そうそう、だから人生相談の回答者にはものを書く人が多いんだと思うんですよね。
INDEX
人生相談の権威は下がったけど、質は上がった
ー最初に相談者の痛みを受け入れるのがとても大事なのかなと思いました。「ここが痛いです」という訴えに対して「気のせいですよ」と返したら診療が成り立たないわけですけど、相談にそうやって答えている人はけっこう多い気がします。
瀧波:うんうん。でも、昔はあんまり相談者に寄り添うことがなかったと思うんですね。私が「こんなに寄り添っていいんだ⁉︎」と思ったのは、雨宮まみさんの人生相談(『まじめに生きるって損ですか?』として書籍化)。びっくりするくらい寄り添っていました。雨宮さんという実例が出てきたことによって、他の人もためらわず寄り添えるようになったんじゃないかという気がしてて。あの連載が始まったのが2010年代前半だったと思うんですけど(※)、そこが分岐点というか、ちゃんと相談者の痛みを受けとめる形が増えていったように思います。
※『穴の底でお待ちしています』のタイトルで2014年からスタート

ーそれまでは、相談に対して「そんなもんは大したことない」という感じで一発かます技法が主流だったような気がします。
瀧波:以前の方がずっと、相談者よりも読者のほうを意識してましたよね。権威的というか。権威といっても社会的に偉いというよりは、サブカルやオシャレのようなちょっと砕けたジャンルで権威とされる人が、雑誌とかで軽妙な語り口を見せつけるようなものが多かったと思います。だから、あまり相談者への寄り添いも求められてなかったというか。今考えると、その頃の人生相談に投稿してた人って、何を期待してたんでしょうね……。
ー自分の悩みが否定されて面白がられるわけですもんね。
瀧波:毒舌系も多かったですし。でも、SNSもまだないから、否定されるにしても有名な人に何か答えてもらえるという価値があったのかもしれない。その価値が暴落したら、「なんでこんなけちょんけちょんに言われないといけないんだ!」という感覚も出てきますよね。そうなると権威的な人よりも、もっと身近なことを書いている人や、同世代のシンパシーを得ている人に答えてもらった方がいいよね、となっていったんじゃないかと。
でも、人生相談自体も権威だったから、今はそれも下がったという感じがしますね。
ー新聞、雑誌、ラジオが舞台だった人生相談が、YouTubeやPodcastで誰でもやれるようになりました。
瀧波:質問箱やマシュマロ、Instagramのストーリーズなど、匿名のメッセージに答えるサービスが出てきたときはけっこうびっくりしました。相手が有名人じゃなくても、相談を送ってそれに答えるということをみんなカジュアルに行っているし、だからといって質が下がったわけじゃないという。全体的には、権威性が下がって質が向上したんだと思います。
古い感覚のまま書いている人は今も寄り添えていないので、昔ながらの媒体に載ってる人生相談を読むとギョッとすることがありますよね。書く人も書く人だし、そのまま載せる人も載せる人だなと。
INDEX
「心構えじゃなんともならんよ」
ー前回お話を聞いた桃山商事の清田隆之さんは新聞で人生相談を担当されているんですが、読者の「相談者に助言したい」「なんなら説教したい」という欲望を感じることがあって、それには抗っていきたいとおっしゃっていました。相談者に寄り添うスタンスが一般的になったとはいえ、読者の野次馬的な好奇心は健在なんだなと。
瀧波:すごく長い相談文を短く編集するので、どれくらい大変なのかが伝わらなかったりもしますからね。私も、読む人のことは多少意識しないといけないと思ってます。
ーどこまでエンターテインメントにするか、というような?
瀧波:私の場合は、相談者にも読者にも役に立つということが一番大事かなと思っていて。読者が相談者をジャッジするんじゃなくて、「自分もこうすればいいんだ」と思いながら読めるものにする。そうすれば相談してくれた人にとっても絶対嫌な内容にならないし、みんなにとっていいじゃんと。

瀧波:私に送られてくる相談は、近い年代の女性からの「困りごとが気にならなくなる心構えを教えてください」というのがすっごく多いんです。
例えば「子供を産んだけど夫がモラハラで何もしてくれない。まだ仕事復帰できないし、未来の展望が見えなくて本当に辛い。こんな私でも前向きに生きていける心構えを教えてください」というような。こういった「心構え系」が本当に多いんですよ。
待って待って待って、心構えじゃなんともならんよ、ということをやんわり説明して、その次に具体的な方法を伝えるようにしてます。二段構えです。
ーどうして「心構え系」が多いんでしょうか?
瀧波:やっぱり構造の問題なんですよね。この例だと、子供を産むことによって完全に夫の支配下になってしまって、逃れようがない。本人もどうにもならないことがわかっているから、その中でどう生きていくか。気持ちの切り替え方を教えてくれというふうになるんです。
上司からのパワハラも、会社という組織構造の問題なので、本人だけでは変えられない。そういう悩みが、女性の場合はすごく多いと思うんですよね。
構造じゃない悩みって何があるんだろう? ……内気で友達が作れないとか、自分の性格や外見に起因する悩みかな。構造と無関係ではないけれど、何かしら自分で解決する方法があるから、それは心構えで変えられるとは思います。

ーでも、本当に悩みの大部分は構造が関わってきますね。
瀧波:「妻として、母として、娘として」となると、いよいよ構造の問題なんですよ。
ーザ・家父長制という。
瀧波:個人になれないことの悩みなんですよね。個人として自由に行動できないことの悩み。でも、思考にも支配が及んでいるから、心構えで解決しちゃおうとするんだけど、それは無理だよと。「構造の問題だから、なんとかこうしてみよう」と答えるんです。
INDEX
知らんヤツの代弁をするな
ー瀧波さんの回答は、非常に具体的な解決法が示されているのが印象的でした。
瀧波:私は何かしらを「やれ」、もしくは「やるな」と言うのが好きなんです(笑)。その通りにするかは、言われた方の選択なので。「そういうことじゃないんだよな」と思うならそれでいいし。でも、読む人がいるから、その中には「なるほど」と思って参考にする人がいるかもしれない。なので、具体的にアドバイスするのは相談者にとっても読者にとっても有益だと思いますね。

ーこの連載に登場いただいた宇多丸さんや清田さんよりも一歩踏み込んだスタンスだと思うんです。これはお2人が女性からの相談を「他者」として受けることが多く、一方で瀧波さんは同じ女性からが多いことに関係しているのかなと思ったんですが、いかがでしょうか?
瀧波:相談者は答える人の性別なんかを考えないで相談してると思うんだけど、やっぱり多かれ少なかれ限界はあると思うんですよね。私は男性に相談されてもわからないですから。男性から相談されてその気持ちがわかるんなら、夫と喧嘩したりしないですよ(笑)。「性別は関係ない」という考えも間違いじゃないけど、社会が私たちを男女に分けて、それぞれに役割を強いたり優劣をつけたりしている以上、悩みも同質にはなり得ない。私はそう考えています。
ざっくりした話になってしまいますけど、男性の振る舞いで困っている女性に対して、男性はどうしたって女性の側には立てないですし。年齢による立場の違いも同様ですよね。例えば、新卒の女の子が上司から「今時の若いヤツはこんなこともわからないのか」という態度をとられて辛いという悩みに対して、親戚のおじさんが「こうした方がいい」とアドバイスしても的外れになるに決まってるじゃないですか。そのおじさんに言えることがあるとすれば、「会社というのはこういう構造になってるんだよね」ということや、「自分が新卒の頃はこんなふうに世界が見えていて、今はこう見えてるよ」ということに止まりますよね。

ーおじさんが理解できるのは相談者を悩ませている上司の方の気持ちだけど、「上司はこう思ってるはずだよ」と言うのが解決につながるのかという。
瀧波:知らんヤツの代弁をするなと。そのことで自分自身も救われようと思ってないか、ということは自省したいですよね。
私も、もし中学生の女の子から人生相談をもらったら、まず娘に聞くと思います。絶対にこの子の気持ちはわからない。わかってたら娘とも喧嘩しないです(笑)。聞いた上で、正直に「娘に聞いたらこう言ってました」と書くと思います。
ー自分と相手の属性が一致しない場合、基本的にはわからないことがあるはずだから、無理に答えようとしないことが大事なんですね。わからないという前提から始めるのが誠実なコミュニケーションだと。
瀧波:占い感覚で相談してくる人もいると思うんですよ。「来年まではキツイけど、その後結婚するよ」みたいな、なんの根拠もない答えでもいいから、というノリで(笑)。それはそれで面白いからいいと思うんです。でも、相談者にも読者にも誠実に答えようとするなら、半端な気持ちではいけないですよね。回答のスキルを上げていくべきだなと。
INDEX
地獄にいる人に、先を見せる
ー自閉症のある息子さんをお持ちのお母さんからの相談(※)への回答はまさに誠実だと思ったんです。
瀧波:はらちゃんですよね。いつサイン会にいらしてもいいように、名前を忘れないようにしてます。
※中等度の知的障害を伴う自閉症を持つ6歳の息子の母親「はらちゃん」から寄せられた、「子供を愛せないかもしれない」、「(子育てに)とにかく疲れた」という相談。

ー安易に「わかる」とも言わず、「私は描き続けることで、はらちゃんに手を振り続けます」で締めるのは感動的ですらあります。
瀧波:これもやはり母親がすごく背負い込まないといけないという構造の問題ではあるんだけど、家庭内の協力体制は比較的整っていそうなことが相談文から伺えるので、あまり具体的に言えることはなかったんです。本人もそれをわかって送ってきていると思ったので、気持ちを外に出したいんだなと。
もし夫が全く育児家事に参加しないとかだったら、「今の状況は当たり前じゃないよ」と指摘したりもできるんですけど、そうじゃなくても辛いものは辛いし、先が見えないということであれば「私は時々サイン会なんかをやったりするので、はらちゃんが来てくれたらいいな」と。先を作るというか。

ー未来に目を向けさせるんですね。
瀧波:「心構えを教えてください」という心境の人は、先を見ようという発想があまりない状態なんです。この先もこの地獄が続くなら、今ここで自分の気持ちを変えちゃいたいという。必ずしもそれが間違いではないんだけど、状況を打開する気持ちを丸めちゃうことにもつながるんです。納得して諦めたい、みたいな。
ー自分を変えちゃうのが一番手っ取り早いですもんね。確かに未来志向ではないのかも。
瀧波:例えば本を読むことも、結果的に心構えを変えることになるんですけど、外から取り入れているから随分違うんです。だから人生相談の中でもよく本を勧めますね。
ー悩んでいる人の中にあるものだけでなんとかしようとすると、現状を肯定することにもなりかねないですよね。
瀧波:免疫が下がってるのに、自分の免疫だけで治そうとしてるようなものですから。それは危ないですよね。