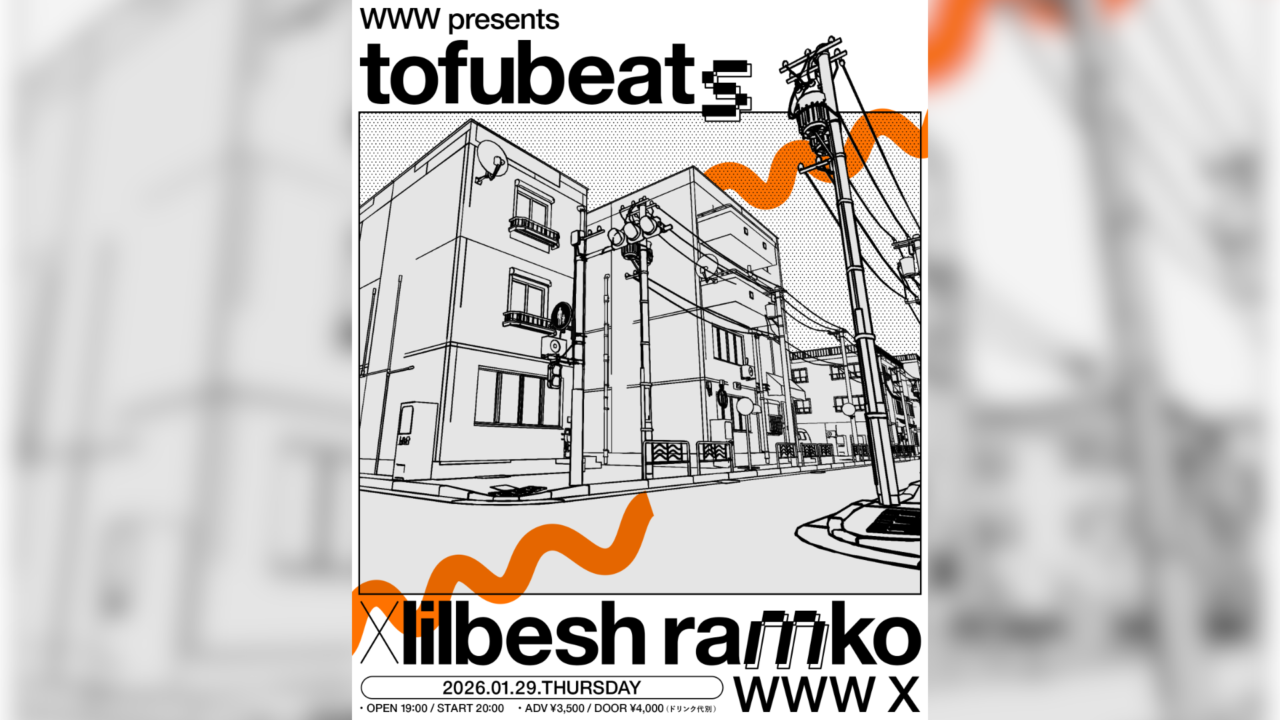1977年に製作され、長く日本未公開だったフランス映画『ペパーミントソーダ』が、4K修復版として12月13日(金)より初上映される。
監督自身の体験を元にしたドラマである本作には、思春期の少女の心の揺れとともに、1960年代後半のいわゆる「政治の季節」へと向かうムードが色濃く反映されており、劇中の音楽もまた、それらと響き合うものとなっている。評論家・柴崎祐二が論じる。連載「その選曲が、映画をつくる」第21回。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
幻のフランス映画、日本初公開
1977年のデビュー以来、フランス映画界における先駆的な女性監督として現在まで活躍を続けてきたディアーヌ・キュリス。ジャクリーヌ・オードリーやアニエス・ヴァルダといった少数の例外を除き、長らく男性監督が覇権を握ってきた同国の映画界において、それまで映画制作の経験がまったくなかったという彼女の登場は、まさしく時代の新風を感じさせる出来事であっただろう。
本作『ペパーミントソーダ』は、そんなキュリスの第一作であり、フランス国内で300万人以上を動員した大ヒット作品である。同年のルイ・デリュック賞を受賞するなど、高い評価を与えられた作品だったが、現在に至るまで日本では未公開のままで、ごく一部のファンのみに知られる「幻の映画」であった。近年、同時代のヨーロッパの女性監督による傑作が次々に初公開・リバイバル上映され話題となる中、同作の4K修復版がこうして日本配給された意義は殊の外大きいだろう。
あらすじを紹介しよう。舞台は1963年夏から翌年1964年夏にかけてのフランス、パリ。13歳のアンヌ(エレオノール・クラーワイン)と15歳の姉フレデリック(オディール・ミシェル)は、普段は父と離れ、母と3人で暮らしている。妹アンヌは、厳格な女子校リセ・ジュール・フェリー校の新学期を眼の前にして、心が落ち着かない。成績優秀な姉の反面、学校でも家庭でもなにかと問題を起こしがちで、性への関心も高まるばかりだ。
一方で姉のフレデリックは、はじめのうちこそボーイフレンドと睦言を交わすことに夢中だったが、友人関係の変化とともに、次第に政治意識に目覚めていく。母親(アヌーク・フェルジャック)はそんな姉妹の言動に気を揉みながらも、ときに厳しく、ときに優しく二人を諭そうとするのだった……。

INDEX
思春期の心象風景と社会状況の巧みな描写
なにか大きな事件が巻き起こるでもなく、淡々と物語が進んでいくように見える本作だが、途中に挿入されるエピソードの数々も実にユーモアと機微に富んだもので、決して飽きさせることがない。また、ファッションやヘアメイク、美術等、徹底した細部への美意識も驚くべきもので、それゆえにこそ、ふとした瞬間に訪れる登場人物たちの心象風景の変化にも、切ないまでのリアリティと深遠な情感が宿っている。「クラスメイトが皆そうしているから」という理由でささいな品物へ強いこだわりを示すアンヌの姿や、恋人との旅行の許しを得ようと発奮するフレデリックの姿に、かつての自分の姿をつい重ね合わせてしまう観客も少なくないはずだ。

一方で、ほろ苦いノスタルジーを誘うそうした描写の傍ら、1960年代前半のフランス社会の状況を強く意識させるエピソードが散りばめられているという点も、本作の重要な魅力の一つだろう。
映画の冒頭部からして示唆的だ。新学期の始業式が終わった後、ある生徒が校庭にぽつんと居残り、一人で泣いている。底意地の悪い教頭が叱責混じりに声をかけると、どうやら「オラン」からやってきた転入生だということがわかる。だが教頭は、その地名を解せず、引き続き叱責をやめない。フランスの現代史に明るい人ならばピンとくるはずだが、おそらくこの女子生徒は、旧宗主国フランスとの長年の戦争状態を経て前年に独立したアルジェリアの都市=オランからやってきた経済移民の一人なのだ(あるいは、戦時中フランス側に協力したことで差別の対象となったアルジェリア人=「アルキ」の家の子供なのかもしれない)。

INDEX
並列される、個人的なエピソードと政治的なモチーフ
1960年代前半のフランスといえば、ド・ゴールの第五共和政下で飛躍的な経済発展を遂げた一方で、なによりも、アルジェリア戦争に伴う様々な事件と、その爪痕によって社会全体が大きく揺動していた時期にあたる。こうしたムードは、映画の全編を静かに貫いており、フレデリックが次第に政治へと目覚めていく描写に並々ならぬ説得性を与える効果も発揮している。
中でも、彼女のクラスメイトのパスカルが、前年に自身の目で見たというデモと、それに対する警官隊の暴力事件(*)について授業中に語るシーンには、特に鮮烈な印象を抱かされるだろう。他にも、画面に目を凝らしてみると学校の壁に極右団体OASの名が落書きされていたり、さらには、人種差別主義者と左派の衝突が直接的に描かれていたりと、各所に政治的なモチーフが頻出するのだ。
*1962年2月8日、アルジェリア独立阻止を標榜するOASとアルジェリア戦争に反対する左翼勢力のデモをパリ警察が暴力で封じこめ、最終的に9名が亡くなった「シャロンヌ地下鉄大虐殺事件」を指す。前年1961年には、民族解放戦線によって組織されたアルジェリア人によるデモが警察の暴力によって破壊され、200人から300人にわたる同国人が殺害されるという「1961年パリ虐殺」事件があった。

一見すると相反するようにも思われる思春期ならではの個人的なモチーフと、そうした政治的な描写を、対立的あるいは扇情的に扱うわけではなく、少女たちの過ごす日々の中で連続して起きる出来事として、あくまで並列に描き出しているということが、私には特に重要に思える。家庭で過ごす何気ない時間の中でジョン・F・ケネディの暗殺のニュースがもたらされたり、上に述べた通り、授業中の他愛もない会話から身近でおきた虐殺の話へと展開していくのだ。
その経過の中で、キュリスはこれみよがしに演出の方法を変えたり、カメラやBGMを感情的に動かしてみるようなこともしない。ただ紛れもない「あの頃の出来事」として、思春期の逡巡を構成する「個人的な」エピソードの中へと配置していく。彼女たちの体験している世界の中では、数ある経験は、いまだ明確な場所付けが難しいものとして、混在しながら存在する。
無垢な戯れと大人への背伸び。憧れと怯え。愛情と軽蔑。別れと出会い。私と他者。揺りかごのような世界から、鉄火場のような世界へ。それらがいまだ不可分な若い心のありようを描くにあたって、おそらくこれ以上に巧みな方法はないように思われるし、あえて穿った風なことをいえば、そうした「若さ」のあり方は、より一層の政治的な混乱状態へと向かっていく同時代のフランスが抱えていた「若さ」と、のちの「革命」への呼び声を描き出しているように思えてならないのだ。

INDEX
ジュブナイル性を象徴するクリフ・リチャード
こうした「若さ」への視線は、劇中で流されるポップソングの選曲にも見いだせる。いや、見いだせるどころか、当時のポップソングの響きそれ自体が、映画全体をそうしたカラーに染め上げる重要な役割を担っているように感じられる。
オープニングに置かれたバカンスのシーンでラジオから流れるのは、当時イギリスを中心にアイドル的な人気を誇っていたクリフ・リチャードとThe Shadows(当時はThe Drifters名義)によるヒット曲“Livig Doll”(1959年)だ。いかにも長閑でポップなサウンドを聴かせるこの曲をはじめ、映画館でアンヌがクリフ主演の『太陽と遊ぼう!』(1963年)を観たいと言うシーン、そして終盤のダンスパーティーで流れるThe Shadows版の“Sleep Walk”(1961年)等、クリフ・リチャードおよびThe Shadowsの曲 / モチーフは、本作の中で繰り返し登場する。
ポップミュージック史の視点から見ると、当時のクリフ・リチャード(およびThe Shadows)は、ロックンロールの英国(およびヨーロッパ)におけるローカライズとポップ化を象徴する存在であったといえる。その作風は、元となったアメリカ産のロックンロールと比べても穏健かつポップで、もっとはっきりいうならば、ジュブナイル的な「無垢さ」と親和的なものといえる。
翻って、『ペパーミントソーダ』の舞台である1963年から翌1964年にかけては、そうした「クリフ・リチャードの時代」であったと同時に、彼と入れ替わるように、もっとワイルドなサウンドを聴かせるイギリス人の若者四人組が、まさにフランスにも旋風を巻き起こさんとしていたそのときにあたる。他でもない、The Beatlesのことだ。

INDEX
選曲が示唆する、「統合されたフランス像」とその変革の予感
The Beatlesのレコードは既にフランスでも発売されていたものの、後のような熱狂的人気を獲得していたわけではなく、1964年1月に行われた初のフランス公演でもそれなりの歓迎を受けたものの、共演者であった地元のスター=シルヴィ・ヴァルタンの人気が上回っていたという話も伝わっている。つまり、クリフ・リチャードのほがらかな歌声によって幕開けし、終盤に至ってもなおThe Shadowsの端正なギターがダンスホールを彩る『ペパーミントソーダ』の世界は、後の「若者の反抗」の象徴たるロックの足音がほんのすんでのところに迫っていながらも、いまだ多くの若者の耳には聴こえていない、ある種のジュブナイルとその終焉の予感のただ中にあることが示されているのだ。
そう考えるならば、映画中盤に描かれる若者だけのパーティーのシーンで流れるのが、叙述のシルヴィ・ヴァルタンのツイスト〜イエイエ“Il Revient (Say Mama)”(1963年)だというのも妙に示唆的に思えてくるし、同シーンではサルバドール・アダモによる大ヒット曲“雪が降る(原題:Tombe la neige)”(1963年)も使われるなど、全編に渡ってシャンソンの名曲も散りばめられている。私には、やはりそのどれもが、当時の一般大衆が(アルジェリア戦争を経てもなお、いや、だからこそ)抱いていたとされる統合されたフランス像への素朴な憧憬と、その変革への気配がうっすらと入り混じった選曲に感じられてならない。

INDEX
「若さ」のきらめきは褪せない
毎年の夏、離れて暮らす父とのバカンスへと出かけていくアンヌとフレデリックの二人は、きっと数年後には家族の元から離れ、それぞれの人生を歩みだすことだろう。アンヌは、姉がたどったのと似た青春の道程を自らの足で巡っていくのかも知れないし、フレデリックは、この映画を作ったキュリス自身がそうであったように、1968年5月の革命の渦中へと飛び込んでいくことになるだろう。
その頃の彼女たちの部屋に流れているのは、The Beatlesや、ひょっとするとThe Rollng Stonesあたりかもしれない。かつて夢中になったクリフ・リチャードの歌声はきっと、映画の中に登場するポートレート写真の数々を引き出しの奥から引っ張り出してみるときにだけ、彼女たちの中で再び鳴り響くだろう。しかしそれは、過去の出来事へのほろ苦い哀切を彼女たちに抱かせるにせよ、決して未来を諦めることには繋がらないはずだ。なぜなら、そこに刻まれた「若さ」とその可能性のきらめき自体が光力を弱めることはないからだ。

本作『ペパーミントソーダ』が、公開から47年の時を経てもなお魅力を失っていないどころか、今まさにみずみずしい青春映画として私達の心を捉えるのも、キュリス自身がそうした「光」の姿を、この初作の隅々へ丁寧に映し出してくれているからに違いない。
『ペパーミントソーダ』 4K修復版

2024年12月13日(金)より渋谷ホワイト シネクイントほかにて公開
監督・脚本:ディアーヌ・キュリス
出演:エレオノール・クラーワイン、オディール・ミシェルほか
配給:RIPPLE V
Une coproduction LES FILMS DE L’ALMA – ALEXANDRE FILMS
© 1977 – TF1 DROITS AUDIOVISUELS – ALEXANDRE FILMS-TF1 STUDIO
https://www.ripplev.jp/peppermintsoda/