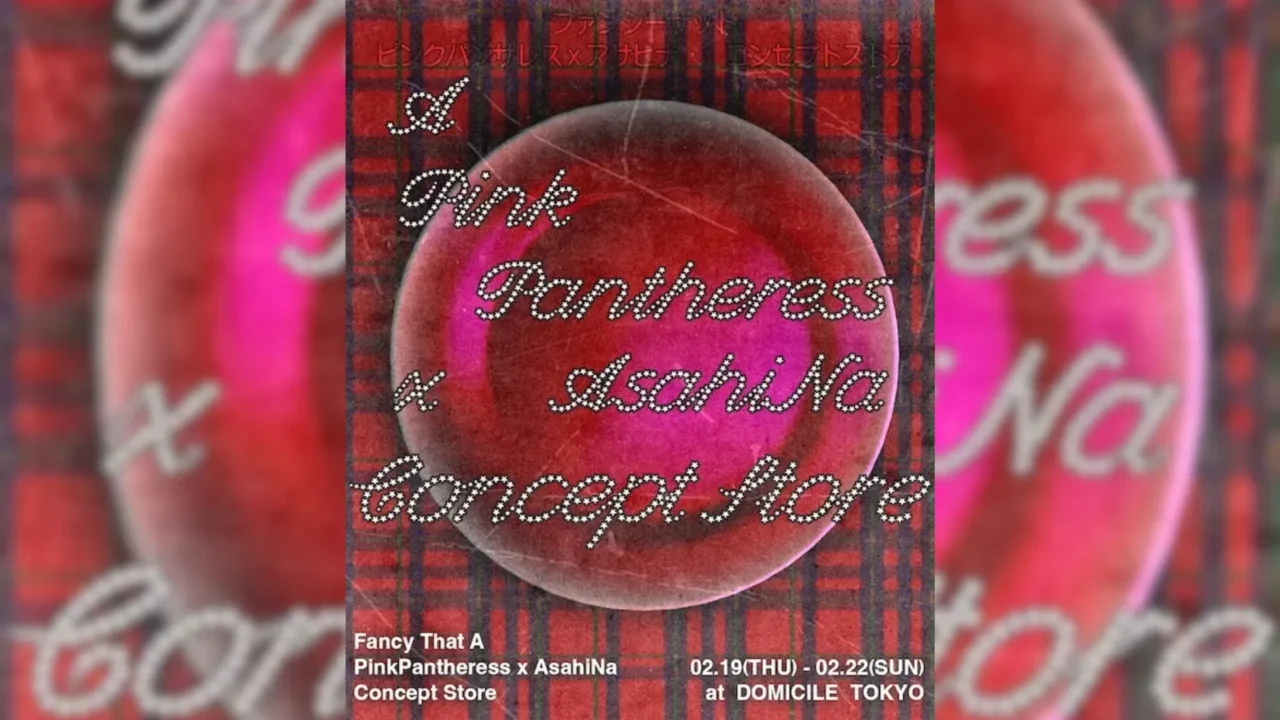INDEX
アーサー=ジョーカーの二重性を思わせる音楽の使用法
しかしながら本作の特徴としてより一層興味深いのは、上述の観察とは矛盾するようだが、それでもなお「中断」としかいいようのなさそうな「ミュージカル的」な瞬間が少なからず仕込まれているという点だ。
そうした「矛盾」が最もはっきりと現れているのが、アーサーが、自ら作り上げた妄想世界の中で歌と踊りを披露するいくつかのシークエンスである。彼の妄想世界は、看守らが支配する冷厳な現実とは、時間の流れは当然ながら、空間から身体的な表象まで、全てが異なっている。それは、かつてのアーサーが(前作『ジョーカー』の序盤で)夢見たマレー・フランクリン・ショーでの晴れ舞台とも似て、なんともゴージャズで、エンターテインメントの輝きに満ちたものである。その世界の中の彼は、下層家庭出身の悲しき青年アーサーではない。まぎれもなき一つのペルソナ=ジョーカーとして、現実から遊離し、現実を否定する虚構のエンターテインメントの時間を、妖しく司っているのだ。リーと共に“To Love Somebody”や“Gonna Build a Mountain”を歌い踊る一連のシーンは、まさしくそうした「中断」を象徴するものといえるだろう。

そう考えるならば、先程の見方を反故にして本作を「ミュージカル映画」と断じてしまってもいいように思われる。だが、それにはなおも躊躇させられてしまうのだ。なぜかといえば、そこに見られる「中断」が、一般的に想像されるミュージカル作品に見られる素朴な「中断」を超えて、あまりに深く、かつ距離の大きなものだからである。
社会学者の宮本直美は『ミュージカルの歴史 なぜ突然歌いだすのか』(中公新書、2022年)の中で、「中断」がミュージカル表現にもたらす効果を論じる一方、黄金期(1940年代〜1960年代)のブロードウェイミュージカルを後年から高く評価する際の価値軸として、「統合」という概念が評論界に共有されていった様を紹介している。その上で、音楽劇研究者ジェフリー・ブロックが整理してみせたミュージカルにおける「統合」の特徴を、次の通り書き出している。
・物語の筋を進める歌
・対話から直接流れる歌
・歌っているキャラクター自身を表現する歌
・筋を進め、歌のドラマ性を高めるダンス
・筋に寄り添い、あるいは筋を補完し、芝居を進めるオーケストラ
宮本直美『ミュージカルの歴史 なぜ突然歌いだすのか』(中公新書、2022年) p.101-p.102
『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の音楽使用の様をこのリストに照らすならば、いくつかの点ではたしかに合致しつつも、同時にいくつかの点でかなりの断絶があることがわかる。

アーサーが自身の妄想の中で繰り広げる虚構のパフォーマンスは、彼のキャラクターの特異性を巧く表現している一方で、しばしば台本上の「筋」を進めたり、補完する機能とはほぼ無関係に、より正確にいえば、映画内の「リアリティ」を撹乱するような形で現れる。つまり、本作における音楽と踊りの一部は、しばしばシナリオの時間の「中断」ですらない、映画内世界それ自体の統合性の決定的な不全として表象されているのだ。
このことは、本来ならば「統合」のために「筋に寄り添い、あるいは筋を補完し、芝居を進める」べきオリジナルスコアの扱いに鑑みても、はっきりとするだろう。一般に黄金期のミュージカル作品では、歌曲とアンダースコアのスムースな切り替えによって「統合」が成される例が多いのに比べ、本作では、ヒドゥル・グドナドッティルによるスコアとミュージカルナンバーが入り混じり、お互いを冒していくように、しばしば不協和音を含んだ不安定なハーモニーが流れ出るのだ。耳慣れた名曲の明るく伸びやかな和音が現れたかと思ったら、次の瞬間には不穏なスコアと混ざり合い、耳心地の悪い響きがすぐにとって代わるのである。
病理学上の概念と安易かつ過度に結びつけることは自制しなければならないが、それでもやはり、この音楽の配置は、アーサーが抱えている(と推察される)解離性障害とのアナロジーを企図したものと解するのが自然であろう。前作から、アーサー(および多くの現代人)が抱えるメンタルヘルスの問題が執拗に描かれ続けてきたという事実を踏まえるならば、そうした見取り図は、より一層の説得性をもって私達観客に揺さぶりをかける。