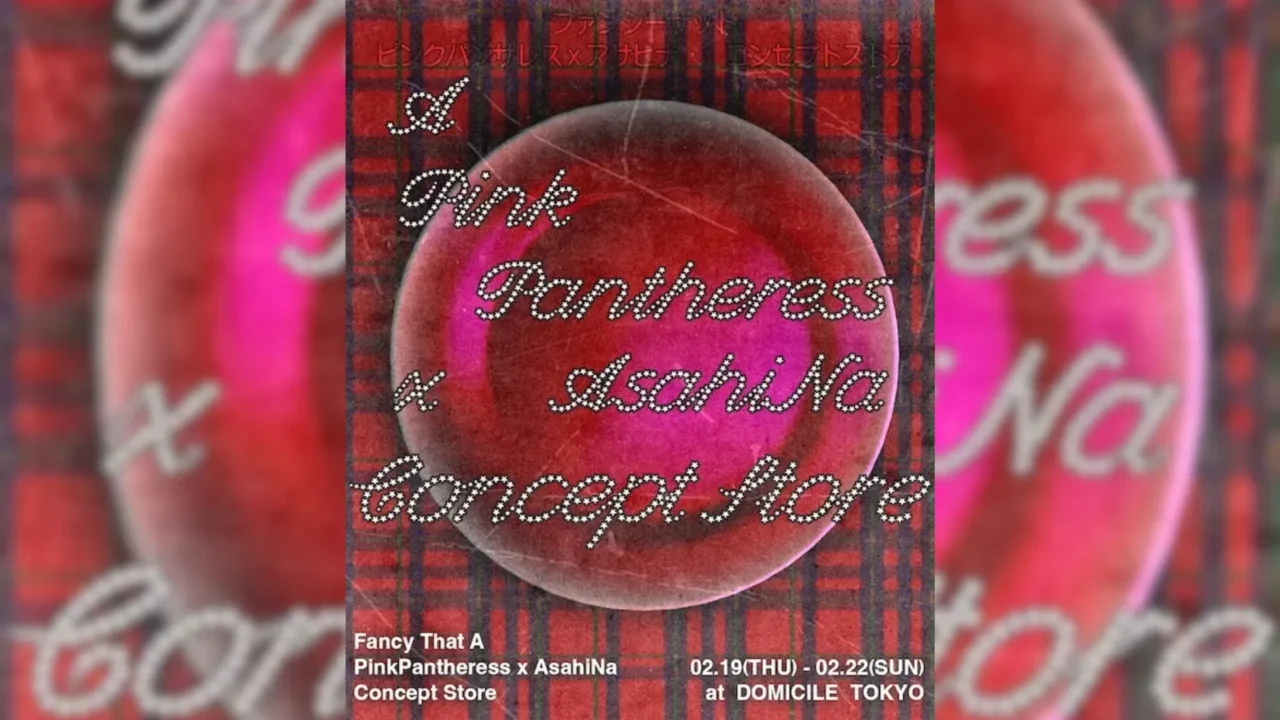『君の名前で僕を呼んで』のルカ・グァダニーノが監督し、ゼンデイヤが主演をつとめた映画『チャレンジャーズ』が、6月7日(金)より公開となる。
トレント・レズナー&アッティカス・ロスがスコアを手がけた大音量のエレクトロニックミュージックと、カエターノ・ヴェローゾが歌うある楽曲が印象的な本作を、音楽ディレクター / 評論家の柴崎祐二が論じる。「その選曲が、映画をつくる」第14回。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
テニスプレイヤーたちの三角関係の物語
ルカ・グァダニーノは、ある少年によるひと夏の情熱的な愛を描いた『君の名前で僕を呼んで』(2018年)や、「人喰い」の若者たちを主人公に据えた前作『ボーンズ アンド オール』(2023年)をはじめ、これまで一貫して様々な人間の抑えようない熱情のほとばしりに肉薄し、それを鮮烈な映像美とともにえぐり出してきた。今作『チャレンジャーズ』でもそうした主題を深く掘り下げているが、そのシャープさ、躍動感という面から言えば、おそらく過去作中で最も充実した成果をものにしている。
映画は、ゼンデイヤ演じる若き天才テニスプレイヤーのタシ・ダンカンと、彼女に恋焦がれる二人の男性プレーヤー=パトリック・ズワイグ(ジョシュ・オコナー)、アート・ドナルドソン(マイク・フェイスト)が約13年間に渡って繰り広げる三角関係を中心に展開する。
パトリックとアートは少年時代からの親友で、性格は正反対ながらもテニスへの情熱を元に固い絆で結ばれていた。ある日、そんな彼らの前に最高に「ホットな女性」が現れる。それが、学生テニスの世界で他を圧する強さを見せつける若きプレイヤー、タシだった。二人は即座にタシに魅了されるが、彼女は、翌日の試合で勝者となった方に自らの連絡先を教えるという賭けを提案する。結果はパトリックがアートを下し、パトリックとタシは恋人関係となる。
歴戦の覇者として将来を嘱望されるタシだが、パトリックとの破局的な喧嘩の直後に臨んだ試合で悲劇が起きる。アートが観戦する中、選手生命を断たざるをえない大怪我を追った彼女は、一旦は悲嘆にくれながらも、新たな人生を力強く模索していく。
数年後、アートと久々に再開した彼女は、一線から退いてコーチとしてのキャリアを歩みはじめていた。長年タシへの恋心を抱き続けていたアートは、彼女にパートナーになってほしいと申し出る。
それから更に数年後。一見すると幸福そうな家庭を築き、テニスの世界でも大成功を収めたようにみえるアートとタシ。かたやパトリックは放蕩生活を送り、選手としてのランキングも下げる一方であった。しかし、運命の悪戯によって三人はあるマッチの場で再び邂逅する。果たして、パトリックはアートとタシに一矢報いることができるのだろうか。それとも……。

INDEX
テニスの映画ではなく、リズムと激情の映画だ
本作『チャレンジャーズ』はテニスを題材とした「スポーツ映画」の外形をしているものの、実のところそれはあくまで一つのモチーフに過ぎない。これはずばり、リズムと激情の映画だ。テニスに己を捧げる女性と、彼女に並々ならぬ熱情を抱く二人の男達が、互いを刺激し、誘惑し、鼓舞し、打ち負かそうと心身を躍動させるその様が、言葉通りリズミック極まりないやり方で表現されていく。テニスのラリーのように交わされる激しいパッションの応酬と、ときに訪れる不安と停滞。それらの織りなすリズムが、彼らが形作る三角形を膨張させ、歪ませ、鋭く尖らせていくのだ。
そうしたリズムを生み出している主要因は、何よりもまず巧みなショットとアグレッシブなカメラワーク、入念なモンタージュだ。各プレイヤーの主観ショットが軽快に重ねられる中、強烈なスマッシュがカメラに向かって放たれる様は、有り体に言えば、まるで鑑賞者自らがテニスコートに立って懸命にラリーを行っているような感覚にさせられる(実際に私は、カメラへと高速で向かってくるテニスボールに対して、つい身をかわしてしまうほどだった)。こうしたシーソーゲーム的なリズムは、コート外のやりとりにも敷衍され、ほぼ全編にわたって特異な緊張感が持続する。

INDEX
熱情と欲動を演出するエレクトロニックミュージック
もう一つ重要なのが、言うまでもなく音楽の存在だ。デヴィッド・フィンチャーの『ソーシャル・ネットワーク』(2010年)を皮切りに数々の優れた仕事を重ねてきた練達のチーム=トレント・レズナーとアッティカス・ロスが今回取り組んだのは、テクノ〜ハウス色の強い、強烈にダンサブルなエレクトロニックミュージックである。
グァダニーノの発言を引こう。
「私がこの映画の音楽についてまず思いついたことは、映画を観ている人たちが踊りたくなってしまうような音楽がほしい、ということだった。だから私はレズナーとロスに言ったんだ。『レイヴコンサートとかハウスミュージックみたいな音楽はどうかな?』と。実際の映画の勢いは音楽からくるものだからね」
プレス資料より
グァダニーノが目論んだ通り、レズナーとロスの作りだしたトラックは目覚ましい効果を上げている。各トラックのビートは、カメラや役者の身体の動き、モンタージュのリズムとダイナミックに調和することで、通常の劇伴音楽がそうするのを超えた密着度で、映画を直接的に「演出」する。更には、巧みなカットバックやスローモーションに合わせて効果的に音楽を配置することで、しばしば私達がフロアで体験するような、ダンスミュージックを大音量で浴びることで時間感覚が溶け出していくようなあの感覚に似た何かを作り出すことにすら成功しているのだ。
加えて、実際にスクリーンで体験する人のほとんどがそう思うはずだが、スコアに限らず、この映画のサウンドデザインはなかなかに特異だ。各シーン、相当丁寧に音響が作り込まれているのがわかるが、スコアの音量が一般的な作品よりも明らかにラウドに設定されている上、それに負けじとプレイ中の具体音にもあからさまに攻撃的なミックスが施されている。特に、ここぞというところで炸裂するラケットの打球音は、ちょっと油断しているとドキリとしてしまうほど、鋭角的でラウドだ。まるでハードなエレクトロニックミュージックのキックのごとく轟く鋭い打球音が、テニスの試合の音響それ自体がダンスミュージックの身体性と重なり合っているような感覚を引き起こすのだ。

レズナーによれば、グァダニーノは、この映画について初めて相談を持ちかけた際、とにかく「とてもセクシーな映画(A very sexxxxxxy movie)」であると説明し、いくつかの具体的なモチーフも提示したのだという。
歴史を紐解ければすぐにわかる通り、多くのダンスミュージックは、性愛等のフィジカルな快楽性、さらに言えばクィアカルチャーとも強く結びついた上で発展してきた存在である。また、映画史上においても、古くからダンスの描写が性愛のメタファーとして読み取られてきたこともよく知られている。
本作にも、タシと二人の男性の間の性愛のみならず、男性同士の肉体的な交歓をふくめ、そこかしこに大胆な描写が溢れており、グァダニーノが過去作を通じて磨き上げてきた肉感的な表現がより一層の高みに達しているのがわかる。そして、その高みへと押し上げるのに直接的な寄与をしているのが、他でもないレズナーとロスの手によるスコアと言えるだろう。また、こうした「エロティック」なスコア(およびいくつかの既存曲)が、性的な描写とテニスのプレイ描写の双方を往復することで、とどのつまり両者が、三人の登場人物にとって熱情や欲動という次元において不可分の存在であることを説得的に伝えているのだ。