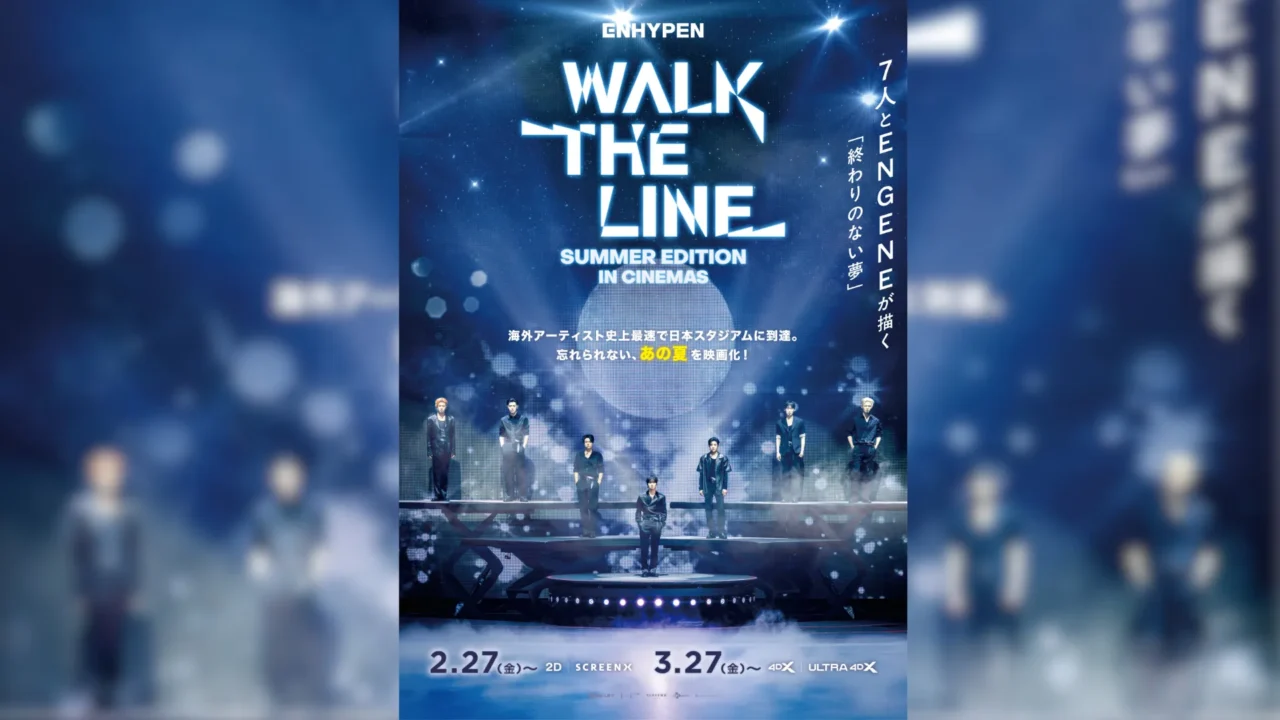INDEX
「“君”は僕のことなんて見もしない」
これまでに述べてきたことを、最も強烈な形で認識させてくれるのが、作中後半のとあるポップソングを用いたシーンだ。
先に述べておくと、この映画では、ニューヨークを舞台としたいかにもゴシカルな不条理劇の雰囲気を印象付ける音楽として、デヴィッド・リンチやデヴィッド・クローネンバーグの映画を思わせるウンベルト・スメリッリによるオリジナルスコアや、The Crampsやルー・リード(※)等ニューヨークアンダーグラウンドシーンの立役者たちの曲が随所で使われている。
※The Crampsがホラーパンク〜サイコビリーの始祖的バンドであることや、ルー・リードが自らのジェンダーと社会規範との齟齬の中で苛烈な青年期を過ごし、ペルソナをかぶるようにグラムロック的表象を実演した人物だという事実も、本作のムード / テーマとの関連という意味で大変興味深く思える。
だがしかし、一瞬の間だけそうしたムードが霧のように晴れる場面がある。あるバーで、エドワード(ガイ)とオズワルドが会話をしていると、店内にいる皆から慕われているらしいオズワルドが、ステージ上の司会者に請われて歌を披露する。すると、店の中の者たちは一瞬にして彼の美声に心奪われてしまう。曲は、ソウルグループ=Rose Royceによる1976年のヒット“I Wanna Get Next To You”だ。
僕はいつも
——“I Wanna Get Next To You”(日本語版字幕より)
この椅子に座って
君を待ってる
ああ ベイビー
分かってくれよ
君は何も言わない
僕のことなんて見もしない
君には金も使った
時間もムダにした
心が折れるまで必死で口説いた
分かるだろ?
君のそばにいたいんだ
君と目が合うと
つい夢を見てしまう
君はキレイだ
君といると不安になる
美しくピュアな君
なぜ僕に冷たいんだ?
僕じゃダメなのか?
僕は金持ちじゃない
君が行きたい店にも
連れていけない
この場面に流れる歌声ほど、ハッとさせられるものはない。まずは、オズワルド(を演じるピアソン)が驚くべき美声と才能の持ち主であったことへの驚き。そして、その堂々たる歌いぶりと華麗なステージングからにじみ出るカリスマ性。人の心を安らかにさせる物腰と佇まい。これはまさに、かつてのエドワードが「そうなりたかった自分」が具現化された姿ではないか。
歌詞の内容も興味深い。ここで歌われる「君」にイングリッドの存在を当てはめ、かつてのエドワードが心の中に抱きつつも言葉にすることが出来なかった思いが歌われていると捉えるのも可能だろうし、さらには、同じ「君」に、他者としての社会一般の姿が託されていると解釈するのも、さほど無理のある類推ではないだろう。そう考えてみれば、「僕のことなんて見もしない」という一節こそは、これまで論じてきたような社会からのまなざしの「不在」を表しているようにも感じられる。