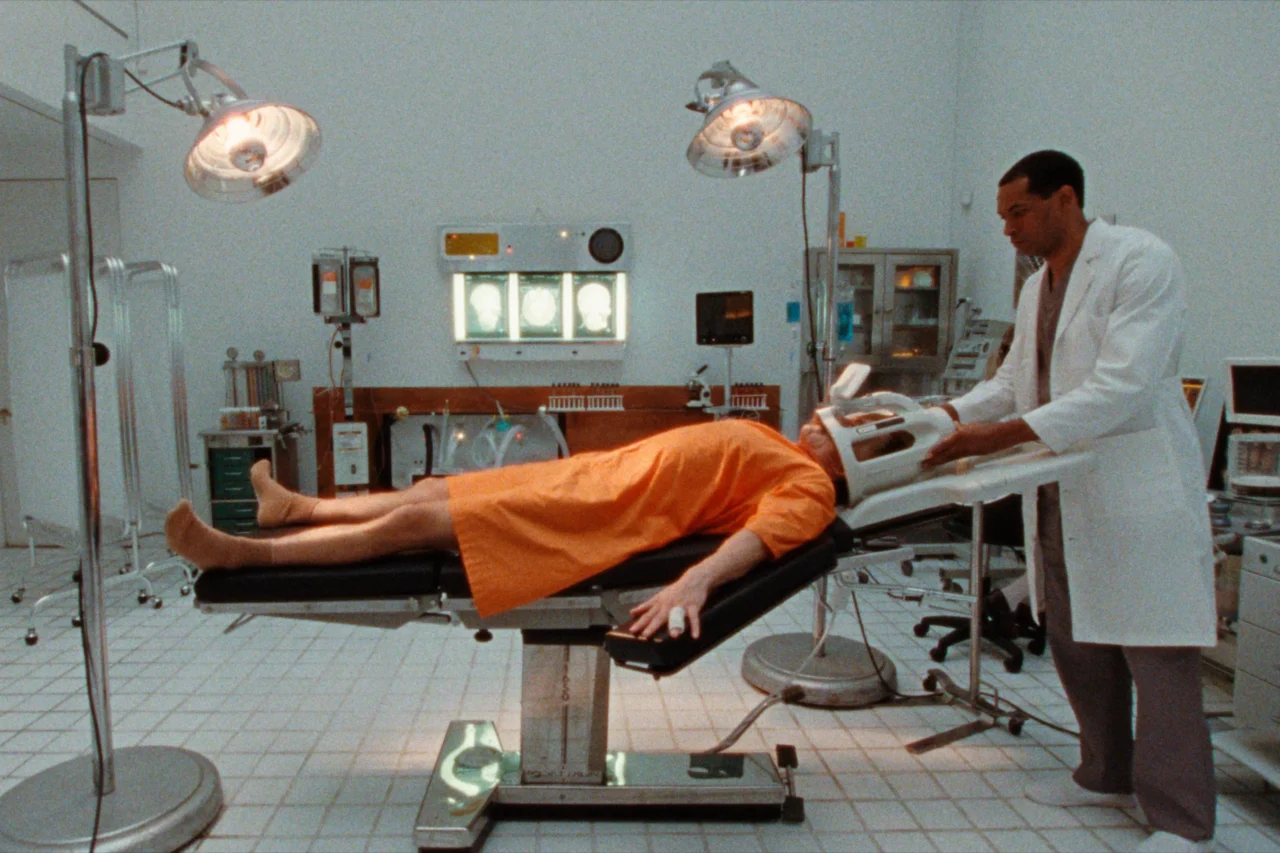INDEX
人のアイデンティティを構築するのは、他者 / 社会からのまなざしである
例として、舞台劇『エドワード』の稽古を重ねる中、台詞の書き換えについて口論する場面を見てみよう。ここで、エドワード(ガイ)とイングリッド以下の劇団員たちは、あたかもその前に配置されていた稽古シーンと連続するような形で、舞台上で「本物の口論」を行っている。おそらくこのシーンのはじめの段階では、少なくない観客が、喧々諤々に繰り広げられるやりとりを、劇中劇『エドワード』の台本に書かれた台詞だと誤認するはずだ(私はそうだった)。この「トリック」の存在は、本作の監督アーロン・シンバーグとその制作スタッフが、劇中劇の及ぼす効果にすぐれて自覚的であったことの証左ではないかと思われる。
加えて、オズワルドの出現を受けて次々に台本が書き換えられていく=それにつれてエドワード(ガイ)のアイデンティティが溶解していくというプロットもまた、ここで上演されようとしている劇中劇が、なにがしかの登場人物のまなざしに(無意識的にでも)さらされることでいくらでも変幻しうる存在であることを示唆しているのに加え、そのメタ的構造の効果として、この映画自体のナラティブもまた、オズワルドの登場によって不可逆に変化してしまったことを匂わせている。
つまり、劇中劇『エドワード』の存在とその制作過程の描写は、登場人物がお互いに発する「まなざし」を可視化させるための、極めて優秀な装置でもあるのだ(※)。
※この劇中劇のメタ的な構造とその効果を一度でも内在化してしまった私たち観客は、舞台劇『エドワード』でかつての自分を演じるガイという存在が、そもそもエドワード自身が作り出した別のペルソナであったことを再確認せざるをえなくなると同時に、もっといえば、そうした入り組んだ人物像を演じているのもまた、(別のペルソナになりきることを生業にしている)俳優のセバスチャン・スタンであるという事実に引き戻されてしまうだろう。

こうした入り組んだ構造の上で、先にも触れた通り、本作にはさらにもう一つの重要な「捻り」が加えられている。「素顔」を渇望し、「本当の自分」を追い求めていたはずのエドワード(ガイ)が自らのアイデンティティを急速に失っていく決定的なきっかけとなったのが、かつて自身が夢想していたような「理想的な容姿」を持つ別の男などではなく、かつての自分と似た「異形の顔」の人物オズワルドの存在だった、という設定がそれだ。エドワードは当初、自分で自らの過去を演じる中で自己回復を果たそうとするが、しかしその野心は、「外見だけは似ているが全く異なる男」であるオズワルドによって、木っ端みじんに砕かれてしまう。これは、過去の「自分」からの復讐なのだろうか。あるいは――。
私たちがここから読み取らないではいられない教訓とは、劇中に流れる陳腐な「共生」啓発ビデオに象徴される類の題目化した「お作法」などではなく、もっと根源的なものだろう。エドワードが身をもって経験したように、人のアイデンティティというものが、外見上の連続性やその反転としての「生まれ変わり」の自覚とは無関係に、遊離性を帯びたものであるならば、結局のところ私たちの自己意識を構築するのは、様々な他者からのまなざしであり、それらを自ずと規範化してしまう(自分自身のそれを含む)社会からのまなざしのほかにありえない――そういう教訓が浮かび上がってくるのだ。とすれば、我々の偏見や、身体的特徴を「障害」とみなして遠ざけたり、あるいはそれを慇懃無礼に無視してみせる行いも、当然ながらそのように社会的に「構築」されたものにほかならない、という理解に行き着くのだ。