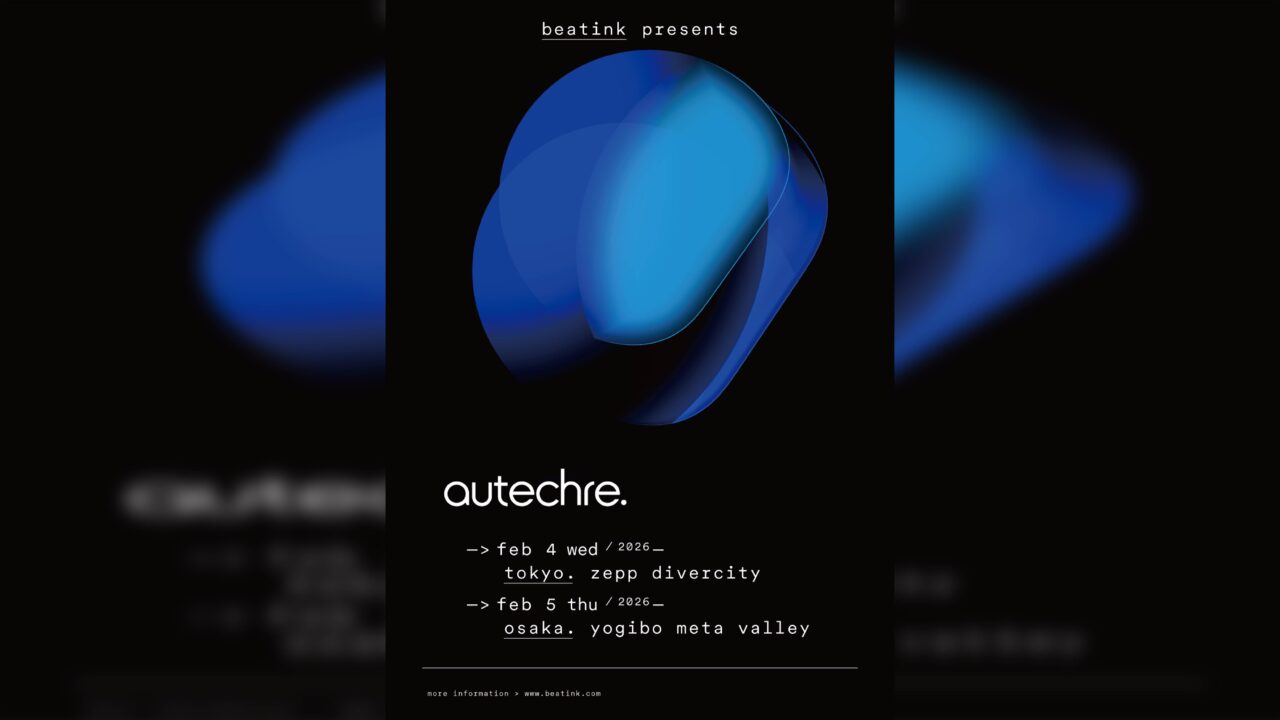青年期のボブ・ディランをティモシー・シャラメが演じた話題の映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が2月28日(金)より日本公開となる。
評論家・柴崎祐二が、本作の魅力、ディランという存在、1965年の「事件」について論じる。連載「その選曲が、映画をつくる」第23回。
INDEX
ボブ・ディランという神秘的で多面的な存在
「Eマイナーをひとつひくだけで、彼は神秘のなかにいる。なぜなら彼自身が神秘そのものだからだ。彼自身が、『ディランはどういう人間なのか』という問題を、『ディランはどういう存在であるか』という問題に変えてしまう。(中略)彼がつながっている世界とは、そして彼がつくったものを見て聞くことによって、結果としてぼくたちがつながる世界とは、いったい何なのか?」
「ディランは自分自身を発明した。彼は何もないところから自分をつくりあげた。自分のまわりにあったもの、そして自分のなかにあったものから、自分をつくった」
「みんなは、それがどんなものなのか、どんなものでないのかをつきとめるのに長い時間をかけたりはしない。みんなは、それをつかって自分の冒険をする」
――サム・シェパード著、諏訪優、菅野彰子訳『ローリング・サンダー航海日誌:ディランが町にやってきた』本文より
ロックの「神様」。偉大なライブパフォーマー。卓越した韻文家、詩人。ビートニクを継ぐもの。ノーベル文学賞受賞者。俳優。画家。伝承歌の紹介者。ボブ・ディランは、20世紀のアメリカ文化を様々な面で象徴しつつも、そこに込められた期待を常に裏切ることで、他に類例の無い強固な象徴性を纏い続けてきた。もしかすると、現代(厳密に言えば1960年代以降の現代)における文化的な「シンボル」とは、そのように逆説的で再帰的な方法のみによって実践されるなにものかなのかもしれない。しかしそうは言ってみても、ボブ・ディラン自身は、なにがしかの綿密な計画に基づいて実践を積み重ねてきたつもりはないと言うだろうし、きっと「すべてはそうだったから」と嘯くのみだろう。

かつて、かのトッド・ヘインズ監督が『アイム・ノット・ゼア』で特異な手法とともに複数のディラン像を描き出してみせたように、彼は多面的な人間である。彼自身がそういう存在であるとともに、ディランを語り、ディランとはどんな存在であるかと問いかける私達も、(ヘインズがそうしたように)自ずと多面的な思考へ誘われていく。
INDEX
キャリア初期の4年間を描いた物語
『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は、そんなボブ・ディランの長いキャリアのうち、彼の青年期にあたる最初の数年間の歩みを題材とした伝記映画で、第97回アカデミー賞の8部門へノミネートされるなど、本国アメリカでも大きな話題となっている作品である。
『ウォーク・ザ・ライン/君に続く道』や『フォードvsフェラーリ』等多くの傑作を手掛けてきたジェームズ・マンゴールドが監督を務めており、音楽史家イライジャ・ウォルドが2015年に刊行したノンフィクション書籍『ボブ・ディランと60年代音楽革命(原題:Dylan Goes Electric!)』を元に、マンゴールドとジェイ・コックスが共同で脚本を執筆した。若手トップクラスの人気を誇るティモシー・シャラメがディラン役を演じ、1960年代初頭のデビューから1965年のエレックトリックサウンドへの「転向」へ至る道筋が、巧みなストーリーテリングとともに描き出されていく。
あらすじを紹介しよう。時は1961年。19歳のボブ・ディラン(ティモシー・シャラメ)は、生まれ育ったミネソタ州から、フォークリヴァイバルの中心地であるニューヨークのグリニッジヴィレッジへとやってきた。すぐに憧れのフォーク歌手ウディ・ガスリー(スクート・マクネイリー)の病床へと赴いたディランは、かつて彼と活動をともにしていた盟友ピート・シーガー(エドワード・ノートン)が見守る中オリジナル曲“ウディに捧げる歌(Song to Woody)”を披露し、二人を感動させる。その後グリニッジ・ヴィレッジのフォークシーンで歌い出した彼は、ある演奏会の場で、人種問題等の社会活動に取り組む女性シルヴィ・ルッソ(※)(エル・ファニング)と出会い、恋に落ちる。
※この役は、当時のディランの恋人で、セカンドアルバム『The Freewheelin’ Bob Dylan』(1963年)のジャケットにも登場しているスーズ・ロトロがモデルとなっている。本作のプロダクションシートによれば、彼女との思い出を今も大切に抱き続けるディラン本人からの数少ない要望として、ロトロの名を架空の女性の名前に変更してほしい旨が伝えられたという。
歌手として徐々にその実力が認められ、ディランはデビュー作を録音する機会を手にする。しかしその内容は、レコード会社の意向もあってカバー曲が殆どを占めていた。その後、当時のアメリカ社会を大きく揺さぶっていた人種問題や核戦争の危機、それらに対するシルヴィの姿勢に刺激を受けたディランは、数々の社会派ソングを自作し、演奏するようになる。その様子を見て感銘を受けたのが、既にフォークシーンのスターとして確固たる地位にあったジョーン・バエズ(モニカ・バルバロ)だった。折しもシルヴィの長期留学中、ディランと彼女は急速に惹かれ合い、公私ともにパートナーシップを結ぶこととなる。

バエズらの後押しを通じて、一躍プロテストソングの旗手と目されるに至ったディランだが、次第に、自らが望む表現と聴衆から向けられる期待感のギャップの中で強い疎外感を抱くようになる。自らの出自を煙に巻き、周囲の要望をかわす彼の言動は、シルヴィやバエズとの仲にも亀裂を生んでいく。そんな中、ディランは純粋主義的なフォークファンやシーガーらの期待とは裏腹に、エレクトリック楽器を取り入れた楽曲作りに乗り出す。ほどなく、1965年の『ニューポートフォークフェスティバル』のトリを任されたディランは、ロックンロールを低俗で商業主義的な存在として敵視するフォークファンの眼前で、激烈なバンドサウンドを奏でるのだった……。