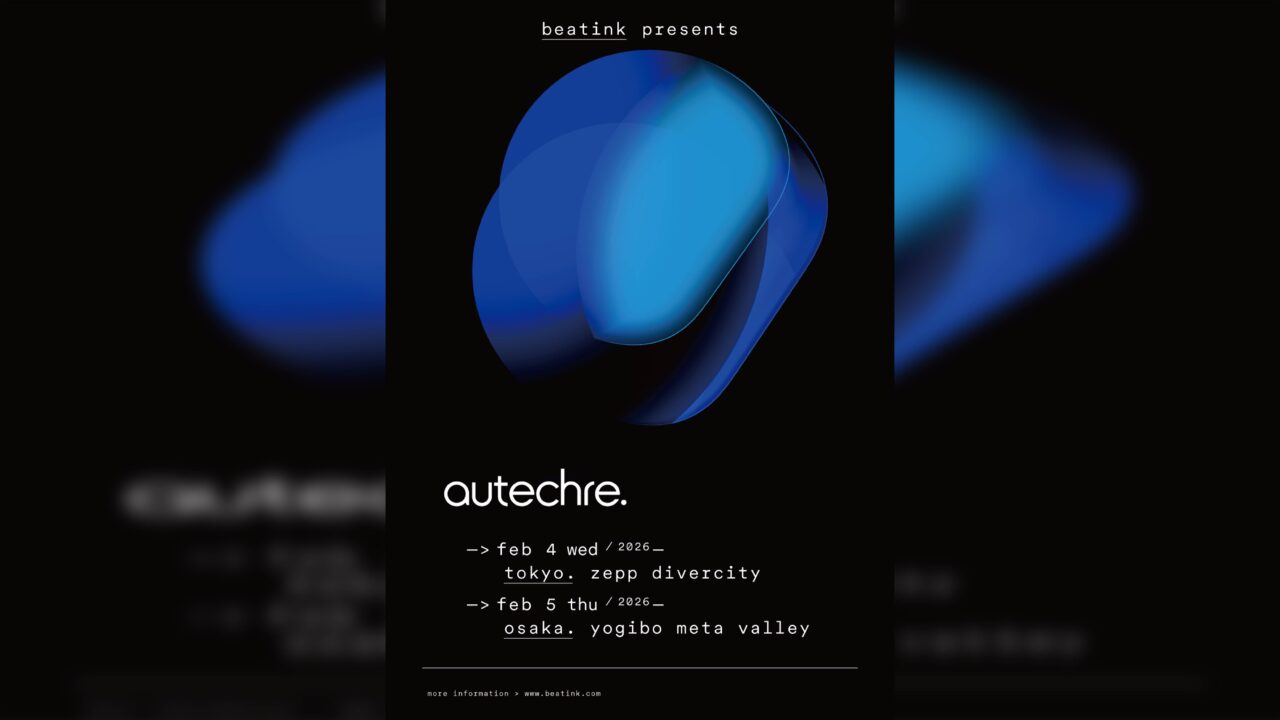青年期のボブ・ディランをティモシー・シャラメが演じた話題の映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が2月28日(金)より日本公開となる。
評論家・柴崎祐二が、本作の魅力、ディランという存在、1965年の「事件」について論じる。連載「その選曲が、映画をつくる」第23回。
INDEX
ボブ・ディランという神秘的で多面的な存在
「Eマイナーをひとつひくだけで、彼は神秘のなかにいる。なぜなら彼自身が神秘そのものだからだ。彼自身が、『ディランはどういう人間なのか』という問題を、『ディランはどういう存在であるか』という問題に変えてしまう。(中略)彼がつながっている世界とは、そして彼がつくったものを見て聞くことによって、結果としてぼくたちがつながる世界とは、いったい何なのか?」
「ディランは自分自身を発明した。彼は何もないところから自分をつくりあげた。自分のまわりにあったもの、そして自分のなかにあったものから、自分をつくった」
「みんなは、それがどんなものなのか、どんなものでないのかをつきとめるのに長い時間をかけたりはしない。みんなは、それをつかって自分の冒険をする」
――サム・シェパード著、諏訪優、菅野彰子訳『ローリング・サンダー航海日誌:ディランが町にやってきた』本文より
ロックの「神様」。偉大なライブパフォーマー。卓越した韻文家、詩人。ビートニクを継ぐもの。ノーベル文学賞受賞者。俳優。画家。伝承歌の紹介者。ボブ・ディランは、20世紀のアメリカ文化を様々な面で象徴しつつも、そこに込められた期待を常に裏切ることで、他に類例の無い強固な象徴性を纏い続けてきた。もしかすると、現代(厳密に言えば1960年代以降の現代)における文化的な「シンボル」とは、そのように逆説的で再帰的な方法のみによって実践されるなにものかなのかもしれない。しかしそうは言ってみても、ボブ・ディラン自身は、なにがしかの綿密な計画に基づいて実践を積み重ねてきたつもりはないと言うだろうし、きっと「すべてはそうだったから」と嘯くのみだろう。

かつて、かのトッド・ヘインズ監督が『アイム・ノット・ゼア』で特異な手法とともに複数のディラン像を描き出してみせたように、彼は多面的な人間である。彼自身がそういう存在であるとともに、ディランを語り、ディランとはどんな存在であるかと問いかける私達も、(ヘインズがそうしたように)自ずと多面的な思考へ誘われていく。
INDEX
キャリア初期の4年間を描いた物語
『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は、そんなボブ・ディランの長いキャリアのうち、彼の青年期にあたる最初の数年間の歩みを題材とした伝記映画で、第97回アカデミー賞の8部門へノミネートされるなど、本国アメリカでも大きな話題となっている作品である。
『ウォーク・ザ・ライン/君に続く道』や『フォードvsフェラーリ』等多くの傑作を手掛けてきたジェームズ・マンゴールドが監督を務めており、音楽史家イライジャ・ウォルドが2015年に刊行したノンフィクション書籍『ボブ・ディランと60年代音楽革命(原題:Dylan Goes Electric!)』を元に、マンゴールドとジェイ・コックスが共同で脚本を執筆した。若手トップクラスの人気を誇るティモシー・シャラメがディラン役を演じ、1960年代初頭のデビューから1965年のエレックトリックサウンドへの「転向」へ至る道筋が、巧みなストーリーテリングとともに描き出されていく。
あらすじを紹介しよう。時は1961年。19歳のボブ・ディラン(ティモシー・シャラメ)は、生まれ育ったミネソタ州から、フォークリヴァイバルの中心地であるニューヨークのグリニッジヴィレッジへとやってきた。すぐに憧れのフォーク歌手ウディ・ガスリー(スクート・マクネイリー)の病床へと赴いたディランは、かつて彼と活動をともにしていた盟友ピート・シーガー(エドワード・ノートン)が見守る中オリジナル曲“ウディに捧げる歌(Song to Woody)”を披露し、二人を感動させる。その後グリニッジ・ヴィレッジのフォークシーンで歌い出した彼は、ある演奏会の場で、人種問題等の社会活動に取り組む女性シルヴィ・ルッソ(※)(エル・ファニング)と出会い、恋に落ちる。
※この役は、当時のディランの恋人で、セカンドアルバム『The Freewheelin’ Bob Dylan』(1963年)のジャケットにも登場しているスーズ・ロトロがモデルとなっている。本作のプロダクションシートによれば、彼女との思い出を今も大切に抱き続けるディラン本人からの数少ない要望として、ロトロの名を架空の女性の名前に変更してほしい旨が伝えられたという。
歌手として徐々にその実力が認められ、ディランはデビュー作を録音する機会を手にする。しかしその内容は、レコード会社の意向もあってカバー曲が殆どを占めていた。その後、当時のアメリカ社会を大きく揺さぶっていた人種問題や核戦争の危機、それらに対するシルヴィの姿勢に刺激を受けたディランは、数々の社会派ソングを自作し、演奏するようになる。その様子を見て感銘を受けたのが、既にフォークシーンのスターとして確固たる地位にあったジョーン・バエズ(モニカ・バルバロ)だった。折しもシルヴィの長期留学中、ディランと彼女は急速に惹かれ合い、公私ともにパートナーシップを結ぶこととなる。

バエズらの後押しを通じて、一躍プロテストソングの旗手と目されるに至ったディランだが、次第に、自らが望む表現と聴衆から向けられる期待感のギャップの中で強い疎外感を抱くようになる。自らの出自を煙に巻き、周囲の要望をかわす彼の言動は、シルヴィやバエズとの仲にも亀裂を生んでいく。そんな中、ディランは純粋主義的なフォークファンやシーガーらの期待とは裏腹に、エレクトリック楽器を取り入れた楽曲作りに乗り出す。ほどなく、1965年の『ニューポートフォークフェスティバル』のトリを任されたディランは、ロックンロールを低俗で商業主義的な存在として敵視するフォークファンの眼前で、激烈なバンドサウンドを奏でるのだった……。
INDEX
随所に盛り込まれたフィクション
ディランのファンにとってあまりに有名な「神話」を題材とした本作は、上のあらすじからも分かる通り、様々な重要人物が交錯する実直な作りの伝記映画となっている。上述した他にも、彼の才能を早くから評価していたジョニー・キャッシュ(ボイド・ホルブルック)との交流をはじめ、マネージャーのアルバート・グロスマン(ダン・フォグラー)、コロンビア・レコードのA&Rジョン・ハモンド(デヴィッド・アラン・バッシェ)、レコード・プロデューサーのトム・ウィルソン(エリック・ベリーマン)、フォーク・ミュージック研究家のアラン・ローマックス(ノーバート・レオ・バッツ)、興行主のハロルド・レヴェンタール(P・J・バーン)といった裏方から、ピート・シーガーの妻で社会運動家のトシ・シーガー(初音映莉子)、ロードマネージャーにしてディランの良き理解者であるボブ・ニューワース(ウィル・ハリソン)、音楽仲間のマリア・マルダー(ケイリー・カーター)、ピーター・ポール&マリーのピーター・ヤーロウ(ニック・プポ)、エレクトリックバンドのメンバーであるマイク・ブルームフィールド(イーライ・ブラウン)やアル・クーパー(チャーリー・ターハン)など、数え切れないほどの実在の人物の姿が映し出されていく。

しかしながら、本作のあらゆる箇所が「史実」に基づいているわけではない。それどころか、かなりゆるく史実を捉え、随所にフィクションを盛り込んでいるのがわかる。ディランのファンならば、『ニューポートフォークフェスティバル』のステージで投げかけられる「ユダ(裏切り者)!」という野次のくだりが、実際には翌年に行われたイギリスツアーでの出来事である旨を指摘せずにはいられないだろうし、ガスリーの病床を見舞う描写や、各ステージでの演奏曲目の微妙な脚色、エレクトリック化の具体的な道程、ロトロ(をモデルにしたシルヴィ)との恋路の顛末、シーガーによる有名な「斧」事件など、史実と異なる部分を言い立てるのは造作もないだろう(※)。
※ジェシー・モフェットなるブルースマンが登場するくだりでは、「はて、そのような人物が実在したかしら」と思ったものの、実のところこれは架空の名前だ。おそらく、ディランと親交のあったビッグ・ジョー・ウィリアムスや、(ディランがカヴァーした)ブッカ・ホワイト、フレッド・マクダウェル等、フォークリバイバル期に活動した古参ブルースマンをモデルにしていると思われる。ちなみに、このモフェット役を演じたビッグ・ビル・モーガンフィールドは、マッキンリー・モーガンフィールド、つまりあのマディ・ウォーターズの子息である。
INDEX
史実の書き換えや捨象にみる「ディラン性」
「描かれていないもの」も数多い。ディランの初期活動に大きな影響を及ぼしたデイヴ・ヴァン・ロンク(ジョー・ティペット)が妙に影の薄い人物として扱われているのをはじめ、ランブリン・ジャック・エリオットやリアム・クランシー、フレッド・ニール、キャロリン・ヘスターといった先達や仲間たちに加え、フィル・オクスという重要なライバルの姿も、ディランにとっての守護聖人というべき詩人アレン・ギンズバーグの姿もない。加えて、エレクトリック化にあたっての最も重要なインスピレーション源であったはずのThe Beatlesの面々も登場しないし、何よりも、(彼の曲作りにとって少なからぬ影響を与えたと推察される)ドラッグに関する描写も丸ごと捨象されている。

熱心なファンの中には、こうした点を指して映画の価値を低く見る方もいるかもしれない。だが、当然ながら制作者側も「ついうっかり」して史実と異なるプロットを配置しているわけはないだろう。私にはむしろ、このような種々の書き換えや捨象の操作こそが、「若きボブ・ディランのピカレスク的な成長譚」という神話を、ある種の表現主義的な次元から強力に語り直すにあたっての最も有効な手法として機能していると感じられるし、おそらくは、本作の持つ価値も、こうした部分と深く関係しているはずだ。
なぜならば、これまで多くの者たちによって語られ、本作の中でも丁寧に描かれている通り、ボブ・ディランという人物自体が、自らにまつわる「史実」を自在に変幻させ、ときに偽り、単一のストーリーへの回収を拒絶しながら、その表現を深化させてきた存在だからだ。だからこそ、ディラン本人は、マンゴールドらとの脚本のやり取りの中でも、意外と思えるほどの寛容を示し実際の映画作りへ口出しすることを控えたのだろうし、マンゴールドらもまた、そうした神話に蓄積された豊かな解釈の余地と、それが必然として孕む伸縮性のようなものへ自らのクリエイティヴティを捧げた、と理解するのが正しいのではないだろうか。
語らないことで、語る。一つの表現それ自体が、様々な解釈に開かれている。しかし同時に、だからこそなにがしかの本質が浮かび上がる——考えみれば、これらの命題のなんと「ディラン的」なことだろう。

INDEX
「擬態」はアメリカ音楽の伝統とも接続されている
本作が類稀な神話的ピカレスクロマンになりおおせている要因は、ディランという題材の特異さに加えて、当然ながら全編に流れる楽曲それ自身の魅力に負っている部分も大きい。ミュージシャンの伝記映画においては、彼 / 彼女を演じる俳優たちが実演を行うことは少なくなく、今作においても同様の手法が踏襲されている(※)。しかし、その達成度の点で、これほどまでに圧巻のパフォーマンスを見せる(聴かせる)例はそうないだろう。
※ジョニー・キャッシュをモデルとしたマンゴールド監督作『ウォーク・ザ・ライン/君に続く道』でも、主演のホアキン・フェニックスがキャッシュの歌唱を、助演のリース・ウィザースプーンがパートナーのジューン・カーターの歌声を、見事と評するだけでは足りない気迫と技術をもって再現している。
主演のシャラメは、予め用意されたプレイバックを使って演技を行うのを嫌い、劇中において歌唱はもちろん楽器の実演も行っているというが、その堂々たるなりきりぶりには、長年のファンである私も相当驚かされた。それは、バエズ役のバルバロ、キャッシュ役のホルブルック、シーガー役のノートンも同じだ。ありきたりな感想だが、改めて一流俳優達の習得力と集中力に平伏するほかない。
ここで再び気付かされるのが、そのような高度な擬態のありようもまた、単に「いかに本人と似ているか」という表面的な次元を超えて、極めて「ディラン的」であるということだ。同じく本編で描かれる通り、ディランは常に自らのアイデンティティを固定する(される)ことを嫌い、ウディ・ガスリーの音楽や彼のホーボー風ファッションを真似たり、「カーニバル出身」という法螺話を披露したり、様々な形で自らを「他者」へと移し替えてきた。
そもそも、ディランが愛したフォークミュージックそれ自体が、ある旋律や物語類型が数珠つなぎのように継承され、様々な改変や歌い替えを通じて発展してきた「オリジナルなき」文化でもある。さらに言えば、このようや継承や模倣の運動とそれに伴う「擬態」への欲望と実践こそは、ポピュラー音楽研究者の大和田俊之が自著『アメリカ音楽史』の中で鋭く指摘したように、フォークミュージックに限らない様々なアメリカンポピュラー音楽の歴史に流れ続ける根底的なエートスでもあるのだ。意図してかせざるか、本作『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』で俳優たちが行ったパフォーマンスは、そのようなアメリカ音楽の伝統とも太く接続されているのである。