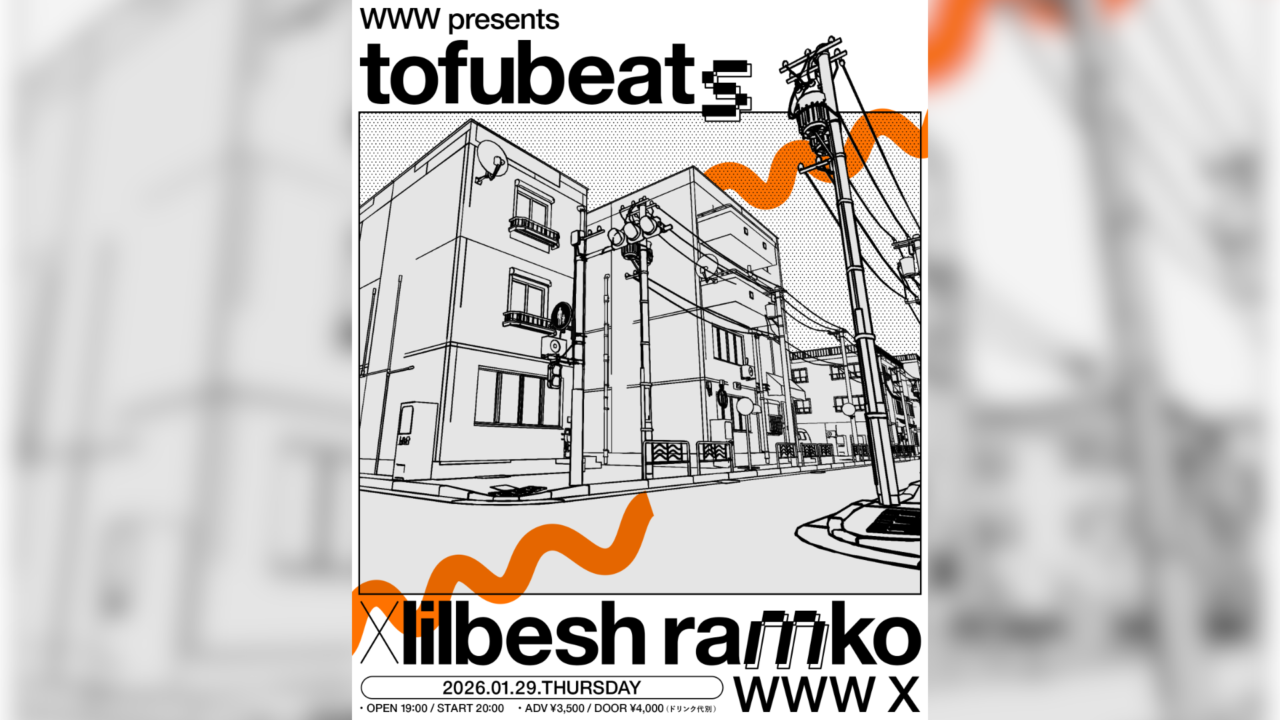映画『ランニング・マン』が2026年1月30日(金)より公開となる。スティーヴン・キングが記した『バトルランナー』の原作小説を、エドガー・ライト監督が再び映画化した同作は、いまの時代に何を投げかけるのか。劇中で流れる1970年代のポップソングに着目して、評論家 / 音楽ディレクターの柴崎祐二が論じる。連載「その選曲が、映画をつくる」第34回。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
エドガー・ライト監督の優れた選曲センス
初期作『ショーン・オブ・ザ・デッド』以来、エドガー・ライトの映画作品において、既存のポップソングは常に欠かせない存在であり続けている。『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』や『ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』『ベイビー・ドライバー』といったヒット作で聴かれた数々のポップソングの存在は、彼自身が抱く音楽文化への並々ならぬ愛情を映し出してきたと同時に、ときにはテーマやモチーフの根幹部分に関わる優れた演出効果を担ってきた。
この度新たに公開される映画『ランニング・マン』においても当然ながらそうした選曲センスは健在で、映画 / 音楽ファン双方の期待に沿うであろう優れたポップソング使用の例を体感させてくれる。

あらすじを紹介しよう。映画の舞台は、独占メディア企業の「ネットワーク社」が政治経済を支配する近未来のアメリカだ。国民はネットワーク社の監視下におかれ、住所はおろか、職歴や病歴などの個人情報が彼らの手の内に握られている。ごく一部の富める者と貧しい者の格差はきわめて深刻で、スラムに住む多くの人々は、日々の生活もままならない状況に置かれている。そんな荒んだ社会にあって、人々は、ネットワーク社が提供する暴力的なリアリティショーに熱中することで憂さを晴らしている。
職を失い、重病の娘を抱える男ベン・リチャーズ(グレン・パウエル)は、なんとかして娘の薬代を得ようと、そうしたショーの中でももっとも苛烈な番組「ランニング・マン」へ出演することになる。もし、30日間殺されずに逃げ延びたなら、1000億円という巨額の賞金を得られると謳われている番組だ。敵役のハンターと懸賞金目当ての視聴者の目が光る中、最後まで逃げおおせた挑戦者は過去に一人もいない。果たしてベンは、生き残ることができるのだろうか──。
INDEX
物語と巧みにリンクする、スライ、イギー・ポップ、ストーンズ
本作『ランニング・マン』は、かのスティーヴン・キングが1982年に「リチャード・バックマン」名義で発表した同名小説を原作としている。1987年にはアーノルド・シュワルツェネッガーの主演によって映画化(邦題『バトルランナー』)されているが、大幅な脚色が施されたその旧版に対し、今回の新版は、比較的原作に忠実なストーリーが展開される。
全体を通じて、エドガー・ライト作品特有のキレの良いアクションが随所で際立つ内容で、急転直下の物語およびカメラワークが、実に爽快なリズムを作り出している。時に過剰とすら言えるほどに慌ただしいプロット運びとなっているものの、そうした慌ただしさこそが、「逃げる男」というメインモチーフを際立たせているのがわかる。

使用される楽曲も、実にリズミカルかつ疾走感に満ちたものが多い。初期Sly & The Family Stoneの名曲“Underdog”にはじまり、南アフリカ出身のシンガーソングライター=ジョン・コンゴスによるカルトヒット“He’s Gonna Step on You Again”、Iggy and the Stoogesのプロトパンク名曲“Search And Destroy”、トム・ジョーンズによるジャキー・エドワーズ曲のカバー“Keep On Running”、カナダ系アメリカ人作曲家ガルト・マクダーモットによるソウルジャズ曲“Coffee Cold”、サザンロックの代表格The Allman Brothers Bandの“Revival”、The Rolling Stonesによるファンク風味のロックンロール“Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)”、カーティス・ブロウのオールドスクール名曲“Tough”、ジャズポエットの第一人者ギル・スコット・ヘロンの代表曲“The Revolution Will Not Be Televised”などの各曲が、オリジナルスコアとともに、映画全体のリズムと調和しながら、ときに物語を牽引していくような役割を負っている。さらに言えば、各曲の歌詞内容も劇中で描かれる心象や状況と巧みにリンクしており、当該の曲たちに慣れ親しんできたファンであれば、否応なく身を乗り出さざるを得ないだろう。
しかしながら、そのように(いつものライト監督作品と同じく)いかにも必然性を伴った選曲だと評しうる一方で、映画の要の一つである美術面における協働性という視点では、一見すると、ややチグハグな感があるのも否めない──のだが、これは、あえてそうしているのだと推察してみるべきかもしれない。
どういうことか。この映画で描かれるテクノロジーによる暴力的な人民支配の様相と、それと対応するような(主にスラム地域の)ビジュアルイメージに通底するある種の美学の存在ついて考えてみれば、おのずと意図するところが見えてくるだろう。
INDEX
レトロフューチャーなビジュアルイメージと音楽のギャップ
まず、先のあらすじ紹介でも述べた通り、この映画の舞台となる近未来においては、巨大メディア企業が社会全体を牛耳り、情報インフラはおろか、法執行機能を含めた国家権力をもその手中に収めている。そこでは、AIを駆使したフェイクコンテンツの生成や拡散が、当のメディア自身によって司られており、人々はそのコンテンツに流されるがまま、感情を操作されている。そして、スケープゴートたる「ランニング・マン」へ憎しみを向けることで、社会的な不満を抑圧されているのだ。

不正の存在を黙殺できない無辜の市民であるはずのベンが、番組のプロデューサーであるキリアン(ジョシュ・ブローリン)の策動によって大衆の憎しみの対象となり、それによって番組の視聴率(=アテンション)が上乗せされていく様は、単なるうそ寒い気持ちを超えて、私たちが現実に体感している現下のメディア生態系の弊害を想起させずにはおかない。加えて、彼らメディアの支配者たちをはじめとする限られた富裕層の人びとが、スラムから離れたゲーテッドコミュニティで(弱者への無関心・無視とともに)華やかな日常を送っている描写も、単なるカリカチュアを超えた胸の悪い気持ちを起こさせる。当然ながら、彼ら富裕層の周囲に存在する建物や、身に着ける衣服、さらには乗り物から手にするデジタルデバイスに至るまで、全てが(見た目上)清潔で、最新のテクノロジーに彩られているわけだ。
対して、当のベンを含む民衆の多くが毎日の生活を送り、あるときはその中からベンに手を差し伸べる同伴者が現れてくるスラム街においては、カメラに映るあらゆるもの様子が、富裕層を取り囲んでいるものとは異なっている。彼らが乗るクルマは旧式のポンコツを改造したもので、各種のインフラもきわめて貧弱だ。街全体の色彩も暗く、ディストピア的なムードに包まれている。また、電子的デバイスの普及率も(ネットワーク社から監視端末として強制支給されるテレビ受像機を唯一の例外として)きわめて低く、ベンの逃走を助けようとする革命勢力の面々も、旧式のコピー機やVHSなど、いにしえのテクノロジーやメディアを駆使して草の根的な活動を展開している。

こうしたビジュアルイメージは、かつて1980年代に隆盛したSF / サイバーパンク系映画で描かれた、当時の最新技術(つまり、現在のレガシーテクノロジー)を交えた未来描写を彷彿させるものであることに気づかされる(前述の『バトルランナー』も、まさにそういう映画だった)。このようなレトロフューチャー美学は、「カセットフューチャリズム」とも呼ばれ、現代のノスタルジア指向と結びついて一部のサブカルチャー空間の中でカルト的な支持を集めているが、本作のプロダクションノートによれば、上述のようなスラム街シーンの美術では、明確にそうした「カセットフューチャリズム」の美学が意識されているのだという。だとするならば、先に触れた「清潔」かつ最先端のテクノロジーが溢れるアップタウンのイメージと、このようなスラムのイメージの自覚的な描き分けは、我々観客が本作の画面を見た際に支配層と被支配層の差異を即座に感得させるための美学的装置として機能していると理解することが可能だろう。
INDEX
時代錯誤的な選曲に込められたメッセージとは
音楽の話に戻ろう。素直に考えれば、上に述べたような「カセットフューチャリズム」的なスラムの中を走り抜けるベンの姿に付随すべき音楽は、先に具体例を挙げたような主に1970年代に生まれたポップソングではなくて、むしろ、1980年代の最新(と当時目されていた)テクノロジーを直接的に想起させるシンセポップの類や、(ニコラス・ウィンディング・レフンが傑作『ドライヴ』で野心的な使い方をしてみせたような)新録のシンセウェイブもの、あるいはシュワルツェネッガー版『バトルランナー』で珍妙な効果を挙げていたようなエレクトロ調のスコアをあてがうのが適当に思える。おそらく私が感じたチグハグ感の正体とは、このきわめて「カセットフューチャリズム」的な画に対してそうした楽曲が使われていないことへの、美学上の違和感だったのだと思われる。
繰り返すように、それでもなおライト監督は、1970年代の、言い換えるならば、デジタルテクノロジーが音楽制作の過程に本格的に導入される前の――さらに言い換えるならば、人間の身体を介した生楽器の演奏が圧倒的に支配的だった時代の楽曲を数多く使っているのだ。これは主に、(今までの過去作品での選曲に照らせば)監督自身の音楽嗜好によるところが大きいように思いつつも、それ以上に私としては、ある本質的なメッセージが託されているように思えてならないのだ。そのメッセージとは一体何なのか。
私はここに、現代のメディア / テクノロジー企業文化、さらにはそれらの私企業が率先して作り上げてきたメディア生態系への痛烈な不信任の叫びを聴き取らないではいられない。ベンは、映画の中でいみじくも描かれている通り、いわばその不信任の声 / 抵抗の声に火を付ける着火装置である。彼は、肉体を躍動させ、地を走り、自らの声を挙げ、人々に交わり、妻と子を愛し、支配者たるメディア企業の存在を打ち破ろうとする。だからこそ、そこで鳴っている音楽は、いかにアナクロニズムのレッテルを貼られる危険を犯そうとも、人びとがデジタルテクノロジーによって自らの身体感覚と倫理を変質させられるより前に生まれ、あの時代のストリートに鳴り響いていた(と想像される)いにしえのロックであり、ファンクでなければならないのだ。
「そういう自分を指してラッダイト(※)と笑うならば笑うがいい。笑っているうちに、私たちの感情はメディア企業によって馴致し尽くされ、末には自らの肉体までもが奪取されてしまうだろう」――古典映画のマニアであることを隠さないライト監督は、多重に時代錯誤的な選曲を通じて、まさにそのような警句を発しようとしているのではないか。
※編注:19世紀初頭、産業革命による失業に反発し、機械の打ち壊し運動を行った労働者たち。転じて、新しい技術に抵抗する人たちを指す。