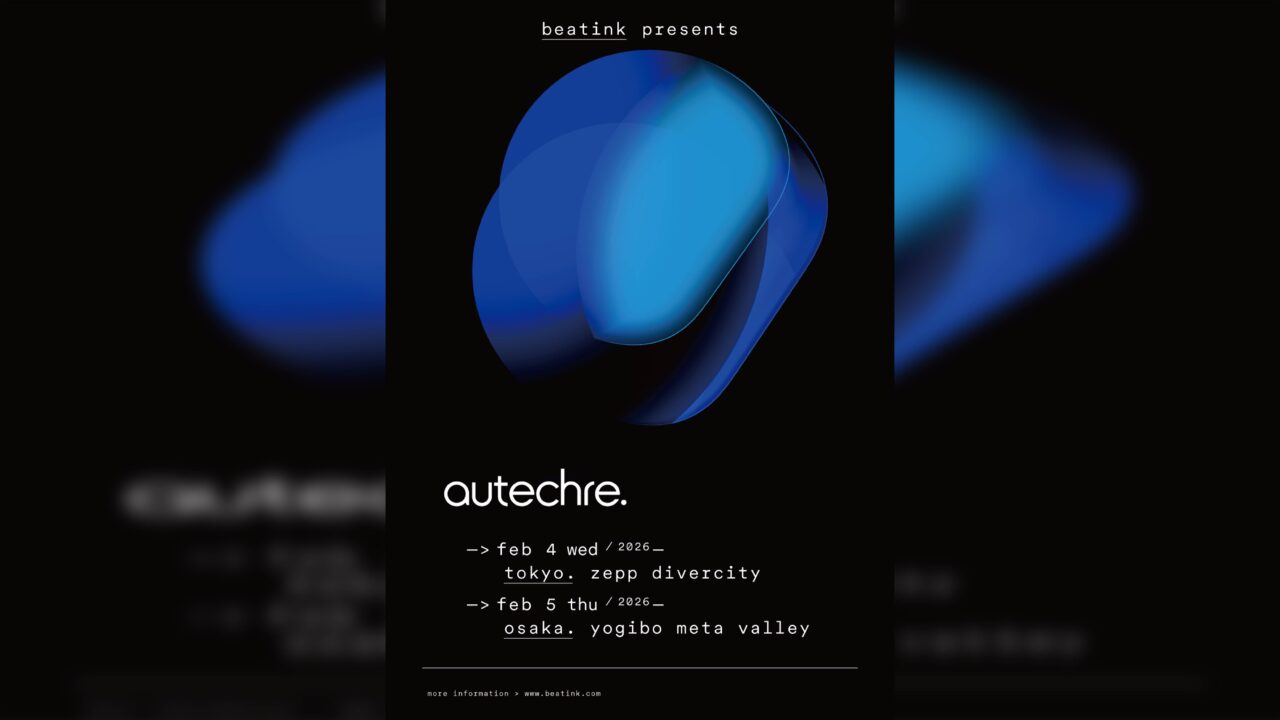ウェス・アンダーソン監督の2年ぶり、11作目となる長編映画『アステロイド・シティ』。氏の作品の持ち味である、神経質ともいえるこだわりぬかれた画面構成や美術と、印象的な音楽使用は、今回も健在だ。
本作に使用されている1940〜1950年代のカントリーミュージックやスキッフルについて、それらがもたらす「異化作用」を、音楽ディレクター / 評論家の柴崎祐二が読み解く。連載「その選曲が、映画をつくる」、第5回。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
ポップミュージック使用の名手、ウェス・アンダーソン監督
『アステロイド・シティ』公開に際して行われたインタビューで、ウェス・アンダーソンは次のように述べた。
「音楽によって映画にたくさんの感情が生まれる。画と音楽が一緒になると、どんな化学反応が起こるかわからない。時々、本当に驚かされるようなものが生まれるんだ」
出典:https://www.nme.com/features/film-interviews/wes-anderson-seu-jorge-reinvented-david-bowie-songs-he-didnt-know-i-didnt-realise-until-i-was-shooting-the-movie-3458990 より
ウェス・アンダーソン作品のファンならよくご存知の通り、彼の映画は、かねてよりポップミュージックの巧みな使用でも高い評価を得てきた。The Rolling Stones、The Kinks、The Who、ニック・ドレイク、ボブ・ディラン、Love、Nico、エリオット・スミス等によるロック〜ポップス曲から、ジャズ、各地の伝統音楽までをカバーする幅広い選曲スタイルは、単に映像への没入を喚起するだけでなく、各曲の隠れた魅力を再発見させてくれるような、卓越したものだ。アンダーソン、および長年のコラボレーターである音楽監修者のランドール・ポスターは、現代商業映画における「ポップミュージックの使い方」の新たな地平を開拓した手練として、大いに称賛されるべきだろう。

INDEX
込み入った構造とファンタジックな設定
本作『アステロイド・シティ』は、ウェス・アンダーソンにとって通算11作目となる長編映画である。自身とロマン・コッポラによる原案を元に、脚本も自らが務めた。
まずは簡単に内容を紹介したい……のだが、いつもながらその設定はなかなか込み入っている。時代設定は1955年。「アステロイド・シティ」と名付けられた架空の新作舞台劇それ自体と、その劇の制作にまつわる舞台裏の模様、そしてそれを特集するテレビ番組……という並列的 / 入れ子的な構造をとっている。アンダーソン映画の常連である主役のジェイソン・シュワルツマンをはじめ、スカーレット・ヨハンソン、トム・ハンクス、ジェフリー・ライト、ティルダ・スウィントン、エドワード・ノートン、エイドリアン・ブロディ、スティーヴ・カレル、マット・ディロン、ジェフ・ゴールドブラム、マーゴット・ロビー他、超豪華キャストが縦横に入り交じり、複雑なドラマを奏でる。
「アステロイド・シティ」の舞台は、アメリカ南西部の砂漠に位置する架空の町だ。人口87人というごく小規模なこの町の中心には、モーテル、ガソリンスタンド、ダイナーがポツンと建っているのみ。少し離れたところには、紀元前3007年の隕石衝突によってできたというクレーターや、小さな天文台がある。その町へ、妻をなくしたばかりで悲嘆に暮れる(シュワルツマン演じる)オーギーと彼の子どもたちや、過去にトラウマを抱えているらしい(ヨハンソン演じる)コメディ女優ミッジとその娘ダイナらが、同地で開催されるジュニア宇宙科学賞の祭典のために訪れる。しかし、祭典の最中に思わぬ訪問者=宇宙人がやってきたことで、現場を目撃した全員が軍の命令によってアステロイド・シティ内に足止めされてしまい……というのがこの劇中劇のあらすじである。
一方で、先述した通り、その劇中劇の上演を巡る顛末も並行して描かれ、劇作家や演出家、俳優たちの繊細な人間模様が映し出される、という仕組みだ。

INDEX
色濃く反映された1950年代アメリカのムード
こうしたメタ的かつファンタジックな構造に加え、舞台となっている1950時代の様々な時代的事象を綿密に取り込んでいく様にも、アンダーソンならではの手腕が発揮されている。本作の舞台となる1950年代のエンターテイメント業界では、テネシー・ウィリアムズやエリア・カザン、リー・ストラスバーグといった気鋭の劇作家 / 演出家 / 演技指導者たちが活躍し、アクターズスタジオの興隆を通じて、ジェームス・ディーンやマーロン・ブランド、更にはマリリン・モンローなど、多くの(既存のハリウッド俳優 / 女優像から逸脱した)スターが華々しく活躍していた。本作では、それら実在の人物たちの姿が各キャラクターに重ね合わせられており、脚本から美術、衣装に至るまで、細部に渡って同時代の美意識を反映した内容となっている。
他方、1950年代のアメリカは、そうした華々しい一面の裏側で大きな社会不安に揺れた時代でもあった。第二次大戦後からはじまったソ連との冷戦と核兵器開発競争の激化による終末論的なムードの浸透、さらには、急激な反共運動(赤狩り)による猜疑的 / 排外的空気の蔓延は、一種の社会病理とすらいえるファナティックな様相を呈していたのだった。

一見、(いつものアンダーソン調というべき)パステルカラーの楽天的な清潔さが覆う『アステロイド・シティ』にも、そうした不穏さがひたひたと打ち寄せている様が見て取れる。日常化している原爆実験のキノコ雲や、猜疑心に満ちた軍部による民間人拘束、さらには、楽天的で牧歌的な宇宙への憧憬に彩られた「スペースエイジ」の裏側に瀰漫していた(共産主義勢力からの侵攻という現実的脅威が仮託された)、宇宙人の襲来というモチーフに、そうしたムードの反映を見出すのは容易い。
アステロイド・シティのBGMは、カントリーミュージック
この、「一見すると明るく健全だが、その裏に荒涼とした不安感が巣食っている」という1950年代像は、「古き良き時代」や「アメリカの黄金時代」という輝かしい公式イメージの裏でしぶとく蠢き続け、これまでも、数多くのサブカルチャーの中で度々再演されてきたものだ。
本作において、ウェス・アンダーソンとランドール・ポスターは、こうしたアンビバレントなムードを、映像だけでなく音楽を通じて表現することに成功している。

彼らは、これまでの作品でも実際の撮影に入る前の段階で自分たちのイメージに合致する楽曲を探索してきたというが、その手法は本作の制作にあたっても踏襲されたようだ。今回彼らが「採集」したのは、主にカントリーミュージック、カウボーイソング、ヒルビリー、ブルーグラス等に分類される、1940年代から1950年代にかけて吹き込まれたヴィンテージな音楽だ。
サウンドトラックを聴けばすぐに分かる通り、これらの曲は、なんとも長閑で明るく、健全な響きを持っている(ように聴こえる)。ボブ・ウィルズ、ビル・モンロー、テックス・リッターらによる曲が閑散としたモーテルの拡声器(ラジオ?)から流れる様子は、いかにも平和で穏やかだ。
しかし……である。このアステロイド・シティのモデルの一つとなっているのが、あのマンハッタン計画の中心地として有名なロスアラモスであると気づく時、にわかに異なるニュアンスをもって響いてくるのだ。

INDEX
音楽が想起させる『アトミック・カフェ』と『マーズ・アタック!』
突然だが、『アトミック・カフェ』という映画をご存知だろうか? 核兵器開発競争に邁進する戦後のアメリカで大量に流通したニュース映画やプロパガンダ映像などをコラージュして作り上げられたドキュメンタリー映画で、1982年の公開以来、カルト的な人気を集めてきた傑作だ。
この映画は、音楽の使い方にも皮肉(以上のもの?)が効いている。様々な有名無名歌手がプロパガンダに乗じて原子爆弾を褒めそやす、戦後期に実際にリリースされた楽曲が大量に使われていたのだ。そして、このサントラの中で、ポピュラーボーカルものやゴスペル等に混じって特に目立っているのが、ヒルビリー系の楽曲だった。
『アステロイド・シティ』を観て私が最初に感じたのが、この『アトミック・カフェ』に使用された「愛国的」なヒルビリーソングを聴いたときに覚えた空恐ろしさ……つまり、先に述べたような「一見すると明るく健全だが、その裏に荒涼とした不安感が巣食っている」という感覚だった。
もちろん、アンダーソンおよびポスターは、あからさまに上述のような「原爆ソング」を使用しているわけではないが、わざわざ幕開け曲“Last Train to San Fernando”に被せる形で核ミサイルを登場させたり、本編中にも核実験によるキノコ雲の描写を複数回登場させているところからすると、少なからず『アトミック・カフェ』におけるカントリーソングの強烈な異化作用を意識していたのではないか、と推察してみたくなる。
やや牽強付会が過ぎたかもしれない。しかし、こうしたカントリーミュージックの異化作用というのは、優れた映画作家が少なからず実践してきた手法でもあるのだ。
最も著名な「異様な使い方をされているカントリーソング」といば、ティム・バートン監督作『マーズ・アタック!』(1996年)におけるスリム・ホイットマン“Indian Love Call”(1952年)だろう。甘いヨーデルボイスをトレードマークとする伊達男ホイットマンの代表的レパートリーである同曲をかけると、火星からの侵略者である宇宙人がその曲の特有の周波数のせいで頭を破裂させて息絶えてしまうという、強烈(かつ超重要)な使われ方をしているのだ(余談だが、曲名通り同曲が先住民の伝説をモチーフとしていると捉えると、ここで頭を破裂させる「侵略者」は、かつてのアメリカ大陸への侵略者=ヨーロッパ人たちを差しているとも考えられる!)。
そして、このスリム・ホイットマン版の「インディアン・ラブ・コール」は、本作『アステロイド・シティ』でも、ラジオから流れる曲として使用されているのだった。『マーズ・アタック!』を観たことのある観客なら、この曲の流れるシーンで反射的にあのビザールでおどろおどろしい火星人の姿を思い出してしまうはずだ(アンダーソンが『マーズ・アタック!』を観たことがないとは考えづらいから、これはどうみても確信犯だろう)。

「スキッフル」がもたらす「フェイク感」の巧みさ
加えて気になったのが、いくつかのスキッフル曲の使用だ。先に述べた通り、劇中劇「アステロイド・シティ」の幕開けとして、“Last Train to San Fernando”が流れるのだが、この曲を歌っているジョニー・ダンカンは、(アメリカ生まれではあるが)生粋のブルーグラス系アーティストというより、英国のトラッドジャズシーンに移ってからスキッフルブームの中で成功を収めたミュージシャンだった。
ロックの歴史書めいてしまうので深入りはしないが、「スキッフル」というのは、元をたどるとアメリカにおける特定のアコースティックバンドスタイルを指す用語であったわけだが、1950年代後半のイギリスでロニー・ドネガンが「スキッフルシンガー」としてにわかに人気者になったのを境に、トラッドジャズやフォーク、ジャグバンドミュージック、ブルース、ロックンロール、ヒルビリーなどを複合したアコースティック編成の音楽を総称する用語として定着していった。それゆえに、音楽的な定義にもゆらぎ(ゆるさ?)を伴った、(純粋主義的なアメリカンルーツミュージック愛好家からすると)やや「ニセモノめいた」ものと理解されがちな音楽だったりするのだ(今となっては、そこまで厳密な種別を意識するリスナーは少数だろうが)。
同様のことは、エンドロール(の前半)に流れる、The Chas McDevitt Skiffle Groupとスコットランドのフォーク歌手ナンシー・ウィスキーによる“Freight Train”の、威勢のいいいかにも英国スキッフル的なカバーにもいえるかもしれない(同曲のオリジナルは、黒人フォーク歌手、エリザベス・コットンによる)。

何が言いたいかというと、それなりにヒルビリーやカントリーミュージックを好んで聴いてきた私の耳には、これらの英国産スキッフルソングの使用が、1955年の米南西部という舞台設定と比較した場合、どうしても「フェイク」っぽく聴こえてしまうということだ。誤解してほしくないが、「だからこの映画の音楽の使い方はダメだ」などと狭量な小言を言いたいのではない。むしろ逆で、この「ニセモノ」っぽさこそが、この映画のプロダクションの傾向にうまく合致し、それどころか、冒頭のインタビューでアンダーソンの言っている「化学反応」を生じさせ、結果的にその演出効果を加速させているように思うのだ。
いかにも「本物」らしいけれど、すんでのところでフェイク性が顔をのぞき、いつの間にか我々観客もその蠱惑に騙され、豊かな人工美の世界へと招かれる……。アンダーソンの映画にあるそういう磨き上げられたフェイクのおかしみ、入り組んだリズム、ありえない画面移動、過剰に緻密な画面構成の美しさが、本作におけるどこかいかがわしげな音楽の使い方の魅力にも通じているように感じるのだ(長くなるので詳述はしないが、そういう意味で、「架空のパラダイス」を描くレス・バクスターのエキゾ曲が使われているのにも、合点がいく)。