漫画家オカヤイヅミさんが、ゲストを自宅に招いて飲み語らう連載「うちで飲みませんか?」。第9回は作家 / アーティストの小林エリカさんにお越しいただきました。
先日インド旅行に行っていたオカヤさん。奇しくも同じ時期に、インドの文芸フェスティバルに招聘されていた小林さんを、現地で訪ねたそう。お二人はインドで何を見て、何を感じたのか。帰国後行われたサシ飲みの模様をお届けします。
当日振る舞われた「鯖マサラ南蛮」のレシピもお見逃しなく!(レシピは記事の最後にあります)
INDEX
小説家の受賞パーティー、漫画家の受賞パーティー
オカヤ:ようこそ。うちにお越しいただくのははじめてだよね。
小林:うん。オカヤさんとはよくパーティーで会うけど、差し向かいははじめてかもしれないね。パーティーだと、私はいつも圧倒されてオカヤさんの後ろに隠れてて、スピーチが回ってくるのにドキドキしたりしてる。

作家、アーティスト。1978年生まれ。著書に『親愛なるキティーたちへ』(リトルモア)、『マダム・キュリーと朝食を』(集英社、第151回芥川龍之介賞候補)、『女の子たち風船爆弾をつくる』(文藝春秋、第78回毎日出版文化賞受賞)など。
オカヤ:そう、作家の人たちの受賞パーティーって、二次会でスピーチが回ってくるんだよね。それで、みんなすごくいいことを言うじゃん。あれ、すごいと思う。私にはできないよ。
小林:漫画家さんのパーティーは、マイク回ってこないの?
オカヤ:漫画家のパーティーもそんなに知らないんだけどね……。当然のように回ってくる文化、恐ろしい! と思ってるよ。作家の人が来てくれてたらマイクを渡さないのは失礼、みたいな感じがあるよね。
小林:歌手がいるのに歌わせないなんて、的なことなのかな。あれは私も毎回びっくりするよ。私はこないだ賞をいただいたとき、スピーチのかわりに私が勝手に出題するクイズにしたよ。そうしたらみんなに「画期的ですね!」「斬新ですね!」って言われて。
オカヤ:楽しそう! それはみんなに感謝されると思う。私だけ特別ドキーンとしてるのかと思ったら、みんなけっこう緊張してしゃべってるんだよね。
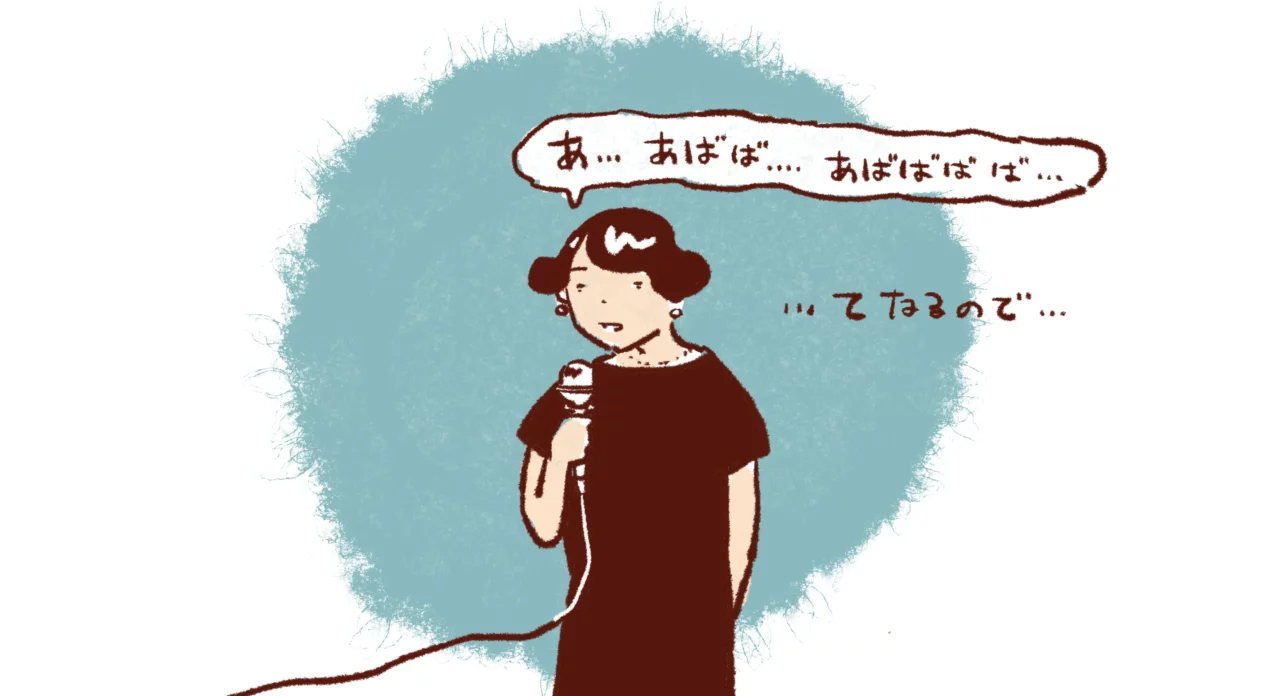
小林:漫画家さんのパーティーは一晩で賞金を使い切るって聞いたけど、それは本当なの?
オカヤ:そんな華やかなところには行ったことがないな……。
小林:手塚賞(※)のときは、賞金を使い切ってないの?
※手塚治虫文化賞。オカヤさんは2022年に短編賞を受賞。
オカヤ:使ってない、ない。アシスタントがたくさんいる漫画家さんで、みんなの慰労会みたいにする人はいるのかも。
小林:そういうことか。人数が多かったらそれだけお金がかかるもんね。
オカヤ:手塚治虫文化賞はわりとアットホームな感じで、その場でお寿司を握ってくれる文学賞のパーティーの方がぜんぜん派手だったよ。
小林:そうなんだね。その噂、どこで聞いたか、読んだんだっけな。漫画家さんってすごい! 100万円のパーティー、憧れ! と思ってたんだけど、幻の伝説なんだ。
オカヤ:どこかではやってるのかもしれないけどね。漫画の世界は広くて、私は業界内でもパーティの会場でも、だいたい端っこにいるから。
INDEX
インドのレストランで考えたこと
小林:オカヤさんは、インドでいろいろ見てこれた? 私はほとんどカンファレンス会場のアライアンス大学とバンガロールのホテルの行き来だけで、マーケットも何も見れなくて。それはそれですごく楽しかったけど、リキシャ(三輪タクシー)とか乗ってみたかったな。
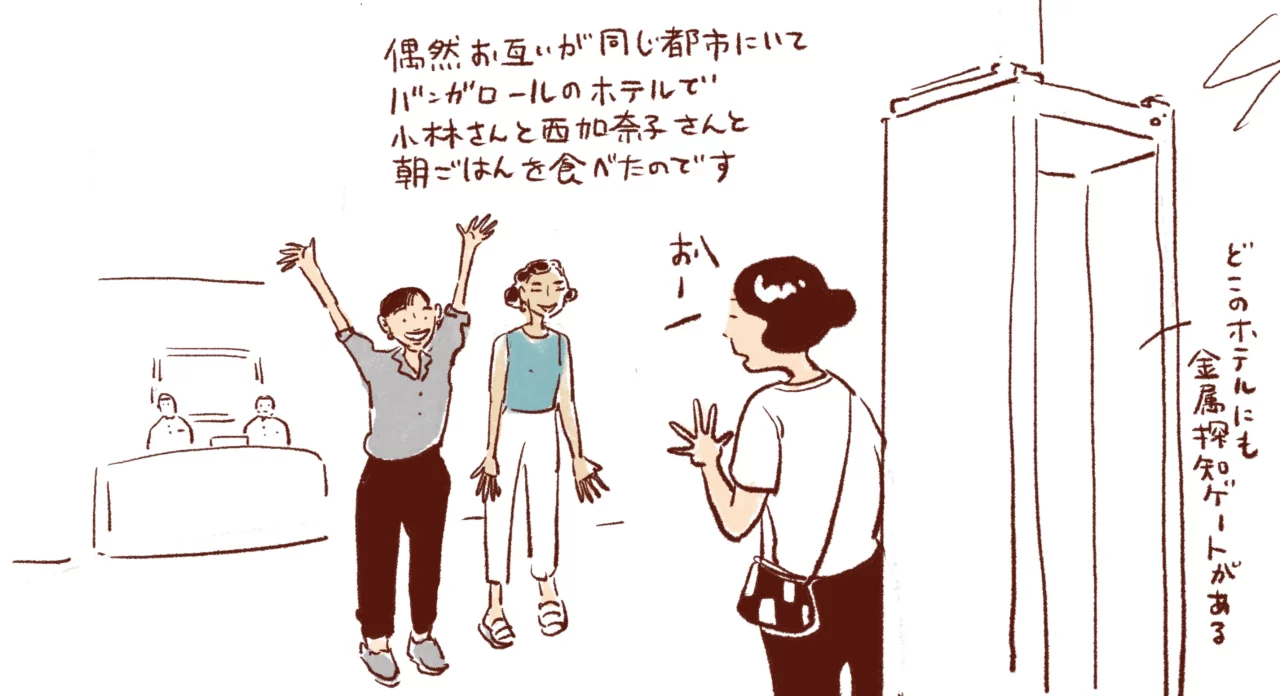
オカヤ:レストランにも行けてないって言ってたよね。
小林:そう、スケジュールがいっぱいだったのとバンガロールの渋滞がハードでなかなか外に出れなくって、ほとんどホテルか大学のビュッフェしか食べてない。でもぜんぜん飽きなくて、カレーはいくらでもいけると思ったよ。あと、肌の調子も良くなった感じがする。
オカヤ:血行が良くなったのかな? たしかにインドの人は肌がきれいに見えた。
小林:カレー、良さそうな気がする。毎日食べたいもん。帰国してすぐ南インド料理屋さんに行って、ビリヤニを食べたりもしたよ。
オカヤ:(小林さんと同じカンファレンスに参加していた)柚木麻子さんも、Instagramを見ていたら、帰国してすぐカレーを作って食べていたね。
小林:カレーって中毒性があるのかな、ずっと食べたい。今日もインドっぽいお料理でうれしい。誰かの家で、自家製のロティが出てくるのなんて、見たことないよ。そうそう、このロティをこねた「のし板」はインドで買ってきたんだよね。
オカヤ:そう。しかもけっこう序盤で買っちゃって、ずっと荷物が重かった。

小林:最後に立ち寄れたチェンナイでは、王宮南インド料理みたいな食事をいただいたんだけど、それがめちゃめちゃ美味しくて。ほうれん草のカレーに、きび砂糖と、ゴートチーズの味がするバターを混ぜて食べる、とか。ちょっとエル・ブリ(※)的な感じでさ。エル・ブリ食べたことないからイメージだけど。
※スペインにあった独創的なメニューで有名なレストラン。
オカヤ:おもしろい。ちょっと高いお店って、すごく店員さんが多くなかった?
小林:そうだったかも。
オカヤ:それで、みんな自分の役割しかしないんだよね。盛る人は盛る、片付ける人は片付けるだけ。だから、日本でインドの人を雇うと、コックの人はコックしかしないから、「ちょっとホール手伝って」みたいなことができなくて難しいんだって。それはカーストが根底にあるからだって本で読んで、なるほどと思ったんだよね。
小林:なるほどね。カーストは理解しがたいところがあるけれど、自分の役割だけをするってところだけ見ると興味深い。料理を作る職能と、お客さんと接する職能は、ぜんぜん違うもんね。日本だとマルチにできないといけないって、実は過剰な働きなのかも……。
オカヤ:そうだね。ゴアという街に行ったんだけど、観光地・リゾート地の、高級な化粧品店や洋品店が並んでいる前の道を工事しててさ。そのへんをボコボコに掘り返してて、積んである資材の間をみんな普通に歩いて通るんだよね。
小林:うん。
オカヤ:土管出てるけど大丈夫? って。お店もすました顔で営業してて、日本の感覚だとちょっと驚くんだけど、でもそれくらいでいいじゃんとも思ったな。
INDEX
日本の街のきれいさと、「慮り」の強さ
小林:自分が真面目すぎたのかな、もっとおおらかに生きたいな、と思うよね。こないだ海外の友だちとしゃべってたら、以前はみんな道のどこでも赤信号でも横断してたのが、罰金制になったら止まるようになったって言ってて、なるほどなと思った。それもそうだなと思って。
オカヤ:日本人は真面目すぎるのかもね。
小林:そうそう。交通ルールはともかく、考えたら、しなくてもいい自粛をしていることって、わりとあるよね。

オカヤ:人との距離感とか不文律が、いつもいる場所とは違う、って思えたのはとても良かった。最近、漠然とした「みんな」がすごく気を使ってるなという感じがしてたから。SNSの向こうに見える人たちがいろんなことに怒ってるから、怒られないようにしなきゃと思いすぎちゃうし。
小林:マナーとか常識って難しいよね。私は察せられないから、明示してもらわないとわからない。慮るのが得意な人はいいけど、私、何が失礼とかも、直接的に言ってもらわないと素でわからなくて。
オカヤ:私もそうだな。子どもの頃「マイペースだね」っていうのは褒め言葉だと思ってた。「急げ」って言ってくれればよかったのに。
小林:そう、私もいつも褒められてると思ってるもん。嫌味を言われてるのがわからなくて、「わあ、ありがとうございます!」って喜んでて、ずっと後から考えたら、もしかして……みたいな。
オカヤ:その方が幸せだと思うけど、京都には住めないね(笑)。
小林:そうだね。「お茶漬けいただいていいんですか? ありがとうございます!」って(笑)。でも本当に、旅に行くと自分のふだんの生活を見つめ直すよね。
オカヤ:帰国して街に出たとき「えっ、きれいすぎじゃない?」と思ったもんなー。慮るからこんなに清潔な国でいられてる面もあるけど、息苦しくなるまで整えるんなら、ここまできれいじゃなくていい気もしたよ。別に道がボコボコでも歩けたし、って。
INDEX
気ままに自炊できることの貴重さを意識されられた
オカヤ:あと、私が行ったインドのスーパーでは出来合いのお惣菜の類がぜんぜん売ってなくて、毎食をイチから作らないといけないのは大変だなと思った。
小林:たしかに、全部の食事を毎回作るのはそれだけで大変だよね。私はインドでまだ幼いうちに結婚させられたサンギータ・ヨギさんとタラブックスが一緒につくった絵本の翻訳をさせてもらったんだけど、彼女は小学校も二年生までしか行けなかったし、結婚してからも家事が忙しくて、ずっと働きどおしだって、言ってた。家族連れが外食することはあまりないのかな。
オカヤ:ちゃんとしたレストランでたまに、というのはあっても、ふだんの食事はお家が多いのかもね。
小林:彼女は肉体労働をしていて、お昼ご飯を食べにみんな家に帰る休憩中に絵を描いていたって言ってて。くたくただよね。そういうのって、女性が無償で食事作ったり家事労働することのうえに成り立っているってことだもんね。
オカヤ:そういえば軽食のお店に行ってもおじさんしかいなかった感じはしたな。
小林:女性が一食をちょっと買ったり外で済ますことができないっていうのは、ハードルが高いね。
オカヤ:インド料理って、作るのに時間がかかるものが多いしね。そういう、家事が大変という話を聞くと、簡単に「料理が楽しい」とか言ってすいません、とも思う。

小林:好きなときに好きなものを作ったり食べられたりするのは、貴重なことなんだよね。
オカヤ:一週間いたくらいでわかった気になってもいけないと思うけど、インドは物乞いの人も多いし、カーストが残っている部分もあるし、自分の特権性を意識することはたくさんあったな。あとやっぱり、植民地についてもいろいろ思わされた。
小林:うん。バンガロールの街で見た本屋さんは、本が横積みなのが面白いと思ったけど、売られていた本はほとんどが英語の本で。
オカヤ:英語だから、横向きに置いた方が背表紙のタイトルが読みやすいんだよね。
小林:多言語の国だから、もちろんいろんな言語の出版社もあって、タミル語専門の出版社の人に会えたのは面白かったけど、基本イギリスの出版社の本が主に入ってくる、というのを聞いて、ああ、そうか植民地だったってことがこんな風に続いているのだな、って。



























