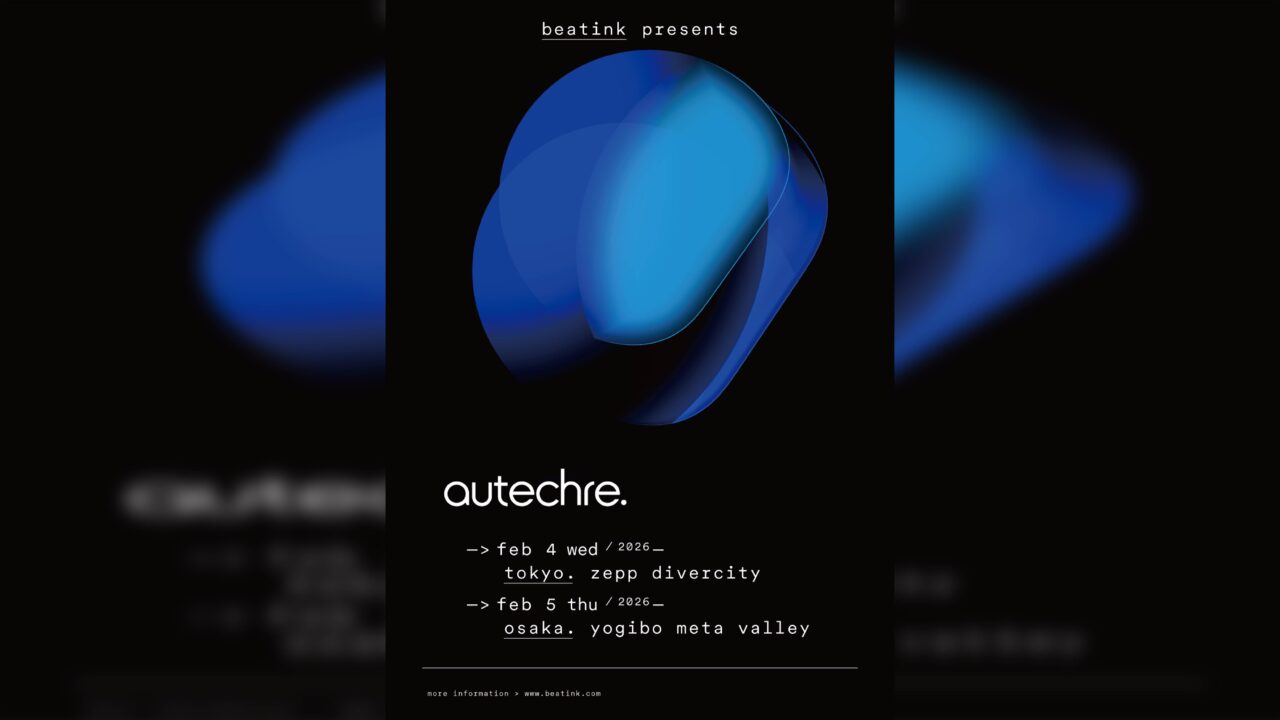YAJICO GIRLがアルバム『EUPHORIA DLX』をリリースし、2月に大阪・3月に東京でワンマンライブ『YAJI YAJI SHIYOUZE 2025』を開催する。結成当初のギターロックから、アンビエントR&B / ヒップホップへと接近し、「シティポップ」とも呼ばれた時期を経て、現在のYAJICO GIRLはダンスミュージックに傾倒。2023年11月に発表した『EUPHORIA』のデラックス版である『EUPHORIA DLX』には、ライブ用のリアレンジやリミックスなどが追加収録され、多幸感に満ちたライブを展開する現在のモードをより明確に示している。
「Indoor Newtown Collective」を名乗っているように、バンドの中心人物である四方颯人(Vo)はクラブ通いをするタイプではなく、どちらかといえば「インドア」、つまり内気でシャイな性格だ。最初にダンスミュージックに惹かれたのも、儚さや諦念を内包するスーパーカーの世界観が自分にフィットしたからだという。だからこそ、YAJICO GIRLのダンスミュージックはハウスやテクノ譲りの快楽性だけでなく、聴き手に寄り添い、「君のままでいいよ」と語りかけ、不安を和らげる力を持っている。変わり続けるバンドの現在地について、四方に話を聞いた。
INDEX
ダンスミュージックのルーツ。「諦念が前提にある」スーパーカーの魅力
―近年のYAJICO GIRLがダンスミュージックに傾倒していった理由について、改めて話していただけますか?
四方:やっぱりバンドをやってると活動の中でライブのウェイトが大きくなっていかざるを得ないんですよね。そこと向き合ったときに、フロアとの関係性だったり、どういうショーが面白いかを考えていった結果、クラブという空間の心地よさみたいなものを、バンドとしてライブハウスで表現できたらいいなと思ったんです。そこからダンスミュージックへの興味が強くなって、そっちに舵を切っていった感じですね。

吉見和起(Gt) / 榎本陸(Gt) / 四方颯人(Vo) / 武志綜真(Ba) / 古谷駿(Dr)からなる5人組バンドYAJICO GIRL(ヤジコガール)のボーカル。自身の活動スタンスを「Indoor Newtown Collective」と表現する。2016年『未確認フェスティバル』『MASH FIGHT』など様々なオーデションでグランプリを受賞。音源制作 / アートワーク / MusicVideo の撮影から編集、その他ほとんどのクリエイティブをセルフプロデュースしている。2020年より活動拠点を地元・大阪から東京に移し、活動の幅を勢力的に拡げている。
四方:あとは時代の流れもあって、僕はずっとトレンドを楽しむタイプのリスナーなので、そこの琴線に引っかかるところもあったと思います。もともと自分のルーツにはスーパーカーがあるし、The Chemical Brothersもロックと同時並行で学生時代から聴いてたんです。そういうのが1周回ったY2Kリバイバルみたいなものと、自分たちが今求めてるダンスミュージックのモードが合致していったのが2023年くらいからの流れで、2024年の11月にその集大成としてアルバムを出し、今回デラックスバージョンを作ったっていう感じですね。
―近年のダンスミュージックで特に影響を受けたものを挙げてもらえますか?
四方:いっぱいあるけど……去年チャーリーXCXが出した『BRAT』はすごく象徴的な作品だったなと思います。Y2Kだったり、その時代に培われてきたダンスミュージックのカルチャー、レイヴ的な感覚とか、自分の中では全部まぜこぜになって、『BRAT』という一つの概念でまとまってると思っていて、すごく意識しました。
四方:コロナが明けたくらいから、いろんな国や人種でクラブミュージックに対する熱量が高まってたと思うんですけど、自分の中では『BRAT』がそれを決定づけて、ムーブメントになったなと思っていて。『EUPHORIA』のジャケットを原色一発でドーンと出したいと思ったのも、『BRAT』の影響があると思います。
ーもともとスーパーカーが好きだったのはどんな部分が大きいですか?
四方:(スーパーカーが主題歌を担当した)映画の『ピンポン』が好きっていうのがあるんですけど、あとはあの無機質な感じ、ミニマルな感じとか、儚さとか、どこか諦念が前提にある部分とか、それが他のバンドよりも自分にしっくりくる部分が大きかったんです。それは当時もそうだし、年をとっていろんな音楽を聴いてきた今でも、やっぱりあの世界観、あのニュアンスは自分にしっくりくるものだなっていうのがありますね。ネガティブなまま言葉を放ってる感じとか、影響を受けてるんだろうなと思います。
ー『EUPHORIA DLX』のディスク2にライブバージョンミックスで収録されている“CLASH MIND”はもともと『インドア』の収録曲でしたが、やはりイメージはスーパーカーの“Strobolights”?
四方:そうですね。当時からスーパーカーっぽいことがやりたいと思って作った曲だったんですけど、もうちょっと解像度が上がって、より明確にやりたいことができるようになったのが新しいバージョンです。
アルバムで言うと『ANSWER』と『Futurama』がフェイバリットで、『Futurama』に入ってる“Easy Way Out”は歌詞の面でもすごく影響を受けたところがあります。<いいさどうせ いい案ないし いいさどうせ 急いでないし 本当がどうだって関係ないし>とか、このちょっと俯瞰してる感じがすごく自分にフィットするなって。
ー<なるようになるさ どうせ>とか、やはりどこか諦念を感じますよね。スーパーカーはデビュー当時は1990年代的なロックバンドだったけど、徐々にエレクトロニックになって、ダンスミュージックの時期があって、ラストアルバムの『ANSWER』もそれまでのアルバムとは少し違っていて。そうやって作風が変化していくのも好き?
四方:確かにそうですね。散るまでの流れがめちゃくちゃきれいというか、美しいバンドだなというイメージがあります。

ーYAJICO GIRLは散られちゃうと困るけど(笑)、音楽的に変遷をしていってるという意味では、リンクする部分もありますよね。
四方:そのときにやりたい音楽を正直にやってるバンドが好きだし、そこに勇気づけられながら自分たちも音楽をやってきたから、そういう部分は大事にしたいです。
ー今は1個しっかり型があって、そのスタイルを続けていくバンドか、1曲ごとにジャンルが変わるソロアーティストが多いイメージで、アルバムごとにモードが変化していくようなバンドは意外と少ない気がします。
四方:アルバムで区切って語られていく、そのストーリーテリング自体が昔より薄くなってるのもあるのかな。でも海外のアーティストを聴いてると、いろんなトレンドとかバズはありつつも、やっぱりアルバムで世界観を表現しているアーティストが多いですよね。それこそチャーリーXCXもそうだったと思うし、そういう楽しみ方が好きなので、自分でも意識してやっちゃう部分はありますね。
INDEX
「インドア」を自称する四方が、現場主義のクラブに対して思うこと
ーダンスミュージックのモードになってからのライブに対する手応えをどう感じていますか?
四方:2024年の11月に東京でやったワンマンライブは、ここ1年でやろうとしてたことが一つ形にできたライブだったと思っていて、僕的に手応えはありました。
ー四方くんはもともとライブよりも曲を作るのが好きなタイプだったと思うのですが、ライブをやっていく上での葛藤はあったりしますか?
四方:イベントをオーガナイズして、その真ん中に立って、先頭を切って空間を作っていくタイプではそもそもないっていうのはあります。でもそこは努力するべき部分だなと思いながらやっているので、葛藤というわけではないかな。けど今ステージに立つ上で、自分自身がアーティストとして、一表現者として表現したいものと、ショーとして考えて、こう表現した方がプラスに働くだろうっていう、そこの葛藤はありますね。

ーアーティストとしてのエゴと、エンターテインメントとして見せる部分と、そこをいかに合致させるかの難しさがある?
四方:そういう葛藤はずっとありますけど、ここ最近はいい意味でエゴが少しずつ取れて、みんなで楽しめるような選択を取れるようにはなってるような気がします。そこは歪な構造かもしれないですけど、ポップカルチャーは抑圧されてたり、苦し紛れで生まれるからこそのオーラがあったりもすると思うんです。苦しんでる人の作品は悲しいけど面白かったりする。
ー四方くんはそもそもクラブ通いをするタイプでもないというか……。
四方:自分で「Indoor Newtown Collective」って名乗ってるくらいですからね(笑)。でもそれで言うと、現場主義的なことの意味もすごくわかるけど、もう少しカジュアルにダンスミュージックを楽しみたいというか、クラブという空間がもっと開いててもいいのになっていうのは、いち音楽ファンとしては思うので、架け橋になりたいとは思いますね。「ライブハウスには行くけど、クラブはよくわからない」っていう人が結構いると思うから、そういう人が「こういう気持ちよさもあるんだ」っていうのを体験できるようなバンドになれたら嬉しいなっていう思いはあります。

ーロックフェス的なノリは苦手だし、でも「好きなように踊って」と言われても、どう楽しんでいいかわからない、どっちにもはまりきれない人って実は多いはずで。ロックバンドとしての魅力もあるし、ダンスミュージック的な快楽も持ってる、YAJICO GIRLじゃないとすくい上げられない層があって、そこには可能性があるのかなと。
四方:そこに賭ける気持ちはありますね。やっぱり僕たちは「バンド」っていうのが一番根本のアイデンティティとしてあるので、全員でDJブースに立ってクラブミュージックだけ流すみたいな方向には進まないと思うんです(笑)。
だからもっと生っぽい、ロックバンドっぽいところもうまく混ぜたいと思っていて、そうなると最初に言ったThe Chemical Brothersとか、Fatboy Slimとか、デジタルロックと言われてたような音楽のニュアンスが、今回のハウスミュージックっぽいところにもう一つ乗っかってくると、よりバンドの音楽としても魅力的になっていくのかなと思いますね。
INDEX
本当や正義が揺らいでいる時代に、<今その向こうへ>と歌う
ー『EUPHORIA』の収録曲の中で、ライブで演奏することでより手応えを感じた曲、文字通りの多幸感を感じた曲はありますか?
四方:どの曲もそうではあるけど、やっぱり“ユーフォリア”はライブでやると特別な気持ちになりますね。あと“平凡”はリリースした当時はもうちょっとストイックな、サンプルで作ったハウスミュージックっていう印象だったんですけど、ライブを重ねるうちにみんなで楽しめる曲になっていて、最近のライブではアンセムっぽい立ち位置になってると思います。“APART”に関しては結構ロックなテイストなので、さっき「次はもうちょっとロック要素を出すかも」と言ったけど、そのヒントになるような1曲かもしれないですね。
ースーパーカーに惹かれるのは諦念や儚さだという話があったように、“ユーフォリア”も歌詞はそこまで明るい曲ではないですよね。むしろ<不安なままでいいよ 自分だけじゃないなら>のように、内省的な側面が四方くんらしさで、でもその先で多幸感を見出そうとしているのが非常に魅力的だなと思うのですが、この曲にはどんな想いを込めましたか?
四方:“ユーフォリア”もそうだし、このアルバム自体そうかもしれないですけど、音を聴いて気持ち良くなる、その単純な行為自体の美しさをすごく持っていると思うので、それが一番感覚的に伝わりやすい曲にしたいなっていうのはありました。
最初に鳴るシンセもそうですけど、一つの音だけで我を忘れて、自分が普段考えてることだったり、思い悩んでることだったりから離れて、音の気持ちよさに浸れる。僕自身がこのタームでそれに救われてたし、その先で自分を肯定したり、他者を肯定したり、そういうことを表現できる曲になったらいいなと考えて作りました。

ー“ユーフォリア”の歌詞で一番大切にしているのはどの部分ですか?
四方:<本当のこと 今思い出してる>って、2回繰り返すんですけど、最後に<本当のこと 今その向こうへ>に変わるのが、自分にとってはすごく意味のある変化で。何が大事なんだろう、何が本当なんだろう、どういうことが正義なんだろう、そういうことがすごく多様化して、揺らいでいる中で、その選択を超越する感じというか、その一歩先、向こう側に進むということが、自分の中では多幸感や陶酔感だったりするんです。
なので、最後の<今その向こうへ>は大事に歌っていて、そこからまたイントロのシンセが鳴り、コード進行が変わるんですけど、そこでいつも泣きそうになりますね。自分で言うのもなんですけど、いい曲やなって(笑)。
ーまさに“Easy Way Out”の<本当がどうだって 関係ないし>と繋がる部分ですね。はっきりとした答えが出なくても、我を忘れて踊って、多幸感を感じて、一夜明けた後にはちょっと違う自分になれた気がする。そんな感覚はクラブミュージックの醍醐味だと思うので、“ユーフォリア”はまさにそれを体現する一曲だなって。
四方:ほんの数ミリ変わるだけでも、それは希望ですからね。

INDEX
音響や視覚要素も整備したワンマンライブ。「今のYAJICO GIRLを見てもらいたい」
ー2月21日に大阪、3月7日に東京でワンマンライブ『YAJI YAJI SHIYOUZE 2025』が開催されます。どんなライブにしたいと考えていますか?
四方:さっきも言ったように、前回のワンマンライブは自分たちが目指してたことが一つ形になったライブだと思ってるので、それをよりブラッシュアップしていきます。ただ毎回来てくれるお客さんもたくさんいるので、長尺でワンマンライブをする上で、体験として前回とどう違うものにして、前とは違う意味で「今回もよかった」と思ってもらうために、どういう工夫ができるかは今もメンバーで話してますね。

ーダンスミュージックは低音の出し方をはじめ、音響面での細やかな部分も大事になってくると思いますが、その点に関してはいかがですか?
四方:ここ1年ぐらいは毎回ワンマンの前にリハに入って、細かい音の調整をしているし、PAをやってもらっている方はすごく低音に長けてる方なので、ダンスミュージックは合ってるなと思っていて。そこに関しても、前回のライブでクオリティは担保できたなと思っているので、今回はもう少し視覚的な面白さにも着手したいなと思ってます。前回は(古谷)駿がオブジェを作ってくれたんですけど、照明も含めて、視覚的な部分のかっこよさは、今まさに突き詰めてる途中です。



ー確かに、クラブミュージックは映像とか視覚的な要素との相性も重要ですよね。
四方:そこに力を入れたいなっていう話は、前回のライブが終わっててすぐにしました。そういう部分も含めて、結構面白いことをやってるなと思うんですよ。ライブに通い慣れている人でも、新しい体験だと思ってもらえるようなライブにようやくなってきたなって、そこは自信を持って言えます。

四方:あとは変化してきてるバンドなので、初めて観る人はもちろん、昔観てあんまりしっくり来なかった人とか、昔好きやったけど最近は観てないとか、そういう人にもぜひ今のYAJICO GIRLを観てもらいたい気持ちがすごくあります。本当に多幸感のある、気持ちのいい空間になると思うので、ぜひ来てほしいなと思いますね。