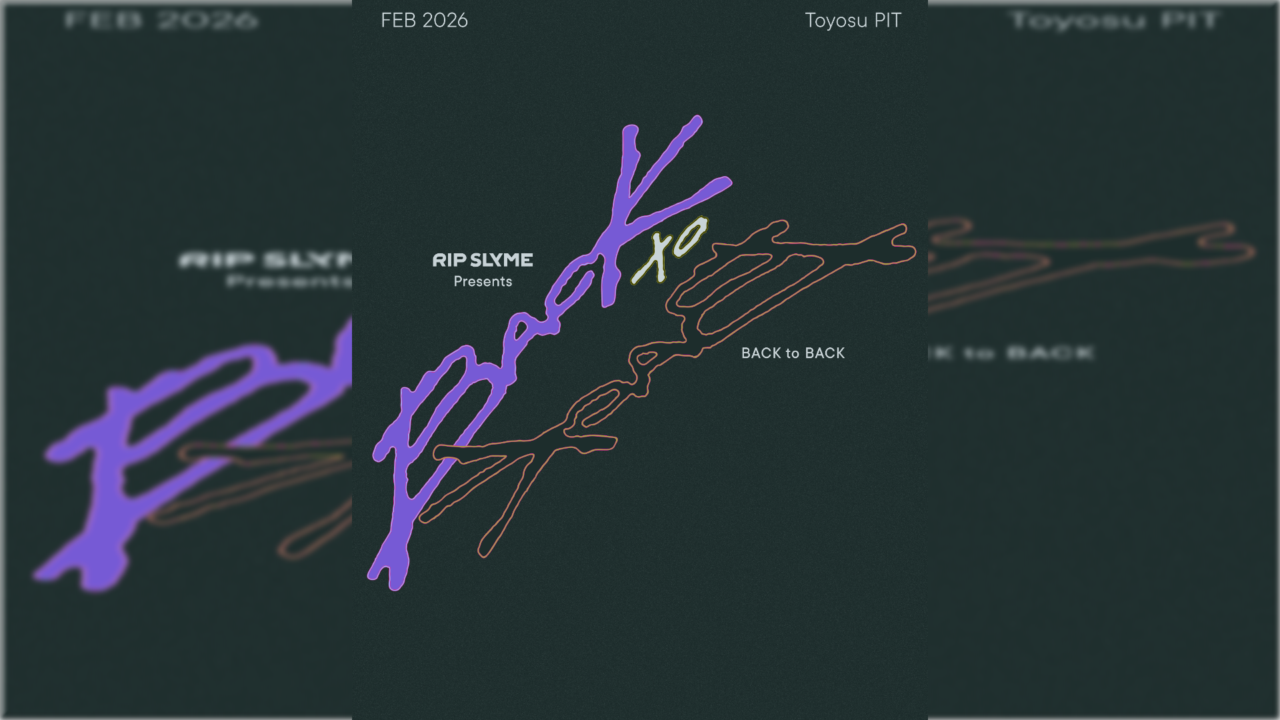砂原良徳、LEO今井、白根賢一、永井聖一によるTESTSETがネクストフェイズに突入した。10月20日(日)にZepp Shinjukuで行われたワンマンライブでは、テクノ、ニューウェイブ、ファンク、ロックがハイブリッドされた強靭でポップなサウンドと、クオリティーの高い映像が組み合わさり、「ユニット」ではなく、あくまで「バンド」として、熱量の高いステージを展開したのがとても印象的だった。
今回、TESTSETの現在地に迫るべく、LEO今井と永井聖一へのインタビューを実施。LEOは2006年に日本での活動を開始し、2008年に『Fix Neon』でメジャーデビュー。永井は同時期に相対性理論のギタリストとして活動を開始し、2007年に自主制作音源の『シフォン主義』を発表。同世代で、同時期に日本の音楽シーンで活動をはじめながら、それぞれの道を追求してきた二人がやがて同じバンドで活動するようになったのは偶然の巡り合わせか、それとも必然の帰結なのか。
なお、この二人の組み合わせでTESTSETの取材が行われるのは今回が初。最新作『EP2 TSTST』の話を聞くとともに、お互いのこれまでのキャリアも振り返ってもらった。
INDEX

KIMONOS、相対性理論など、両者の活動が合流するに至るTHE BEATNIKSという伏線
ー今年からライブでの立ち位置が変わって、以前はLEOさんと砂原さんがステージの中央にいましたが、現在はLEOさんと永井さんが中央にいますね。
LEO:そのアイデアを言い出したのは砂原さんです。最初は「なんで? いまさら?」と思ったんですけど、実際にやってみて、正面から四人が並んでいる絵を客観的に見ると、やっぱり歌も歌うし、動きも多い我々二人がセンターにいると、よりバンド感が増すんですよね。
永井:白根さん、まりんさん(砂原の愛称)のインタビューを読むと、「2人(LEOと永井)は正反対だから、そのコントラストが面白いと思って真ん中にした」という意図もあるらしいです。自分たちからすると全然わからないですけど(笑)。まあ、気持ち的にはこれまでと変わらないです。
LEO:永井くんはセンターに来てから演奏中にこれまでより激しく首を振ってる気がするんですよ。だから、いいことじゃないですか。
永井:オルタナティブで汗くさいバンドもすごく好きなので、そういう要素をTESTSETで出しても全然大丈夫かなと思ってます。

『FUJI ROCK FESTIVAL ‘21』にMETAFIVEの特別編成として出演した砂原良徳とLEO今井が、GREAT3の白根賢一(Dr)と相対性理論の永井聖一(Gr)を迎え、グループ名を新たにTESTSET(テストセット)と冠してライブ活動を開始。2023年7月、1stアルバム『1STST』をリリース。2024年10月9日に『EP2 TSTST』を配信した。
ー実際お二人は世代的にも近くて、キャリアの本格的なスタートも2000年代半ばの近しい時期だと思うんですけど、当時から交流があったのでしょうか?
LEO:ちゃんとした交流はまったくなかったけど、スタジオで会ったことはありました。そのときすごくニコニコしてて、いいやつだなあとはずっと思ってて。
永井:僕は(LEOの)ライブを観に行ったことがあるんだけど、そのときはちゃんと挨拶はできなくて。だからその十数年前にちょっと顔を合わせたときから、一気にTHE BEATNIKS(※1)とLEO IMAIバンドで共演したときに飛ぶんですよね。(高橋)幸宏さんを中心に、いろんなプロジェクトが動いていた貴重な時代に『フジオロックフェスティバル』(※2)っていうのがあって、そこで久しぶりにちゃんと会ったのかな。
LEO:その打ち上げでEntombed(スウェーデンのデスメタルバンド)の話とかで盛り上がって、「やっぱりいいやつだ、第一印象は間違ってなかった」と思いました。
※1:1981年に結成された高橋幸宏と鈴木慶一によるユニット。2018年発表のアルバム『EXITENTIALIST A XIE XIE』には、砂原良徳、小山田圭吾、LEO今井、ゴンドウトモヒコといったMETAFIVEの面々が多数参加。永井聖一は同作のリリース直後、2018年5月に開催されたライブ『THE BEATNIKS Live 2018 “ビートニクスがやってくる! シェ! シェ! シェ!”』にてライブメンバーとして初参加。同ライブには砂原、白根賢一も参加しており、2019年にライブアルバム『NIGHT OF THE BEAT GENERATION』としてリリースされた。
※2:赤塚不二夫の没後10周年に合わせ、2018年8月に開催された音楽と落語の融合イベント。永井は砂原、白根とともにTHE BEATNIKSのバンドメンバーとして出演、LEO今井も白根をドラマーとする自らのバンド「LEO IMAI」で出演した。

ー当時のお互いの活動に対する印象を教えてください。
永井:特にKIMONOS(※)の“Mogura”が大好きで、こういうユニークでかっこいいことができるのはLEOくんだけだなと思いながら聴いていました。
常に追いかけていたわけではないにしろ、METAFIVEも含め、活動の様子が普通に耳に入ってくるというか、自分が聴いていいなと思うことをやっている人だなっていう印象ですね。大きな括りでロックをやっている同世代の人でも、情報が右から左に抜けていく人はいっぱいいるわけで、でもLEOくんの場合はそうではなかった。
※:2010年に結成された向井秀徳(ZAZEN BOYS)とLEO今井によるプロジェクト
LEO:私は相対性理論の『シフォン主義』(2007年)をよく聴いていたんですよ。リリースされた当時からすげえなと思って、特にギターが印象的でした。アンディ・サマーズ(The Police)みたいだなって。で、実際にスタジオで会ったらめっちゃナイスガイで、すごく好きになりました。その十数年後に一緒にバンドをやっているのは奇跡というか、運命ですね(笑)。
永井:そういうことってあるよね。自分じゃコントロールできない運命は絶対に存在する。だってあの二人(砂原と白根)も同時期に活動しているけど、全然違うフィールドだったじゃないですか。だからTESTSETってすごく不思議な組み合わせというか、運命的な組み合わせというか、これまでのことを思うと、結構ドラマチックだとは思います。

INDEX
LEO今井、永井聖一の現在のキャリアがあるワケ
ー当時、音楽シーンのなかでどんなことを意識して活動されていましたか?
LEO:私の場合、そもそもシーンがなかったというか、「どこに属せばいいんだろう?」っていう葛藤がね、特に最初の頃はすごくありました。どこにも馴染めないし、どこにも居場所がない。でもやっていくうちにね、自然と同じフィールドの人たちと出会いますよね。
ーそれがKIMONOSであり、METAFIVEだった。
LEO:そういうことですね。

永井:ちゃんとその人なりのユニークさを持っている人は、キャリアを重ねるとともに必要とされるようになっていくというか、そこに関しては僕も一緒だとは思います。そうすると自然と自分の周りにつながりが形成されていくんですよね。
相対性理論も相当孤高の存在というか、「どのバンドと仲がいい」みたいなことはほとんど語られたことがないような気がする。もしかしたら誰かが書いているのかもしれないけど、本人たちはまったく意識したこともないし、未だに「このバンドには親近感があるから一緒にツアーをした」みたいなことはないですね。
永井:そういう意味で孤独ではあったんですけど、でもやっぱりいろんなバンドをサポートしたりして徐々に変わっていった。それこそTHE BEATNIKSをやったり、いまではGREAT3でもギターを弾いているし、何よりこのバンドに呼ばれたわけですからね。
ー永井さん個人のキャリアで言うと、相対性理論が軸にあった頃から徐々に個人としてのプロデュースやサポートが増えていったわけじゃないですか。もともとそういう道に進みたかったのか、結果的にそうなっていったのか、どちらの側面が強いですか。
永井:これはあくまで僕の主観なんですけど、アルバムを重ねるごとに制作の重みが出てくるというか、納得のいくまで推敲を重ねるようになると、1枚ごとのインターバルも長くなるわけです。そうなってくると、「空いてる時間にプロデュースもサポートもできるな」と思うようになって、「私、空いてます」みたいなサインを出すようにはなりました(笑)。
THE BEATNIKSに関しては(鈴木)慶一さんに「ギター、いつでも呼んでください」みたいなことを言ったら、その2日後ぐらいに「THE BEATNIKSでどうですか?」って連絡が来て、「慶一さんのソロじゃないんだ」みたいな(笑)。
まあ、いろいろやったほうが面白いじゃないですか。いろんな経験をしないと人生すぐに終わっちゃうなっていうのは、歳を重ねるごとに思っていることでもあるので、活動するフィールドを広げられたのはすごくよかったと思います。

ー2000年代は「所属」の概念が強くて、それぞれで動いていた人たちが、2010年代に入るとSNSの普及もあって、いろんな点がつながりはじめた。2000年代には挨拶を交わすぐらいだったお二人が一緒にバンドをやっているというのは、偶然でもあり必然でもあるように感じます。
永井:「いまの人たち」っていう、おじさんみたいな言い方にどうしてもなっちゃうんですけど(笑)、みんなすごい数のサポートをやってますもんね。
自分のバンドがアイデンティティーとしてあった上で、「あれもこれも君なんだ?」みたいな、(大井)一彌くんも(西田)修大くんもそうだけど、「君たちはいつ自分のバンドの制作してるの?」っていうくらいバイタリティに溢れている。いまはそれが日本のミュージシャンのスタンダードなのかもしれないし、刺激をもらっていますね。
ーLEOさんは時代の変化をどう感じていますか?
LEO:昔みたいにひとつのバンドで、アルバム、ヒットシングルを出して4年間ツアーを回るみたいなケースはますますレアになってきていますよね。ミュージシャンはいろんなことをやらないと成り立たない。そこは単純にマーケットが縮小しているということだと思うんですけど。

永井:それもその通りだし、だからこうやって一緒にバンドをやっているのはすごくいろんな要因があるわけで。TESTSETもなかなか数奇な運命だなとも思いますけど。
ーいまもそれぞれいろいろな活動をされていますけど、TESTSETの活動はお二人にとっての軸のひとつになっている?
永井:いやもう、軸オブ軸ですね。
LEO:そうですね。いまはTESTSETは軸のひとつです。
永井:変な言い方ですけど、通好みの音楽に見られるのはまた違うというか、TESTSETは質の高い音楽を目指して集まった集団であると自負しているし、いろんな人に聴いてもらわないと意味がないと思います。だからライブもいろんな場所でやりたくて、国内はもちろん、海外への展開もできる限りしていきたい。来年も中国に行きたいし、他のアジアの国にもチャレンジはしていきたいですね。
INDEX
個人的な内省が、世界の終わりとつながる——TESTSETに合流した永井聖一のカラー
ー新作の前に1stアルバムのことを改めてお聞きしたいんですが、あの作品には、現実と非現実の境界が曖昧になることで混迷の度合いを深める現代社会へ目線が含まれていますよね。<Feel like dystopia No more escape>と歌われる永井さん作詞の“Stranger”からもそんなムードを感じたのですが、あの曲の歌詞はどのようなモチーフから書かれたものだったのでしょうか?
永井:僕は渋谷に実家があったんですけど、あの曲の歌詞は実家に帰れなくなってしまった自分の実体験がもとになっています。駅が変わりすぎて、いつもの西口に出られない。スルッと帰れていたのにいきなり帰れなくなったんです。
いまは半蔵門線から地上に出るエスカレーターもいつも長蛇の列だし、新しくしたはずなのに、なんでこんな不便になったんだろうっていう。渋谷の街並みを支配している空気も、人の種類も、全部僕が知っているものとは違うものになっていて、そういう意味での「Stranger」です。とてもディストピアを感じてはいます。
ーもちろんコロナ禍もあったし、やはり1stアルバムには「これからこの社会はどこに行ってしまうのだろう?」というムードがあったように思います。
永井:LEOくんもそういうメタファーが得意というか、それはソロのときからそうだと思うんです。ストレートにパンキッシュなわけでもなく、褒めているように見せてめちゃめちゃディスってたり、皮肉が効いてるというかね。TESTSETは四人ともそういう人だと思います。特にまりんさんに一番毒があるかもしれない(笑)。
ー“Stranger”にしても、もともとの着想は個人的な体験ではあるけれど、結果的に社会のムードや時代性を表しているなと。
永井:僕自身、パーソナルで、ナイーブなことをわりと歌詞にするかもしれない。自分の個人的な内省や小さな悩みを、世界の終わりや全人類的な危機とつなげて捉える、みたいなコンセプトがすごく好きなんですよね。
今回の“Yume No Ato”も内容的にはとてもパーソナルな曲だけど、ここ数年で何かを失った人はたくさんいると思うので、そういう人たちの思いと重なる部分もあるかなと思います。“Stranger”もそうで、別に渋谷に住んでなくても、都市に住んでなくても、右も左もわからないような状況はいろんな人にあると思うし。

―『EP2 TSTST』に収録された4曲はどのように選ばれたのでしょうか?
LEO:2ndアルバムに向けての初期段階のセッションというか。完全に新しく作ったものもあれば、1stアルバムの前からあった未完成のデモを形にしたものもあります。
音楽のスタイル的には4曲ともかなりバラけてるんですけど、でもどれもTESTSETの、この四人の魂がこもっている感じがする。それはこの1年、コンスタントにライブをやってきたことがいい形で反映されているんじゃないかなと。あとはEPだからこそ、ちょっと実験をしたり、別の側面を見せる狙いもあったと思います。
INDEX
皮肉とメタファーの裏で、TESTSETの音と言葉が打ち出すイメージ
―音楽的な変化ももちろん感じつつ、EPは都市、アルバムは自然というアートワークの対比が面白いなと思いました。
LEO:今回この写真にした一番の理由は、“Sing City”で描写されている風景だからなんです。東京の近郊外。

LEO:歌詞は、まず日本語で書いてみようと思って自然と出てきた感じなんですけど、特に社会に対してどうというのはなくて、私の心境、自分の日常のスクショみたいな感じです。そういうセンチメンタルな歌だから、それに合う写真を探して。何でもない日常というか、そこがいいなと。
ー“Sing City”は当初「TESTSETには合わないかも」と思いつつ制作を進めたそうですね。
LEO:そうですね。でもTESTSETの新たな側面が出せるかもしれないと思ってやってみたら、いい感じになりました。トム・ペティとDepeche Modeが合わさった感じ(笑)。
永井:1990年代のU2の感じもあるよね。“Sing City”はLEOくんのシグネチャをすごく感じるんだけど、制作が進んでいろんな要素が肉付けされていくうち、だんだんバンドとしての命を持っていった。今回のEPは全曲がそうで、メンバーそれぞれがもともと持っているものがより強く出ているんだけど、でもバラバラな印象を感じさせないものになっていると思います。
ー永井さんが詞曲とボーカルを担当した“Yume No Ato”はもともとどのようなイメージだったのでしょうか?
LEO:Cocteau TwinsとThe Cureみたいな感じですよね(笑)。あと全然違うんだけど、これを聴くとなぜかR.E.M.の曲が思い浮かぶんですよ。すごいポップで軽やかで楽しげなんだけど、中身は絶望的に悲しい、みたいな。R.E.M.はそういう曲が結構あるじゃないですか。
永井:“Shiny Happy People”とかね。
ー曲調的には1980年代のネオアコ感がある頃のR.E.M.ですね。
LEO:それも含めそうですね。私、たぶんTESTSETの曲のなかで一番よく聴いてます。
永井:そうなんだ。僕はギタリストなので、僕の曲はギターで作ったのが見えやすいものが多くて、ネオアコ感とか、The Cureっぽさとかもコードワークによるところが大きいと思います。その上でメンバーそれぞれのカラーが混ざって、TESTSETらしい感じになっているなと。
ー歌詞は強い喪失感が感じられますが、どんなモチーフがあるのでしょうか?
永井:特定はあえて避けますけど、いろんな喪失がありましたよね。結果的にはTESTSETという大切な財産を得ることができて、それが何よりの救いなんですけど、トータルではここ数年は失ったもののほうが大きい。僕はすごくペシミストなんですよ。喋っているときは逆に気持ちをブーストしているけど、普段は暗いことしか考えてないから。
LEO:そうなんだ? ピエロなの?
永井:ピエロとはまた違うな(笑)。だからといって死にたいとはまったく思わないんですけど、心の底から楽しい瞬間はすごく限られる。やっぱり基本的に暗くて重い空気感ですよ、ここ数年は。世の中を代表してそんなことを言う筋合いはないけど、それが歌で表現できるのであれば隠さないでもいいかなとは思う。
ただあまりにストレートな表現は好きではなくて、さっきのR.E.M.の話みたいに、めちゃめちゃテンションが高いけど暗いことを歌ってるようなバンドが昔から好きだったから、自分もそうありたいって無意識で思っているんじゃないかな。