空音央監督の長編デビュー作品『HAPPYEND』は、混迷を極める2020年代が求めた傑作であり、日本映画の未来の希望だと思う。1990年代のアジア映画のような映像的美質をもって現代の日本社会を鋭く批評し、世界の観客に対しても開かれた問いも投げかけてみせている。
このタフな作品の出発地点にあるのは、友情という普遍的なテーマ。ゆえに本作は、政治的でありながら、「思想」によって観客を選ぶことをしないという二重の要求をクリアしている。そんな本作の奥にあるものに触れるべく、監督の友人でもある井戸沼紀美に取材をオファーした。「社会的な正しさ」に先立つ、愛情や友情、喜怒哀楽について、作品の描き出すものとともに話を聞いた。
INDEX

米国生まれ、日米育ち。ニューヨークと東京をベースに映像作家、アーティスト、そして翻訳家として活動している。2024年公開の坂本龍一のコンサートドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』では、ピアノ演奏のみのシンプルかつストイックな演出ながら『ヴェネツィア国際映画祭』でのワールドプレミア以降、山形、釜山、ニューヨーク、 ロンドン、東京と世界中の映画祭で上映、絶賛された。2024年10月、長編劇映画デビュー作となる『HAPPYEND』が公開。
映画的な喜びとともに表現された「怒る」ということ
―映画の冒頭で「古い枠に人を収めようとする勢力がうるさい」という文字が映し出されて、その直後に赤い光が映し出されたとき、この映画は「怒り」を大事にしているのかなという予感がしました。作品を観進めていく中で、その予感が確信に変わっていく部分があったのですが、今作を作るうえで怒りを意識した部分はありましたか?
空:ありました。怒りって大事だと思う。怒ることができるのって、その対象に対してまだ希望を感じているからこそじゃない? 諦めていることとか、何も気にしていない相手だったら、そもそも怒ろうともしないだろうし。
怒りは個人間においても、社会的なスケールにおいても、めちゃくちゃ大事な愛情表現だと思う。だからそれを鎮静化するのはよくないんじゃないかって思うことがあります。
―怒りの感情を人に伝えるとき、一つひとつの言葉を発するのにも苦労するけど、伝えるほうがいい結果につながる場合もありますよね。一方で、普段の生活の中では「イラつき」まではいっても「怒り」まではいけない自分もいて。だから監督が日常のレベルで、どう怒りと向き合っているのかが気になりました。
空:僕は沸々と怒るタイプで。あまり爆発しないし、自分の感情を自分で理解するのに割と時間がかかるから、感情の瞬発力がない。だから悶々と考えて、沸々と怒りを込めて、文章にしたり、作品にしたりするわけです。

―数秒でドカンと怒れる人もいるし、数日、数週間、数年かけて怒る人もいるだろうし、本当に人それぞれですよね。『HAPPYEND』はそのグラデーションごと、大事にしているような印象も受けました。たとえばコウとユウタが言い合いになるシーンがあるけれど、そのある意味ドラマチックな場面の直後に、二人で協力してものを運んでいる素朴な場面が映し出されます。
空:あのシーンでは、恋人同士の喧嘩ってどういう感じだったっけ、ということを考えていました。経験がある人も多いんじゃないかと思うのですが、喧嘩していると、時間が急に飛ぶような感覚がある気がしていて。叫び合った次の瞬間、微妙に関係が修復されている、みたいな。「いつの間にこんなに叫び合っていたんだろう」「経過はどこにいったんだっけ」って。その主観的な体験を映画でも試してみたいから、シーンをポンと飛ばしてみたんです。
―面白いですね。そういう不思議な撮影や編集もたくさんあったし、遊び心を全編に感じました。楽しんで撮っているんだろうな、って。
空:それは意識していました。撮影中、自分に課した課題があって。一つひとつのシーンに、達成しなきゃいけないプロットポイントがあり、語るべきことがあると思うんだけど、そこへさらにもう一つ、何かしら映画的な喜びを感じさせる要素を入れたい、と考えていたんです。
言葉にすると曖昧なんだけど、それは単純に視覚的なギャグみたいなことでもあるし、音のこだわりでも、ショットの美しさへのこだわりでも、編集の遊びでもある。全シーンに映画的な喜びが感じられるものを入れよう、っていうチャレンジをしていました。
INDEX
感情を動かす練習、くだらないことに反抗する練習
―その「喜び」の感情と、最初に話した「怒り」の感情は、もしかしたら結びつくのかもしれないなとも思いました。というのも、私は音央に対して、何かを楽しんだり、面白がったりする力がすごく強い人だなという印象を抱いていて。それはもしかすると、普段から喜怒哀楽のいろいろな部分をちゃんと動かしているから、感情の筋肉がほぐれているということなのかもしれないなと。
空:そう言われて思い出したんだけど、自分にはどんな体験も経験できてよかったと思おうとする傾向があるんです。ちょっと、職業病みたいなところもあるかもしれないんだけど。たとえば、すごく嫌な感情とか嫌な出来事でも「それって、これまで感じたことがなかったじゃん」と考えている自分がいる。
自分は最近、父親が死んで。すごく悲しいし、死に際に立ち会うというのはショッキングな経験だったんだけど、人生で一度きりの体験なわけで。変な話かもしれないけど、それは経験できてよかったな、と思う自分がいることに気がついた。自分の感情が、今まで感じたことのない状態に動かされたことが、すごくありがたいなと思う部分もありました。

―「この感情を経験できてよかった」と考えるようになったのはいつ頃から?
空:中学か、高校のときかな。その頃、意図的に「痛い」と感じる映像を見ていたような時期があったんだよね。
―それはどうして?
空:知りたいから。
―痛い感情を?
空:そう。
―たとえばどんな……?
空:うーん、その頃、ちょうどYouTubeが出てきて、コンテンツの制限もあまりなく、手術の動画や戦場のリアルな映像とかを見ていました。……楽しんで見ているわけではなくて、本当はみたくないと思いながら、こういうことも世界にはあるんだから見る責任があるんだ! と自分に言い聞かせてみる、みたいな感じです。こんなこと言ったら、すっごいヤバい人みたいですけど(笑)。
―(笑)。
空:でもそのように、日常生活では経験できないことをメディアを通してやけに摂取しようとしていた時期がありました。世界ではいろいろな出来事が起こっているけど、それを自分は全ては経験できないし、ものによっては経験しにいく勇気もない。けど、できるだけいろいろな感情を知りたくて。

空:それは映画をよく観にいくようになった大きな理由の一つでもある。もちろん嫌なことだけじゃなく、ロマンティックな映画を観たら、自分が感じたことのないような、素晴らしい愛の感情を知れたりもするし。人がそれを観てどう感じたかを聞くのもすごく好きで。いろいろな感情を自分の中で蓄積させていきたいな、という気持ちが学生時代に芽生えたんです。
―感情を動かす練習みたいなことですよね。音央が『HAPPYEND』のプレス用資料で「筋肉をつけていかないと、本当に大きいルールや法律を破らないといけない状況に陥った時行動できなくなる」と書かれていたことも思い出しました。
空:日常の小さなレベルから無意味だったり、害があると思ったことに反抗して壊していくことを「アナキズム準備運動(anarchist calisthenics)」と言ったりもするんだけど。くだらないものに遭遇したらしょうがないと思うのではなく、それを変えるために直接的な行動に移せることは、本当に大事だと思ってる。映画の中では、ユウタがそれを無意識に、自然体のままでやっているキャラクターなんだけど、より自覚的にできればなおいいのかな、って思うんです。

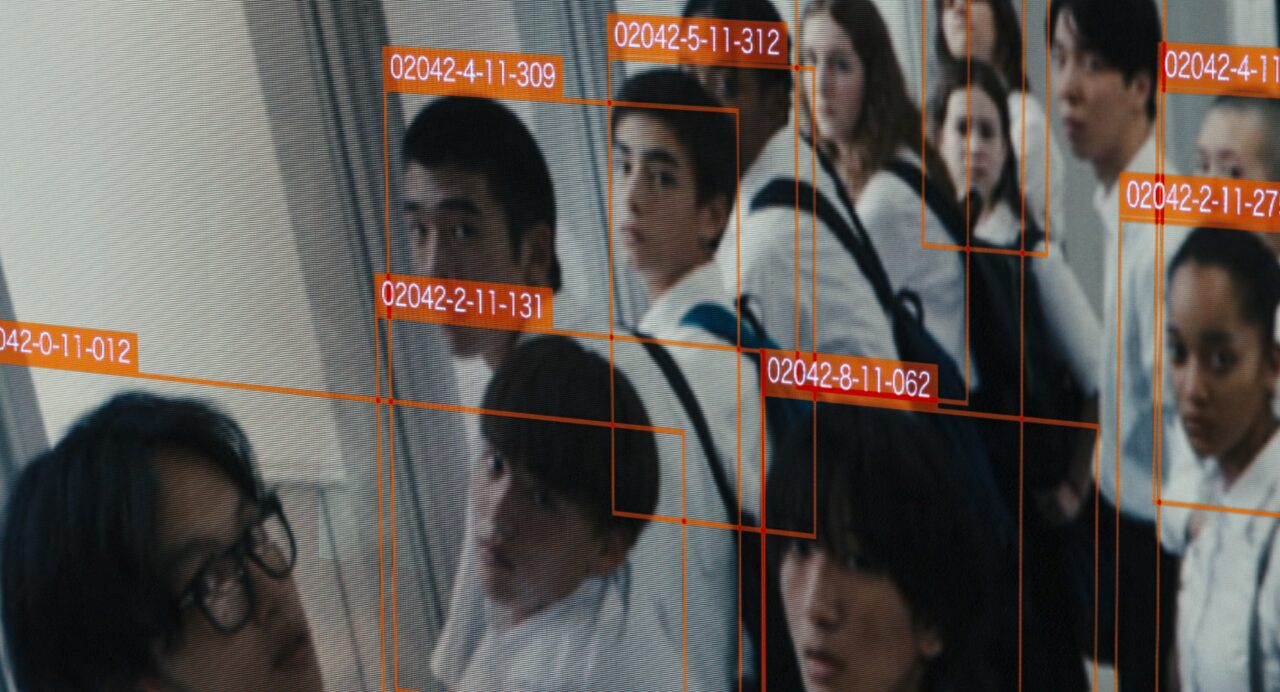
空:自覚的にならないと、表面的に見えにくい構造的な暴力にはちゃんと抗えない。同時に、自覚しているだけでなく、積極的に反抗して壊していくというのも大事だと思ってる。そうじゃないと、徴兵制とか、人を戦争や虐殺へ向かわせるような法律やシステムが科されたときに、太刀打ちできなくなってしまう。
システムではなく「自分に従う思考能力」みたいなものを今後さらに培っていかないと、日本は戦争に加担してしまうと思うし、巻き込まれるとも思う。すでに日本社会に存在する暴力的な構造にも気付けない。たとえば、日本で年金を払っている人は知らず知らずのうちにそのお金がイスラエルの国債や軍需企業に投資されているんです。確実にそういう世界的な局面にいるんじゃないかな。



























