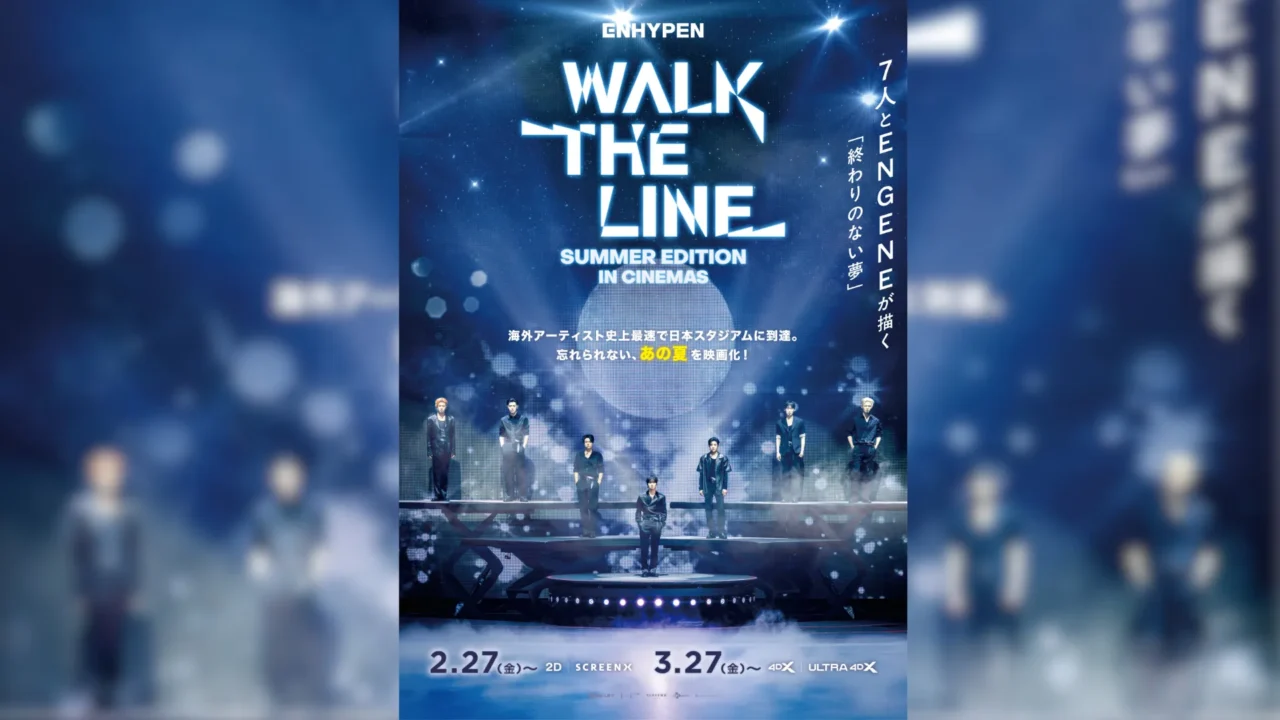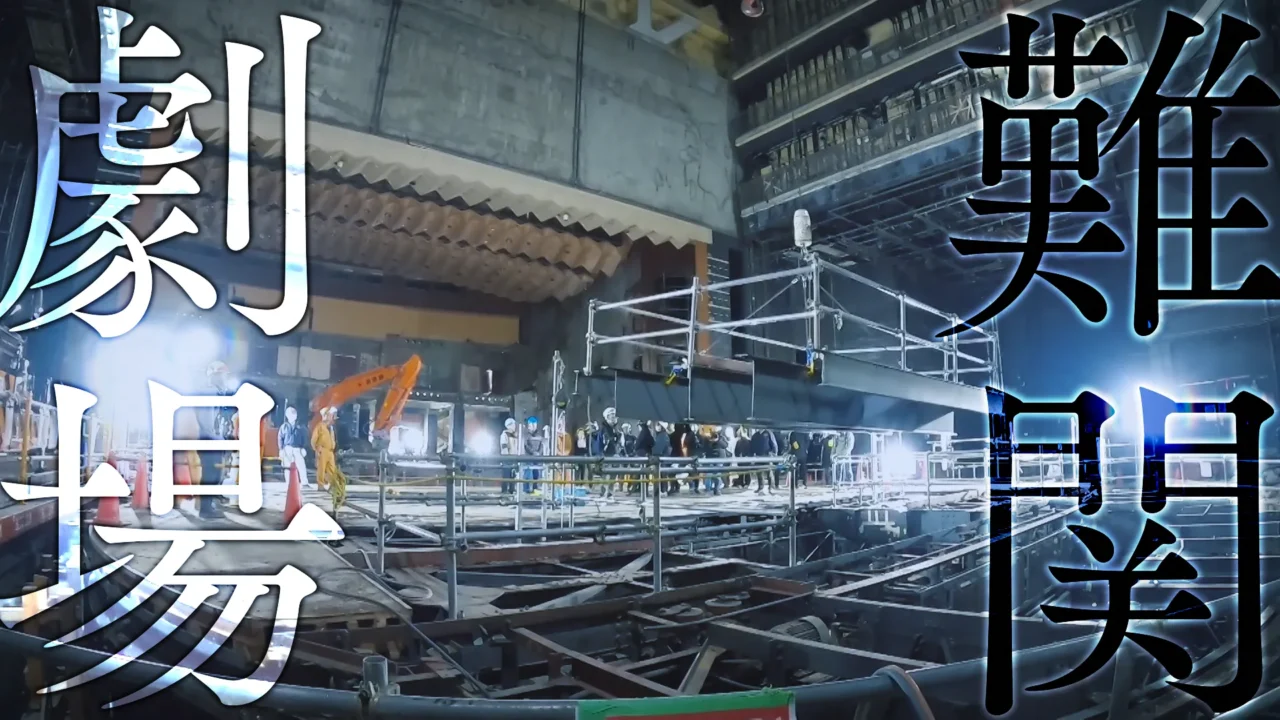INDEX
怒りから始まり、愛を歌うようになった
―これまで発表されている楽曲を時系列で聴いた時、どんどんと生まれるものが変化している印象もあったんですけど、作詞作曲をされているこーしくんは、そういった実感がありますか?
こーしくん:あります。そもそも僕らはパンクバンドとして始まったんです。パンクとは怒っているものであり、僕はずっと怒っていたんですよね。でも、その怒りの上で何かを提示しなければいけないと思った。それで作ったのが“僕らのラプソディー”という曲なんです。この曲もまだ怒ってはいるんですけど、それでも「何かメッセージを言わなきゃ」と考えた時に、愛について書きたくなった。
―最初の頃の怒りというのは、何に対しての怒りだったと思いますか?
こーしくん:僕はワガママなので、自分の中にある「こうしたい」という思いがあって、でも現実はそうではなくて「ちくしょう」と思う……そういうことを日々、蓄えていて生きていた感じなんですね。それは「こういうギターが弾きたい」と思って、でもそれが弾けないことに対してもそうだし、仕事で「なんでおまえはこれができないんだ?」という怒りがあれば、その怒りは自分に向く時もあるし。

―聴き手としては、自分自身の無力感からくる怒りとか、どうしようもない現実に対しての怒りでもあるのかなと、初期の曲を聴いていると感じました。
こーしくん:そう思います。
―“僕らのラプソディー”の頃に変化が起こったのは、僕も曲を聴いて感じたことでした。この時期から、描かれるものの前提に戦争などの社会的なことが入り込んできている気がしたし、“僕らのラプソディー”も収録されているアルバム『少年キッズボウイ 1』は、ある意味では反戦歌が集まった作品でもあると感じたんです。この時期の変化がどのように生まれたのか、具体的に知りたいです。
こーしくん:「社会と繋がってなきゃいけない」と思ったのは大きいと思います。少年キッズボウイは「楽しければいいよね」で始まったバンドだし、ずっと大学のサークルのノリでやってきたけど、バンドは他者に見てもらうものでもあるわけだし、「内輪ノリじゃダメだよね」と思った。それで久しぶりに外を見てみたら、世界は荒れに荒れていて。ここは俺が一筆したためねば、という感じでした。少年キッズボウイは、「自分が楽しいことやりたい」と言って始まったバンドだけど、この時期、「みんな楽しかったらいいじゃん」という形にちょっと広がったんだと思います。ライブも「お客さんもみんなメンバーだよ」という気持ちでやるようになったし。
山岸:“僕らのラプソディー”の時期はバンド全体が明確に変わったんですよね。それまでは自分たちだけで活動していたけど、“僕らのラプソディー”から今も一緒にやっているスタッフと一緒に活動するようになって。あとこの曲を出す前に1度解散の話が出たことがあったんです。「今ある曲でアルバムを作って、解散しようか」って。でも、そのタイミングで後にスタッフになる方に声を掛けていただいて。明確にバンドが切り替わった時期だったんですよね。
アキラ:生まれ変わった時期だったね。
こーしくん:“僕らの”ラプソディーのあとに“君が生きる理由”という曲ができたんですけど、この曲では「世界はこんなに素敵なんだから、君も生きてみようぜ」というメッセージを書くことができたと思っていて。
―“君が生きる理由”は、より訴えかける力が強い曲だなと感じます。
こーしくん:この曲は「みんなも楽しまなきゃ!」という気持ちですね。「死ぬなんて言うなよ」っていう、その一心です。あとその時期、自分がずっと好きだったバンドのメンバーの方が「俺たちの世界は変わらない」と言っていたのを聞いて、すげえ寂しかったんです。その言葉を聞いた日、自分が乗っていた京王井の頭線で人身事故があって、2時間くらい何もできずに座っていた時間があって。その時に、携帯のメモ欄に書いた歌詞が“君が生きる理由”の歌詞でした。
―こーしくんは、自分を寂しくさせるものに対して常に抗っている感じがしますね。
こーしくん:『花束みたいな恋をした』をハッピーエンドにするためにやっていますから。最高のハッピーエンドを目指します。
―最高だと思います。