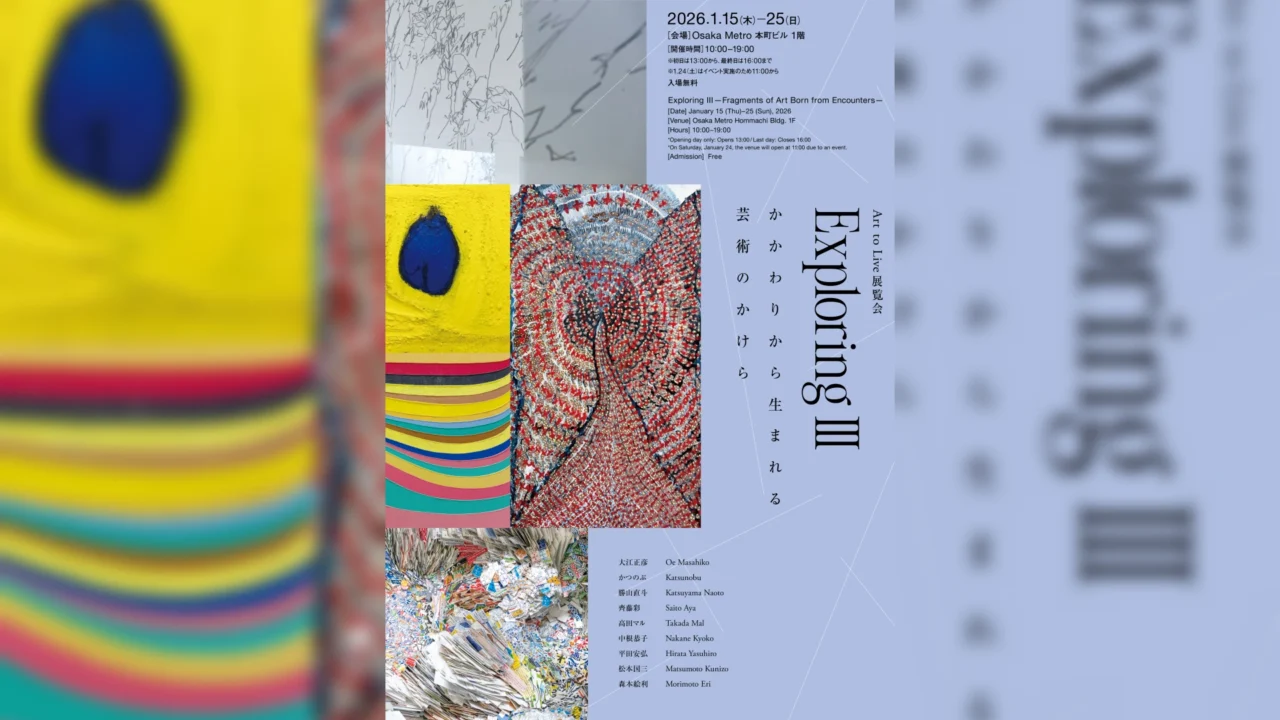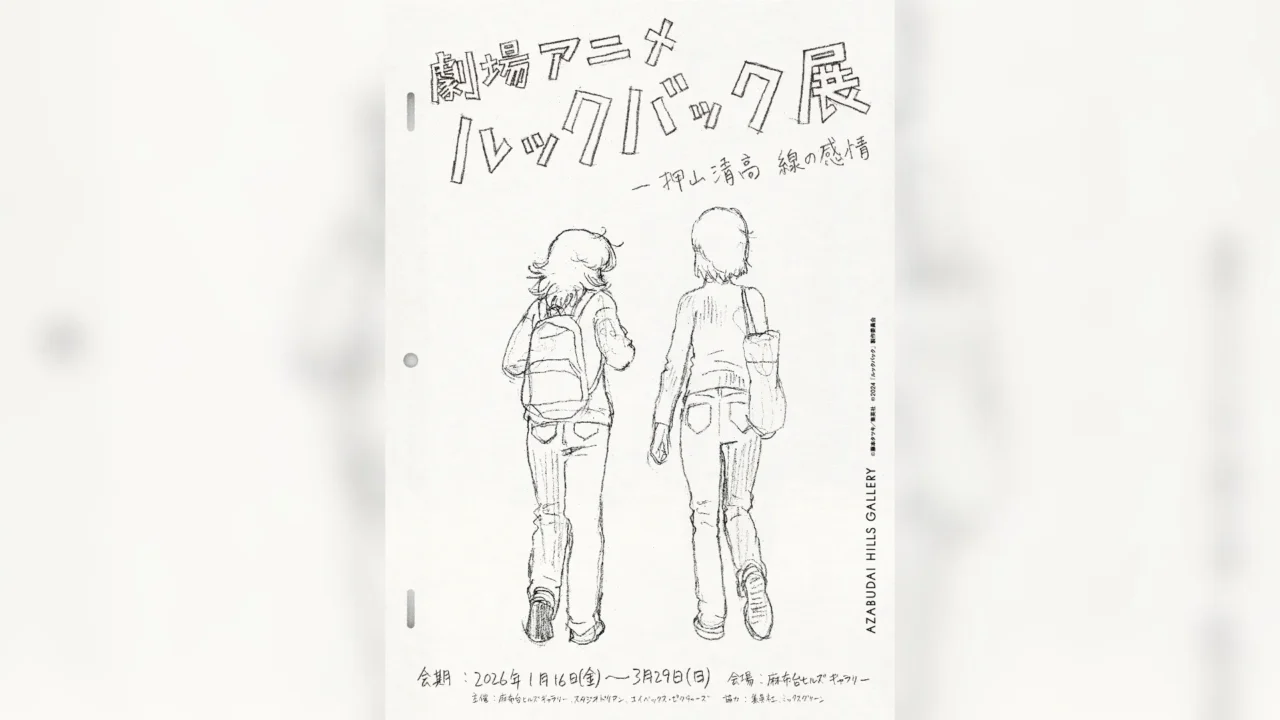テレビで、「フォロワー約84万人、インスタのカバー動画で有名な人」という紹介のされ方をしていた三味線奏者・駒田早代の存在を知った時、「やっぱり伝統芸能も今はショート動画なんだな」という月並みな感想を素直に抱いた。「はやりには逆らえない」という聞き馴染みある教訓の事例が更新されたと思った矢先、彼女は動画を更新する理由を語り始めた。三味線という伝統芸能を後世に受け継ぐための一つの手段であるという。伝統芸能というフィールドから急速に市民権を得たフォーマットに歩み寄った彼女の動機が、自身の承認欲などではなく、もっと大きいものであると知り、問い合わせフォームから取材の申請をするまでそう時間はかからなかった。
「三味線がメインストリームではないという自覚はある」と冷静に語る駒田は、楽器への熱意と、次世代へと繋げていくための信念を熱心に語ってくれた。マネージャーを務める母を交えながら、三味線との出会いや楽器の種類さえ知らずにがむしゃらに練習した子ども時代、そしてしきたりに捉われずに自分が信じる方法で伝統を守っていく決意を伺った。
INDEX
志村けんの弾く三味線の音に憧れた幼少時代。楽器の種類なんて知らないまま没頭した練習
ー志村けんさんがきっかけで三味線を始められたと伺いましたが、志村さんのどういったところに惹かれたのでしょうか?
駒田:志村さんは三味線と出会わせてくれたきっかけの人で、最初に惹かれたのは志村さんが弾く三味線の奏でる音でした。子どもながらに、弦が3つしかない楽器を1人で弾いてるとは思えなかったんです。最初に音源で”南部荷方節”という民謡を聴いたとき、てっきり合奏だと思って。「どうすればこんな音が出せるのか」という楽器への興味と、「自分も弾けるようになりたい」というのがきっかけだったと思います。

津軽三味線と長唄三味線の二刀流奏者として活動。7歳から津軽三味線、10歳から民謡を始め、15歳の時に第9回津軽三味線日本一決定戦で優勝。2022年東京藝術大学音楽学部邦楽科を卒業 。2023年四代目杵屋五三郎お家元より「杵屋五司駒(きねやごしこま)」の名を許される。Instagramに投稿している洋楽のギターリフカバー動画が話題で注目を集め、伝統音楽とポップカルチャーを融合させた独自の音楽性を展開。2024年には、1stアルバム『月前恋歌』を発表したほか、11月にはペルーで開催された日本人ペルー移住125周年記念コンサートに出演するなど、多くの反響を呼んでいる。
ーそもそも、なぜ三味線だったのですか?
駒田:志村さんの三味線を見た母が勧めてくれたんです。
駒田(母):以前、テレビ番組の『新春かくし芸大会』でドリフターズさんが黒紋付きを着て三味線を弾いているのをたまたま見たことがあったんです。当時は三味線に津軽や長唄などの流派があることも知らず、ただただ圧倒されました。
私もやってみたかったんですが、インターネットもない当時は、簡単に情報にアクセスできるわけでもなく諦めざるを得なくて。そしたらある時、娘が習い事をしたいと言い出したので、「三味線はどう?」って。
ーなるほど。元々はお母さまがやりたいことだったんですね。
駒田:そうみたいです(笑)。ゆくゆくは、習い事として一緒にできたらという気持ちもあったらしいのですが、私の方が忙しくなってしまって……。母にはマネージャーとして支えてもらっています(笑)。
ー先ほどお話されていたように、三味線にもいろいろ流派があると思いますが、津軽三味線を選んだのには理由があるのでしょうか?
駒田:正直に言うと、三味線って一種類しかないと思ってたんです。たまたま近所にあった教室が津軽三味線で、種類があるなんて気づかないまま、ひたすら技術だけ磨いてました。三味線にいろんな流派やタイプがあるって知ったのは、高校生になってからでした。志望校の東京藝術大学には長唄三味線の専攻しかなかったんです。
ーということは、そこから長唄三味線を練習されたんですか?
駒田:はい(笑)。
ーそれでも、東京藝術大学には現役で合格されたんですよね?
駒田:そうなんです。「私はこれから新しい楽器を習うんだ」っていう気持ちで割り切って習ってました。

ーすごい……。実際に、津軽三味線と長唄三味線はどれくらい違うものなんですか?
駒田:全くの別物ですね。演奏スタイルも全然違うし、使ってる道具も違うんです。津軽はべっこうのバチを使ってるけど、長唄は象牙だったりして。三味線の形からして違うし、譜面もまったく別なんですよ。
ー普段あまり縁がないので、三味線の難しさに想像が及ばないのですが、ギターで言うところのFコードのように、初心者がつまずきやすい三味線の奏法はありますか?
駒田:基本のテクニックとして、1弦だけを鳴らす弾き方があるのですが、始めたての方の多くが苦戦していますね。弦に当てられずに、すかしてしまったり、他の弦も弾いてしまったりしてしまうんです。ギターのようにどうしても左手の運指が大事なように思えるけど、その前に右手の使い方がとても大事なんです。
ー1つの弦だけを狙って弾くのが難しいっていうことなんですね。
駒田:そうなんです。それができるようになったら次は「前バチ」「後ろバチ」という動きがあります。左手に近い方の三味線のボディを叩くことが「前バチ」、反対側を叩いて太く大きい音を出すためのものが「後ろバチ」です。グルーヴを出すための奏法で、民謡の手拍子にあたるリズムを生み出す役割があります。

ーなんで「前バチ」「後ろバチ」が難しいんですか?
駒田:単調に前後に叩いていればいい訳ではなく、「前に行くとき」と「行かないとき」があるのですが、感覚で覚えるものなんです。規則性がない。ギターとかトランペットとかの楽器経験者であればあるほど、その感覚を掴むのが難しいみたいで。説明することもできますが、例外も多いので、本当に慣れるしかないですね。
INDEX
三味線への情熱とマイナーな習い事へのコンプレックスを抱えた学生時代
ー駒田さんの経歴にお話を戻すと、高校2年生で津軽三味線日本一決定戦のA級女性の部に輝き、東京藝術大学にも一発合格されています。最初は三味線への憧れや熱意から始まった趣味という側面もあったようですが、これまでに挫折しそうになったことや、表現に行き詰まった経験はありますか?
駒田:私の地元の三重県は周りに三味線をやっている人があんまりいなくて、同年代の仲間もなかなかできなかったんです。全国大会ではみんな三味線を弾いてるけど、友達って感じじゃなくて。むしろライバルみたいで楽屋の雰囲気も常にピリピリしてました。だから三味線仲間っていう存在がいなくて、年に一度の大会に向けてモチベーションを保つのが結構大変だった。いつも悔しさが原動力だったように思います。
それでも、救いになったのは7歳の頃から始めた演奏活動。近所の高齢者施設で演奏して、「上手だね」「いいね」って言われるのがすごく嬉しかったんです。「次呼ばれたら新しい曲も演奏できるようになりたい」って思えたことがやる気につながってましたね。
ー三味線との関係は、孤独なものだったんですね。でも、子どもの頃って、友達と好きなものを共有したい年頃だと思うんです。はやりのキャラクターがあしらわれた文房具とか。でも、駒田さんのやられていたことは周りと分かち合えるものではなかった。もどかしい気持ちにならなかったんですか?
駒田:そうですね。大人になった今でこそ、「自分にしかできない」という使命感や誇りを持てるようになりましたが、子どもの頃は、やっぱり周りと違うことをしているのに気遅れて恥ずかしく感じる時期もありました。みんながピアノやバイオリンなどの西洋音楽をやっている中で、自分は昔からある古い楽器をやっていることにコンプレックスを持っていたんです。スポーツをしている方がかっこいいと思ったり、周囲の共感を得られなかったり、好きなことを友達と共有することは諦めていました。

ー相反する感情のように聞こえますが、コンプレックスと「三味線が好き」っていう気持ちは自分の中で共存する感情だったんですか?
駒田:共存してましたね。周りと共有できないと感じたときに、「じゃあもう無理に分かってもらおうとしなくていいや」と思って、自然と割り切るようになったんです。別に隠していたわけじゃないけど、学校で三味線のことを自分から話すこともなかったです。
学校の全校集会で入賞した人がステージで表彰される謎の時間があったじゃないですか? あれがすごく苦手で。部活だったら大体表彰されるけど、私の三味線はそうではないので、自己申告もせず黙ってました。自分で言わない限り学校も何もしてこないし、それがちょうどよかったんです。だから、三味線に関しては完全にプライベートなものとして割り切って、学校生活とは分けて考えていました。
ーそんなプライベートなものとして割り切っていた三味線を「仕事」として意識するようになったのはいつからなんですか?
駒田:もちろん三味線はずっと好きで続けていたけど、もともとは看護師や管理栄養士を目指していて、進路としては現実的な職業を考えていたんです。高校2年生になって進路を本格的に決めるタイミングで、看護学部や栄養学部を中心に志望校を選んで、進路希望調査を提出したんですが、三者面談のときに先生から、「あなたは(三味線で)日本一を取っているのに、それで本当にいいの?」って言われて。「本当にやりたいことを4年間学ぶ場所が大学なんだよ」という言葉が妙に刺さって、「私の進みたい道ってこっちじゃなかったかも」と思い始めたんです。
負けず嫌いな性格なので、それからは迷いなく「どうせ行くなら一番のところに行きたい」と、ほとんど何も知らないまま東京藝術大学を志望するようになりました。今思えば、現役で合格できなかったら三味線は続けていなかったかもしれません。大学合格後は、迷いなくプロを意識するようになりました。

駒田(母):周囲に同じ境遇の人も少なかったですし、受験の情報も少なかったので、ある意味、知らなかったからできたかもしれないなって思います。難しさを知っていれば身構えてしまったかもしれないけど、考えすぎる前にやってみたことがよかったのかもしれません。