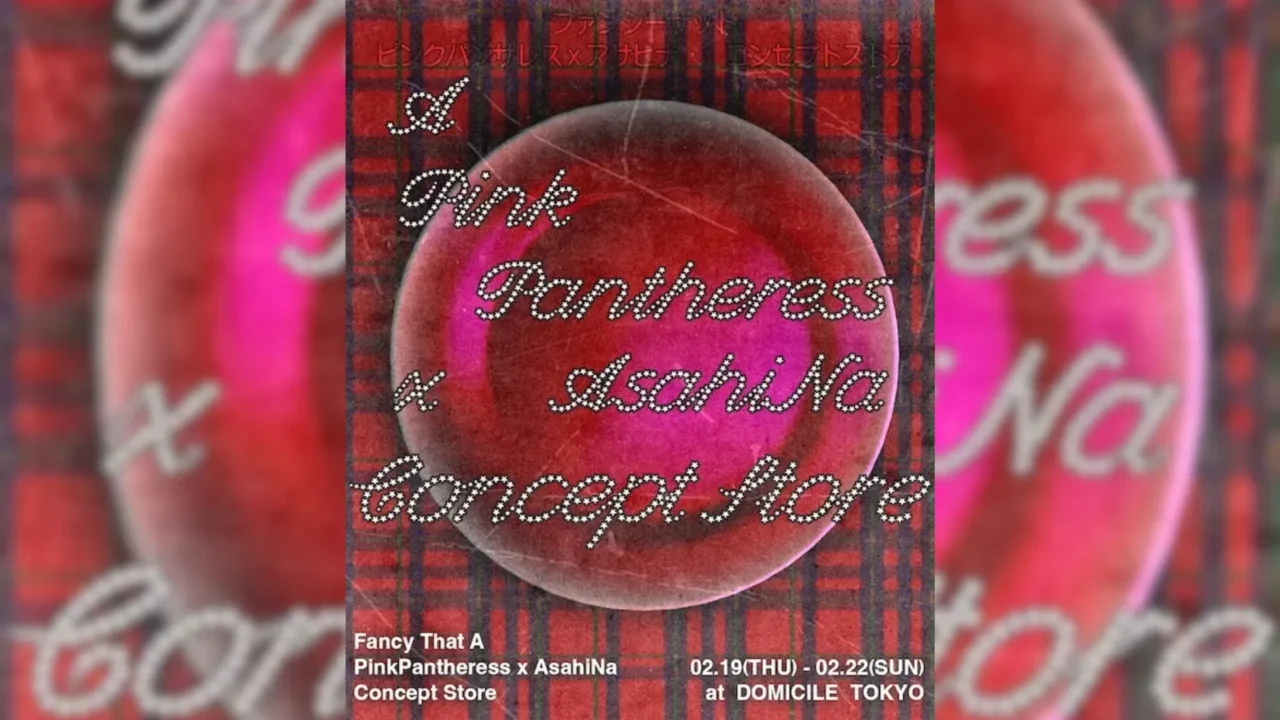シンガーソングライター・大石晴子の楽曲は、それぞれの日常を肯定し、そこから生まれる大小さまざまな光が呼応し合う世界を賛美している。決して壮大な物語を立ち上げるわけではないが、いつどこで何が起きてもおかしくない人生と、喜びも悲しみも内包した自らの心を深く見つめることによって、スムースなソウルミュージックをベースとしたアレンジや歌声から、確かな魂の息遣いを感じさせることがとても素晴らしい。
BREIMENの高木祥太やBialystocksの菊池剛などが参加した2022年発表のファーストアルバム『脈光』がASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文主宰の『APPLE VINEGAR -Music Award-』で特別賞を獲得するなど、音楽ファンの中で大きな話題に。昨年10月と12月に発表された新曲“サテンの月”と“沢山”では新たに高橋佑成や細井徳太郎らを迎え、新たなフェーズの始まりを示した。しかし、基本的にライブの本数やメディアの露出は多くなく、まだまだ彼女の実像に触れたことのあるリスナーは少ないかもしれない。そこでNiEWとしては初となる今回のインタビューは、改めて彼女のパーソナリティとキャリアを紐解き、大石晴子という稀有な表現者の実像に迫った。
INDEX
原体験にあった、ソウルミュージックと讃美歌の存在
―プロフィールによると、大阪生まれ神奈川育ち、音楽好きのご家庭だったそうですね。
大石:小さい頃は特に気にしていなかったんですけど、家でソウルミュージックを耳にする機会がよくありました。ダニー・ハサウェイとか、ミニー・リパートンとか、大きくなって聴いた時「この曲知ってる」って。家族も音楽が好きで、家で楽器を弾きながら歌ったり、一緒にカラオケに行ったりすることもありました。ゲームで『パラッパラッパー』を遊んでいて、あの音楽好きだったなって今もたまにサウンドトラックを聴くことがあります。
―お兄さんはラッパーのRYUKIさんで、『脈光』に収録の“手の届く”に参加されていましたよね。好きな音楽も共有していたのでしょうか?
大石:少し年が離れているので、直接共有することはあまりなかったですね。兄がHIPHOPを好きそうだと認識したのも大学に入ってからだし、私が音楽を始めてからも、お互い「何かやってるな」ぐらいの感じだったと思います(笑)。

大阪生まれ、神奈川育ち。大学卒業後から本格的に活動を始め、2018年りんご音楽祭出演、2019年シングル『怒らないでね』、同年8月EP『贅美』、ついに2022年4月1stフルアルバム『脈光』をリリースし、SNSを中心に各所、話題騒然となり多くのミュージックラバーの心を掴む。『脈光』でAPPLE VINEGAR – Music Award -の特別賞を受賞。
―中高が一貫校で、毎朝讃美歌を歌うような生活だったそうで。そこはやはり歌との接点という意味では一つ大きかったのかなと思うのですが。
大石:確かに。毎年合唱コンクールがあるんですけど、みんな結構燃えるんですよね。合唱も好きだったし、讃美歌を歌うのも好きでした。毎朝全校生徒が集まって、ちょっと眠いんですけど、歌うことはその頃からすごく好きだったなと思います。
―朝の礼拝は当時の自分にとってどういう時間だったか、今振り返るといかがでしょうか?
大石:本当は説教を集中して聞くべきなんですけど……わりと考え事をする時間でもあったかなと。今も散歩をしながらあれこれ1人で考えたりするのが好きなんですけど、毎朝そういった時間が確保されていたのが貴重だった気がします。説教を聞きながらいろいろ考えたり、想像したりしてました。
INDEX
GRAPEVINEとラジオからの影響
ー中学時代はGRAPEVINEをよく聴いていたそうですね。
大石:お笑いにしても音楽にしても、はまるとしばらくはそれに集中してしまう性格で。GRAPEVINEを知ってから、擦り切れるほど聴いてたんですよね。小学生のときはアニメの曲やドラマの主題歌、当時流行していたORANGE RANGEとかを聴いていたと思うんですけど、GRAPEVINEは何だか大人っぽい雰囲気に惹かれたのかもしれないです。

―GRAPEVINEを知るきっかけになった曲はありますか?
大石:シングル曲の“スロウ”とか“光について”だったと思います。歌詞に、学生だった私にはピンとこないようなわからなさもあって、でもそこが気になるというか。わからないけど、わからないままでもいいのかな、みたいな。「とにかく最高なんだわ」とGRAPEVINEが好きな同級生と盛り上がってました。
―直接的過ぎない歌詞は現在の大石さんの作風とリンクする部分があるように思います。
大石:私はまっすぐ書くのがちょっと恥ずかしくて、照れがあるのかもしれないですけど、必ずしもわかりやすくなくていいんだという部分で影響を受けているかもしれない。GRAPEVINEの歌詞は文学的だと語られることが多いけど、ところどころに「この景色、知ってる気がする」みたいな、かなりキュンと来るポイントがあって。自分が書く歌詞からも、空気感や心の揺れみたいなものが浮かんだらいいなと常々思ってます。音の力も存分にかりながら、歌詞を受け取った人が各々でじわっと何か感じてくれたら嬉しい。聴いた全員が同じものを思い浮かべるより、そんな曲を作りたいですね。

―もともと詩や言葉にも興味・関心があったのでしょうか?
大石:お恥ずかしい話なんですけど、学生時代に本を読んできていなくて。集中力がなかったので、全然入ってこないんです。読んでるつもりでも文字を追ってるだけで、気づくと「あの番組録画したっけ」とか別のことを考えていて。読書には苦手意識があったので、文学はちょっと遠い存在でした。
―昔からお笑いが好きで、特にラジオを聴くのがお好きだそうですが、ずっと聴いていて、人格や価値観において影響を受けている番組はありますか?
大石:ラジオを聴き出したのは大学に入ってからで、通学しながら聴いてました。毎週聴いてたのはバナナマンの『バナナムーンGOLD』とか。番組内のヒムペキっていう替え歌のコーナーが好きだったけど、10年以上続いてたのに最近無くなってしまって、寂しいです。あとはダイアンの『よなよな…』も番組終了まで聴いてました。結構くだらないのがぼーっと聞けて好きかもしれない。馬鹿馬鹿しいメールを真剣に送るハガキ職人たち、みたいな存在も好きなんですよね。自分でもメールを送ったことがあるんですけど、すごい真剣にアホなことを考えるんですよ。コーヒーを飲みながら、あたかも仕事をしているような、論文を書いてるような感じで、人には見せられないようなことを書いてる時間。そういうのが好きですね。歌詞を書く時間と似てるかもしれない。人格形成と言えるかはわからないですけど、好きなものは何かと聞かれたら、ラジオと答えてます。音楽よりラジオを聴いている時間の方が長いと思います。
INDEX
本格的に音楽活動を始めた早稲田大学時代
―早稲田大学で音楽サークルに入って、そこから本格的に歌うようになったそうですね。
大石:ブラックミュージックをカバーするサークルに入りました。早稲田はたくさん音楽サークルがあるので、最初は色んなジャンルを見て回ったんですけど、新歓ライブで見たソウルやファンクが格好良くて。セッションに行くと、みんな楽譜も見ずにその場でキーを変えながら演奏していて新鮮でした。
―ちなみに、楽器はいつ頃からどの程度やっていたんですか?
大石:小学生の頃、クラシックピアノを習ってました。中学に入って練習が続かずやめてしまったんですけど、中高でも家に帰って時間があると、それこそGRAPEVINEを弾き語りしたり。あとは家にあったアコースティックギターを触ってコードを覚えてみたり。サークルに入ってからも歌だけだったので、楽器演奏にのめり込むということは特になかったですけど、ピアノやギターに馴染みがあったのはその後作曲を始める上で幸運だったと思います。

ー大学では主にコピーをしていて、コリーヌ・ベイリー・レイやミニー・リパートンを歌っていたそうですね。クレオ・ソルもお好きだそうで、パワフルに歌い上げるよりは、もうちょっとスムースで、クールさもありつつ、じんわり熱もあるみたいな、そういう感覚に通じるものがあるのかなと。
大石:サークルには声量があって歌が上手い子がいて、自分はそれができなくてもいいかと思いました。大きな声を、高い声を出せなくても歌える歌は沢山ある。サークル時代に、自分がどういう歌を歌えるのか、歌いたいのかを身をもって知れたのは大きかったと思います。
ー大学卒業後にオリジナルでの活動を始めたそうですが、進路についてはどのように考えていましたか?
大石:サークルを引退して大学を卒業してからも、「音楽をやめる」みたいなことは考えたことなかったです。それで、続けるなら自分で作った曲を歌いたいし、そうするべきだと感じました。水餃子屋さんで働きながら、オリジナル楽曲の制作やライブ活動を本格的に始めました。
INDEX
「何かっぽい」ものではなく、いつ聴いても古い感じがしない音楽を目指して
―最初にリリースした『賛美』(2019年)はどのように生まれた作品だったのでしょうか?
大石:私は全くのフィクションみたいな曲がなくて、普段感じたことや考えていたことが溜まって、それを何か形にしたい思いから曲を作ります。たとえば“怒らないでね”は、飼っていた愛犬が亡くなったことがきっかけで書いた曲だったりとか。何か感じたときに、それだけではいられないというか、どうにか形にしないと平気でいられないという感じかもしれないです。その時期に考えていたことがその作品にすごく反映されてるような気がします。
―2022年リリースの『脈光』も主にコロナ禍で感じたことや考えたことがベースになっているわけですよね。
大石:その期間に感じたことをいつかちゃんと曲として残したいという気持ちはありましたけど、コロナ禍で時間があるんだからどんどん曲を作るぞという風にはなれなかったですね。もしかしたら「もっと焦った方がいいよ」って思われてるかもしれないですけど(笑)。リリースもライブも少ないって。でも私自身はあまり焦ったことはなくて、焦ってもしゃあないし、できるときにできることをやろう、と。

編集・柏井:「焦らない」っていうのは、言うほど簡単なことではないですよね。特に20代半ばにコロナ禍で活動を制限されたと思うので。大石さんはなぜ焦らずにいられたんだと思いますか?
大石:もちろん不安になりました。あの時期は友達にも会えず、目前に何も楽しみがないから、私の内側が、未来の漠然とした不安とか、過去の後悔だけでいっぱいになってしまって、かなり落ち込みましたね。節分の時期にスーパーで、恵方巻きコーナーに人が集まっているのを眺めていたら勝手に涙が出てきて……「私つらいのかな?」と思うことにさえ罪悪感があったけど、今思い返せば結構きつかったんだと思います。
だからこそ意識的に、不安になりすぎないようにしていたのもあるかもしれない。危ないなと思いました。健やかでいないと、音楽もなにもできないなと、バランスを整えたいという気持ちが強くなりました。焦らずに、まずは落ち込む感情と少し距離をとって、“さなぎ”を書きました。過去を受けて、未来に向けてできること、今の私が何かを生み出すことの大切さを歌った曲です。
―『脈光』には『APPLE VINEGAR -Music Award-』の特別賞をはじめ、大きなリアクションがありましたが、今振り返るとどんな作品になったと感じていますか?
大石:「何かっぽい」ものにならない方が面白いなと感じていて。「この曲のこの感じで」という作業も私はあまりうまくやれないので、つい抽象的な相談をバンドメンバーにしてしまっていたと思います。
私にとって曲のきっかけになった出来事が開始点としてあるけど、聴く人によって浮かぶ景色が違っていいし、むしろそうなるといいなと制作中も思ってました。音像も、斬新であることを目指さなくていいけど、説明しきれない余地が残るといいなって。数年後聴いても古く感じない音楽に魅力を感じるので、せっかくアルバムを作るなら、いつ誰が、どう聴いてもいいような、そういう作品を残したいという気持ちがありました。

―今言ってくれたような意味でも、中村公輔さんのエンジニアリングは重要だったと思うんですけど、中村さんとも抽象的な言葉でやり取りをしていた?
大石:本当にそうですね。リファレンスになる音源を挙げた方が進めやすい場面も多いかと思うんですけど、私は抽象的な要望に対して「これはどう?」と実際にいくつか音を聴かせてもらうほうがやりやすくて。ただ中村さんは、それでもいろんな音楽を聴いた方がいいよと、私が知らない曲をいつも教えて下さるのでありがたいです。
ーではあえて抽象的な聞き方をしちゃいますけど、『脈光』で描いた光のイメージというのは、大石さんの中ではどんなイメージでしたか?
大石:そのときその人にとって、だけでいいなというのは思っていて。好きだと気づいたことーー明日にはもう好きじゃなくなるかもしれないですけど、一時でも何かすごくいいものだったなら、それでいいんじゃないかって。
それに、全員にとっていいものでなくてもいい。私にとっては特別なもの、みたいなのを表現したかったです。アルバムを聴いた人が「今日の私はこの曲のこの音が気になるな」とか好き好きに思ってもらえたら嬉しいです。『脈光』で描きたかった光はそういうものかもしれないです。
―「脈光」は造語ですけど、ぼんやりとした、ふとした光のような感覚で捉えました。強いメッセージを放つわけではないけど、たしかな存在感がある。
大石:そうですね。どの曲も、「こうなんです」っていう眩しいメッセージはないかも。「私はこう感じているんだけど、どう思う?」ぐらいの、「ちょっと置いておくけど、気になったら拾ってみて」ぐらいの感じですね。

INDEX
「日常を尊ぶ」というより、ただそれがあることを歌う感覚
―昨年の10月と12月に新曲のリリースがありました。『脈光』以降の1年半はどんな時間でしたか?
大石:長い目で計画的にアルバムを作れたらいいだろうな、という考えはうっすらあったんですけど……今回ばっかりは少し焦ったのかもしれないですね。去年の年始に近しい人が病気になってしまって、早く届けたい気持ちがあったので、今あるものをとにかく形にして出したいと思ったんです。それでシングルを2曲、「配信したから聴いといて」ではなく、何か渡せるものを作りたくて、カセットテープにしました。
―ライブに関してはコロナ禍以降も決して数は多くないと思いますが、どのような考えがありましたか?
大石:「ライブが大事」という意識がそもそもなかったかもしれないです。私自身これまでライブに足を運ぶ機会がそれほど多くなくて、どちらかというといつも音源に救われてきたからなのか、音源を出した時点で一旦完結してる心地なんです。
音源制作においてはテイクを選択したりして、ある程度自分でゴールを決められるけど、ライブは自分の意思以外の要素があまりに多いので、そこが怖いなという思いがありました。リハと同じにはならないし、会場もお客さんもどんな様子かわからない。でも今回は直近で楽曲のリリースもありましたし、「やった方がいいよ」って各所が言って下さったので(笑)、チャレンジできました。
編集・柏井:はい、ライブの出演オファーを出しまくっておりました(笑)。
―やってみてどうですか?
大石:「やっぱり難しい!」と思いました。お客さんが「すごくよかった」と言って下さるのを一つの結果として、それに一先ず安心しつつ、自分の中の感触はまた別ものとして大切にしたいです。

―アルバムで注目度が上がったことによるプレッシャーを感じたりもしましたか?
大石:そこは全然なかったですね。あくまで自分の中での不安――自分が納得いくものにならなかったらどうしようっていうところだけで。でも今回リリースした楽曲の参加メンバーとであれば、少し探れるような気がしたというか、いいライブができるのかもしれない予感があったから、踏み切れたというのはありそうです。制作からライブにかけて高橋佑成さんが中心メンバーとして、私の相談役になってくれて、それはかなり大きかったですね。
―10月にリリースされた“サテンの月”はどのように生まれたのでしょうか?
大石:夜散歩をしていて、大きな道路沿いをずっと歩くんですけど、横断歩道を渡るときに中央分離帯があるじゃないですか。信号が赤になりそうなら諦めるか走るかすれば良かったんですけど、渡りきれずに真ん中で青信号になるのを待つ時間があって。私の前後をすごいスピードで車がバーって行き来して、まるで自分がいないような気もしてくる。ここに私が立っていることを、こうやってあれこれ感じていることを、誰も知らないんだと。孤独を強く意識して、じゃあその孤独を前提にこれから考えられること、やれることもあるはずだと思って、この曲を書きました。

―お話を聞きながら、現在の大石さんはアーティストとしてのキャリアの中央分離帯にいるようなイメージが湧きました。孤独なんだけど、車が通ってるから戻ることはできなくて、進んでいくことしかできない、みたいなことだったり。
大石:アーティストのキャリアに限らずですが、「戻れない」という意識は大きいですね。何か知る前の状態には戻れないし、できないことは増えていく。そういう状況に自分がいて、「じゃあどうしたいか?」っていうことについて考えていた期間だったと思います。
曲としては、前半で孤独への気づきがあって、後半では、だとしても一つの影があるのは私がここに確かにいるからで、鼓動が鳴ってるのは私が生きてるからであって、と。ポジティブに変換とまではいかなくても、でもできることはあるよな、みたいな感じですね。<この街を初めて走ってる>って、別にどこに行くっていうこともないんですけど、目的も勝算もなく走ってる。「こんな自分もいたんだ」みたいな、ちょっと笑えてくるというか、少し気が楽になってるような様子です。
―12月にリリースされた“沢山”に関してはいかがですか?
大石:去年は年始から災害があって、「お正月なのに」とか思ってしまったんですけど、そんなの関係ないんだと。その日が社会的にどうとか、他の人にとってどうとかは関係なく、嬉しいことも悲しいことも、大小問わず何だってあるんだというのを改めて実感したので、それをもとに書きました。
本当は嬉しいことだけ続いてほしいけど、選べないから、普通に生活をしていくだけでも結構きついと思うんです。それでも人生が続いていくとしたら、どうやったら自分を保っていられるかと考えた時に、やっぱり誰かと共有したい、話したいっていうのがありました。曲を作ることも私にとってその手段で。こういうことを考えてる、感じてるっていうのを共有するために作ってる気がします。家族や友達、距離も時間も超えて、今は会えない人にさえ届くかもって思うと、困難でも私は取り組みたいです。
―<君に果物をむく>というラインが印象的で、他者への意識を感じます。
大石:<君に果物をむく>とか<表で子供達は遊ぶ>とか歌ってはいるんですけど、「ささやかな生活を尊ぶ」みたいにはしたくなくて、ただそういう生活があるというのを言うだけでいいなと思ってました。

―「生活を尊ぶ」とか「ささやかなことだけど大事にしていこう」ではなく、ただそれがあることを歌う、その温度感が重要だったと。
大石:そうですね。だから<君に果物をむく>と書いてるけど、君という存在への愛情、みたいなことはあまり意識していなくて。そこにフォーカスするというよりは、嬉しいことも、悲しいことも、座標みたいに点が沢山打ってある、っていうのを言ってるだけ。そんな暮らしがあることをみんなが知っていたら、あるいは想像できたら起こらないようなことが、残念だけど起こるから。願いがあるとすれば、誰かに何かを強制される、逆に何かを取り上げられるということが無いといいなということです。子供たちが何も気にせず遊びに行けるような、そういう世の中であり続けてほしいと込めたつもりです。
―では最後に、ここから先何を大事にして、どんな表現をしていきたいと考えていますか?
大石:去年はリリースにライブに、カセットテープやグッズの制作にも挑戦してみたけど、ぼんやりする時間をあまり持てなかったので。年末から本屋さんで本を買ったり、服の破れてたところを繕ったり、そういう時間を確保していて楽しいです。今年は旅行にも行きたいかも。そうやって少ししたら、自ずとまた曲もできていくのかなって。シングルで2曲出してみて、アルバムの強さを改めて感じた部分はあったので、次リリースするならアルバムかなと思ってます。その準備をしたいです。
―誰かに強制されない、その人が生きたいように生きられることへの願いというのは、自分自身の創作活動においても大事にしていることだと言えますか?
大石:私の場合は多少お尻を叩いてもらった方がいいのかもしれないですけど(笑)、これまでも制作から少し離れる期間があったとしても、そのうち「やっぱり作りたい」と気持ちが湧きました。本を読んだり、お笑いや落語や映画を観たり……それだけで勿論楽しいんですけど、結局その先に「私も何か作りたい」があって。それが自分にとって自然なことだし、制作でしか満足できない部分がある気がしてます。タイミングや熱量は自分でもコントロールできないんですけど、その「作りたい」と思ったときのために、心身ともに健やかでいることを心がけて過ごしていきたいです。

INFORMATION

シングル曲『サテンの月』『沢山』が各サイトにて配信中。
サテンの月:https://ssm.lnk.to/satinmoon
沢山:https://ssm.lnk.to/things
また、上記2曲収録のカセットテープとグッズを通販にて販売中。
https://shop.oishiharuko.com/

大石晴子HP
https://oishiharuko.com/