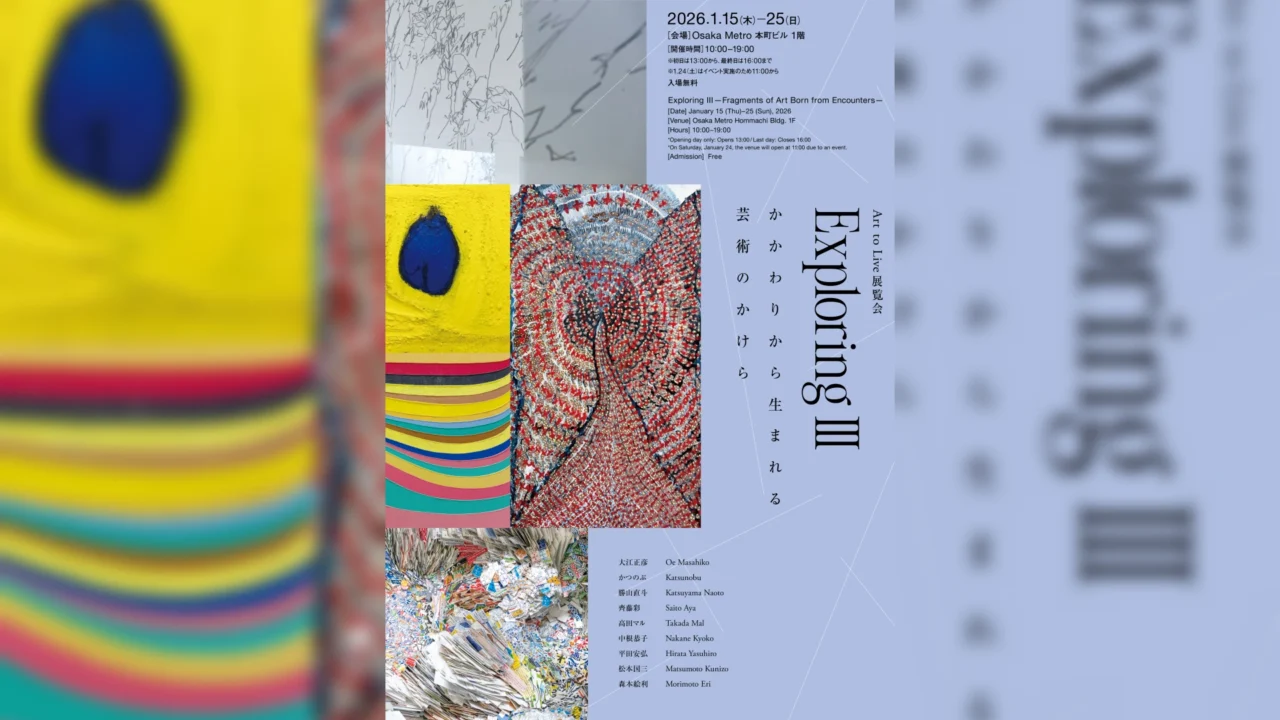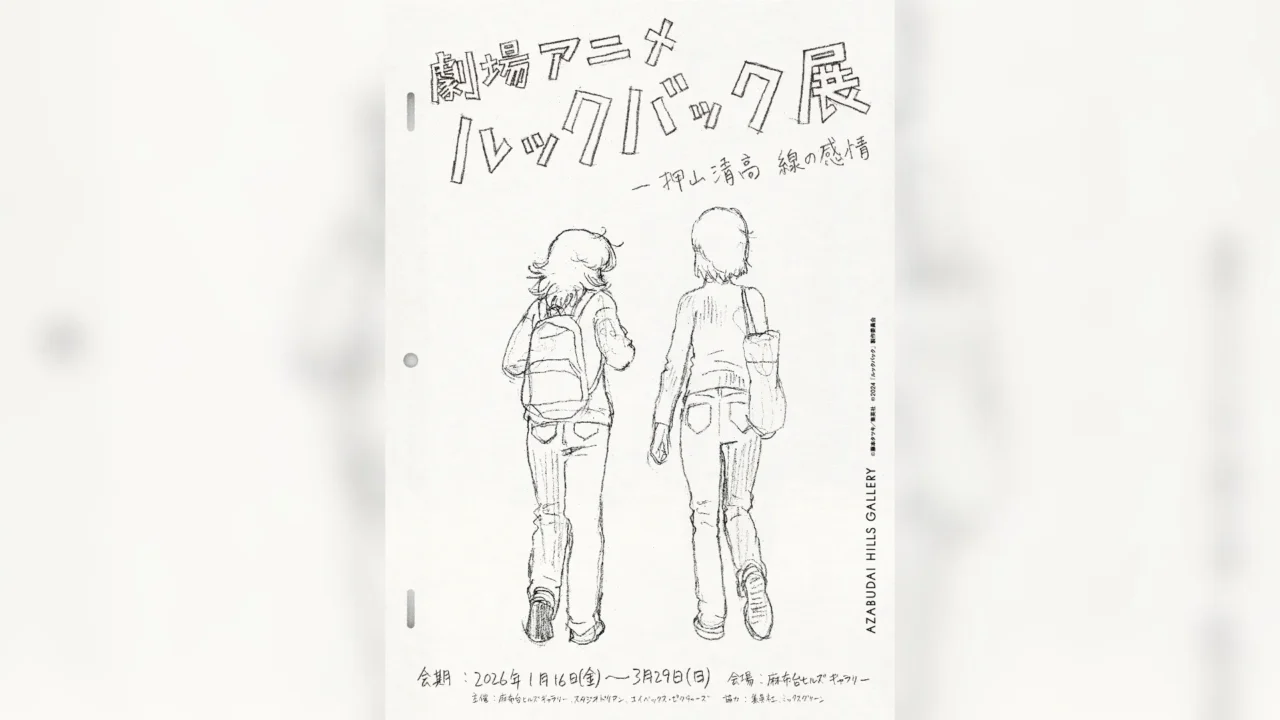『FUJIROCK FESTIVAL’25』の2日目のヘッドライナー、Vulfpeckの楽曲プロデュースも手がけたことで知られるカナダ出身の音楽家、Mocky。
来日公演で日本のミュージシャンをバンドメンバーに迎えてきただけでなく、過去にはKID FRESINOやCampanellaの楽曲プロデュースを手がけるなど、国内の音楽家との関わりを深めていることでも知られる。さらに9月22日(月)からはじまる来日ツアーの東京公演のサポートアクトには、んoonの出演も発表されている。
そんなMockyに、んoonのメンバー、Mockyの大ファンであることを公言する角舘健悟(YOGEE NEW WAVES)、鳥居真道(トリプルファイヤー)、出戸学(OGRE YOU ASSHOLE)から質問を集めて取材を実施。
最新作『Music Will Explain (Choir Music Vol. 1)』で追求したAI時代における「人間の響き」について、そのサウンドが魔法的な魅力を持つ秘密について、探ってみた。
INDEX

カナダ出身の音楽家。コンポーザー、アレンジャー、プロデューサー、ベースとドラムを主軸に様々な楽器を弾くマルチプレイヤー、ラッパーとさまざまな側面を持つアーティスト。6月、『Music Will Explain (Choir Music Vol. 1)』をStones Throwより発表、9月からは東京・大阪・京都をめぐる来日ツアーも開催する。
AIの飛躍的発展の裏で、Mockyが追求した「人間の響き」とは?
―Mockyの新作『Music Will Explain (Choir Music Vol. 1)』は、「Stones Throw Records」からリリースされました。あなたにとって、Stones Throwという場所やコミュニティーはどのようなものですか?
Mocky:Stones Throwは音楽の歴史のなかですごく大事だし、そんなレーベルから自分の作品を出せるのは光栄なことでした。クラシックもたくさんリリースしていて、J Dillaの『Donuts』やJaylibの『Champion Sound』は特に外せない作品。
Mocky:今も素晴らしいアーティストがたくさんいて、エディ・チャコン、ベニー・シングス、メイリー・トッド、Bardoは友達です。人生のなかで面白いレーベルやアーティストと関われるなんてラッキーだなって。僕の音楽を見つけ、日本に初めて呼んでくれた「Windbell Records」と主宰の富田和樹さんにも感謝してます。
―2019年、あなたはアニメ監督の渡辺信一郎さんとの対談で、AIについて語っていましたよね。最新作はまさに今飛躍的に発展するAIに対する意識が反映されているそうですが、音楽家としてそのアティチュードをどのように作品に落とし込んだのでしょうか?
Mocky:まず渡辺信一郎さんと一緒に仕事できたこと自体が光栄でした。
Mocky:AIは他のツールと同じように使えるものだけど、同時に人間らしくいられる場所を狭めたり、僕らを置き換えようとするような怖さもあるなって。それが『Music Will Explain (Choir Music Vol.1)』はスタート地点だった。AIには絶対に真似できない「人間の声のリアルな響き」を残したかったから。
だからこそ声とドラムという基本に立ち返った。古いテープマシンにボーカルを何人も集めて、全員で同じ音をユニゾンで歌って、ひとつの声に溶け合うまで繰り返して、1本のマイクで録ったという。「人間の響き」を追い求める執念の作業だったよ。
―「人間の響き」を具体的にどういうものとしてMockyさんが捉えているのか知りたいです。あなたがこれまでの取材で繰り返し語っていた「ミス」の重要性と、何か関係あるのではと感じています。
Mocky:人間が何かをやるとき、そこには何らかの芸術的な理由があって。自分の内面や外の世界を理解するために「どうしても表現したい」という強い欲求——僕が「A. why?」って呼ぶその感覚は、AIにはないと思う。そこに至るまでに起きる「ミス」と呼ばれるものも、僕にとっては全部「詩」なんです。その詩的な感覚が人々の闘いと美しさの物語を語るし、アートの大事な要素なんじゃないかな。
コンピューター的な「完璧さ」は、僕には冷たく感じられるし、疑念のようなものが投げかけられるような気がする。解決策よりも、問題が出てくるほうが多いように僕には感じられるというか。

―すごく興味深いです。Mockyさんは活動の初期、シンプルな機材しか所持していなかったからこその「物理的な制限」をクリエイティビティーに転換していましたね。プロンプトをAIに入力すれば音楽を生成することも可能になった時代において、音楽の創造性はどこに宿ると思いますか?
Mocky:「音楽」をどう定義するか次第だけど、僕にとって音楽は生きているもので。録音前から「曲が生きている」ことすらあると思う。つまり音楽は常にあって、ただ耳を澄ませればいい、という。
僕の音楽は自分の頭のなかとか、ミュージシャン仲間や友達と過ごす時間のなかでよく生まれるんです。その時間は、物語としてあとから伝わってくることもある。近くに機材が少ないほうが曲作りはだいたい上手くいくし、むしろ機材がないときに最高のアイデアが浮かぶことが多いかな。AIを使っても僕にはアイデアが出てこないし、AIは僕から楽しみを奪ってしまう感じすらあるよ。
INDEX
んoonからの質問。演奏者、プロデューサーとして大切にしていること

2014年にハープ、キーボード、ベースのインストゥルメンタル編成でスタートした んoonは2016年ボーカリストJCの加入を境に、ノイズ、フリージャズ、ヒップホップ、ソウル、パンク、クアイヤー、エレクトロなど、あらゆる音楽のエッセンスを不気味に散りばめた音を演奏するバンドとなる。2025年9月、Mockyの東京公演にサポートアクトとして出演する。
んoon:Mockyさんにとってコンポーザー(作曲能力)と、楽器プレイヤー(演奏能力)であることのバランスについて教えてください。
Mocky:僕にとっては演奏も作曲の一部って感覚なんです。人や楽器をイメージして曲を書くのが一番いい。僕は自分の作品でほとんどの楽器を演奏するけど、役者になりきるみたいな感覚があるかな。
例えばドラムを叩くときは「自転車でスタジオに来て疲れてるドラマー」を想像したり、ピアノを弾くときは「失恋したばかりのピアニスト」を思い浮かべて弾いたり。映画のキャラクターにちょっとした背景を与えるような感覚というか。楽曲が一番大事だけど、瞬間に合わせて変幻自在であることも大切にしているよ。
んoon:バンドセットで自分の楽曲を演奏するとき、自分以外の演奏者へ期待することや指示することは何ですか?
Mocky:基本的には「自分らしくいてほしい」ってお願いするだけかな。ちゃんとアレンジされていれば、それで十分と思ってて。僕が一番大事にしているのは、「信頼」と「音楽がどんな方向に行っても支える姿勢」、そして「楽しさ」。純粋に「音を出す喜び」とも言えるかな。一緒に演奏するミュージシャンにはそういうことを求めてるよ。
んoon:我々のライブPAであるカツラはMockyさんの大ファンで2016年、2019年の来日公演を観に行ってあなたとの2ショット写真を撮っています。彼のことを覚えていますか? 彼も我々んoonも東京公演で再び会えることをものすごく楽しみにしています!
Mocky:光栄だよ! 今度の東京公演で、答えを言うね(笑)。あのときも本当にたくさんの人と写真を撮って、感謝の気持ちでいっぱいだった。
―今回の来日ツアーでも、日本のミュージシャンを招いたバンドセットで演奏を予定していますね。Mockyさんから見て、日本のミュージシャンの演奏、リズムやグルーヴにはどんな特徴があると思いますか?
Mocky:音楽は言葉と同じようにひとつの「言語」なんだと思ってて。だから違う国のミュージシャン同士が一緒に演奏するってことは、コミュニケーションの方法を探るような感じでワクワクする。
これまで一緒に演奏した日本のミュージシャンは、スピリットも音楽に対する感覚も素晴らしいし、演奏レベルもめちゃくちゃ高い。だからいつも本当に楽しいよ。
INDEX
トリプルファイヤー・鳥居真道からの質問。Mockyのメロディーとベースラインの秘密

1987年生まれ。トリプルファイヤーのギタリスト。他アーティストのレコーディング・ライブへの参加および楽曲提供を行うほか、Rolling Stone誌でKraftwerkのコラム、Vulfpeckへのインタビューを担当する。
鳥居:バリー・マンとシンシア・ワイルのペンによるダスティ・スプリングフィールド“Just Little Lovin’”(1969年)を新作で取り上げた理由は? 1960年代西海岸のコーラスグループを思わせるアレンジがフレッシュでした。こうしたサウンドは日本では「ソフトロック」と呼ばれていて、カルト的な人気があります。
Mocky:Feistという大親友のコラボレーターがその曲を教えてくれて、すごく心に響いたんだよね。とてもシンプルだけど大事なテーマだと感じて、そこにバックビートをつけてみたのが始まりで。もともとはワルツだったのに全然違う雰囲気に変わって、すごく新鮮に聴こえたんです。それが嬉しくて録音したんだけど、これが僕にとって初めてのカバー曲になったよ。
鳥居:タイトル曲“Music Will Explain”の歌詞が興味深かったです。一般的な考えをすると、音楽の主体はあくまでミュージシャンであり、彼らが音楽を通じて何かを表現する、と言えるかと思います。しかし、この曲の主体は音楽そのものです。音楽に自律性があるという考え方はとても素敵だと思いました。この曲はどういう着想からできたのでしょうか?
Mocky:この曲は、感情と一緒に瞬間的に降りてきたんです。自分の心の声を聞いて、ピアノに歩み寄る途中、鍵盤に触る前にサビが頭のなかに鳴ってる感覚があって。音楽そのもののなかに潜って答えを探しているような気持ちというか。きっと誰もがそうやって音楽から、言葉では言い表せない感情を音やメロディーを感じ取っていると思うんだよね。
鳥居:Mockyさんの音楽はベースが躍動していて、踊らずにはいられません。影響を受けたベーシストはいますか? 好きなベースラインなどあれば教えてください。
Mocky:まさに! 僕にとってベースはメロディーで、曲のなかでずっとしゃべり続けるキャラクターみたいな感じ。数々のモータウンの名曲を支えたベーシスト、ジェームス・ジェマーソンが僕は大好きで、彼のベースラインはもう魔法みたいキャッチーだと思ってる。
もちろんスティーヴィー・ワンダーのベースラインも最高だし、他にもたくさんあるけど、有名なところだとハービー・ハンコックの“Chameleon”が大好き。
INDEX
OGRE YOU ASSHOLE・出戸学からの質問。Mockyの音楽を形作るレコード、機材、本

メロウなサイケデリアで多くのフォロワーを生む現代屈指のライブバンド、OGRE YOU ASSHOLEのフロントマンでコンポーザー。2000年代USインディーとシンクロしたギターサウンドを経て、サイケデリックロック、クラウトロック等の要素を取り入れる。
出戸:好きなレコードを3枚教えてください。
Mocky:これは難しい質問だ(笑)。強いて挙げるなら、まずはスティーヴィー・ワンダーの『Music of My Mind』(1972年)。自分で多重録音を始めたときにすごく影響を受けたよ。
あとはマイルス・デイヴィスの『Round About Midnight』(1957年)。これは何千回も聴いたと思う。特にジョン・コルトレーンの音が素晴らしよね。最後の1枚は……コンピレーションでもいいかな(笑)。ジョルジ・ベンジョールやTrio Mocotóとかが入ってるブラジル音楽のコンピはやっぱり最高だね。
出戸:今回のアルバムでよく使ったマイク、マイクプリアンプなどの録音機材を教えてください。
Mocky:ほとんど1本のマイクだけで、Neumann(ノイマン)のオリジナルM7カプセルにSiemensのチューブを組み合わせたもの。これは昔、ベルリンで見つけたレアなやつで。この作品はプラグインを一切使ってなくて、AmpexのC440テープマシンに入れて、ビンテージのEcoplateリバーブを使ったよ。
出戸:おすすめの本を3冊教えてください。
Mocky:1冊目は『Temperament: How Music Became a Battleground for the Great Minds of Western Civilization』かな。アメリカの音楽評論家、ピアニスト、作家のスチュアート・イサコフが書いたもので、音階をどのように調整・調律するか、つまり音律の歴史をたどった本。
2冊目は『The Orientalist: Solving the Mystery of a Strange and Dangerous Life』。トム・ライスというジャーナリストによるレフ・ヌッシムバウム(※)の伝記的ノンフィクション。3冊目は『Elephant to Hollywood』。イギリスの俳優、マイケル・ケインの自伝だよ。
※レフ・ヌッシムバウムは、バクー(現アゼルバイジャンの首都)のユダヤ人家庭に生まれた作家。20世紀のふたつの世界大戦のさなかにヨーロッパを流浪しながら複数のペンネームを使い分けて活動、クルバン・サイード名義で発表したとされる恋愛小説『アリとニノ』(2001年、河出書房新社、松本みどり訳)などを残す
INDEX
YOGEE NEW WAVES・角舘健悟からの質問。Mockyの音楽がミラクルで魔法的なワケ

1991年生まれ、東京出身。2013年にバンド、Yogee New Wavesを結成、ボーカル/ギターを担当。2014年4月にデビューe.p.『CLIMAX NIGHT e.p.』でデビュー。今年3月にカバー企画へ参加し、『瞳はダイアモンド』をリリースする。
角舘:来日心待ちにしていました。パンデミック中、Mockyの音楽を繰り返し聴くことで、音楽の楽しさを思い出させてもらったことをここでお礼します。ありがとう。
Mocky:嬉しいよ!
角舘:Mockyの作品のなかで特に好きなアルバムが『Overtones for the Omniverse』です。偶発的で、ミュージシャンの持つポテンシャルを神秘的に結びつけた傑作だと思うんですが、1テイクのアイデアはどんなところから着想を得ましたか? スリリングで、ワクワクに満ちた制作だったんじゃないかと想像をめぐらせています。
Mocky:そう言ってもらえて本当にありがたいよ。今はテクノロジーが発達しているのに、アルバム制作に時間がかかるのは不思議だなってよく考えるんだよね。
Mocky:でもマイルスの『Kind of Blue』(1959年)みたいな史上最高のアルバムだって、たった1日の午後で録音されたわけじゃない? それを思い出して「自分も現代にそういう作り方ができないかな」って。だからアルバムに入っている曲の多くは一発録り。初めて弾いてみた瞬間のテイクがそのまま入ってる曲もあるよ。
角舘:これは僕の個人的な経験なんですが、2024年に子どもが産まれました。分娩するときにBGMを選ぶことができて『Overtones for Omniverse』を流していたら“Humans“という曲のタイミングで産まれました。なんてミラクルで、この作品が持つ偶然性と重なったこと、僕にとってスペシャルな曲になりました。感謝しています。Mockyさんはどんな想いでこの音楽を制作するに至りましたか?
Mocky:最高な話をありがとう! この曲を書いた理由がわかった気がする。自分の曲が誰かの人生の大切な瞬間に立ち会えたなんて想像もしてなかったな。
正しい道を進んでこれた証拠に思えるし、これからも曲を書き続ける力をもらえたよ。人と人がつながる場所を探して、思いやりを持って、心を開いて素直でいることが僕の音楽の軸だから光栄に思うよ。本当にありがとう!