INDEX
脚本に織り込まれた戦争とエノケン、喜劇の関係
北沢:エノケンという明治37年(1904年)生まれの人物の生きた時代が、戦前から戦中、そして敗戦後25年が過ぎた昭和45年(1970年)に亡くなるまで、かなりの幅があるなかで、又吉さんが一番意識したポイントはどこでしたか?
又吉:メインとなる時代はやっぱり戦時中かと思います。あとはエノケンさんがお年を召されてからの戦後の時代。病気や右足を失ったこととエノケンさんがどう向き合っていったのか。この2つの時代を一番意識して描いています。どちらにも戦前の浅草の華やかな雰囲気は軸として考えつつ、エノケンさんが晩年を過ごした時代にあった戦争の余韻も感じながら書いたところがあります。
北沢:やはりエノケンさんの人生において「戦争」は大きな要素としてあると思うんです。小林信彦さんがリアルタイムで見聞したコメディアンのプロフィールを群像劇風にドキュメントした名著『日本の喜劇人』(1972年、晶文社 / 2008年、『定本 日本の喜劇人』新潮社 / 2021年、『決定版 日本の喜劇人』新潮社)のなかで、晩年のエノケンさんに直接取材したときのやりとりが再現されているんですが、「喜劇映画がなぜ退化したと思いますか?」という問いに、「やはり戦争のせいでしょうね」と答えています。
今回の音楽劇では豊原功補さんが演じる菊谷榮という座付き作家を戦争で失い、それがどんなに痛手だったかをエノケンさんは繰り返し語っている。やはり戦争で失ったもの、奪われたものの大きさを痛感しつつ、戦後を生きられたのかなと思います。

又吉:そうですね。ただそうやって、何かひとつの軸を持って戦前・戦中・戦後の3つの時代を演劇という限られた尺と状況で描くのはなかなか難しいんですよね。
そもそもエノケンさんはすごく濃密な人生を送られているので、舞台に立つまでの話だけでも物語として成立してしまうし、逆に名場面だけ集めて編集しても作品にはなると思う。でもそれだと実人生からシーンを引いていくことになってしまうんですよね。だからこそ、エノケンという人物の実人生を網羅はできないにせよ、「ああ、これはエノケンだな」と思えるものにするには工夫が必要でした。
北沢:どんなふうに脚本を書いていったのでしょうか?
又吉:今回は、ひとつの場面にあらゆる時間の流れや要素を入れながら、同時に削っていき、残した線に削った部分を託す、というイメージで書きました。それは舞台上の時間だけでは描き切れない、実際にエノケンという人物のなかにあったものを複合的に描くということで。そういったことをいろんな場面でやることで時間の流れをシームレスにつなげようと試みています。
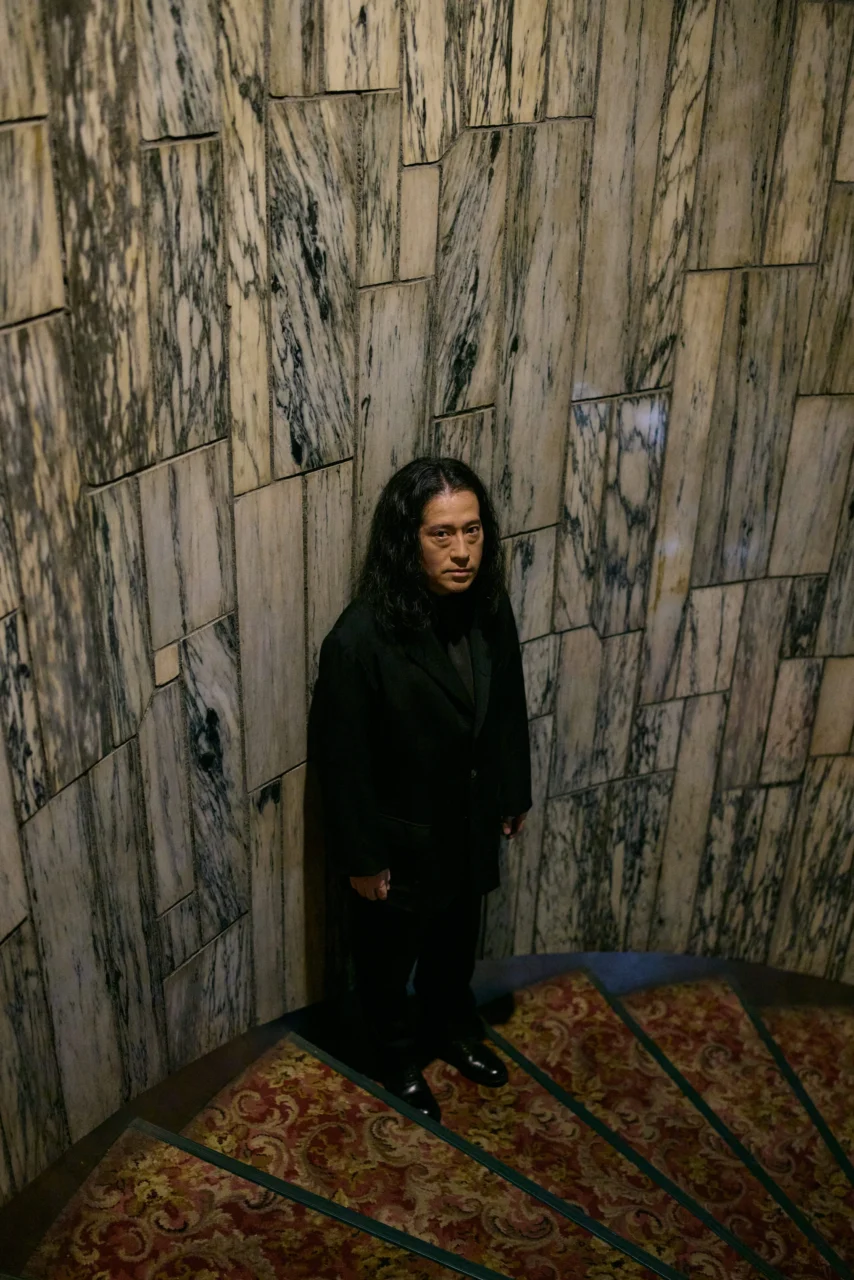
北沢:座員が150人、オーケストラが25人という大所帯の一座の座長としてのエノケンさん、小林信彦さんいわく「〈新劇〉に対してコンプレックスを持っていなかった珍しい喜劇人」だったひとりの喜劇役者としてのエノケンさん、そして経済問題や家庭の不幸、自身の肉体の衰えと向き合いながら、それでもなおコメディアンであろうとするひとりの人間としてのエノケンさん——
そういう稀有な人物の人生上のドラマをただつなげるだけでも比類のないストーリーになることは想像できますが、製作発表では又吉さんの脚本の斬新さを演者のみなさんが絶賛されていました。
又吉:ありがたいです。
北沢:舞台上の限定された時間のなかで、複合的な要素を同時に抜き差ししながら、継ぎ目を感じさせないようにつなげる、しかもそんなはなれわざを編集可能な映像作品ではなく生のステージでやる、とはいったいどういうことなのか? すぐにでも拝見したくてたまらなくなります。



























