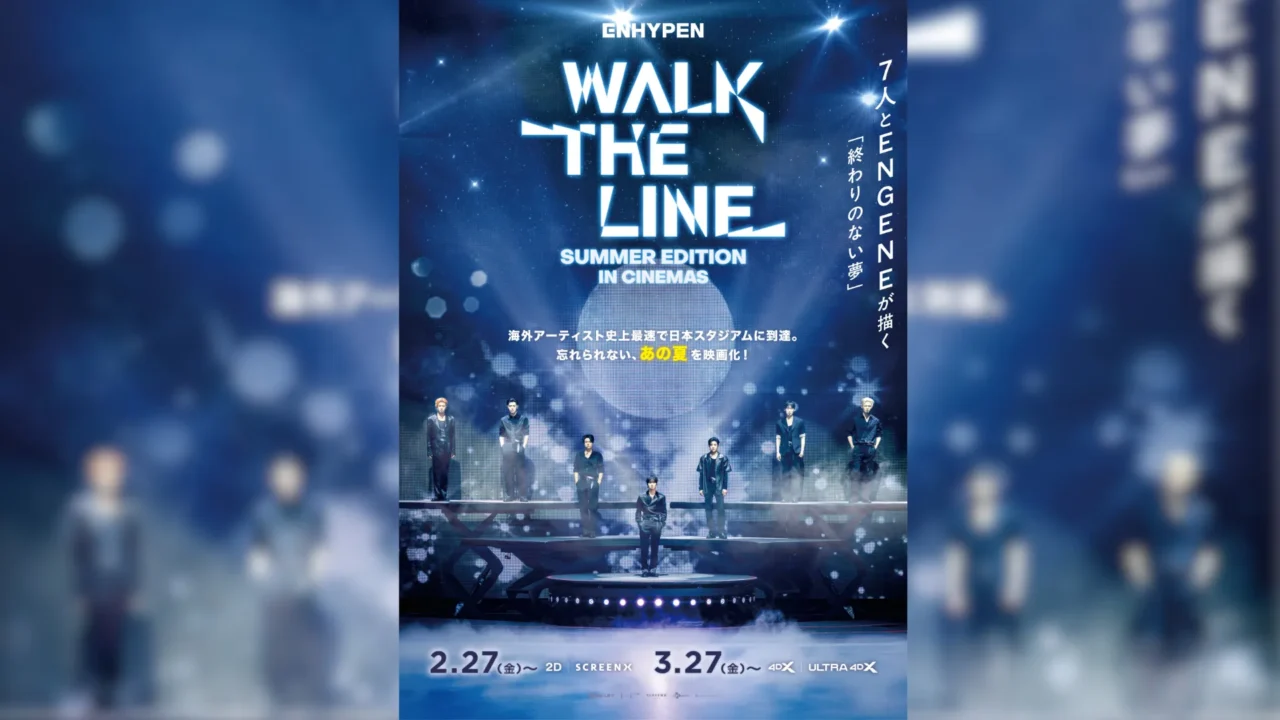現代は自分の直感に従って物事を決めることが難しい時代だと言えるかもしれない。SNSで見聞きした誰かの意見やアルゴリズムに左右され、いつの間にか受け身になっていたり、打算を働かせてしまった経験は誰にでも少なからずあるだろう。
そんな時代において、the telephonesと台湾のバンド・PAPUN BANDが果たしたコラボレーションは、それぞれが直感に従うことで最良の成果を生み出す稀有な実例となった。共通の言語を話さなくても、所属や出自が違っても、「好き」を共有することで生まれる純粋な喜びがあることを思い出させてくれる。
まだコロナ禍が続く2021年にオンラインイベントで知り合い、2023年のPAPUN BANDの初来日時に意気投合した2組は、その後お互いの楽曲に参加。PAPUN BANDのボーカル・Shinyが日本のポップカルチャー好きだったこともあり、11月に発表したPAPUN BANDの“LV99 勇者”は『ドラゴンクエスト』、12月に発表したthe telephonesの“Zan“讚””は『ツインビー』と、それぞれゲーム音楽をモチーフにしているのも非常にユニークだ。
1月・2月に日台で開催される合同ツアーを前にリモートで行われたthe telephonesの石毛輝とShinyの対談は、好きな音楽やゲームで交流を深めた2人の絆を強く感じさせるものとなった。
INDEX
PAPUN BAND・Shinyとthe telephones・石毛「AKIRA」。日台バンドの馴れ初め
ー両バンドが知り合ったのは2021年のオンラインのイベントだったそうですが、まずはそのときのお互いに対する印象を聞かせてください。
石毛:オルタナティブな空気を感じたし、共通して好きなものがたくさんありそうで、すぐ仲良くなれるなと思いました。そのときはオンラインで話をして、好きなバンドの話と、あと「メンバーで誰が一番モテるか?」みたいな話で盛り上がって(笑)、前から知り合いかのように話してた気がします。国を超えて音楽で友達ができたように感じて、すごく嬉しい気持ちになったのを覚えてますね。
Shiny:オンラインで対談した時も漫画の話をしたことがあって。最初に輝さんの名前を聞いたときに、「(僕の一番好きな漫画の)『AKIRA』と同じだ!」と思ったんです(笑)。日本では一般的な名前かもしれませんが、何かの縁だと感じました。それからblink-182のようなポップパンクの話でも意気投合して。誰かこんな風に自分をわかってくれるのは、これまでにあまりなかったので、本当に特別な時間だったし、昔からの知り合いなんじゃないかって思いました。

2005年5月に結成されたポストパンク / ニューウェイブリバイバルの影響を受けたダンスロックバンドthe telephonesのボーカル。2009年7月にメジャーデビューを果たし、結成10周年を迎えた2015年に初の武道館単独公演を成功させる。同年11月3日さいたまスーパー アリーナにて盟友と先輩をゲストに迎えて開催した自主企画を最後に無期限活動休止をしていたが、2019年12月Zepp Tokyoでのワンマンライブで完全復活。2023年5月に長島涼平(Ba)が脱退し、石毛輝、岡本伸明、松本誠治の3人体制で新たに始動。今まで以上に「オーディエンスを踊らせる」事をテーマとし、ハウスやテクノといったクラブミュ ージックをバンド編成で演奏する新たなフェーズヘ移行。2025年1月から、台湾のバンド・PAPUN BANDとのツアー『PAPUN BAND×the telephones Presents LV1 to LV99 Tour -GAME START-』を開催。
ー実際に会ったのは2023年にPAPUN BANDが来日したとき?
石毛:そうです。初めて直接ライブを見た印象はオンラインで見た時のものとはいい意味で全然違ったんですけど、Shinyのステージングはやっぱり好きなギタリストが共通してる印象で、すごくシンパシーを感じました。ギターのネックの上げ方とか、そういうところで好きなギターヒーローが一緒な感じがしたし、ライブでお客さんを盛り上げようとする姿勢もthe telephonesと共通する部分があると思いましたね。
ー一緒に飲んだりもしたんですか?
石毛:the telephonesはそのライブには出てないんですけど、その日の打ち上げで初めて一緒に飲んで、笑いのツボがかなり似ててすぐに意気投合しました。『BEAVIS AND BUTT-HEAD』とか『jackass』(※)のようなブラックジョークがお互いに好きなんですよね。そのノリはthe telephonesにも通じるものでもあるし、お酒もたくさん飲んでたので、本当にノーストレスで一緒にいられる仲っていうか。もちろん言語の問題はあるんですけど、共通して好きなワードがあるから、それだけで盛り上がれちゃう感じでした。誠治くん(松本誠治 / the telephonesのドラマー)はドラムのLeeさんが泊まっているホテルの部屋に泊まりに行ってましたからね。
※BEAVIS AND BUTT-HEAD(ビーバス・アンド・バットヘッド)
エクアドル共和国生まれのプロデューサー / アニメーター / 脚本家のマイク・ジャッジ原作のテレビアニメ。アメリカ合衆国の架空の都市・ハイランドを舞台にしたビーバスとバットヘッドによるブラックコメディ。
Jackass(ジャッカス)
子供じみたくだらないイタズラを大人があえてやるというコンセプトのアメリカの番組。Jackassは「馬鹿・まぬけ」という意味。危険を顧みないスタントや過激な内容が人気を博し、アメリカでは、真似をする大人や未成年者が後をただず、社会問題にまで発展した。

ーすごい、コミュ力高い(笑)。
Shiny:そのとき輝さんは酔っ払って、顔が真っ赤だったんですけど、急に真剣な表情で、エフェクターを踏む順番だったり、パフォーマンスについてだったり、僕がもっと成長できるポイントをたくさんアドバイスしてくれて。「僕のことをちゃんと見てくれている」と感じて、すごく感動したんです。僕のいいところも、改善が必要なところも、すべて見抜いていて、すごく信頼できるお兄ちゃんみたいだなって。
石毛:酔っ払ってたから覚えてないなあ……嫌われてなくてよかったです(笑)。
Shiny:とんでもない!(笑)

2007 年に結成されたPAPUN BANDのギタリスト兼ボーカリスト。初の大型イベント出演となった『台客ロックカーニバル』で、多数応募のあったバンドから見事優勝を果たす。2008 年の『コンリャオ・オーシャン・ミュージックフェスティバル』のオーシャンスター賞受賞をきっかけに、台湾全土の音楽フェスティバルや学園祭、その他のイベントに出演機会。これまでに、 4 枚のアルバムと 1 枚のミニアルバムをリリースし、“魚”のミュージックビデオは YouTube で 1900 万回以上の再生回数を記録したほか、“我沒有用,辦沒辦法給你想要的生活”や“月旁月光”などのMVを世界中のファンから注目を集めている。
ーお互いの好きな音楽の話もしたんですか?
石毛:しましたね。僕はもちろん日本のアーティストも好きだし、Shinyも台湾のアーティストが好きだと思うけど、アジアのミュージシャンがアメリカやヨーロッパに憧れてる感じも共通してる気がするんです。今でこそそういう話ができる友達はたくさんいるし、聴く音楽も少しずつ変わってきたけど、僕が10代の頃はそういう話ができる友達が全然いなかったから、国を越えて友達ができたのがすごく嬉しかったんですよね。
ーShinyさんも若い頃は欧米の音楽からの影響を受けて自分の音楽を作ってきた?
Shiny:そうですね。子どもの頃からずっと洋楽を聴いて育ちました。最初に聴いたのはマイケル・ジャクソン、その後はLinkin Park。特に大きな影響を受けたのは、blink-182、SUM41、Weezer、Simple Plan、Limp Bizkitといったバンドで、今の自分の音楽の基礎になってますね。
INDEX
アジア人である以上、アジアの旋律やフレーズを出していかないと、本当にオリジナルなものはできない。(石毛)
ー石毛さんが別のインタビューで、若い頃は欧米の音楽から影響を受けていたけど、最近は自分たちがアジアのバンドとして、いかにオリジナルな音楽を作っていけるかを意識するようになった、という話をしていたのを拝見しました。それは今回のコラボにも繋がる話かなと思ったんですけど、今はそういう意識が強いですか?
石毛:そうですね。若い頃は尖りも含めて、「絶対に洋楽の方がかっこいいじゃん」みたいな感じだったけど、海外の音楽を100%真似することは日本人である以上は難しいので、サウンドのデザインや曲の構成を自分の血肉にしたとして、あとは自分がアジア人である以上、アジアの旋律やフレーズを出していかないと、本当にオリジナルなものはできないと思ったんです。そう思うようになったのと同時期に、韓国の音楽とかが世界に台頭してきた。時代の流れも痛感してたし、最近の若い日本のミュージシャンはそれが自然にできてる気がします。自分が音楽を作るときは日本人であることを意識してますね。
ー日本人であり、「アジア人」という意識もある?
石毛:ありますね。やっぱり近年の『Coachella Valley Music and Arts Festival』(※)とかを見ると、アジアのみんなが集まって一つのことをやるのは、今までの音楽史ではなかったことなので、すごく嬉しく思ったし、自分たちも混ざれるぐらい頑張りたいと思えたのも事実で。そういう意味で台湾もそうだし、韓国やタイの音楽とかも聴くようになって、やっぱりすごく面白いバンドが多いなと思いますね。
※2022年には、ショーン・ミヤシロ率いる88risingがメインステージで披露した『Head in the Clouds Forever』に宇多田ヒカル やインドネシアのアーティストリッチ・ブライアンら、多くのアジア人アーティストが登場。翌2023年には、BLACKPINKがアジア人初となるヘッドライナーを務めた。

ー先ほど『AKIRA』の話もありましたが、Shinyさんは日本のポップカルチャーがかなりお好きだそうですね。
Shiny:日本についての知識はまずゲームで知りました。子どもの頃から任天堂やPlayStationなどのゲームで遊んでいたので、自然と日本に興味を持つようになって。日本の文化が好きで、日本に行くたびにたくさんおもちゃを買うんです。特に中野に行って、アニメや漫画、ゲーム関連のものを買うことが多いですね。
ーアニメや漫画で特に好きな作品はありますか?
Shiny:『AKIRA』はアニメも漫画も大好きです。あとこれも好きです(スマホで松本大洋の『鉄コン筋クリート』の画像を見せる)。
石毛:松本大洋だ。『ピンポン』とかね。
Shiny:『ピンポン』もわかります。
石毛:(映画では)SUPERCARが曲をやっていましたよね。
ーお互いのバンドや国への興味がありつつ、実際のコラボレーションに至ったのはどういう経緯だったのでしょうか?
Shiny:あるとき『ドラゴンクエストⅪ』をプレイしていて、“LV99 勇者”のメロディーやサビのベースができたんです。その後に続編の『ドラゴンクエストⅤ』をプレイして、やっとサビも完成したんですが、曲全体を完成させることはできなくて。しばらくそのままにした期間があったんです。
そんなときに、the telephonesと出会って意気投合して、「“LV99 勇者”の完成にはthe telephonesが必要なんじゃないか」と直感的に思ったんです。それでマネージャー経由でコラボをお願いしたら、快諾してくれて、ついに曲を完成できました。最後に「仲間」と出会って、『ドラクエ』にインスピレーションを受けた曲が完成したんです。
石毛:スバラシイ!
Shiny:スバラシイ! テンサイ! アキラ!
石毛:テンサイ! シャイニー!


INDEX
サントラを聴くためだけにゲームを起動することもあるくらいゲーム音楽が好き。(Shiny)
ーいい関係性ですね(笑)。じゃあ今回のコラボ曲が2曲ともゲーム音楽がテーマになっているのは、特に話し合って決めたわけではなく、もともとShinyがドラクエを基に曲を作ったから、石毛さんもゲームを基に曲を作った、みたいな流れなんですか?
石毛:そうですね。Shinyから最初にもらったデモにゲームっぽい音が入っていたので、それに乗っかる形でアレンジをして返したんです。で、それを聴いて僕も曲を作りたくなっちゃって、できたのが“Zan“讚””。ゲーム要素をこの曲にもめちゃめちゃ入れたら“LV99 勇者”と親和性も出て、結果オーライでした。2バンドで曲を作るなら、何か共通してるものはあった方がいいと思ったし、それがゲームだったっていうのは、きっとお互いの中に潜在的にあったもので、だから自然と出てきた感じじゃないですかね。
ーShinyさんはもともとゲーム音楽がお好きだったんですか?
Shiny:そうですね。『キングダムハーツ』の街のBGMも好きだし、オープニング音楽も好きです(スマホで『クロノ・クロス』や『封神演義』の画像を見せる)。これらの音楽を聴くために、ゲームをわざわざ起動していたくらいです。
ーShinyさんは『ペルソナ』の音楽もお好きだそうですね。
Shiny:本当に大好きです。ゲームを語る上で、サントラが果たす役割も大きいと思います。サントラCDが付属する豪華版も購入して、iTunesに入れて何度も聴きました。『ペルソナ』のサントラ音楽を聴くためだけにゲームを起動することもあるくらいです。

ー今やゲーム音楽は世界で聴かれる日本の音楽の1ジャンルとして確立されていて、『ペルソナ』シリーズを手がけるアトラスサウンドチームはSpotifyが2024年末に発表した「海外で最も再生された国内アーティスト」のランキングで3位だったりするんですよね。
石毛:僕は『ペルソナ』はやってないので、誠治くんとかノブ(岡本伸明 / the telephonesのシンセサイザー)に聞いて、いろいろ教えてもらったんですけど、確かに独特というか、他の国ではあんまり聴いたことがないような音楽ですよね。ジャンル名でも上手く形容できない、そういう日本の音楽が海外でも評価されるというのは、すごくいい時代だなと思います。
Shiny:日本と比べたら、台湾生まれのゲームは1990年代の『軒轅剣』くらいしかないし、完成度も日本のものほど高くなくて。日本のゲーム音楽は本当にレベルが高いなと思います。
INDEX
「『ドラクエV』はビアンカ一択!」で生まれた、制作のグルーヴ
ーそういう背景もありつつ、“LV99 勇者”に関しては『ドラクエ』からインスピレーションを受けて作られていると。
Shiny:今思い出したんですけど、日本でのレコーディングの前日、the telephonesのみんなと食事をしたときに、誰からともなく「『ドラクエV』の花嫁を選ぶなら誰」という、ゲームをやったことがあれば一度は経験する話題になって。僕はビアンカ一択なので、「ビアンカ」と答えたらみんなも「ビアンカ!」と叫んでて(笑)。台湾ではあんな風に「ビアンカ!」で盛り上がったことはないから、本当に感動したし、今でもあの夜のことを覚えてますね。音楽的にも同じスピリットを共有する人たちと一緒に「ビアンカ!」と叫べるなんて、本当に貴重な経験でした。
ー『ドラクエⅤ』でビアンカとフローラのどっちを選ぶかはゲーム好きの中で必ず盛り上がる話題ですが、国を越えて盛り上がるテーマになっているとは(笑)。石毛さんは最初のデモを聴いてどんな印象を受けて、どんな要素を足したら面白いと思いましたか?
石毛:すごくPAPUN BANDっぽい曲だったんですけど、もっと彼ららしさを押し出した曲にしたいと思いました。ポップパンクの要素を足してみたり、『ドラクエ』っぽい階段を下りる「ジャッジャッジャ」みたいな音をシンセで作ってみたり。僕が勝手にShinyの頭の中を想像して、もっとこうしたら喜ぶんじゃないか、みたいな感じで作りました。
Shiny:輝さんのアレンジは本当に素晴らしかったです。僕がこの曲でやりたいことを全て見抜いて。どうしてこんなにも僕のことをわかっているのかと驚くくらいでした。例えば、イントロを自分で作ったときに、うまく表現できなかったゲーム音楽っぽい感じも、輝さんが手直しして送ってくれたら、まさに僕が頭の中で思い描いていた通りのサウンドになってたんです。お互いにつたない英語でやり取りしていたにも関わらずデモが送られてくれるたびに、「なんて素晴らしいんだ!」とびっくりしたし、僕のアイデアを送ると、輝さんは必ず褒めてくれて。素直な気持ちを伝えながら、全てがスムーズに進んだ奇跡みたいな制作でした。輝さんは神様です!

ー“LV99 勇者”の歌詞は日本語・中国語・英語の3カ国語が混ざっていてすごくユニークですが、どのように作っていったのでしょうか?
Shiny:最初にコラボが決まって歌詞を書こうとしたとき、頭の中に突然<もしもし だれ>というフレーズが浮かんできたんです。僕が知っている日本語はとても簡単なもので、「もしもし」とか「すみません」とか、台湾人なら誰でもわかるような言葉だけなんですけど、あと『進撃の巨人』もすごく好きなので、<進め>という言葉もどうしても入れたくて。
石毛:そこからだったんだ!
ー「もしもし」は世界の共通言語なんですね。
石毛:イギリスにもMoshi Moshi Recordsという名前のレーベルありますしね(笑)。
Shiny:<Don’t wanna say goodbye>は自然に出てきたフレーズで、一つの曲に3ヶ国語もあると複雑かもなと心配でしたが、直感を信じてそのまま進めました。
ー“Zan“讚””はどのようなアイデアから作っていったのでしょうか?
石毛:「讚」は、僕らが10年ぐらい前に台湾でツアーやフェスに出させてもらったときに覚えて帰ってきた向こうの言葉のうちの一つで、「いいね」とか「最高」、「素晴らしい」という意味で。当時ノブがことあるごとに「讚! 讚! 讚!」って言っていて(笑)。僕らが作る曲のタイトルはもう「讚」しかないなと思ったので、サビのシンガロングパートから作りました。
ー“Zan“讚””は『ツインビー』がモチーフになってるんですよね。
石毛:最初に曲の本筋を作って、このメロディーと相性がいいゲームを探したんです。曲自体がすごく80sな、レトロな雰囲気があるので、ファミコンのゲームがいいなと思っていたときに、『ツインビー』のテーマをアレンジしてみたら上手くハマったんです。ベルの色が変わる音をシンセで作るのとか楽しかったですね。
ーShinyさんは“Zan“讚””を聴いてどんな印象でしたか?
Shiny:本当に本当に本当に本当に大好きです! 特にサビのギターが最高で、まるで「一目惚れ」というか「一耳惚れ」みたいな感じでした。この曲は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』みたいな感覚になるんです。輝さんが何を歌っているのかはわからなかったのですが、歌詞を入れてほしいと頼まれたので、<Back to the future / Everybody coming>というフレーズを加えてみました。
石毛:テーマがシンセウェイヴとかレトロウェイヴ系の、The Weeknd以降のものを作ろうと思ってたので、そこから『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を連想してくれたのはすごく嬉しかったし、歌詞ももちろんなんですけど、メロディーもShinyが作ってくれて、めっちゃいいなと思って。
Shiny:“Zan“讚””の制作過程はすごく印象に残っています。台湾でミックスをしていたときに、輝さんが修正したい箇所を伝えてくれたのですが、言葉が専門的で、翻訳が難しかったんです。でも、おざなりにはしたくなかったので、日本語のまま伝えてもらいました。輝さんが真剣に話す日本語に向き合っていると、言語がわからないなりに伝えたいことを感じ取ることができたんです。エンジニアの人にも伝えて修正したら、輝さんが大きく頷いてくれて。言語を超えて意思疎通ができたことが、本当に不思議で感動しました。言葉ではなく、感覚や感情でつながるソウルメイトになれた気がしたんです。
ー“Zan“讚””は7ORDERの諸星翔希さんによるサックスもすごく印象的でした。
石毛:今までこういう曲を作った時はサックス吹きが知り合いにいなかったのでギターで弾いてたんですが、7ORDERのモロと出会って、友達にサックス吹きができたんですよ。
ー2022年に対バンをして、そこから親交を深めたそうですね。
石毛:そう。今後お願いできるなと思っていたら、まさに“Zan“讚””がそのタイミングで。PAPUN BANDが最初に来日したときに、打ち上げにモロを呼んだら、みんなとも仲良くなってて。そこでお願いしたら、みんなの雰囲気もわかってるし、想像以上のサックスを吹いてくれた。最高でしたね。
Shiny:モロさんには本当に感謝しています。初めて演奏を聴いたとき、感動して泣きそうになりました。輝さんがモロさんのことをちゃんと紹介してくれたのもとても嬉しくて。僕が曲を聴いて『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を連想したのは、モロさんのサックスに「記憶」や「回想」を感じさせるような力があるからだと思います。