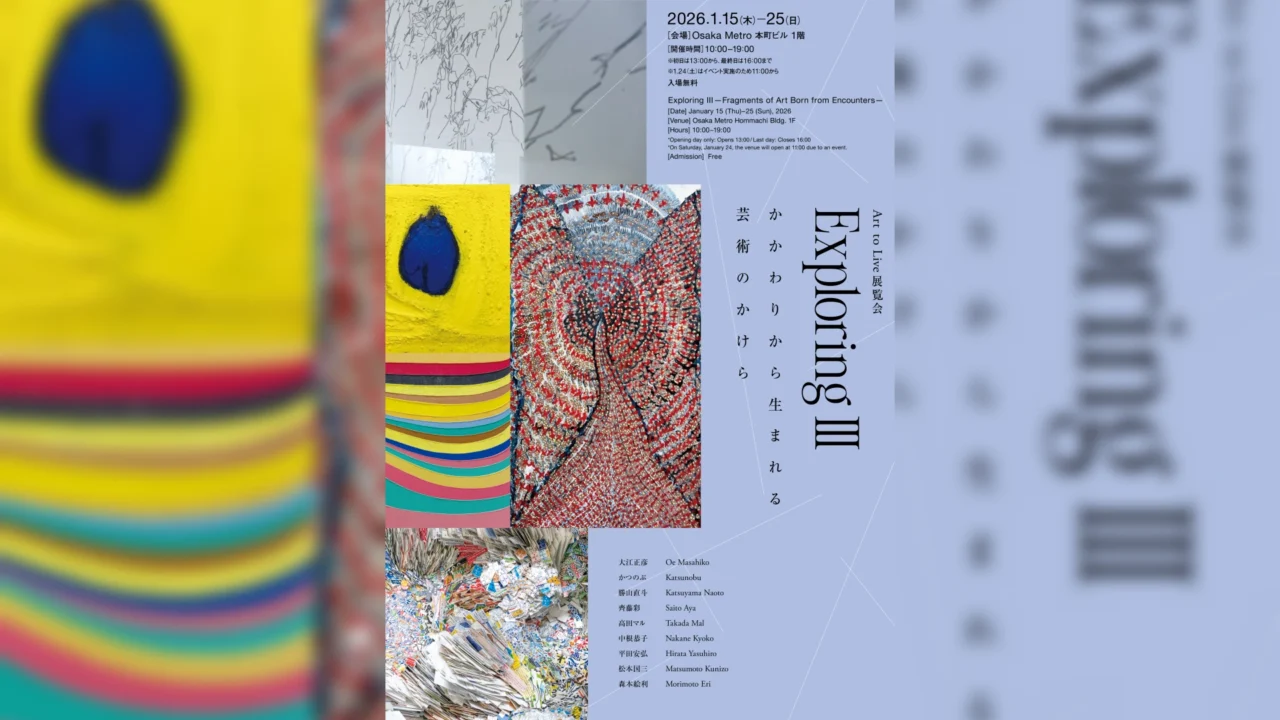『水曜日のダウンタウン』を筆頭に、飽くなき攻めの姿勢で作品を作り続けるTVディレクターの藤井健太郎。
スペースシャワーTVのアーカイブサイト「DAX」のインタビュー企画「My Favorite X」特別編として、NiEWにてテキスト形式でのインタビューが実現。
ヒップホップに傾倒した経緯から、 地上波マスメディアで賛否を呼ぶ番組を作り続ける意図を語ってもらった。
INDEX
ヒップホップ好き、藤井健太郎の10代
―相変わらずお忙しそうで。
藤井:ありがたいことに配信系の仕事もオファーを頂くので、可能な範囲で受けつつ、そういった配信番組も『水曜日のダウンタウン』も全部編集は自分でやっちゃっているので、「この齢でまだ徹夜するのか……」とか思いながら、相変わらず休みなくやってます。
―でも、自分で編集しないと気が済まない。
藤井:そうですね(笑)。やると結局そうなっちゃうので、これ(『水曜日のダウンタウン』)が終わったら、自分が演出を担当する形でのレギュラー番組はもうやらないつもりですけど。やっぱり、途中から降りることは出来ないじゃないですか。その理由が「自分がしんどいから」ってのもちょっとカッコ悪いし。
―ところで、藤井さんと言えばヒップホップ色が強いイメージですが、最初に音楽に夢中になったのはいつ頃ですか?
藤井:たぶん中1中2ぐらいのときに、スケートビデオでかかっていたヒップホップとかパンクとかがJ-POP以外の音楽との出会いで。『100%RAP』や『RAP To The MAX』っていうヒット曲のコンピに、K7やヴァニラ・アイスとかの一発屋系と並んで入っていた、Run-DMCとかNaughty By Natureを聴いたのが、ヒップホップの入口だったと思います。中学はほぼ洋楽オンリーでしたけど、中3の終わりから高1にかけてが、キングギドラやBUDDHA BRANDが出てきてシーンが盛り上がってきたタイミングだったので、その頃からは日本語の曲も聴くようになった感じです。『さんピンCAMP』は高1の夏でした。
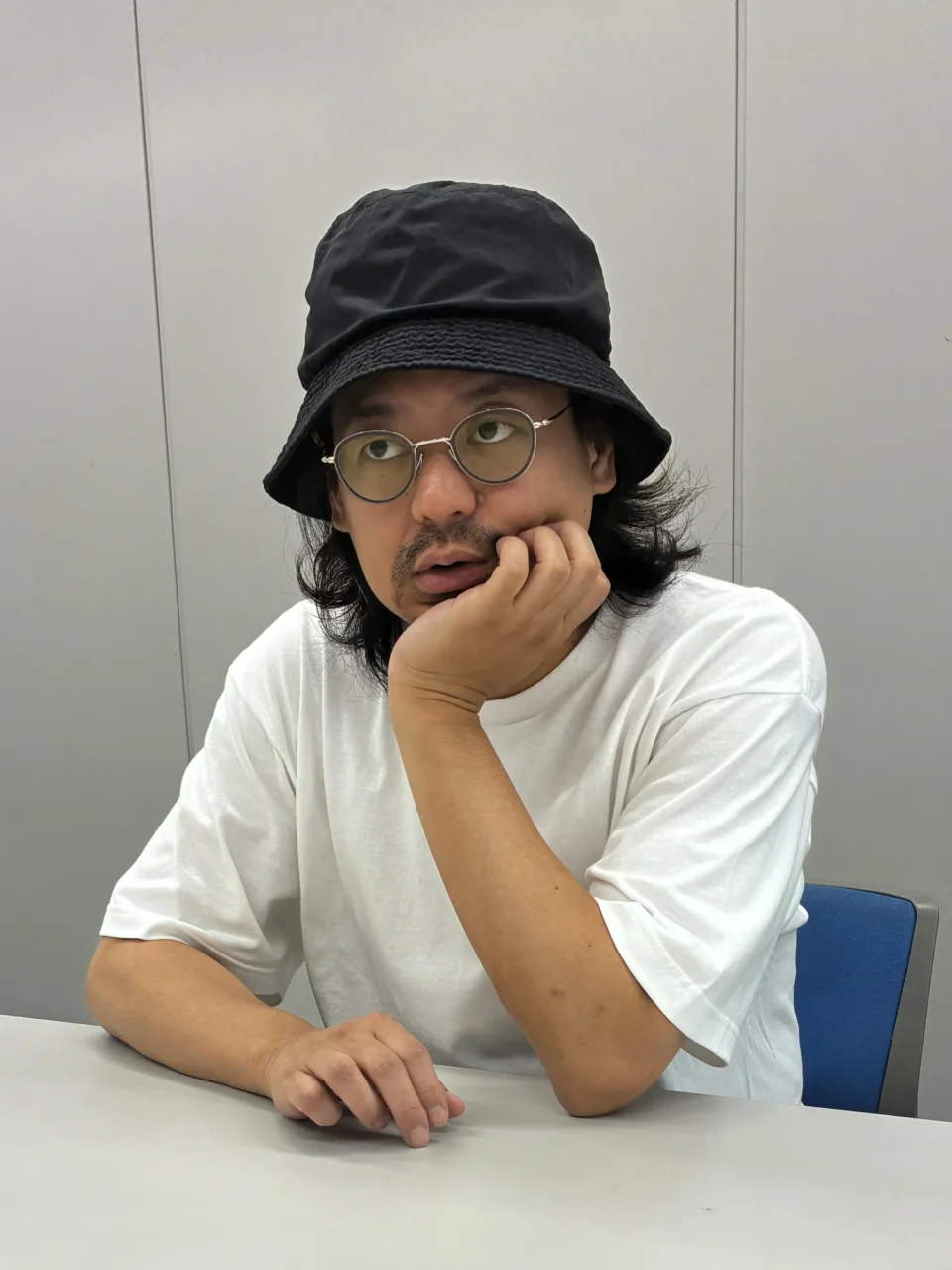
TVディレクター。1980年生まれ、東京都出身。大学卒業後にTBSテレビに入社。『クイズ☆タレント名鑑』等の演出・プロデュースを経て、現在は『水曜日のダウンタウン』『クイズ☆正解は一年後』『オールスター後夜祭』などの番組を手がける。
―出身は東京ですよね? 周りの友達も日本語ラップを聴いてたんですか?
藤井:聴いてましたね。いわゆる高校生がパー券を売ってイベントをやっていた時代で、基本高校生のパーティで流れるのはヒップホップだったし、周りはみんな日本のヒップホップも聴いてましたね。ただ、それでラップを始めるってヤツは当時まだほとんどいなくて、逆にDJは高校生のイケてる趣味の代表っぽいところがあったので、自分も中3の時にターンテーブルを買って、DJをやってたりはしました。
―著書『悪意とこだわりの演出術』(2016年)では「『さんピンCAMP』には行けなかったけれど、年越しの『鬼だまり』には行きました」と書いてますね。
藤井:そうですね。別に変な入り方をした記憶はないんで、16歳でも普通にオールナイトのイベントに入れちゃった時代なんだと思います。
―16歳で『鬼だまり』に行くのって、早くないですか?
藤井:いや、一緒に行った2歳上の先輩はオープンマイクのステージに上がってましたし、そんな感じはなかったと思いますよ。当時、高校生だった般若さんも鬼だまりのステージに上がってたはずですし。
―『さんピン』や『鬼だまり』とは別に、いわゆるLBネイション(スチャダラパーを中心とした日本のラップグループ・クラン)周辺は聴いてましたか?
藤井:いや、当時はいわゆるのハードコアなスタイルが目新しくて、そっちに強く惹かれていたので、LB周りはそこまで積極的にチェックしてなかったですね。今となれば、結局、スチャダラがある意味一番ハーコーだったんじゃないかって話なんですが、15、6歳の頃は、それまで音楽の中では聴いたことのなかった言葉が飛び出すリリックにグッときてしまってました。
―その当時一番好きなアーティスト、曲は?
藤井:当時は「日本語で韻を踏む」ってことが目新しくて、面白く感じてたので、やっぱり最初はキングギドラですかね。で、一番好きだった曲はK DUB SHINEソロの“スタア誕生”だったと思います。ストーリーテリングのスタイルに触れるのも当然初めてだったので、衝撃を受けました。Kダブさん、今はなんとなく面白キャラみたいになっちゃってますけど、もっと真っ当にリスペクトされる存在になってた道もあったんじゃないかな、と。
INDEX
「僕の番組が本質の部分で嘘をついていることはないし、かなり誠実に作ってる方だと思う」
―自分は『第三会議室』(※)のプロデューサーでもあったので、若干責任は感じてます(笑)。仰る通り、彼は優れたリリシストですし、過小評価されてる面はあると思います。さきほど“スタア誕生”の話が出ましたが、その頃からドキュメンタリーに興味があったんでしょうか?
※スペースシャワーTVの音楽番組『Black File』中のトークコーナーで、宇多丸とK DUB SHINEが出演していた
藤井:『ゆきゆきて、神軍』のようなスタンダードな作品は見てましたけれど、本格的に興味を持ち始めたのはこの仕事を始めてからですかね。やっているとどうしても「素材が強いもの」に惹かれてしまうんですよね。本も、学生の頃は小説も読んでましたが、社会人になってからはノンフィクションばかり読むようになってしまいました。
―先日、自分がプロデュースした純烈のドキュメンタリー映画にコメントを頂いた際にも、「途中から純烈よりもあの夫婦が気になってしまいました」と仰ってましたし。
藤井:とくにあの旦那さんは気になりましたよね。もっとあの夫婦を見てたかったです。
―そこは(カンパニー)松尾さんも同意見でした。ただ、ここは意見が分かれるところでもありまして、何故藤井さんが「攻め続けるテーマ」ばかり採用してしまうのかなんとなく分かるエピソードだなと。藤井さんの作品はドキュメンタリーの要素が強いと思いますが、藤井さんにとって「ドキュメンタリー論」的なものはありますか? 「ドキュメンタリーとは真実を映すものである」「ディレクターの意図が入ってはならない」と認識してる人もいるかと思いますが。
藤井:自分で作ってる人もそう思うんですかね? 編集経験のある人がそう考えるとはあんまり思えないですけど……編集した時点で「どこを強調するか」というディレクターの視点は避けられないし、それ自体が嘘でないのは大前提として、当然、誰かの気持ちは入ってしまいますよね。
―撮影する時点で演者をけしかけることはあるんですか?
藤井:うーん、選択肢として右と左があったとして、どっち側に転んでくださいと誘導することはないと思います。ただ、その転ぶ地点まで誘導することはときにあるかもしれないですね。まぁ、僕の番組が本質の部分で嘘をついていることはないですし、自分の知りうる限り、テレビ番組の中ではかなり誠実に作ってる方だと思います。
―誠実に作れば作るほど、逆に風当りも強くなる面もありますよね。
藤井:最近だと、見る前から「これはテレビで放送して大丈夫なのか?」とか心配する人もいますからね。どのくらい本気で言っているのかはともかく、視聴者の立場でその心配をする感覚があまり理解できないんですけどね……。
―自分の周りでも「これ大丈夫なの?」って心配する人は増えました。
藤井:食べ物だって「美味しそうだけど、カロリー高いな」って思って食べるより、シンプルに「美味しそうだな」って思って食べる方が、食事を楽しめるじゃないですか。しかも、カロリーは確実に自分に影響しますけど、番組の方はとくに影響しないことの方が多いですし(笑)。
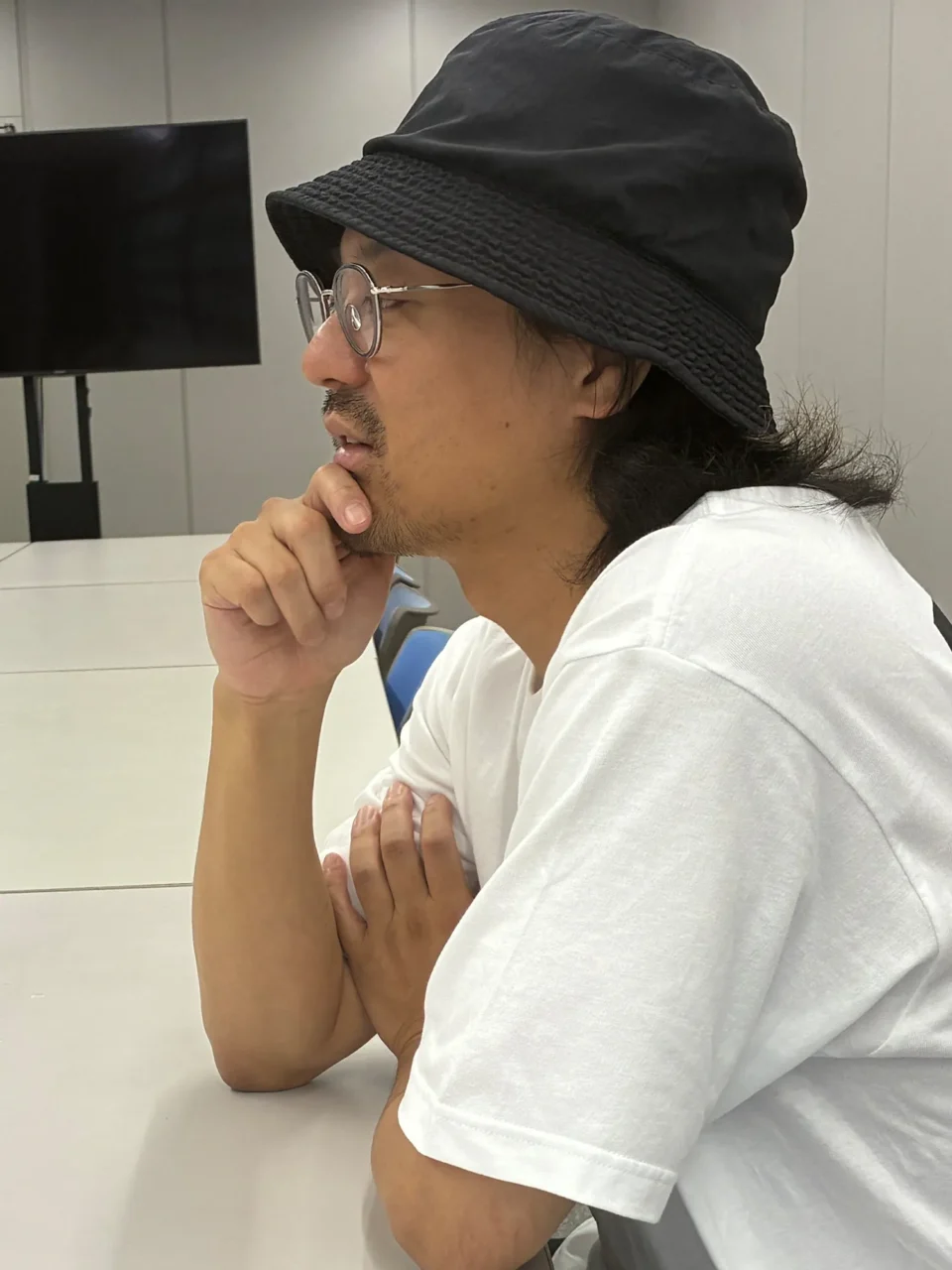
INDEX
抗議を避けようと思ったら「触れないのが一番」になってしまう
―と言いつつ、先日放送された「インディアンス改名ドッキリ」に関しては、藤井さんのXで告知を見た瞬間に「これはヤバいのでは?」と思いました。
藤井:まあ、この回って放送を見てもらえれば分かるんですけど、ネイティブアメリカンの方々への差別的な表現というのは当然なくて、問題があるとすれば、その差別に対して「抗議を行っている人」の描き方ですよね。番組には「変なテレビプロデューサー」も出てくれば「変な学校の先生」も出てくるわけで、それと同じことだとは思いつつ、センシティブなネタではあるので、通常の「抗議を行っている人」とはちゃんと切り離して見てもらえるように、明確に「変な人」にしたつもりではあったんですけれどね。まぁ、何にしても、この回に対してSNS上で何か言っていた人は、基本、放送自体は見ていなくて、告知の文言を見て勘違いをした人がほとんどだったので、その辺はもうちょっと注意するべきだったなとは思いますけど。で、ちなみに放送を見た人から実際に局に対してきた抗議は「ネイティブアメリカンを差別するな」よりも「ベッキーを出すな」の方が多かったというオチです。まぁ、この手の問題は、そういう面倒を避けようと思ったら、ただ「触れなければいい」だけになってしまうので、それはそれでどうなんだという気持ちもありますよね。
―このインタビューシリーズ「My Favorite X」の第1回に登場した東出昌大くんも、以前「世の中、真っ白なことなんてほとんど無いのに、とにかく漂白しよう、潔癖にしようという流れには抗いたい」と言ってました。
藤井:そうですよね。もちろん自分たちも気をつけてはいて、この時も、事前に専門家の方や複数の弁護士さんに相談して「ここの言い回しはこうしよう、この表現は避けよう」などと話し合いや修正を重ねています。特に地上波は不特定多数の方が見るメディアですし、その分いろんな意見も寄せられるわけですが、とにかく抗議を避けようと思ったら「触れないのが一番」になってしまうので、タブー化していくわけです。それで、結果、一番損をしてしまうのは当事者の方々だったり……というのもよくある話なので。ところで番組を見てどう思いました?
―自分は番組の内容自体に問題があるとは思いませんでした。ただ、藤井さんも仰るように「抗議する団体」を面白く描くことに「大丈夫なのか?」と感じた部分はあります。一方で、何故自分がそう思うのか、むしろそういった抗議団体の方々をある種差別的に捉えてしまってるのではないか、と自問しました。
藤井:当然、出てくれた出演者が損をしたり悪く見えるようには番組を作らないじゃないですか。なので、その分番組を盛り上げるために僕ら番組サイドが悪者になるのは構わないし、もっと言えば自分たちをよく見せようとするヤツってちょっとキツいんで(笑)、それが当たり前だと思ってきたんですけど、最近はその境が本気で分からなくなっている人も増えてきたなという印象があって。悪役プロレスラーをプライベートでも悪人だと思っている的な、それは、ちょっと怖いとは思ってますけどね。
―お話を伺ってて、藤井さんは一体何をモチベーションに番組を作ってるのだろうか? と益々わからなくなってきました。
藤井:(笑)。ホントにそうですよ。自分が納得するものを作って、多くの人に面白いと思ってほしい……という気持ちはもちろんあるんですけれど、高視聴率が取りたくて作ってるわけではないし、賞が欲しくてやってるわけでもないし。
―出世するために番組を作ってるわけじゃないですしね。
藤井:評価はしてほしいですけどね。出世=「経営に携わること」ならそこに興味はないと言いますか。会社の経営陣を見て楽しそうだなともあまり思えないですし(笑)。
―藤井さんの特異性は、そんなチャレンジングな姿勢を続けられるところだとも思ってます。しかもそれを地上波のゴールデンタイムで続けているという。頻繁に非難にさらされるのは、メンタル的にもキツイと思いますが……。
藤井:繰り返しになりますが、何より「面倒だから触れないでおこう」というのは一番良くない気がするんですよね。ただ、かといって「社会に切り込んでやろう」ともまったく思っていなくて。面白そうなものがあれば、そこに貴賤はなく、取り上げているという感じですかね。
―最後の質問です。どうやったら藤井さんみたいに独創的な作品を組織の中で作り続けられるんでしょうか?
藤井:自分はとくに師匠のような存在もいなくて、ほぼ独学でこうなったんですけど、ただ、ディレクターになりたての頃はややアシスタント的なポジションで動いてた時期もあって、その時はやっぱり上の影響も受けるので、自分の得意な型を見失いそうになりました。なので、自分の下で働いてるスタッフたちも、あまり長くそこにいすぎない方が良い気はしていて。やっぱり誰かの影響を受け過ぎちゃうと、本来の自分の得意なところを見失ってしまう気がするんですよね。
―天才らしいお言葉です。
藤井:いやいや、自分で言うのも何ですが、むしろ努力型だと思いますけどね。だから、天才だと褒められるよりも頑張ってることをもっと褒めてほしいですよ。じゃないと、続けるのしんどくなってもう番組作り辞めちゃいますよ(笑)。

『水曜日のダウンタウン』
毎週水曜夜10時から
https://www.tbs.co.jp/suiyobinodowntown