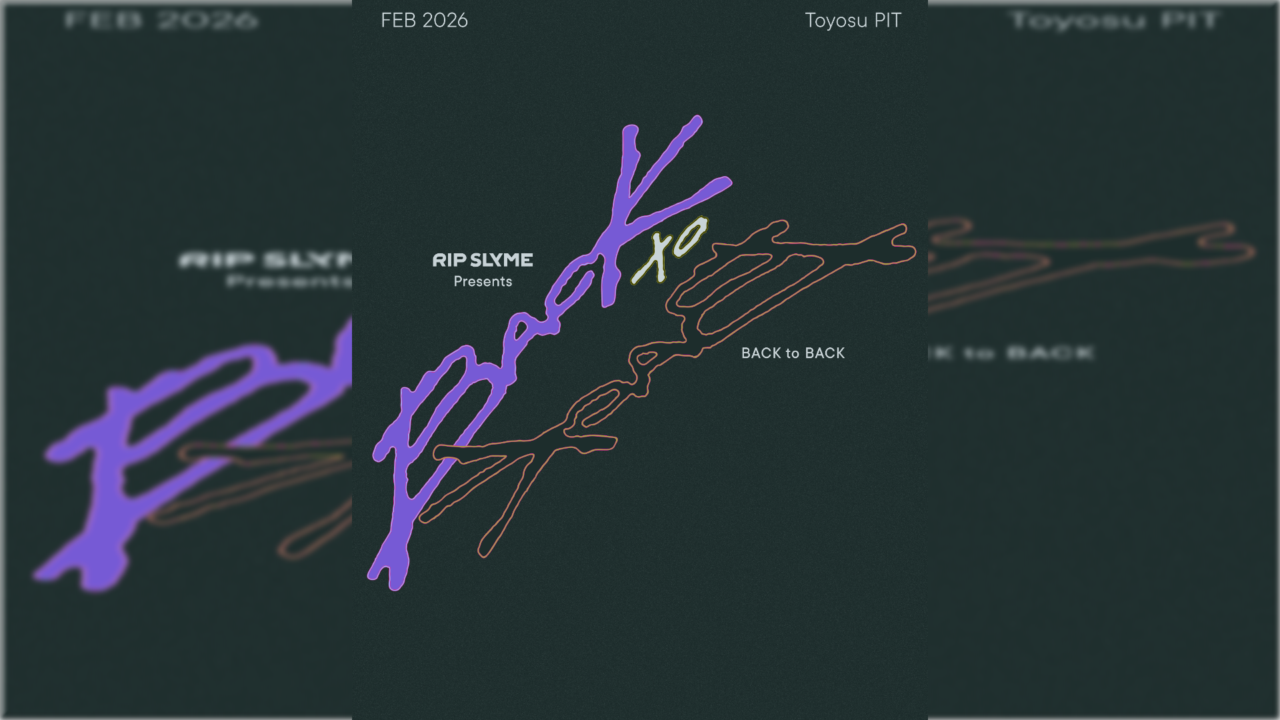現代中国映画の巨匠、ジャ・ジャンクー。激動の時代や社会のうねりの中で、もがきながらも生きる個人の生活や町の記憶を見つめてきた。
新作『新世紀ロマンティクス』は、2001年の中国WTO加盟と北京オリンピック開催決定から、2006年の三峡ダム建設、そして2022年のコロナ禍まで、ふたりの男女の軌跡を辿る物語だ。過去作『青の稲妻』『長江哀歌』のフッテージ、ドキュメンタリー、フィクションが混然一体となった、新鮮な作りになっている。しかも同2作で恋人役だったチャオ・タオとリー・チュウビンがそれぞれの役名で再び登場し、映画内で自然に年を重ねていくのも見逃せない。
20年前に映画学生だった自分の時間、映画内の時間、日本と中国の時間がすべて繋がっているのだと、まさに映画という時間芸術でしかできない表現に胸が熱くなる。
今回NiEWでは、ジャ・ジャンクー監督へのインタビューが実現。激動の中国社会とその中で生きる個人、テクノロジーの発達における人間の感情と身体、場所と空間が持つ魅力について、思いを聞いた。
当時『青の稲妻』を絶賛し、「批評は時代と並走すること」と映画の楽しさを教えてくれた故・梅本洋一先生に、改めて感謝したい。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
長い時間軸で世界を見る視点が、今の時代にはとても大切
―『新世紀ロマンティクス』は『山河ノスタルジア』『帰れない二人』に続いて、長いスパンの物語です。「21世紀に入り、100年に一度と言われる変貌を遂げた中国」について、どんな課題や魅力があってこの映画を撮ったのでしょうか?
ジャ・ジャンクー:おっしゃる通りその3作品は、非常に長いスパンを扱っているんですよね。なぜそんな風に長い期間を描くのかというと、この10数年ほどで、インターネットの普及によって様々な細かい情報が脈絡もなく一気に流れ込んでくる時代になったからです。だからこそ、長い時間軸で世界を見る視点が、今の時代にはとても大切なんじゃないかと考えています。
―混沌とした時代だからこそ、俯瞰的な目で物事を見るということですね。
ジャ:私はある程度システム的かつ歴史的な視点を持って、物事を観察することが必要だと思っています。細かな情報ばかりを追っていると、結局は世界の一部、局所的なものしか見られなくなってしまいます。そうなると、歴史の理解や物事の本質が抜け落ちてしまう。なので、ある程度長いスパンで、歴史的な目線で物事を見ていく必要があると感じたんです。
それから、自分が年齢を重ねてきたこともかなり影響していると思います。自分の変化にも気づきますし、それと同時に社会の変化ともリンクしているんじゃないかと思うんですね。20歳過ぎの頃は目の前にあるものしか見ていなかったのが、今の年齢になって色んな視点で世界を見るようになり、それが撮影にも反映されるようになってきたと感じています。

1970年生まれ、中国山西省・汾陽(フェンヤン)出身。93年に北京電影学院文学系(文学部)に入学。初長編作『一瞬の夢』が98年ベルリン国際映画祭フォーラム部門でワールドプレミア上映され、ヴォルフガング・シュタウテ賞(最優秀新人監督賞)を受賞したほか、プサン国際映画祭、バンクーバー国際映画祭、ナント三大陸映画祭でグランプリを獲得、国際的に大きな注目を集めた。06年、三峡ダム建設により水没する古都・奉節(フォンジェ)を舞台にした『長江哀歌』がヴェネチア国際映画祭金獅子賞(グランプリ)を受賞。13年、『罪の手ざわり』がカンヌ国際映画祭脚本賞を受賞。15年、カンヌ国際映画祭でフランス監督協会が主催する「金の馬車賞」を中国人監督として初めて受賞。17年、平遥国際映画祭を創設。現在、中国映画監督協会の代表。名実ともに、現代中国を代表する映画監督である。
―文化センターでの毛沢東の絵が印象的で。この映画を中国社会史的な文脈と、どう接続させようと思ったのでしょうか?
ジャ:あのシーンは2001年に文化センターを訪れた時に、たまたま撮ったショットなんです。2001年というのは中国の改革開放が進み、計画経済から市場経済に移行している時期でした。その過渡期において、多くの工場労働者が解雇された時期でもありました。
その時、毛沢東時代を懐かしむ工場労働者もたくさんいたわけです。私はそのことについて批評するつもりはありませんが、労働者たちが非常に厳しい生活状況にあったのは確かです。毛沢東の肖像画のショットを通して、その時代の人々の思いや中国の文明を見つめることにしたのです。
―そんな社会情勢に翻弄される個人の姿を、監督は見つめ続けてきましたよね。今回『青の稲妻』『長江哀歌』でも恋人役だったチャオ・タオとリー・チュウビンが再び出てきます。どんな新しいチャオとビンにしようとしたのでしょうか。そして人が老いていくことに対してどのように感じていますか?
ジャ:2001年から今日まで、ふたりの変化も映画の中で記録されています。それぞれ異なる人生の過程を経て、様々な問題に直面し、ここまで来ているわけです。たとえば、人間は20年の間に健康状態が変わったり、体調を崩したり、病気をしたりするものです。人が絶えず変わり続け、老いていくという現実の中で、どんな生き方をするか。人生の価値観や生きる態度は、彼らふたりの間でも違ってくるわけです。
チャオは『青の稲妻』の時には、愛に寄りかかりたい、愛を追い求めている女性でした。しかし20年という道のりの中で、次第に自分のために選択し行動する、自立した強い女性へと変わっていきます。そうした年齢による人間の変化というものも、映画として追いかけたいテーマの一つでもあります。

INDEX
自分の足で運命に向かって進むこと、そして自分がそれを決めていく
―様々な音楽ジャンル、様々な質感の映像の中で、チャオは一言も言葉を発しません。表情と沈黙に語らせた意図は?
ジャ:撮影に入ったばかりの頃は、チャオに話をさせていました。彼女と周りの人々とのやり取りは、言葉で進んでいたわけです。しかし、その後でその言葉を取り除いたのには理由があります。この物語が描いている長い期間の中で、主人公に話をさせることが、かえって世界を狭めてしまうのではないかと思ったからです。むしろ、彼女の身体表現や目の力で、もっと広い範囲を物語るほうがいいと感じました。
また、これは中国の伝統的な考え方にも関係しています。空間になにもない状態から「有(ゆう)」が生まれる考え方、つまり「空(くう)は有(ゆう)」という意味があるんですね。そういった伝統的な手法を取り入れて、私は彼女に言葉を与えなかったんです。

―劇中には時代の変遷とともにパソコン、携帯電話、TikTok、ロボットがハッとする形で出てきますね。先ほど「自分の変化と社会の変化はリンクしているように思う」とおっしゃっていましたが、テクノロジーの発展は監督含め個人の内面や感情にどのような影響を与えていると感じていますか?
ジャ:私自身は幼い頃からインターネットに触れて育った世代ではありません。それでも、その後の世代、特に若い世代は、最初からインターネットがある社会で育っています。ですので、インターネットや科学技術が人間の情感に及ぼす影響は非常に大きいと思います。
インターネットが普及する前と後では、人間の感情に対する影響がかなり違っていると思います。インターネット普及前は、知っている人と交流する時代でした。でも今では顔も名前も知らない、どんな人かもわからない、未知の人と普通に交流する時代になっています。人と人との関係も以前とはまったく異なるものになっていますよね。
また昔なら愛し合うふたりが離れた場所にいると、その距離が生み出す様々な出来事が文学作品のテーマになったわけですが、今はすぐにSNSで繋がることができてしまいます。このように、インターネットやスマホが人間の情感に与える変化は非常に大きいと思います。

―バイク、列車、船、飛行機と様々な移動手段が登場する中で、チャオが最後に辿り着いたのが「自分の足で走ること」。あのラストシーンに込めた思いを教えてください。
ジャ:確かに2001年から振り返ると、移動手段はどんどん変化していきました。それらの変化は、人間の運命とまさに同じ速度で進んできたように思えます。チャオは自分の愛を追い続けてきましたし、ビンは自分の運命を変えるために外に出たいと思ってきました。だからこそ、ふたりは絶えず移動し続けているんですね。
その移動の中で、AIの出現や科学技術の進歩といったものに出会うわけです。そして辿り着いたラストシーン。最終的には「自分の足で運命に向かって進むこと、そして自分がそれを決めていくんだ」ということを描きたかったんです。