INDEX
中村茜のキュレーション作品を解説。歴史に遺されたものと遺されなかったもの、両面から考える
—中村さんにお聞きします。アル・カシミ芸術監督から何名か作家の紹介がありましたが、今回参加する日本の作家が抱える問題意識とつながっているようにも思います。
中村:今のお話はマユンキキが抱える問題意識につながってきます。共同体や文化が大事にしてきた言葉——それは書き言葉ではなく例えば彫刻や服飾、音楽が(支配者側の)博物館に納められてしまっているという歴史。和人により土地を奪われ、同化政策により言語や生活習慣、生業などの変更を余儀なくされた歴史がある。そんな歴史の中で彼女は、アイヌの女性だからこそ起こる“出来事”から着想を得て、作品にしています。でも、一方で彼女は「自分が作品を作らなくていい世の中になってほしい」という話をよくしています。
今回の作品でパフォーミングアーツでは、これまで共演・共作を行なってきたメンバーとともにマユンキキ⁺として参加するマユンキキがテーマにしたのは、三信鉄道(現JR飯田線)という鉄道と祖父の川村カ子ト(かねと)です。愛知県の豊橋から長野県の飯田方面まで続く長い鉄道で、史上最大の難所の一つと言われた険しい渓谷(天竜峡駅から三河川合駅まで)の測量を、彼女の祖父で旭川アイヌのリーダーでもあった川村カ子トが手がけました。それは非常に偉大な功績なんですが、近代化にはもちろん負の側面もつきまとっています。善いことと悪いことには連続性がありますよね。鉄道が開通することによって、人が住めるようになる。すると電気が必要で発電のためのダムができる。ダムを作る裏側には強制労働をさせられた人たちがいて、そこには朝鮮からの労働者も多かった。そうした負の遺産にもきちんと目を向けていきたいとおっしゃっています。
作品は、世代や地域を越えて分断したものを、新たにつなぎなおすように創作され、美術とパフォーミングアーツの両方で発表します。美術はサウンドインスタレーション、パフォーマンスは音や影絵が織りなす舞台体験を予定しています。

中村:アーカイブや記憶という意味ではAKNプロジェクトにも通ずると思いました。彼らは、沖縄が抱えている記憶を現代の人たちにどう継承していくかということを継続的に考えているチームで、戯曲『人類館』の3回目のリクリエーションに挑みます。もともとの戯曲は故・知念正真が書いたものですが、今回は20代と40代という世代の異なる女性演出家の視点で喜劇として作り直します。
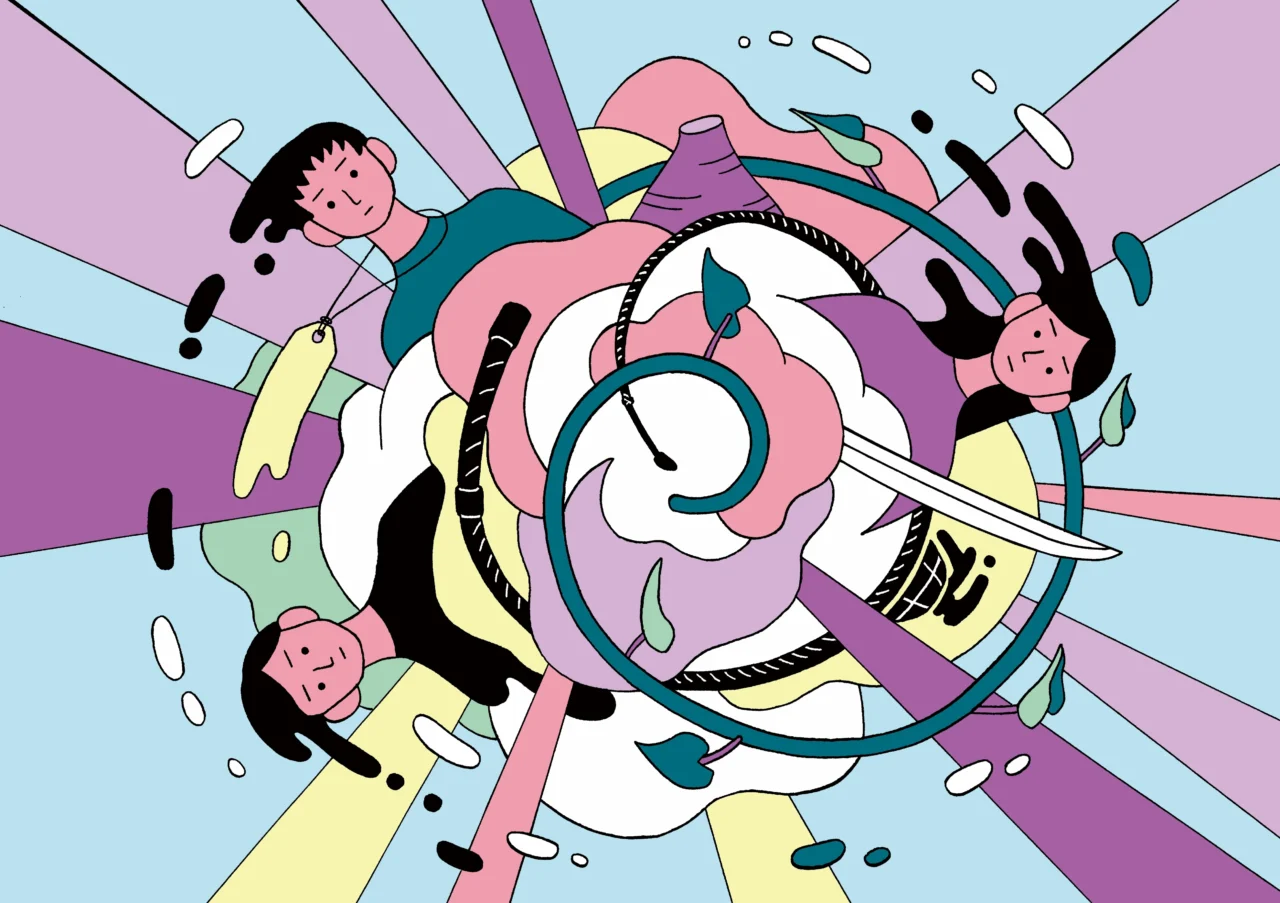
中村:先ほど「近代化の影響」という話が出ましたが、オル太の作品の重要なテーマになっています。今回、芸術祭の会場にもなっている瀬戸は、1000年以上続くやきもの産業が、近代化を経て、形を変えていきながらも継続している土地です。瀬戸のやきものの近代化を支えた大きなエネルギー資源の一つに石炭があります。そして、実はこれらの石炭の多くは、九州は筑豊の炭鉱で掘られたものでした。オル太の作品『Eternal Labor(エターナル・レイバー)』は、九州の筑豊、対馬、朝鮮半島に滞在し、炭鉱をはじめ近代化の歴史と現代へのつながりを掘り下げ、現代の女性の労働とも掛け合わせ、近代化の歴史を再解釈しています。




























