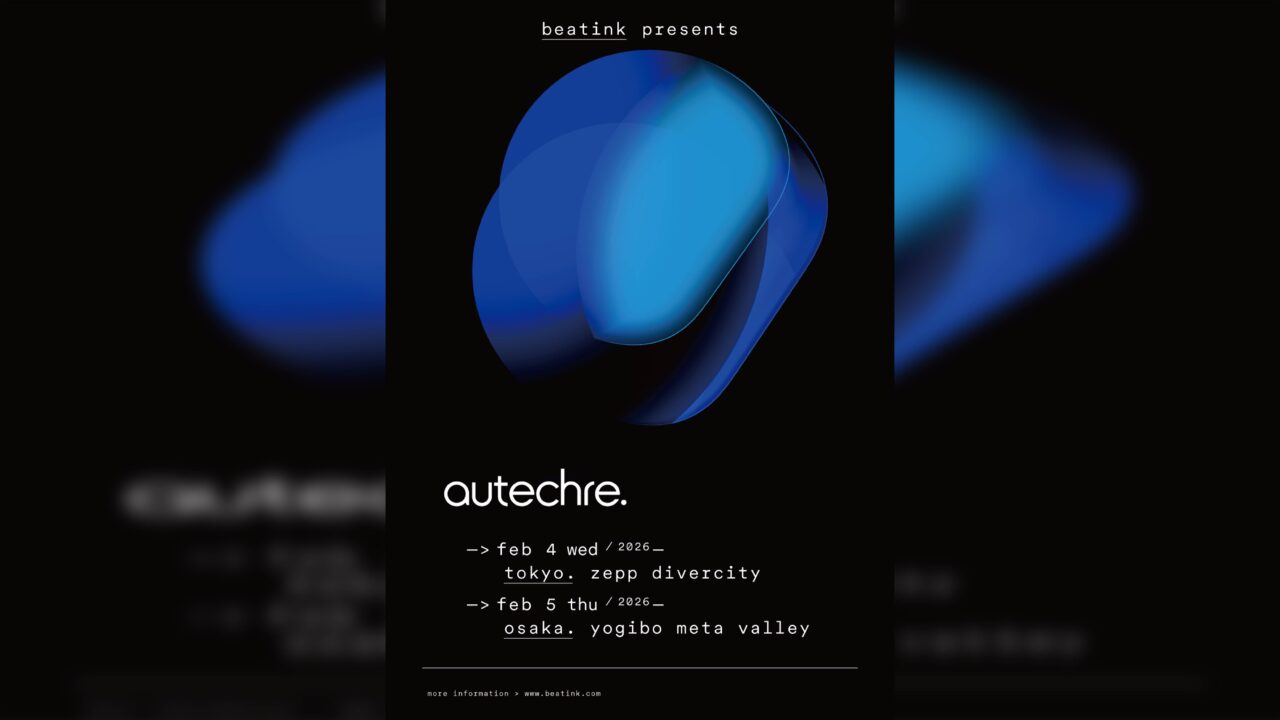日本でも興行収入3億円を突破する大ヒットを記録した『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』をはじめ、いま香港映画の躍進が目覚ましい。
2025年3月14日(金)〜23日(日)に開催された『第20回大阪アジアン映画祭』では、「Special Focus on Hong Kong 2025」と題した特集プログラムが組まれ、新潮流の多様な香港映画が上映された。
本記事ではその中から、香港で『トワイライト・ウォリアーズ』を超えて広東語映画の歴代観客動員数No.1を記録した『ラスト・ダンス』、聴覚障がいを繊細に描いた青春映画『私たちの話し方』など最新の注目作を、監督への取材を交えながら紹介する。
INDEX
『トワイライト・ウォリアーズ』超えの大ヒット作『ラスト・ダンス』
『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』が日本でも大ヒットを記録する中、昨年香港では同作を超える大ヒット映画がもうひとつ誕生していた。それが、『ラスト・ダンス』(原題『破・地獄』)だ。香港では『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018年)に迫る勢いといえば、そのすさまじさが伝わるだろうか。
日本では昨年の『第37回東京国際映画祭』と『香港映画祭2024 Making Waves』で上映されたが、2025年3月14日(金)~23日(日)に開催された『第20回大阪アジアン映画祭』では、13分間の未公開シーンを加えた『ラスト・ダンス<ディレクターズカット>』がワールドプレミアを迎えた。これまで多様な香港映画を毎年紹介してきた同映画祭には、監督のアンセルム・チャン、出演者のレイチェル・リョンも来日し、観客とのQ&Aをおこなっている。

驚くべきは、『ラスト・ダンス』がアクション映画ではなく直球のヒューマンドラマ、いわば「香港版『おくりびと』」とも言うべき葬儀文化を題材とした物語であることだ。
主人公のドウサンは元ウェディングプランナーだが、コロナ禍の不況ゆえ転職を余儀なくされ、恋人の叔父から葬儀社を引き継ぐ。ところが、年老いたパートナーの道士・マンは気難しい性格だった。プロとしての力量は確かだが、こだわりが強く、伝統を重んじるあまり家族との関係はうまくいっていない。家業を継ぐ予定の息子を認めておらず、「女性は不浄だ」という考えゆえに、救急隊員の娘との間にも埋めがたい溝があった……。
ドウサンは飛び込んでくる依頼を引き受け、さまざまな死者を悼むことで成長しながら、マンやその家族との距離を縮めてゆく。短いエピソードをいくつも連ねながら、ドウサンの心境の変化や、いがみ合っていた家族の修復に収斂してゆく脚本が秀逸だ。原題の「破・地獄」とは道教の葬儀における儀式のことだが、ここにも複数の意味が込められている。

INDEX
きっかけはコロナ禍。コメディ監督が喜劇要素を封印
監督のアンセルム・チャンは喜劇の脚本家としてキャリアを確立した人物で、以前監督を務めた『不日成婚(原題)』シリーズはウェディングコメディ。初めて喜劇要素を封印した本作で葬儀業界を描いたことは、主人公のドウサンが結婚業界から葬儀業界に移ってきた設定とそのまま重なっている。
「コロナ禍で祖母や親戚、友人たちを何人も亡くし、葬式に何度も参加しました。そのうち、人間の存在意義がだんだんわからなくなってきたんです。人は何のために存在し、生きているのか。命や存在には意味なんかないんだ、と思ったことが構想のきっかけでした」

ところが脚本のアイデアを温め、周囲のスタッフやキャストと話し合ううちに考え方が少しずつ変化していき、物語は当初想像もしなかったところに着地した。「本作を通じて、僕自身が命や人生の意義を知った。とても個人的な映画になったと思います」と言う。
その個人的な映画が、香港社会にひとつのムーブメントを起こした。生と死、失われゆく伝統と現代、ジェネレーションギャップや男女差別を描いた本作は、約1.5億香港ドルという興行成績が示すとおり、今を生きる観客に深い感動をもたらしたのである。映画館を訪れた人々からは、「この映画に救われた」というメッセージが寄せられたという。

俳優陣の優れたアンサンブルを牽引するのは、ドウサン役のダヨ・ウォンと、マン役のマイケル・ホイ。ともに香港を代表する喜劇俳優だが、本作ではコメディ演技を封印し、抑制された芝居で人間の心理をじっくりとあぶり出す。ちなみにディレクターズカット版を製作したのは、「ダヨ・ウォンさんが観客の皆さんに約束してしまったから」だとか。
「通常版も僕が編集したので、どちらも本当はディレクターズカットなんです(笑)。だけど『もっと観たい』と言ってくださる皆さんの思いに応えたい、感謝したいと思い、上映時間の問題でやむなくカットした場面を復活させることにしました。以前のバージョンでは描ききれなかったことも十分に伝えられる、拡大版にして完全版だと思っています」
『大阪アジアン映画祭』のプログラミング・ディレクターを務める暉峻創三さんによると、本作はギリギリまで準備が行われていたそう。満を持しての世界初上映、もとより大きな注目を集めていた作品とあって、チケットはわずか数分で完売したという。