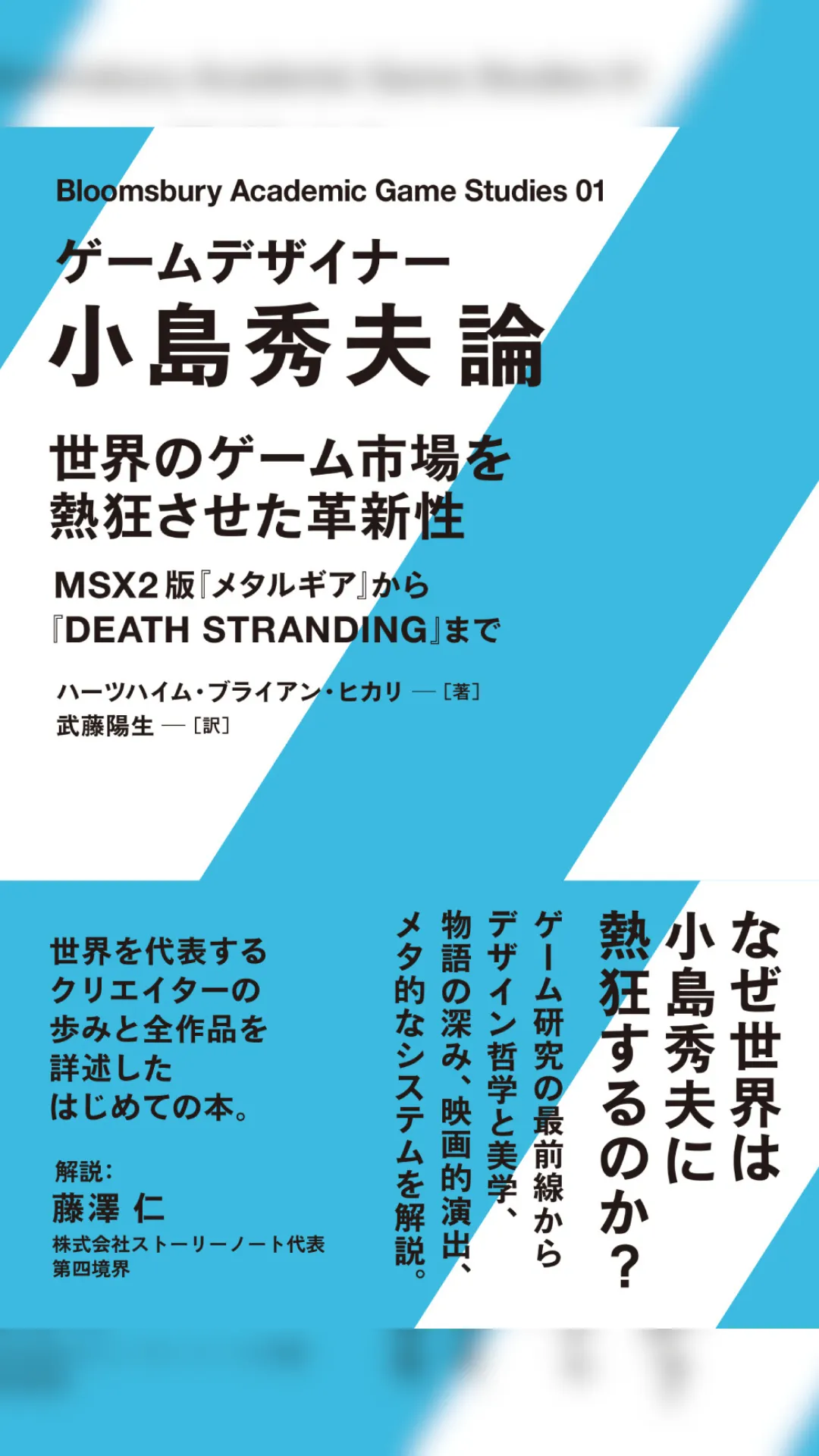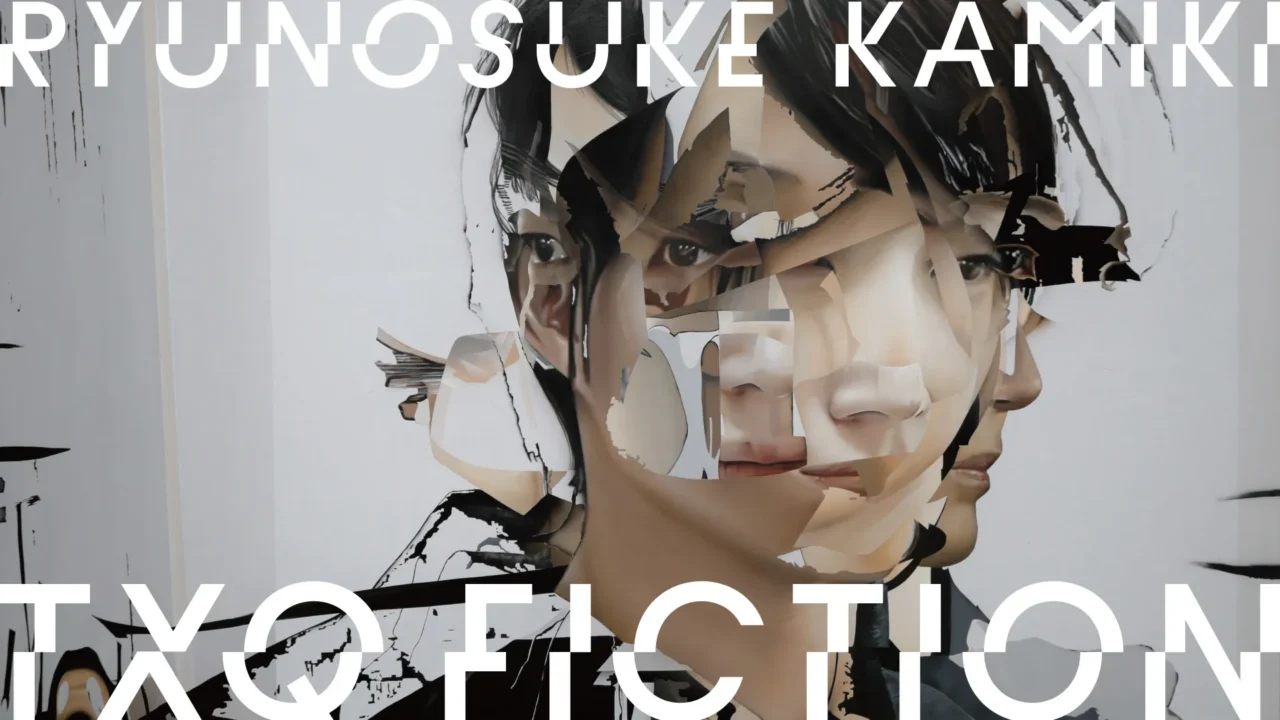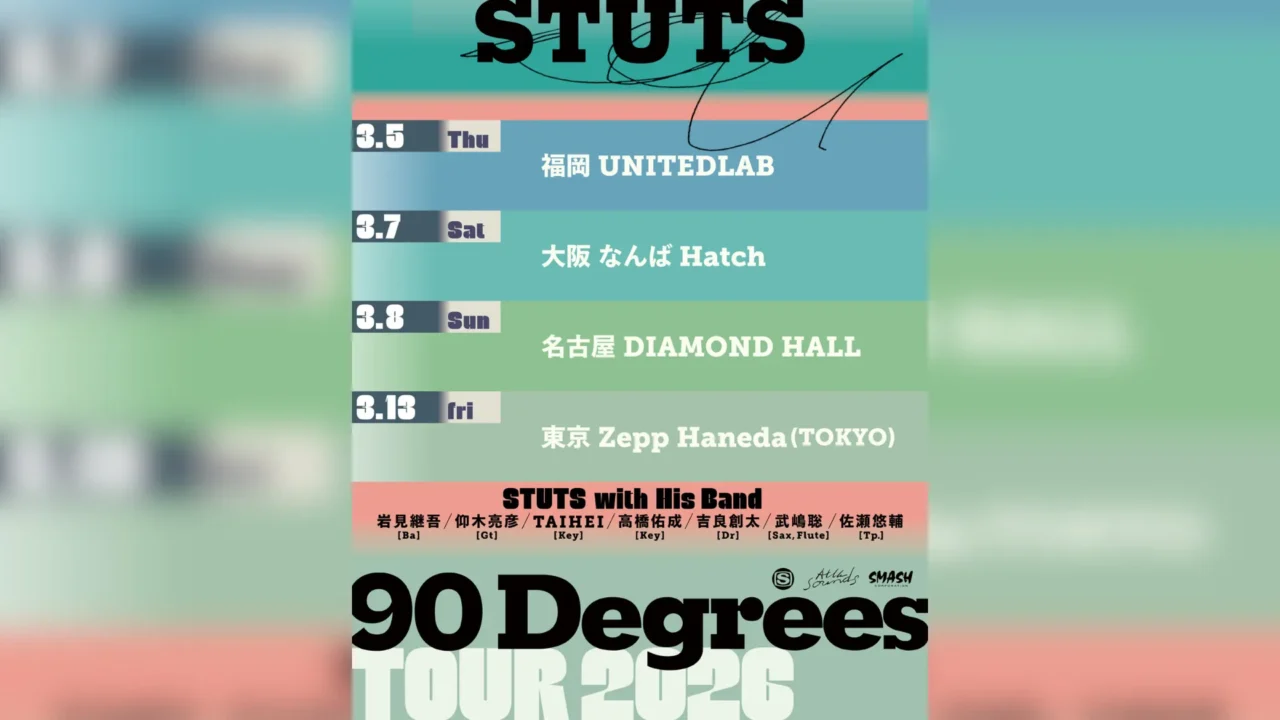INDEX
第四境界が小島秀夫に学んだ、プレイヤーとの関係性の設計
しかし今になって考えれば、浅慮なのは僕の方だった。小島監督の意図は、「破壊」ではなく「設計」だったのだ。多くのメタ表現が「第四の壁を壊す」という言い方をされる一方で、小島作品はむしろそこに「もうひとつの領域」を築こうとしていた。現実とフィクションの間に、安易には越境できない境界線を引き、そのうえで両者を響き合わせる。そうすることで、作品の品位を保ちながらも、プレイヤーとの関係性を絶妙なバランスで再設計していた。
それは、物語の外側にいるプレイヤーに語りかけるのではなく、プレイヤーが物語の中に「気づかずに入り込んでいる」という体験をもたらす。つまり、メタであることを前面に出すのではなく、あくまで没入の一部として機能させる。その絶妙なバランス感覚こそが、小島監督の作品におけるメタ表現の巧みさだったように思う。
僕たち「第四境界」が描こうとしているのも、まさにその中間領域──現実と虚構の間に立ち上がる、新たな接続点だ。そこに登場するキャラクターたちは、ときに現実の参加者に声をかけ、参加者はある瞬間から自分が物語の一部になっていたことに気づかされる。
こういった表現手法は、誰かから影響を受けて始めたものではなかった。だがあるとき、ふと気づいたのだ。──これは、小島監督がやっていることと、同じなのではないかと。
第四の壁を壊すのではなく、その壁の向こう側に人の気配を感じさせること。あるいは、境界線そのものをひとつの作品として作り上げていくこと。本書でも詳述されるように、小島監督は、ゲームという形式の中で、それを最も繊細に、最も豊かにやってのけた人だった。メタ表現とは、決して「すべてを揶揄するための視点」ではない。むしろそれは、表現を通じて築かれる「両者の関係性」をもう一段深く掘り下げるための、ひとつの視座でもある。自分がプレイヤーであることを忘れたとき、ふとその境界を思い出させてくれる。それは没入を妨げるものではなく、かえってその深度を深める作用を持つのだ。
僕自身も、かつてARGの初期作品でメタ表現を試みたとき、それが単なる「意外性狙いのトリック」として捉えられ、誤解されてしまったことがある。演出意図を十分に伝えきれなかった自分の力不足を感じつつ、それでもやはり、物語の境界に触れようとする試みはやめられなかった。なぜなら、そこにしか描けない物語があると、強くそう信じているからだ。