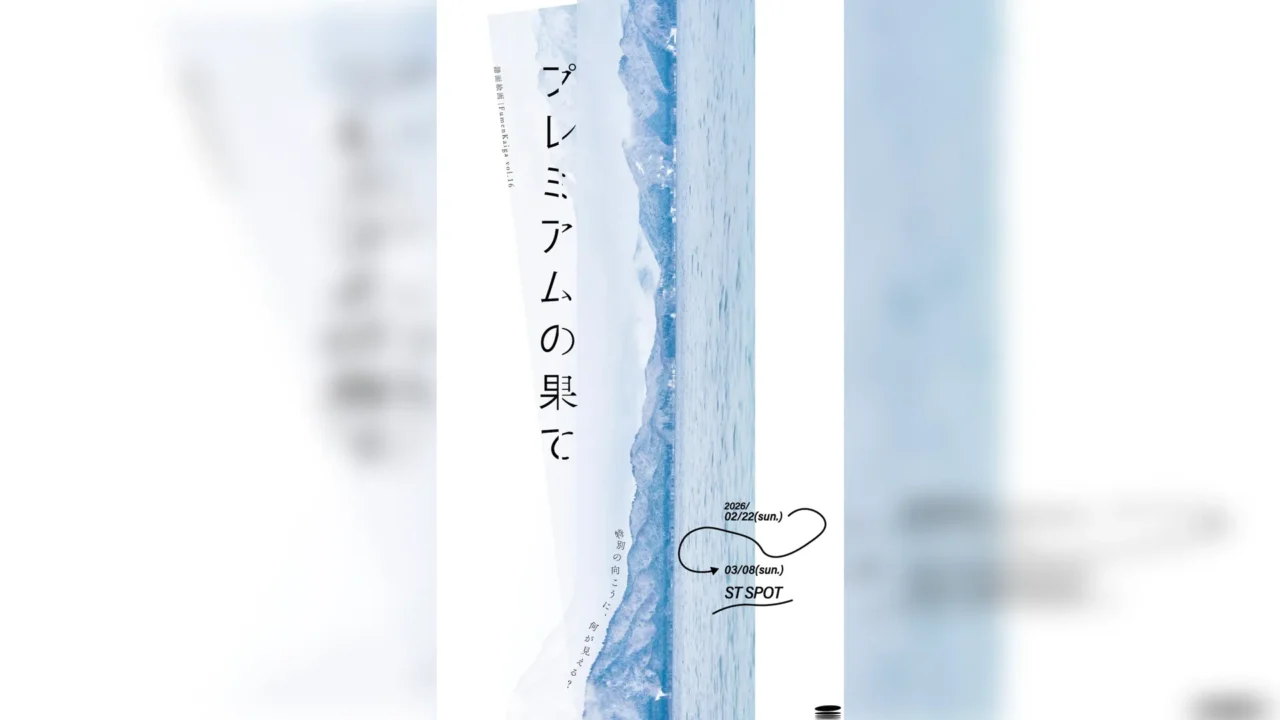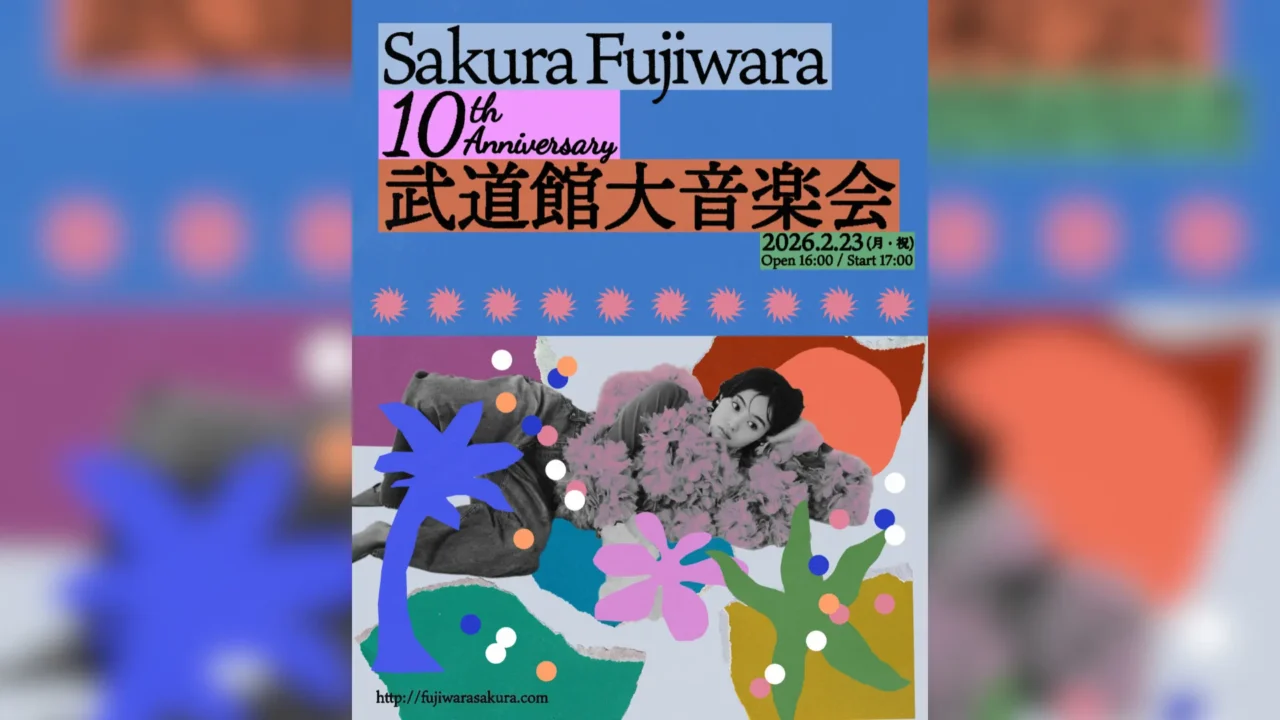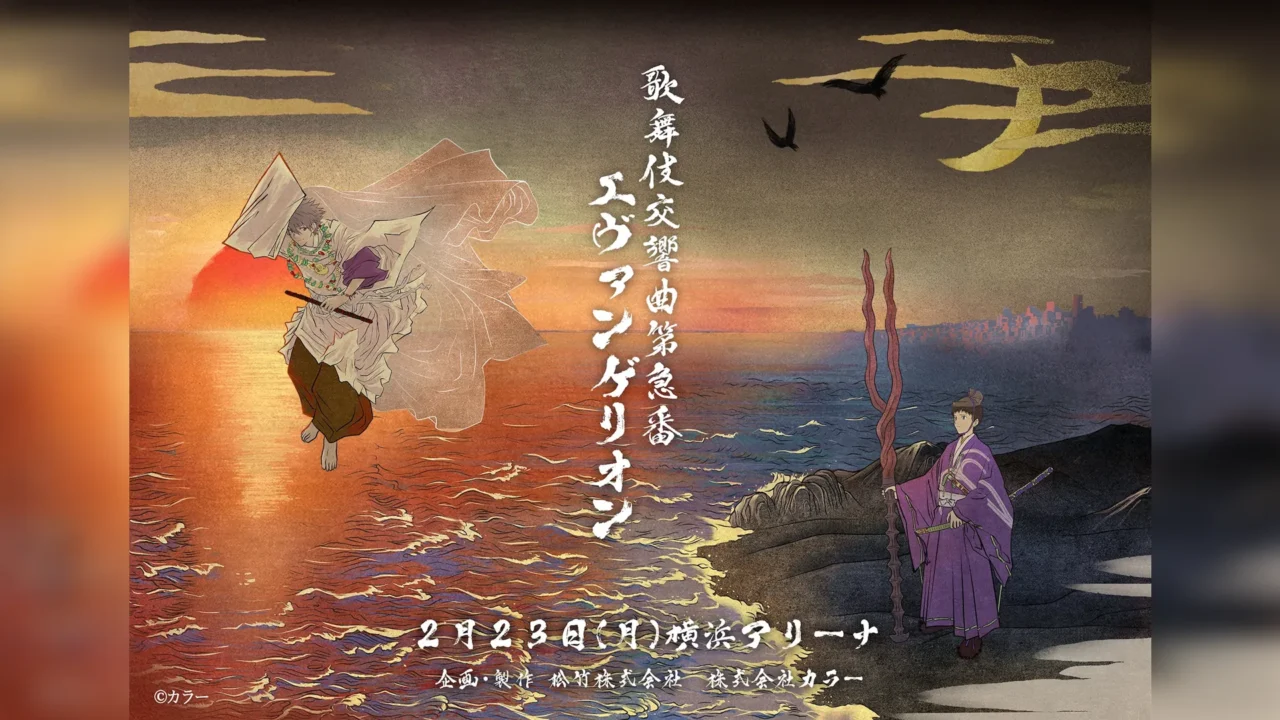INDEX
そもそも「PA」とは? 同じ「エンジニア」でも、レコーディングとPAは手法や考え方が真逆
ー話の順番が前後してしまいますが、改めてライブやコンサートにおいてPAとはどういう役割なんでしょうか?
佐々木:PAって、「パブリックアドレス」の略。言葉としては、公共放送みたいな意味ですよね。
DMX:まあ、音を拡散させるって感じだよね。
佐々木:一般的にPAエンジニアって言ったら、アーティストが出す音の音量バランスをコンソールで調節して、最終的にスピーカーで再生する役割。アーティストからすれば、出した音がそのPAの人のフィルターを通るってことなんで、アーティストの考えを理解するのが大事です。また、うちの会社の場合、「サウンドリインフォースメント」……SRっていう、もうちょっと音に特化した役割のイメージなんですね。それらはざっくりPAってまとめられていますけど。さらに加えて、Dubさんとかウッチーは、「ダブエンジニア」って言われる人たち。
内田:とは言え、僕は知識がないままPAを始めていますから、最初は事故だらけでしたよ。レコーディングとPAって、使う機材は一緒だけど方法がまったく違う。というか、手法や考え方が真逆なんです。それを知らずにレコーディングのようにコンソールを操作していたので、事故だらけ。基本がまったくできていない状態で、独学で始めていましたから。
ー少し脱線してしまうのですが、PAの現場で言う「事故」とはどういったことを指すのですか?
DMX:ハウリング。ハウリングが起きたらそのポイントをEQで切っていくしかないんだけど。
佐々木:そういうことも、最初は分からないもんね。自分は会社にいたんで基本を教わってから現場に出ていたんだけど、PAの場合って、必ずスピーカーのチューニングをするとこから始まるんです。その中に、「そこを知らないとヤバい」みたいなポイントがたくさんあるんだよね。レコーディングから始めると、その段階がないっていうか。
内田:それを知らずにPAを始めているから、ハウリングが起きたときに「どこがおかしいのか分からない」って状態になって、「あわわわわ!」って(笑)。

DMX:綱渡りしていることは多かったね。卓のオールミュートのボタンを外すのが怖い、みたいな。ライブが始まる直前、オールミュートのボタンを外した瞬間にノイズが出て、「どうしよう!」みたいなね(笑)。でも、昔はなんであんなにハウったんだろうね。
佐々木:今はあまりハウらない。スピーカーの性能が上がって、初期設定が昔に比べて格段に良くなっているから。言ってしまえば、素人の人がやってもそれなりに良い音が出る。あと昔は、音響的にきっちりしたライブハウスもそんなになかった。クラブでライブをやるときのPAも難しかったよね。スピーカーの位置とか、音響設計自体がライブハウスとは全然違うから。
DMX:クラブでのPAは辛かったな~! さんちゃんみたいにPAカンパニーに入っている人は、初めは先輩から「てめぇ何ハウらせてんだよ!」とか言われながらやっていたわけじゃない。で、俺もウッチーと一緒で独学。上手いPAの人に「それ、どうやってるんですか?」って質問して、「自分で考えろよ」とか言われて、結局そのまま事故を起こしたりして。そうやって勉強してたんだよね。