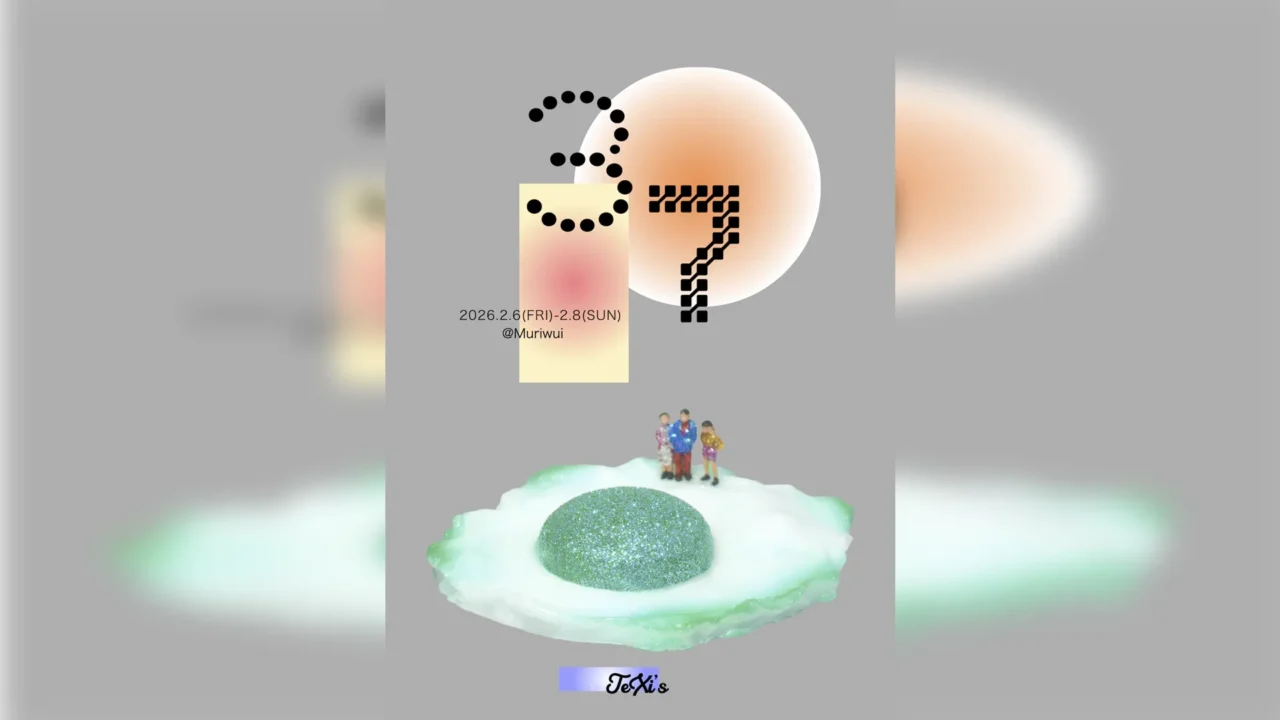4月25日(金)よりサイコスリラー映画『異端者の家』が公開されている。プロットは「若い女性2人がサイコパスな男性の家に足を踏み入れてしまう」とシンプルながら、そこには、「宗教」の本質に迫る「寓話的」な側面も。その魅力を紹介しよう。
INDEX
若い女性宣教師が「ばつが悪くて帰れない」に状況に
主人公のパクストンとバーンズは、モルモン教の女性宣教師だ。布教活動がうまくいかない中、彼女たちが訪れたのは森に囲まれた一軒家。そこに住む気さくな男性・リードは「妻がいるから心配ない」という建前のもとで彼女たちを家へと招き入れる。彼女たちが神の教えを説き始めると、リードは「どの宗教も真実とは思えない」などと持論を展開する。実は、その家は数々の「罠」が張り巡らされた、迷宮のような場所だったのだ。

まず描かれるのは、多くの人に経験あるであろう「帰りたいのに、ばつが悪くてなかなか帰れない」心理状態。そして、そこから主導権を奪われていく過程が恐ろしい。主人公2人はもちろん布教の目的があるので、最初こそ積極的に「教える」立場だったが、リードはあらゆる宗教に精通しているようで、正論めいた言説で2人を圧倒していく。さらに、リードはブルーベリーパイを焼いているという「妻」にたびたび話しかけているのだが、その姿は見えず、2人は「どう考えてもおかしい」と気づいていく。さらに、決定的な「物理的に玄関から出られない」状況にまで陥ってしまうのだ。
INDEX
キュートにも思えるヒュー・グラントが「主導権を握る」過程が怖い
本作の最大の魅力は、なんといってもうさんくさく、同時にキュートなヒュー・グラントの快演っぷりだ。笑顔は朗らかで、出会った直後の話し方も気さくそのもの。映画を見ている観客には彼が悪役であるとわかりきっているのだが、それでも「安心してしまう」ことがむしろ恐ろしい。目線の使い方や緩急をつけた話し方などから、しだいに彼の狂気も伝わってくるのだが、同時に「逆らいたくない」という気持ちも生じてくる。
ヒュー・グラントは近年『パディントン2』(2017年)や『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』(2023年)でも悪役を演じてきたが、その役柄もどこか憎めない人物だった。善人のイメージのある俳優がサイコパスを演じるとより恐ろしいということはままあるが、その中でも今回のヒュー・グラントは「かわいいのに怖い」役を演じた俳優として、頂点を極めたとさえいえる。

ちなみに、ヒュー・グラントは本作の準備のため、リチャード・ドーキンス やクリストファー・ヒッチンズなどの宗教的な偶像破壊主義者について学び、連続殺人犯やカルト教団のリーダーについて調べ、何が彼らに悪事を働かせたのかを突き止めようとしたという(プレス資料より)。話し方や表情の奥にキャラクターの「背景」が垣間見えるのは、その成果だろう。
INDEX
表向きには「選択肢」を用意しているが、結局は支配している
リードの言説には「どの宗教も反復である」「2人が信じる神も茶番だ」という乱暴なものもある一方で、ボードゲームの「モノポリー」やロックバンドの「Radiohead」といった具体的な例を用いての解説はわかりやすく、一理あるとも思えてしまう。ヤバいやつなのは間違いないのに、その言葉には確実に正論も含んでいる、なんなら物事の本質を突いているように思えることも、彼の話につい耳を傾けてしまう理由だ。
そして、リードが主導権を握る様は、「『信仰』と『不信仰』と書かれたドアのどちらかを心に従い選べ」と迫るシーンで、さらにはっきりと表れる。表向きには「選択肢」を用意しているわけだが、それ以前に「選ばなければならない」状況を生み出しているのは他ならぬリードだ。結局彼は、独善的な言葉で相手を支配しているし、そのドアの先にあった衝撃的な光景や事実、彼の言う「真なる唯一の宗教」は、その欺瞞やおぞましさをさらにはっきりと映し出すことになる。
総じて、本作は宗教を題材として描いているが、宗教そのものを貶めたりはしていない。問題となるのは宗教そのものではなく、「宗教の教義を利用して誰かを罠にはめて人生を破壊させる」ことだ。日本でも、その恐ろしさが他人事ではないというのは言うまでもないだろう。同時に、男性が女性を無知だと見下し、一方的に知識をひけらかし、価値観を押し付け、高圧的な態度を取る、いわゆる「マンスプレイニング」の問題もはっきりとわかるはずだ。

INDEX
物語の元となった、監督が体験した恐怖体験
ちなみに、本作の物語の原点は、監督コンビがティーンエイジャーの時に短編映画のロケ地を探していたときの実体験にあるという。優しい老夫婦が暮らす家を訪れた際、短編映画の内容が「隕石が衝突して地球上のあらゆる生命が絶滅するという話」だと説明すると、老夫婦は紅茶をすすりながら相槌を打ち「隕石が来るのは知ってる。2〜3ヵ月後にやって来て人類を全滅させる」と言ったため、会話に不穏な雰囲気が忍び寄り、家に閉じ込められたような感覚を覚えたのだそうだ(プレス資料より)。
また、主人公のパクストンとバーンズは、脚本のリサーチ中に出会った宣教師がモデルだという。そのモデルの人物は「表層的な純真さを感じる瞬間があった」一方で、「実際は聡明でクール」「宗教や社会、文化に対する考え方は大胆不敵」だったそうで、その「表裏」をキャラクターに取り入れることで、「リードが彼女たちを過小評価する」重要な要素につなげられたようだ(プレス資料より)。本作は荒唐無稽ともいえる設定が土台にあるフィクションだが、リアリティーを感じるのは実際の人物や出来事を参考にしたためでもあるのだろう。