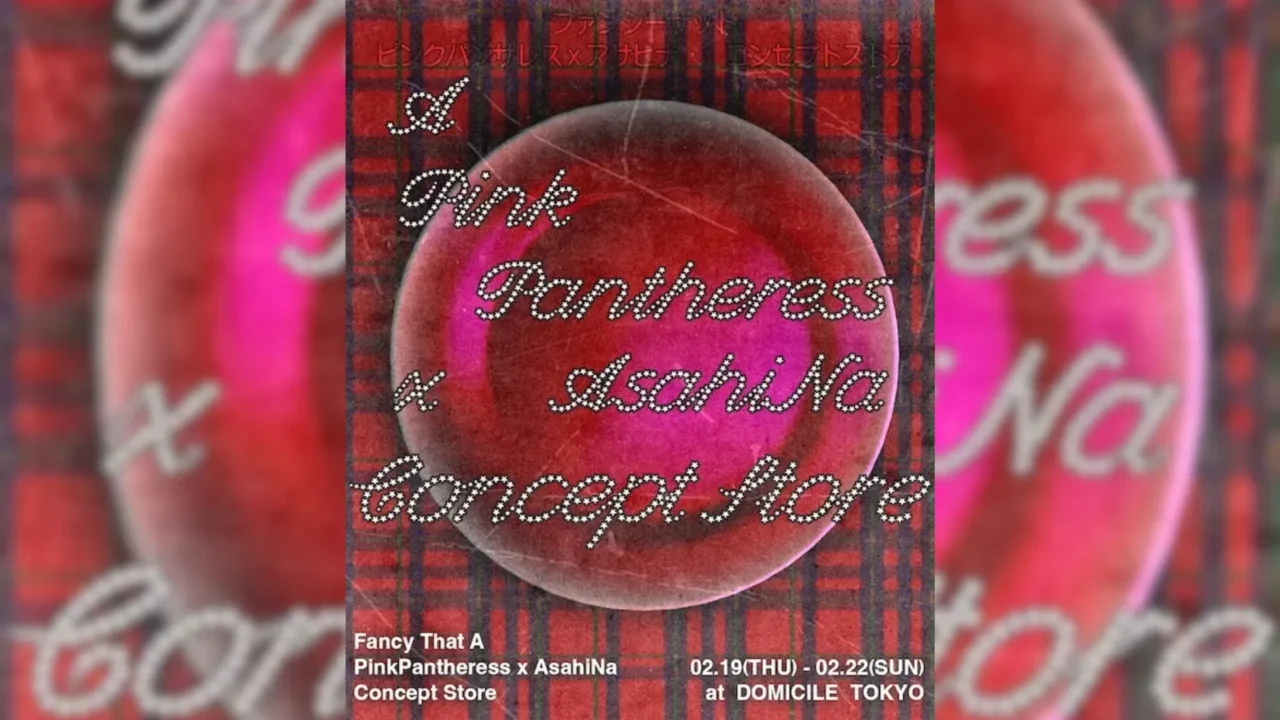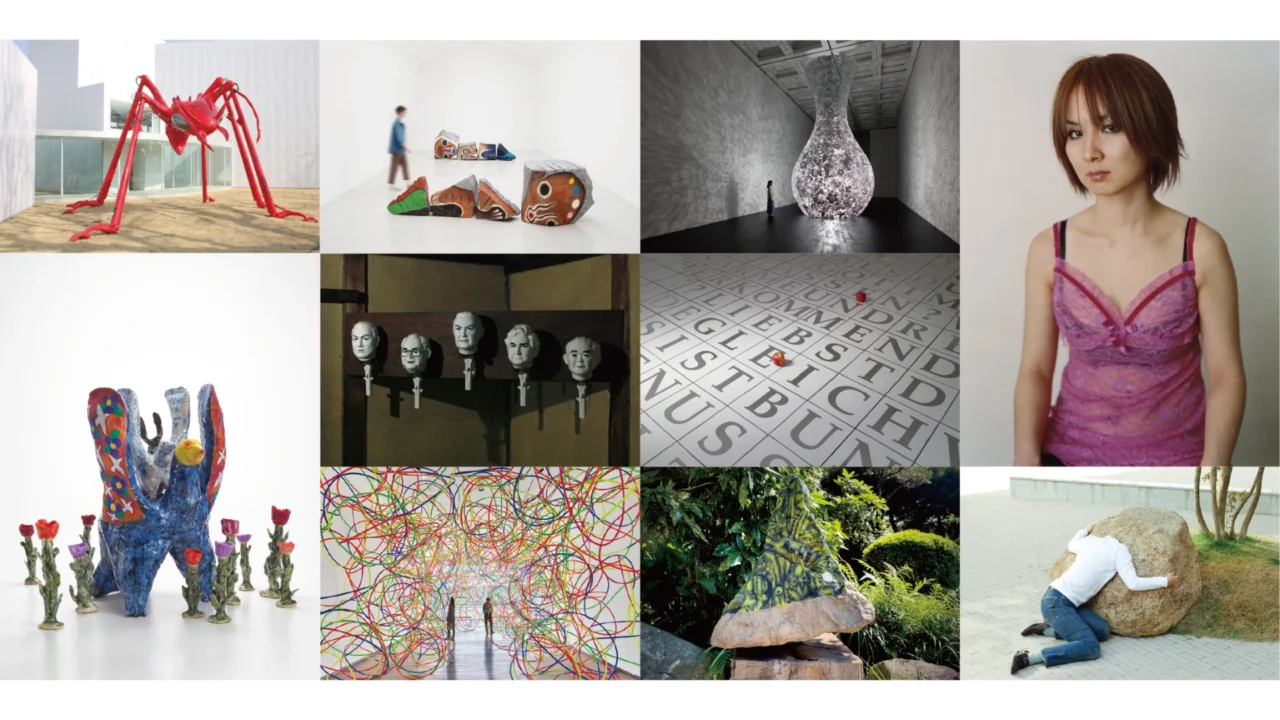今日もまた、有名人の過去の発言がテレビやネットで晒し上げられ、整合性のなさを糾弾されている。「仏じゃないんだから」と思いつつ、有識者がそれっぽいことを言っている光景からそっと目を逸らす自分もまた、昨日誓ったばかりの節制を来月の自分に押し付けてモバイルオーダーしたトッピングたくさんのご飯が届くのを待っている。
Helsinki Lambda Clubが2024年11月にリリースした最新EP『月刊エスケープ』は、そんな辻褄の合わない我々を受け入れてくれるような作品だ。前作『ヘルシンキラムダクラブへようこそ』を彷彿とさせるキャッチーなインディーロックもあれば、「Helsinki Lambda Clubとはなんなのか」とさえ思うポップソングも収録。積み上げてきたものへの執着やわかりやすさへの迎合はまるでないかのように、「今やりたいこと」を常々形にしてきたボーカル橋本薫のサウンドスタイルが今作でも発揮され、得体の知れなさが彼ららしい。
自身が抱える矛盾を認めつつ、「自分の心に従っていたい」と話す橋本の姿勢は「かくあるべし」という考えに捉われない強さと説得力をまとっていた。リリースとツアーを控えた橋本に、自分の心に従った音楽作りへの想いとわかりやすさへの抵抗について伺った。
INDEX
いつも自分の心に従った音楽を
―2024年、Helsinki Lambda Club(以下、ヘルシンキ)はアメリカの『SXSW』への出演や初のイギリスツアーなど、バンドの音楽的ルーツでもある国での公演を多く果たしました。イギリスのステージから見えた景色はいかがでしたか?
橋本:バンドも自分自身の生き方も、欧米の音楽やカルチャーに憧れて影響を受けたところから全てが始まったので、満を持して挑戦したツアーでいい反応をもらえたことは素直に嬉しかったし、ホッとしました。「受け入れられた」という感覚があるからこそ、これまでの活動の根底にあった憧れや、欧米のロックの下地に個性をどう足すかという音楽作りの考え方にも執着がなくなりましたね。好きなものは好きにやればいい。フォーマット的な部分でとらわれる必要はないと思えるようになりました。

2013年夏に千葉で結成された橋本薫(Vo, G)、稲葉航大(B, Cho)、熊谷太起(G)による3人組バンドHelsinki Lambda Clubのボーカル。2023年には結成10周年を迎え、3枚目のフルアルバムとなる『ヘルシンキラムダクラブへようこそ』をリリース。2024年にはアメリカ『SXSW』への出演やイギリス・ブライトンのフェス『THE GREAT ESCAPE』を含む初のイギリスツアーを達成。同年11月にはEP『月刊エスケープ』をリリースし、12月より全国11カ所を回るライブツアー『冬将軍からのエスケープ」を開催中。
―日本と海外のライブでは盛り上がる曲が違うという話はいろんなバンドの方が話していると思いますが、ヘルシンキの場合はどうだったんですか?
橋本:やっぱりありましたね。イギリスは日本のようにメロディー重視な感じがあって、リフで合唱が起きるのがすごい印象的でした。でもそれ以上に、海外はどこの国でもビートが重視されてますね。
―ライブでのオーディエンスのアプローチ方法に変化はありましたか?
橋本:今までよりどっしり構えられるようになりました。堂々と楽しんでやれてさえいれば、下手にオーディエンス側を意識しすぎる必要もない。自分たちのやりたいことやパフォーマンスをとことん追求すればいい。純度が高いことを貫くことで、結果として満足度も高くなる。自信が欠けていると相手の顔色を伺ってしまったり、無関係な部分で頑張ろうとしてしまうんですよね。どっしりと構えてやることで、演者とオーディエンス双方にとって健康的な関係性を築けるんじゃないかなと思います。

―「ヘルシンキはキャッチーなインディーロックを得意とするバンド」という印象が世間的にあるとしたら、それは橋本さんにとっても欠かせないバンドのアイデンティティだと思いますか?
橋本:元々、枠組みに属するという意識は強くなかったし、年々薄まっている気がしていて。一番コアにあるものは、心に従って作品を作ること。やっぱり正直な人間でありたいから。日々の生活のなかで、自分の心にいつも従って生きることは難しいかもしれないけど、音楽を作る時だけは自分の気持ちに素直になれる。そうでないとただお金を稼ぐためだけのものになってしまう。根幹にあるのはピュアな気持ちです。
INDEX
海外公演後、最新作で取り組んだチャレンジ
―そんな経験を経て『月刊エスケープ』がリリースされました。今回のEPの手応えはどうでしょう?
橋本:Helsinki Lambda Clubとして、前作『ヘルシンキラムダクラブへようこそ』から更新できたなという手応えはありつつ、チャレンジも多い作品になったかな。前作はバンドとして一段と気合いの入った作品で、いろんなノウハウも得られたので、今回はそこまで難産になるとは思ってなかったんです。いつもは、制作中に次作の構想やアイデアも同時に考えることがあるんですが、今回そんな余裕はなくて、気づいたら目の前のEPに没頭してて。チャレンジする余白がまだまだあることを実感した制作になりましたね。アルバムよりは短いEPというフォーマットではありますが、「出し切ったな」と思える作品になったと思います。

―チャレンジにもいろいろあるかと思いますが、どういったことが難しかったんですか?
橋本:いろいろあるんですけど、特に「歌」ですね。実はボーカルとして、「歌があまり得意じゃない」という問題意識をずっと抱えていたんですけど、歌が上手くなくても問題ない音楽性だと思っていたので、これまであまり自分の歌に向き合ってなかったんです。僕の歌い方は比較的平たくて感情が出ないんですけど、まあそれでもいいと思っていた。でも今回は明確にやりたい音楽があって、たとえばEP収録曲の”Yellow”のようにブラックミュージックを参照にした楽曲を自分が歌うには、カルチャーへのリスペクトに欠けると思ったんです。自分の歌に向き合わざるを得なかった。
INDEX
相手を理解する前に、自分自身を理解すること
―癖や欠点は誰にでもあると思いますが、ヘルシンキとしても10年以上積み上げてきたものがあるなかで、自分の癖に向き合うのは簡単ではなかったと思います。
橋本:抵抗があったからこそ10年もの間、向き合えなかったんだと思います。でもやっぱりこの先も音楽を続けていきたい。そしていろんな表現方法を身につけて、できることを増やしていきたいという気持ちは変わらないので。足りないところに目を向けたり、やりたいことを実現するための方法を考えたりするフェーズになってきたんだと思います。

―ライナーノーツによると、「相互理解」がEPのテーマの一つだったそうですね。互いに理解し合うという意味ですが、制作を通して橋本さんご自身の理解も深まったのではと思いました。
橋本:「わからないものが怖い」という無意識に近い感情が人間の根本にあるように感じていて。好奇心が強い自分でさえ、わからないことに直面すると怖くなってしまう。怖いものを目の前にすると、臆病であればあるほど、加害的な反応をしてしまうと思うんです。だからこそ、わからないものがある時は「今自分は怖いと感じている」と素直に認めるようにしていて。怖いと自覚できると、「なんで怖いのか」という問題にも向き合えるようになるはずなんです。
相手を理解する前に、自分自身を理解すること。SNSで起こっているヘイトや衝突を見ると「自分は我慢しているのに」っていう怒りに基づいたものもあるような気がしていて。その我慢って本当は誰に強いられたものなんだろうなと思います。自分を一度見つめ直すことは素直に生きる上でのキーワードかもしれないですね。
INDEX
「世間とズレている」ならポップソングで歩み寄る。Helsinki Lambda Clubの相互理解の実践
―“たまに君のことを思い出してしまうよな”は「今までで一番ポップスに接近した曲を作りたい」という思いから生まれた曲とのことですが、ポップな曲に取り組もうと思ったのはなぜなんですか?
橋本:最近のヘルシンキはサイケな路線が多いですし、「この路線を貫いた方がいい」と近しい人に言われることもあるんですが、僕はポップなこともやりたくて。ヘルシンキはそれが可能なバンドであるとも思うんです。
これまでも、できるだけたくさんの人に届けることを意識して作った楽曲はありますが、「世間と多分ズレてんだろうな」っていう意識は年々増すばかりで(笑)。“たまに君のことを思い出してしまうよな”も、自分としては最大限ポップスに歩み寄った楽曲で、胸を張ってリリースしたけど、どこまでポップスになっているのかというテスターであり、どれくらいズレているのかを測るものさしでもありますね。
―なぜ「世間とズレている」と思うんですか?
橋本:例えば、自分が好きなアーティストの楽曲は、サブスクのアーティストページで表示される人気曲の7番目とか8番目のものが多くて(笑)。みんなと好きな曲が違うんだなって。それに、売れてないとは思いませんが、Helsinki Lambda Clubというバンドがもっとデカくなってもいいんじゃないかなという気持ちも常にあるんです。

―「ヘルシンキなりのポップソング」を通して、世間とのズレの距離を測る努力はまさに、相互理解の実践だなと思いました。”たまに君のことを思い出してしまうよな”では、久しぶりに外部プロデューサーとして堀江博久さんを迎えての制作となりましたが、外の人を迎えた制作で見えたバンドの気づきはありましたか?
橋本:「ライブで表現できないことはやめよう」という堀江さんが示していただいた方向性のもと、サポートメンバーを含む4人でできることを尊重してもらった、学びの多い制作でした。そしてやっぱり、打ち込みなどのいろんなアプローチをこれまで試してきたものの、ヘルシンキはシンプルにバンドなんだなと再確認できたんです。これまでいろんなことに手をつけてきたんですけど、無機質なものではなくて、有機的な人の繋がりでできているバンド。だから時には矛盾することだってある。