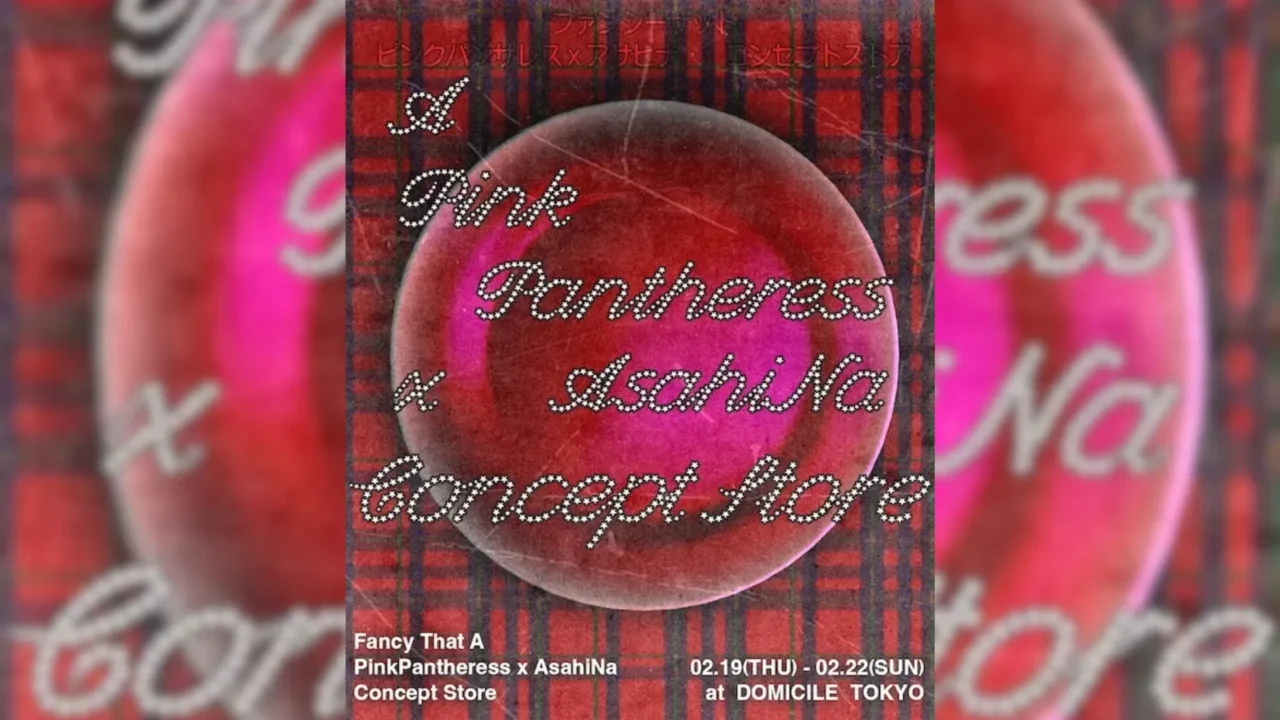ORICON NEWSの「2025夏ドラマ-序盤-ランキング」で1位に輝くなど、ドラマ好きの中で評価が高まっているドラマ『舟を編む~私、辞書つくります~』(NHK総合)。
8月2日・3日にはドラマで使用した小道具なども展示された『舟を編むファンフェスティバル in 神保町』も開催され、行列ができるほどの盛況となり、その人気度の高さも伺えた。
原作小説から舞台となる時代も変え、コロナ禍もしっかりと描いた本作の第6話~第9話について、前半を振り返った記事に続き、ドラマ・映画とジャンルを横断して執筆するライター・藤原奈緒がレビューする。
※本記事にはドラマの内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
「業」を持ち寄って、皆で「その先」に向かう後半戦

『舟を編む~私、辞書つくります~』の登場人物たちは皆、辞書作りに限らず、何か「好き」という思いを原動力に行動する。物語後半の第6話から第9話で、その「好き」はさらに極まって、「業」になる。
辞書によれば「業」とは「人が担っている運命や制約。主に悪運」を言うそうだ。辞書『大渡海』の紙での出版を廃止し、デジタルのみにするという提案をもたらした玄武書房の新社長・五十嵐(堤真一)もまた、「会社を守る」という「業」を背負うからこそ、みどり(池田エライザ)や馬締(野田洋次郎)たちとぶつかる。同じく後半に登場した、『大渡海』の装丁を担当するブックデザイナーのハルガスミツバサ(柄本時生)も、「本が大好き」だからこそ、「白紙でも売れる」と言われる自分がこの仕事を受けることが『大渡海』を貶めることにならないかと葛藤する。その姿を見たみどりは、これもまた「業」なのだと思う。
「もう辞書編集部だけの舟じゃない」という第9話の西岡(向井理)の台詞ではないが、本作後半戦は、五十嵐もハルガスミも含めた大勢の人々が、それぞれの「業」を持ち寄って『大渡海』という舟に乗り、皆で「その先」に向かう話だ。「言葉」も「人」も、誰一人取りこぼさずに前に進もうとする、三浦しをん原作×蛭田直美脚本の力に圧倒される。