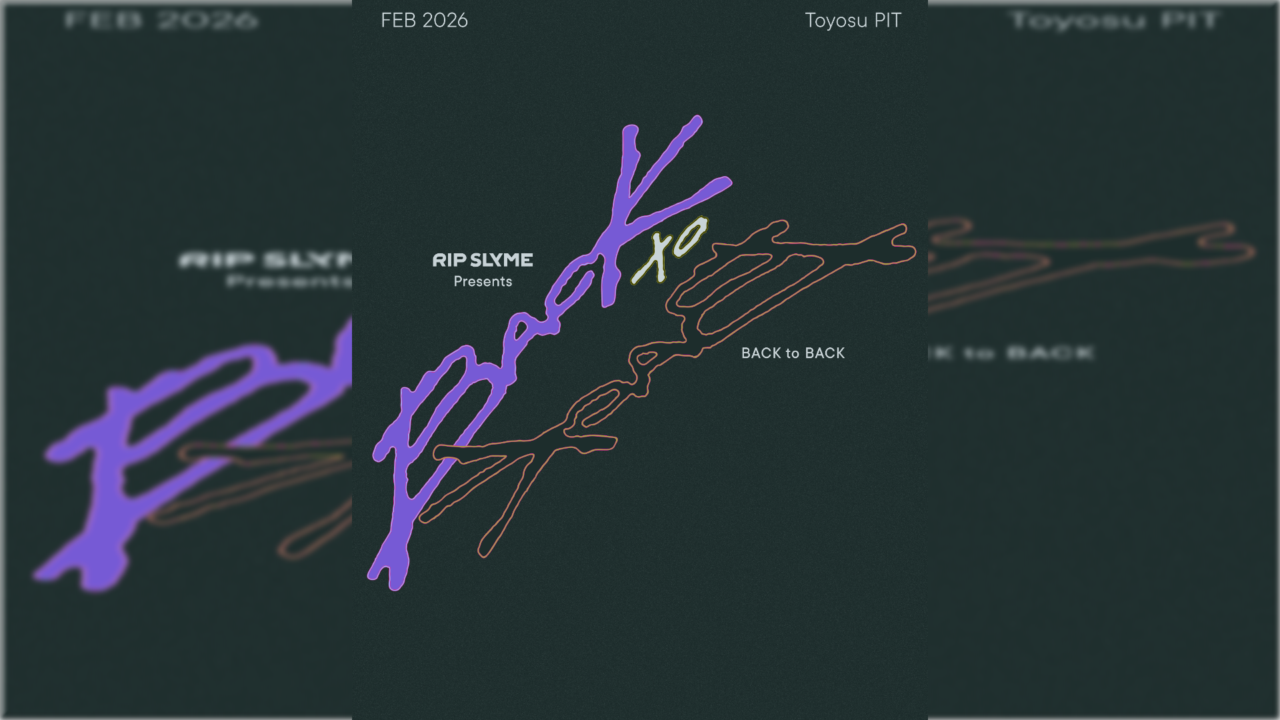なぜ音楽家たちは「ライブ」をするのだろう。なぜ私たちは「ライブ」に足を運ぶのだろう。そのとき、その場所で起こる奇跡、あるいは事件を、その唯一無二の「時間」を複製することは、今後どれだけ録音技術、映像技術が発達してもきっと不可能だ。ceroが作り上げたライブ作品『Live O Rec』を聴くと、過去・現在・未来を自由に行き来し、あらゆる可能性を内包する、その「時間」について考えさせられる。
『Live O Rec』という作品は、2日間にわたって行われたライブ録音を下地にしているが、いわゆる「実況録音」的なものではない。編集、録り直し、オーバーダビング、あらゆる音響操作が積極的に施されたこの作品には、いくつもの時間と空間が混在している。しかし、それでいてceroの三人の意識は、あの日、あのとき、あの場所の「ライブ」に収斂しており、それが作品としての独特な手触りを担保している。
ドキュメンタリーと呼ぶには、その制作にはあまりに制約がなく、現実を曖昧にすることによって生み出された作品であるが、モキュメンタリー的とも言えない。音像の中でゆらゆらと揺らめく時間、現実は、不思議なリアリティーを感じさせる。
このインタビューはそんな『Live O Rec』の種明かしを目的としたものではない。取材執筆はceroのライブを初期から見守り、ときにはツアーの地方公演にまで足を運ぶライターの松永良平。この文章が、作品に向き合う一人ひとりがそれぞれに解釈する手がかりになれば、と願って。
※高城晶平の「高」は「はしご高」が正式表記となります
INDEX

2004年結成。3人それぞれが作曲、アレンジ、プロデュースを手がけ、サポートメンバーを加えた編成でのライブ、楽曲制作においてコンダクトを執っている。今後のリリース、ライブが常に注目される音楽的快楽とストーリーテリングの巧みさを併せ持った、東京のバンドである。2023年5月、5作目となるアルバム『e o』をリリース。2024年9月、初のライブ音源作品『Live O Rec』を発表した。
INDEX
なぜceroが今、ライブアルバムを? 映像がないことで「制約」からの解放が
─「ライブアルバムを作ろう」というアイデアはどこから出てきたんですか?
高城:去年のLIQUIDROOMツーデイズ(2023年12月2日、3日)をやるときは、もうレコーディング前提だったよね。ツーデイズだから、2テイク録れるっていうのもあったし。
荒内:きっかけとしては、『e o』のリリースツアーのファイナルのライブから“Tableaux”の映像をYouTubeにあげることになったことで。
高城:そうだね。
荒内:あの曲はライブのスネアの音作りが難しくて。
高城:みっちゃん(光永渉)がクッキーの缶で叩いたりしてた。
荒内:それもあってライブのミックスでいろいろ考えていたんですけど、みっちゃんが、「いつもドラムの横に置いてるiPhoneで録った音を貼り付けたら面白いんじゃないか」って提案してくれたんです。YouTubeのミックスは(エンジニアの)柳田亮二さんにやってもらったものですが、そのミックスにiPhoneの音を貼ってみたバージョンを勝手に作ってみました。結局それは締め切りには間に合わなくて、実際には使われなかったんだけど、みんなに送ったら面白がってくれて。
荒内:それを踏まえて、高城くんが年末のツーデイズでは、ライブ録音を前提にしてそういうアプローチをいろいろやったら面白いんじゃないかって。自分たちだったらいろいろアイデアが出てくるだろうし、(ライブレコーディングを)やってみようという話になった。
高城:ceroは映像作品はいくつも出しているけど、ライブ映像って音をいじりすぎると映像との乖離が生まれて画も触らなきゃいけなくなる。そういう制約から解放されて、音だけのライブ作品でいろいろやりたいなってことは前から思ってて。
橋本:DVDでも少しは音の直しをしていたんですけど、欲を言えばもっとこだわりたかったんですよね。だから今回、いい機会だなと思いました。
高城:当初はお客さんにも参加してもらう構想があったんですよ。
─ライブレコーディングの演出に観客も参加するような演出?
高城:そうそう。「ここで叫んでください」とか「変な拍手してください」とか。お客さん全員後ろを向いてもらって、ステージを誰も見てない写真を撮ってジャケットにしよう、とか(笑)。結局ライブの準備が忙しくて、当日は普通にやったけど。
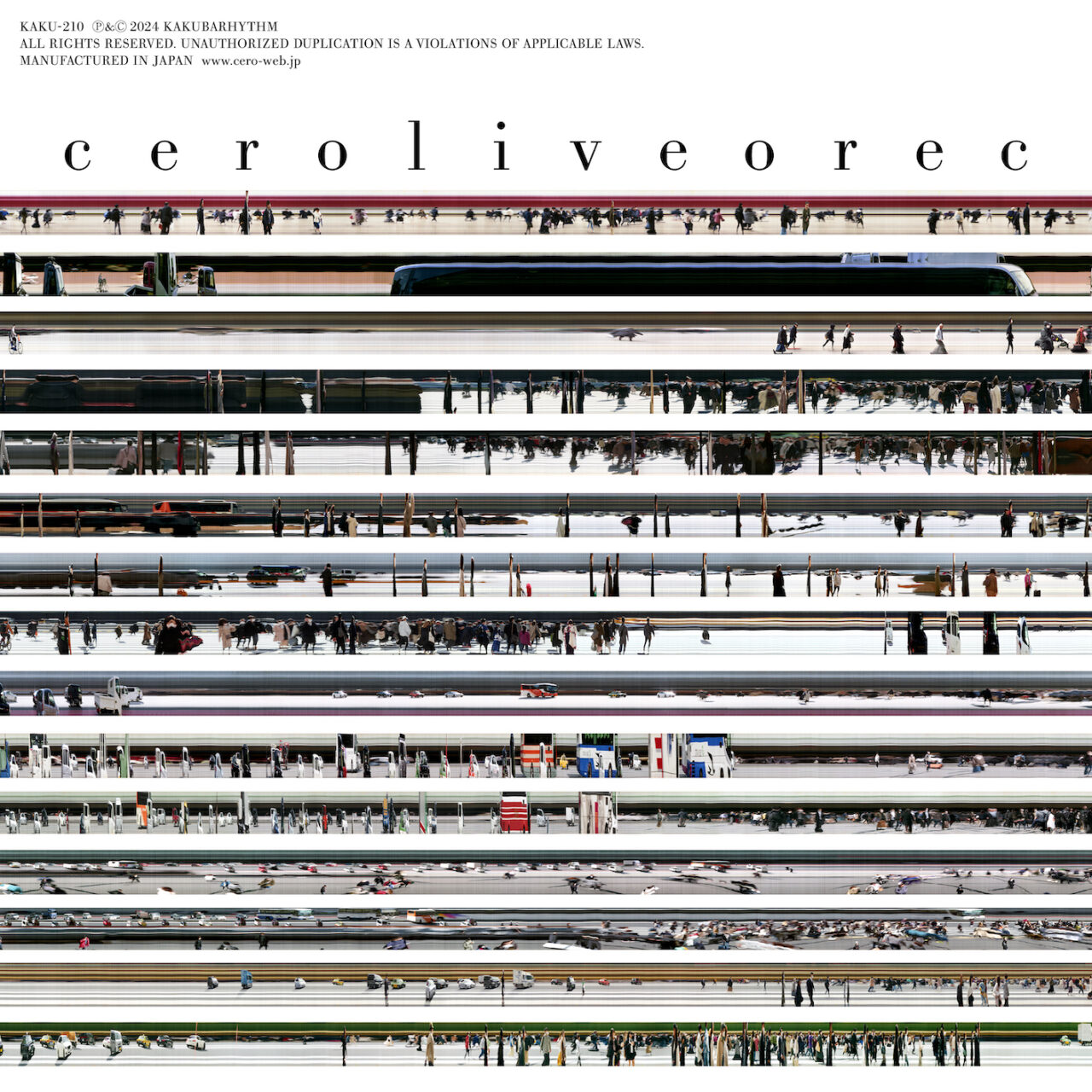
INDEX
ライブを通じて音楽を深化させてきたcero。ステージ上では何が起こっているのか
─ceroほど楽曲のアレンジがライブで変わってきたバンドはないと思うんですよ。
高城:「僕ら三人が飽きっぽいから、次々にアレンジを変えちゃうんですよね」ってインタビューでもよく言うんだけど、最近、サポートの人たちも結構飽きっぽいんじゃないかって思ってるところもあって(笑)。一緒になってアイデアを考えてくれるし、ライブは誰が中心に考えているのか、作っているのか、さらによくわからないことになってます。だからこそ、この状態をひとつの作品にしておかないと、って思いました。
荒内:今の編成になったのが2016年の後半だから、成熟期なのかな。2020年くらいから、「結構仕上がってんな」と手応えを感じています。コロナ禍でライブの本数が減って、1本1本のライブが特別になってきたというのもあるし、サポートメンバーも新鮮に取り組んでくれている感覚がまた出てきて。だから成熟してるし、フレッシュだし、すごくいい状態なんですよね。

─ceroのライブがどういうコミュニケーションのもと成り立っているのか、不思議に思ってる人も多いと思う。
高城:サポートメンバーとライブ中にアイコンタクトをとろうとしても、全然目が合わないってことがよくあって(笑)。みんな踊ってたり、くるくる回ってたりするから(笑)。
荒内:みっちゃんもめちゃ演奏に入り込んで、こっちを見ないこともあるし(笑)。
高城:「あーーーーー!」って叫びながら叩いてたりするからね(笑)。
荒内:まあ、リハで何回も試すからそれでも成立するんだけど。
高城:ceroみたいなタイプの音楽だったら、マニピュレーター入れたり、イヤモニつけてドンカマ(クリック)を聞いて、みたいな方法は普通になされるべきなんだけど、なぜか二の足を踏む傾向がある(笑)。特に信念があってやらなかったわけじゃないんだけど、結局ここに至るまで人力でやっていて、気がついたら特殊な存在になっていた。
─クリックを聞いて合わせたり、トラックを同期したライブを否定するわけじゃないけど、ceroがそうせずにライブを続けてきたことで保たれた詩情みたいなものはありますよね。
高城:それはある。スネア一発の音にしても毎回違うわけだし、ステージ上の隣近所でそういう違いが群発して、それが何か大きな流れになっていくことがceroのライブにはあると思う。そこはわりと重要なところかな。
INDEX
『e o』以降で変化したライブの心構え
─去年、リリースした5thアルバム『e o』がすごく話題になったでしょ? そして、ツアーを始めたらさらに驚きの声が上がったじゃないですか。Zepp Shinjuku公演や僕が観に行った仙台公演でも、今までceroを観に来てなかったタイプのお客さんが増えたと感じていました。
高城:確かに、各所で初めてceroのライブに来たお客さんに手を挙げてもらったら、結構いたんですよね。そういう変化はあった。ストリーミングで音源を聴いただけでライブに来た人は、どういう状況で演奏するのか全然想像できてなかっただろうし。
荒内:ポジティブな意味で、今のceroのライブには「お決まりの盛り上がり」みたいなのがなくて。そこはノリが変わったように受け取られているのかもしれないけど。
─『e o』は「静けさ」をひとつのキーワードに作られたという話をリリース時のインタビューでもしていましたよね(※)。それが時代とフィットした部分もあるかもしれない。
荒内:ライブに関しては『e o』の楽曲はちょっとフィジカルになるというか、スタジオ音源より熱量を持ってくるので、それが面白いなと思いますね。
高城:自分たちで説明するのは難しいですけど、ceroは、基本的に一番新しい曲のモードによって過去の曲も変わっていくんですよ。今でいうと『e o』が他の曲の構造を変えていく、ということが常にあるから、また新しく出てくるもの次第でライブも変わっていくんでしょうね。
※編注:CINRA掲載記事「ここがceroの本当の始まり――高城晶平&荒内佑が語る『e o』。真新しいものがなくなり、音楽はどこへ?」を参照(外部サイトを開く)
高城:何が『e o』的なのかは言葉にしづらいけど、今回の“マイ・ロスト・シティー”にしてもそういうモードになっている。『e o』を聴いてて感じる高揚って、表に発露するものとは必ずしも言えない、もっと内的な体験みたいなところが大きいと思うんです。
かつての自分だったら、ライブでは楽しくなったら楽しいだけでそれを表現してしまうところですけど、『e o』以降はその楽曲の中で起きていることを粛々と提示するだけで心は高揚するだろうと思えた。つまり、それって「聴く」ってことですよね。
僕にとってもそれは、「今、演奏で起きていることをきちんと聴いてから歌う」ということ。自分も聴いている者の一人だという意識を持ってプレイする。それが『e o』以降の心構えかな。それはこのライブ盤を作ってより思うようになりました。メタ的な視点でceroで起きていることに驚きながら、その驚きを表現しているという感じかな。
INDEX
ceroが提示する「内的な高揚」を醸成するものとは
─『Live O Rec』のミックスは橋本くんが中心だけど、荒内くんとの間で音のやりとりがかなりあったと聞きました。選曲面でも橋本くんが主導したんですか?
橋本:この『Live O Rec』をより『e o』っぽくするために、実際にLIQUIDROOMで演奏した曲からも毛色の違う曲は外しました。でも、“Elephant Ghost”や“マイ・ロスト・シティー”みたいな曲は激しいタイプなのに、音に冷たい感じがあるから収録されたものもある。
それが『e o』的と言えるのかな。そういうモードを今楽しんで聴いてもらえているのは、「騒げるんだけど無条件に騒ぐような気分にならない」っていうコロナ後の絶妙に微妙な気持ちにもフィットする音楽だからなのかも、と思いました。

荒内:時代とフィットするということで思い出したことで、『e o』の前に“Nemesis”を作ったとき、最初はもっとゴスペルっぽくしたいという案があったんですけど、それだとゴスペル文化に近寄りすぎるから避けたんですよね。そうじゃなくて、自分たちとかけ離れていない、身近な感覚のものとして作りたかった。そういう距離感の持ち方が『e o』にはあるかもしれない。
─ライブ盤としてこの方向性で行く、というのが最初に見えた曲は?
高城:“Nemesis”だよね。
荒内:方向性に関しては、俺のなかでは明確にビジョンはあったんですよ。最初に“Nemesis”と“Hitode no umi”を自分で試しにミックスしたんです。それもただのミックスじゃなく、鳴ってない音を鳴らしたり、トラックメイキングに近いやり方。
できた音源をみんなに送って意見を聞いてから、はしもっちゃん(橋本の愛称)に仕上げを頼んだんです。はしもっちゃんが作業するから「橋本翼の音」になるわけだけど、いろんな矢印がまたそこから出てきて、こっちでまた考える、みたいなプロセスもありました。

橋本:気がつけば全然違うものになってしまうという。
高城:当初は、曲数も少なくていいんじゃない、とか言ってたよね。5曲とか8曲とかでもいいくらい。でも、あらぴー(荒内の愛称)、はしもっちゃんの間でどんどんラリーされた音源がその時点でもう11曲くらいあった。であれば、ボツ曲を作るくらいならフルアルバムのサイズでやったほうがいいのかなとなったんです。
─つまり、それだけ触って変化させる楽しさがあったんでしょうね。ある意味、この作業はミックスというよりリエディットだった。
荒内:そうですね。ライブの素材を使ったスタジオ音源のつもりでした。俺の最初のミックスではお客さんの歓声も全部カットしてた。
─結果的に、それなりに歓声は残ってるけど。
荒内:あれは切り貼りしてるんですよ。ないと不自然な流れになるところもあるから。
高城:そうそう。違うシーンの歓声を持ってきたりね。

INDEX
『Live O Rec』は、ライブ作品の「制約」をどのように外していったか
─ライブから一番表情を変えた曲は?
高城:“Evening News”は、ライブテイクというより、あらぴーが自分で録り直したから、ほぼスタジオテイクとも言えるんじゃないかな。
橋本:僕が一番変えたのは“Poly Life Multi Soul”かな。
高城:あれは時空が曲がりまくってるよなー!
橋本:歌が入るところまでは別のライブなんですよ。
高城:そう、あれは2022年の野音(7月16日)のテイク。
橋本:その前の“outdoors”は2020年に野音で無観客配信をしたときに多摩川で撮った映像と当日(6月27日)のライブのミックス。そこから2022年の野音の“Poly Life Multi Soul”につないで、歌からようやく去年のライブになる。
最初はLIQUIDROOMの音源で通してミックスしてたんだけど、後で高城くんから、野音でやったときの“outdoors”と“Poly Life Multi Soul”のつなぎが気に入ってるから入れたい、と提案があって。まあ今回は、やったらダメなことなんかない作業だったから、つなぎだけ変えたんです。
荒内:アウトロも違う日のテイクを使ってない?
橋本:そう、ベーシックには12月3日のテイクを使ってるんだけど、エンディングは初日(2日)を使ってる。
─“outdoors”の導入に使われているのが、コロナ禍の多摩川でのアコースティックセッション映像の音源(無観客ライブに配信で使用された別映像より)というのも印象的。曲から曲へ時系列が提示されたことで、今のceroがたどってきた道筋を奇しくも表現しているように思えます。なんなら“outdoors”はceroのレパートリーに残っているなかでは一番古くからある曲のひとつでもあるし。
高城:確かに。もっともっと古いアーカイブから出してきても面白いかもね。
橋本:あらぴーが初期に使ってたサンプラーがあったじゃない? 僕がまだメンバーじゃなくて客としてceroを観に行ってた頃、“outdoors”であらぴーが声を逆再生にしたような音源をサンプラーで鳴らしていて、すごくよかったんですよ。それを使えたりしたら面白いねとか話してたね。結局使われなかったけど。
荒内:使ってもよかったよね、あのサンプラーまだあるし。スイッチ入るかわからないけど。
橋本:じゃあ、それはまたの機会に。
INDEX
バンドを始めた頃のように、三人の個性を混ぜ合わせた制作プロセス
─ライブ作品として参考にしたのがKing Kruleの『You Heat Me Up, You Cool Me Down』(2021年)だったそうですね。
高城:作り始める前は、そうだったかな。あの作品はお客さんの声をスローダウンさせたり、いろいろいじってて最近のライブ盤のなかでは面白い作りなんですよね。
高城:作っていた段階で方向性にちょっと迷ったとき、僕が個人的に聴いていたのは、ゆらゆら帝国の『な・ま・し・び・れ・な・ま・め・ま・い』(2003年)とか、FISHMANSの『男達の別れ』(1999年)とか。
別にああいう作品にはなってないから参照元ではないですけど、ライブ盤ってどんな感じかを確認したくて聴き直したりしました。「お客さんの声、どれくらい入ってんのかな?」みたいな。今回は特にエアー(場内の音)はあんまり使わず、ライン(PAを通した音)をたくさん使っていじったから。
橋本:今回はライブ盤を作るアイデアがそもそも面白かったから、ライブのノイズが入っちゃったり、演奏がちょっとおぼつかなかったりする細かいところはあえてそのままでいい、というのもありましたね。スタジオ作品ではそういうところは残さないじゃないですか。その感じがあったから、ミックスの判断はちょっと気楽だったかも。

橋本:あと、「ここは小田(朋美)ちゃんがすごく印象的なフレーズを弾くところだから(ギターは)聴こえないようにして」みたいな指示を聞いて、それは今、自分のライブには活かされてるんですよね。この作業を経てライブに反映されている部分は多い。
高城:そういうところは、めちゃたくさんあるね。みんながやってることがやっとわかった、みたいな(笑)。個々のいいプレイを判別しないままずっとやってきちゃったから、この段階で整理されてよかったというのはある。特に歌ってると、ほとんど演奏のディテールはわからないから。
荒内:作ってる途中でミックスを聴いて思ったのは、はしもっちゃんの心象風景を見ているようだな、と。たとえば、バンドが盛り上がってるところに、俺だったらキュッと抑えたくなるんだけど、はしもっちゃんはさらにエフェクトで広げているんですよね。演奏に対してそういう認識を持っているのが見えて、それをさらに拡大しているように思った。デカい音をさらにデカくするとか。

橋本:“Fdf”のシンセソロとかね(笑)。もうその音しか聴こえなくなるくらい。
高城:当初、はしもっちゃんは「その曲を通して起きてる事件性」みたいなものをプッシュしてたんだよね。それも面白かったんだけど、そこからあらぴーとの往復があって、抑えるところは抑えて、曲としての成り立ちを取り戻しつつ、事件性もある程度残すべきところは残しつつ。
そのやりとりが制作のハイライトで、俺はそれを「よしよし」「いいね」と取り持つ立場だった。結構大変だったけど、そこが面白いプロセスだから、またこれからもやったほうがいいんじゃないかなと思いました。お互いの一番際立った部分をどう音に落とし込んでいくのか、みたいな。
荒内:そういうのってバンド始めた頃にする話じゃない?(笑)
高城:いや、でも、案外ceroは三人の個性を混ぜ合わせるようなことをやってきてないかもなって思った。サポートの人たちを含めて自然と混ざってきたけど、その中心にいる三人を混ぜるには今回のライブ盤作りは最適な材料だった。俺も、作業中にななチキとかレッドブル買ってきたりね(笑)。
橋本:あれはうれしかったな。
高城:あれは今回一番いい仕事だった! ちょっと煮詰まった雰囲気になってたから、ここぞというタイミングでななチキとレッドブル投入するぞって思ってたんだよね(笑)。そしたら投入後にすごくいいディスカッションが生まれた。俺のハイライトはそれ!